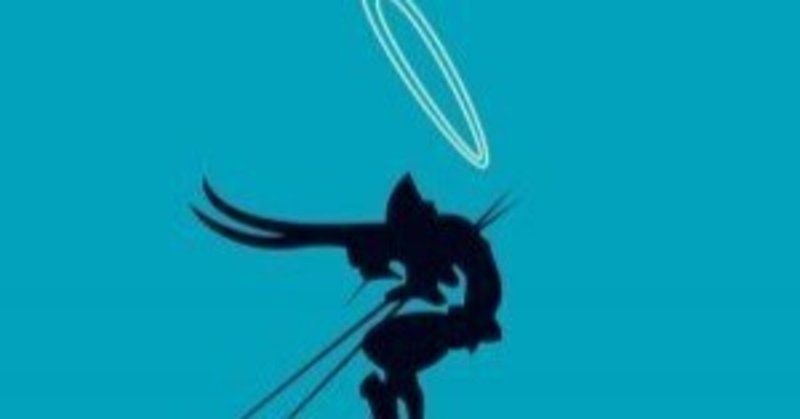
「母」の解体、「妻」の捏造ーー『シン・エヴァンゲリオン』論ー
*以下は、小説トリッパー2021年夏号(朝日新聞出版)に掲載された長編論考です。初稿なので実際に掲載されたものとは多少異同があると思います。
同誌では現在、これに続く長編の庵野秀明論が連載中です。
なぜなら「成熟」するとはなにかを獲得することではなくて、喪失を確認することだからである。
江藤淳『成熟と喪失 ー“母”の喪失ー』
1。エヴァンゲリオンと私
最初に断わっておくが、私はアニメファンではない。これまで長年生きてきて、嗜み程度にさえアニメを観てきたとは到底言えないし、今もそれはまったく変わっていない。率直に言って私はアニメにはほとんど興味がない。なにしろ宮崎駿作品でさえ数本しか観ていないのだ。
にもかかわらず、これから『シン・エヴァンゲリオン劇場版』というアニメ作品について幾らかのことを述べてみたいと思うのは、庵野秀明という表現者に強い関心を抱いているからに他ならない。すぐさま茶々が入ることはわかっている。それはお前だけじゃないよと。もちろん承知している。アニメというジャンルに留まらず、いや、実写映画等を含む映像表現という分野に留まることなく、庵野秀明という存在は、もう長らくさまざまな意味で衆目を集めてきたし、それは『シン・エヴァンゲリオン劇場版』(以下『シン』と略す)の大の付く成功によって決定的なものとなった。いまやアニメ内外の数多の人々が嬉々として『シン』を話題にし、論じ、庵野の人となりを語り、評し、実に多種多様な言説合戦を繰り広げている。その末席に自分も加わろうというわけである。
とはいえ、アニメについて素人未満でしかない私が『シン』を相手取って何が言えるのかと問われたら、むろん言えることがあると思うからこうして始めるのだと返したくはなるものの、あとでもう少し詳しく述べるように、私はここでいわゆる「謎解き」に属する作業をするつもりはほとんどない。まあ多少はするしせざるを得ないだろうが、そういうことがやりたいわけではないということはあらかじめ言っておきたいと思う。だからこの先に続く文章を読んでも、謎と秘密に満ちた『シン』という作品がよりわかりやすくなることはたぶん、ない。もしもわかりやすくなるとすれば、それは通常とはかなり異なった意味合いにおいて、になるはずである。
早くも先走ってしまった。まずは始めに「新世紀エヴァンゲリオン」という一連の作品群と自分のかかわりについて、少し書いておきたいと思う。そんなのどうでもいいよと思う方もいるだろうが、論述の大前提としてやはり必要だと思う。あらゆる批評は常に必ず批評しようとする者が位置している時空間的な座標に何らかの仕方で拘束されている。その拘束を超えて機能し得る思考と多少とも汎用性を持った言葉を編み出し、より広範な読者へと届けることを目指すからこそ、まずそこをはっきりさせておく必要がある。
最初のテレビ・シリーズ『新世紀エヴァンゲリオン』(以下『新世紀』)は、一九九五年十月四日から翌一九九六年三月二十七日まで、全二十六話が放映された。私はリアルタイムでは観ていない。先に述べたように私はアニメにまったくと言っていいほど関心がないので、しかもインターネットがまだ未発達の頃だったゆえ、放映期間中に噂を聞くことさえなかったのではないかと思う。私が『エヴァ』のことを知ったのは、一九九七年三月に出版されることになる二冊の『エヴァ』関連本ーー『スキゾ・エヴァンゲリオン』と『パラノ・エヴァンゲリオン』ーーの装幀を当時私の事務所に所属していたブックデザイナーの佐々木暁が手掛けることになり、おそらくその仕事のために初めて『エヴァ』をまとめて観たアキラックス(私は彼をこう呼んでいる)がたいそう興奮して絶対に観たほうがいいと教えてくれたのだった。興味を引かれた私は然るべき手を尽くして全話分のビデオを借り受け、これはよく覚えているが一気観した。2クール丸々なのでかなりの時間が掛かったはずだが、体感的には一瞬(は大袈裟だがそのぐらいの体感時間)だった。アニメのテレビ・シリーズを全話続けて観たことなど後にも先にもこの時限りである。先の『パラノ』『スキゾ』を筆頭に関連本や研究本の類いもけっこう読み漁った。要するにハマったのだ。
だがしかし、物書きとしての私は『エヴァ』にかんして何かを書いたりはしなかったと思う(短い言及くらいならあったかもしれないが)。たぶん特に依頼もなかったのだろうが、当時の私には門外漢の自分がアニメ作品について云々することを差し控える慎ましい気持ちがあった(今はもうあまりないのでこうして書いている)。なのでもっぱら一視聴者というか俄かファンのひとりとして、あれこれ『エヴァ』周辺を渉猟していたに過ぎなかったのである。周知のように『エヴァ』は社会現象と言ってよい空前のブームを巻き起こし、庵野秀明は一挙にアニメシーンの外部からも大いに注目されるようになった。その流れで製作・公開された劇場版第一作『新世紀エヴァンゲリオン劇場版 シト新生』および第二作『新世紀エヴァンゲリオン劇場版 Air/まごころを、君に』(ともに一九九七年)は映画館に観に行った。庵野秀明の初の実写映画監督作で村上龍原作の『ラブ&ポップ』(一九九八年)も観た。庵野が原案と脚本も自ら手掛けた実写映画第二作『式日』(二〇〇〇年)も観た。その後の『キューティーハニー』(二〇〇四年)も、もちろんあの『シン・ゴジラ』(二〇一六年)も公開時に映画館で観たのだが、とりあえず話を「エヴァ」に戻そう。
「新劇場版」の第一作『ヱヴァンゲリヲン新劇場版:序』(二〇〇七年)と『同:破』(二〇〇九年)も私はいそいそと劇場に観に行った。だがこの頃になると私の「エヴァ」への関心はかなり減退していた。正直に言えば「こんな仕切り直し、語り直しに何の意味があるのだろう、大人の事情で必勝法に頼ってるだけなんじゃないの?」という疑惑さえ抱いてしまった。そんなわけで私は続く『ヱヴァンゲリヲン新劇場版:Q』(二〇一二年)を公開時には観に行かなかったのだ。周囲の人間がどれだけ騒いでいても話を聞くだけに留まっていた。『Q』を私は今回『シン』を観る直前にAmazonプライムビデオで初めて観たのである。『Q』と『シン』のストーリーは(『序』と『破』がそうであるように)ほぼそのまま続いているので、結果としてこれでよかったと思っている。私は『Q』と『シン』を。約九年というけっして短いとは言えぬ歳月を挟んだ、だがひと続きの、あたかも一本の作品であるかのようにして観た。そして観終わった時、何とも言えない感覚を抱いた。それはこれまで「エヴァ」や庵野の作品を観てきて一度も感じたことのないものだった。要するに私は批評したくなったのだ。『シン』は私の思考を刺激し、起動した。それからずっとあれこれ考えてきて、今やっとこうして筆を起こしたわけである。
そもそものはじまりのテレビ・シリーズを観た時、私はまだ三十代の前半だった。ちなみに先にも触れた自分の事務所HEADZを立ち上げたのは偶然にも同じ一九九五年のことだった。「新劇場版」の開始時には四十三歳。そして『シン』を観てまもない現在は五十六歳である。庵野秀明は一九六〇年生まれ、私は彼の四歳年下である。
このことに何の意味があるのだろうか? 何かの意味があるのだろうか?
それはまだよくはわからない。わかっていることは、私はこの後も何度か、何度も、この事実に立ち返ることになるだろうということだ。すなわち庵野秀明と自分が同じ一九六〇年代前半の生まれで、同世代とまでは言えないが近接した年齢であり、九〇年代に三十代で自分の仕事をほぼほぼ確立し、二〇〇〇年代=ゼロ年代に四十代、二〇一〇年代=テン年代に五十代になって今に至る、という事実に。青年期の終わりから中年を経て初老と呼ばれる現在へ、私は庵野秀明と、そしてエヴァンゲリオンとともに歩んできたわけである。私の『シン・エヴァンゲリオン』論、そして庵野秀明論は、かくのごとき条件のもとで立ち上げられる(しかない)。
というわけで、始めたいと思う。
2。〈考察〉の空虚な迷宮
というわけで始めたいのだが、本論に入る前にあともうひとつだけ別の角度からの前提を記しておかねばならない。『シン』を観て驚いたのは、いや、本当はたいして驚かなかったのだが、完結編なのにまだ新たなワードが山ほど出てきたことだった。私が渋谷の東宝シネマズに観に行った際、劇場入口で特典の冊子(見開き2p)が貰えたのだが、そこには六十四項目ものキーワードがずらずらと箇条書きに並べられていた。解説は一切無い。それら全てが作品の中で口にされたのか、以前の作品にすでに登場していたものも含まれているのかはちゃんと確認出来ていないが、いずれにせよ、どれもこれも極めて意味ありげで曰くありげなワードの数々は過去の「エヴァ」シリーズと同様、説明も注釈も碌になされぬまま、先刻ご存知とばかりにどんどん発話されてはあっさりと通り過ぎていくのだった。
もちろんこれは「SFアニメ」の常套手段ではある。そのくらいは私だってわかっている。だがこうした趣向が「エヴァ」によって徹底的に突き詰められ、加速されたということに異議を差し挟む者はいないだろう。基本中の基本である「人類補完計画」や「ATフィールド」を始めとして、このシリーズには重要度や発話される頻度の差はあれ膨大と言ってよい用語群が存在しており、それらのほとんどが作品内でじゅうぶんな説明を与えられることがない。作品の外で作り手側から何らかの補足や言及が為されることはあるが、それもあくまで散発的かつ限定的でしかなく、どこかに公式の「エヴァ事典」のようなものがあるわけではない。
つまり「エヴァ」におけるキーワードの意味や解釈は、基本的に観る側に委ねられている。たとえばウィキペディアには「新世紀エヴァンゲリオンの用語一覧」という項目があり、そこでは基本用語が手際よく解説されている。集合知の産物なのでかなり客観的な記述になっており、私も適宜参考にさせていただくことになるだろう。だがそれは客観的たろうとするがゆえに却って不じゅうぶんにならざるを得ない面もある。というわけでネットを見回してみれば、有名無名の誰某による所謂「考察」が大量に存在している。それらの信憑性や分析のレベルなどは当然ながらまちまちだが、しかし「エヴァ」が数多くの人々に「考察への欲望」を激しく喚起させる作品であることは疑いない。要するに謎を解きたくさせるわけだ。秘密を探り当てたくなるのである。
このことをより一般化して述べるなら、フィクションに何らかの「謎」や「秘密」が設けられている場合、そこには大きく二通りの方向性がある。すなわち、その物語の「作者」(それは一人であるとは限らない)が「答え」や「正解」をちゃんと知っている/持っている、というパターンと、実は「作者」もそれらを知らない、というか「答え」や「正解」などはなからない、というパターンである。そして重要な点は、作品の内でも外でも「答え」や「正解」が開示されないままだと、受け手には二つのパターンのどちらなのかという判別さえ困難になってしまうということである。結果として、受け手は自らの努力によって「答え」や「正解」に(もしもそれを望むなら)辿り着くしかない。もちろん答え合わせは誰もしてくれない。むしろだからこそ、この手法は終わりなき「考察」を惹き起こし続けることになる。アニメに限らずとも、このような「考察」や「解釈」のゴール無きゲームは、こんにちのーー主にSNSを舞台とするーー「話題消費」における最大の誘因のひとつである。
言うまでもなく「エヴァ」は、このことを最大限に利用している。次から次へと出てくる用語群の「定義」、その「答え合わせ」の権利は「作者」にしかない。だから「作者」がそれをしないのならば、全ての用語に明確な意味や背景や設定が十全にありながらそれらがただ隠されているだけなのか、そうではなくて、そもそもそのワード自体が一種の撒き餌というか「考察」への誘惑の罠でしかなく、そこにはほんとうは(ほとんど)何もありはしないのか、私たちには確かめる術がない。こうしてネットには大量の「解答」が溢れ帰り、無数の「考察」が乱立し、SNSでは喧々諤々の議論が行われることになる。そしてそれこそが「作者」の狙った事態なのであり、現実に「エヴァ」はそうなっている。
だからこそ私は、そんな誘惑に乗るつもりはない、と敢て言っておきたいと思う。私はこの文章の続きで、それは必要に応じて『シン』に出てくる幾つものワードを取り上げもすれば時には自分なりの解読や推論を述べたりもすることもあるだろうが、積極的に謎解きをやってみせる意志も欲望も持っていない。私は「考察」のゲームに参戦する気はない。それは愉しくはあるかもしれないが結局は不毛な作業でしかないと、『シン』を、「エヴァ」を論じるにあたって、そちらに向かうのは明らかに得策ではないと考えているからだ。何故ならば、繰り返しになるが、それらのワード群は要するに私にそれをさせるために(だけ?)存在しているのだから。私は「考察」の空疎な迷宮に迷い込むつもりは毛頭ない。そうではなくて、私がこれから考えてみたいのは、むしろそのような巧緻で狡智な策略が隠し持っているものは何なのかということ、『シン』の、「エヴァ」の、強力に誘惑的なターミノロージーの鎧の裏側で、複数形の「作者」たちが、庵野秀明が、いったい何を語ろうとしたのか、何を語ってみせたのか、何を語ってしまったのか、ということなのである。
というわけで、今度こそ始めよう。
(以下の論述では『シン・エヴァンゲリオン劇場版』及び「エヴァンゲリオン」シリーズの内容に大々的に触れていますので未見の方はくれぐれもご注意ください)
3。「成熟」の年齢
『ヱヴァンゲリヲン新劇場版:Q』には虚を突かれた。前作『ヱヴァンゲリヲン新劇場版:破』から、いきなり物語上で十四年もの月日が流れ去っていたからだ。『破』の終わりで、紆余曲折あった末にエヴァンゲリオン初号機に乗ったシンジは「第10の使徒」を倒したが、覚醒した初号機自体がトリガーとなって「サードインパクト」が始まりそうになる。EVAパイロットで実は「使徒」でもあった渚カヲルの、そして「使徒」との戦いを統括する組織「NERV(ネルフ)」主席監察官の加持リョウジの命と引き換えの働きもあって、それはギリギリ回避されたものの、結果として「ニアサードインパクト」は甚大な被害を齎した。それから十四年間、シンジはエヴァ初号機の中で眠り続けていたのだ。その間に情勢は大きく変化しており、NERVに所属していた葛城ミサトや赤木リツコ博士、式波・アスカ・ラングレー、真希波・マリ・イラストリアスの二名のEVAパイロットはゲンドウらNERVと敵対する組織「WILLE(ヴィレ)」として活動している。シンジが目覚めたのもWILLEの旗艦である空母「AAA ヴンダー」の内部だった。だが『破』の結末でシンジが助けたはずの綾波レイは発見されなかったという。
「ヱヴァンゲリヲン新劇場版」四部作は、二作目の『破』以降、最初のテレビシリーズとも、基本的にその総集編/再編集版だった「劇場版」ともかなり異なったストーリー展開になっていくのだが、とりわけ『Q』での十四年の経過は過去作にはまったくなかった設定であり、そして前述の通り『Q』と『シン』は時間的に連続しているので、まずはこの「十四年」をどう捉えるのか、ということが問題になるだろう。何故、十四年なのか?
そもそもの始まりだった『新世紀エヴァンゲリオン』は、放映開始時の一九九五年から二十年後の二〇一五年が物語上の現在時とされていた(したがって『Q』と『シン』の間に現実の時間が物語の時間を超えてしまったわけである)。全編の主人公である碇シンジは十四歳。何故、十四歳なのか? (この当時は存在しなかったが)「中二病」という語を思い出すひともいるだろう。楳図かずおの名作『14歳』(『新世紀』放映開始時にはまだ雑誌連載中だった)との関連を指摘する者もいるかもしれない。だが、おそらくもっとシンプルな理由がある。それは何故、最初のシリーズが『新世紀』とされていたのかを考えてみればわかる。二〇一五年に十四歳ということは、碇シンジは二〇〇一年六月六日生まれ、すなわち「新世紀」に入って最初の年に生まれた子のひとり、ということになるのだ。彼は新世紀の子ども、二十一世紀を生きる新しい人間として誕生し、そして十四歳にして試練に晒されることになるのである。
『破』の終わりから『Q』の始まりまでに十四年が過ぎ去っており、しかもシンジはその間ずっと眠っていた。しかし彼だけではなく、EVAパイロットたちは全員、容貌に経年変化が全くない(「エヴァの呪い」とされる)。だが、失神して目覚めてみたら十四年後になっていたシンジと、その間もずっと闘ってきたアスカたちとでは当然ながら内面的な成長に大きな違いがある。実際、『シン』でアスカは「私のほうが先に大人になっちゃった」とシンジに告げるだろう。つまり『Q』のはじまりの時点で見た目も心も「十四歳」のままなのはシンジだけなのである。
ここには二重の含意があると思われる。ひとつは、この壮大かつ複雑で混乱したサーガのスタート時点で十四歳だった碇シンジは、『破』と『Q』を隔てる十四年の間、ひたすら眠り続けていたことで、もう一度、最初の段階へとリセットされた、いわば初期化されたのだということである。だからこれはもう何度目かとなる[やり直し」なのであり、シンジはこれまで直面してきたさまざまな困難や問題にまたもや対峙させられ、そして以前とは違う選択や判断を求められることになる。
もうひとつは、と同時に、やはり現実には十四年が過ぎているのであり、したがってシンジは『Q』の時点で、ほんとうは二十八歳なのだ、ということである。彼自身はまったく意識し得ていないが、もうすっかり大人なのだ。それは他のEVAパイロットも同じであり、先のアスカの発言はそのことを意味している。この点はあとでもっと重要になってくる。
『序』から『破』にかけて起こった出来事、いや、それ以前の「エヴァ」で起こったあらゆる出来事を強引にキャンセルし、むりやり初期化したところからもう一度すべてを語り直すこと。考えてみれば、これは「劇場版」がテレビシリーズに対して有していた立ち位置であり、また「新劇場版」が「劇場版」に対して有していた立ち位置でもある。「エヴァ」の「作者」たちは、庵野秀明は、「新劇場版」の中途で、またもや同じことをやろうとしたのである。だが今回ばかりはこれまでとは違い、物語を冒頭からやり直すことは許されておらず、しかもすべての結末に向かってゆかなくてはならない。逆に言えば、今回のリセットは、この長い長い物語を今度こそほんとうに終わらせるためにこそ要請されたのだと言っていい。そして実際、そうなるのである。
碇シンジは、二度目の、あるいは何度目かの「十四歳」、実は「二十八歳」でもある「十四歳」として、「エヴァ」の最終章である『Q』と『シン』の物語を生きてゆく。言い換えればそれは、シンジが仮初めの「十四歳」から、本当の年齢である「二十八歳」へと変身(!)を遂げる物語ということである。要するに、シンジは遂に「大人」になるのだ。だが、ならばもちろん問われるべきは、それはどのような意味で「大人」なのか、ということであり、「大人」になることにどんな意味があるのかということであり、そしてそのような意味で「大人」になることは、ほんとうに望ましいことなのか、ということである。「十四歳」という年齢が、ひとりの人間が(ひとりの「男性」が?)「成熟」への階梯を歩み始める時期であり、そして「二十八歳」という年齢が、そのプロセスがおおよそ完了する時期なのだとするならば、シンジはいわば早回しで「成熟」へと至ることになるのだが、それは果たして正しいのか?
4。「人類補完計画」とは何だったのか?
『シン』を最初に(というのはこの論考を書くために何度か観に行ったからだが)観終わったとき、私がまず思ったのは「エヴァって度を超した愛妻家の話だったんだな」ということだった。愛妻家とはもちろんシンジの父、碇ゲンドウのことである。
『エヴァ』で登場した時から、ゲンドウの実の息子シンジへの冷淡さ、残酷さには目に余るものがあった。確かに、このキャラクタライゼーションは、「エヴァ」以前のロボットアニメでも何度となく繰り返されてきた、「(自らの意志とは無関係に)ロボットに乗らざるを得なくなる主人公」と「ロボットに乗ることを強いる者」という対立軸ーー端的に言ってそれは「大人になること=成熟」の隠喩であり、したがってこのような設定のアニメはどれも一種のビルドゥングス・ロマンであるーーの反復なのだが、それにしてもゲンドウはあまりにも酷い。なるほど後で触れるように、『シン』ではゲンドウ自身の述懐によってその理由らしき心情が吐露されはするのだが、それを聞いたうえでも尚、ゲンドウのシンジへの仕打ちはほとんど異常とさえ言ってよい。そしてシンジへの過剰な冷たさ、ほとんど憎悪にも近い態度とは裏腹に、ゲンドウがシンジの母親である妻ユイを如何に狂おしく愛していた/いるのかが、『Q』と『シン』では前景化されてゆく。
ゲンドウとその副官(にして元教師)の冬月コウゾウが謎めいた会話を交わし、NERVを裏で操っているとされる秘密結社「SEELE(ゼーレ)」の名を出しては「すべてはゼーレのシナリオ通り」などと口にする場面は、「エヴァ」シリーズのお約束の一つであり、何度となく出てくるにもかかわらず、彼らと「ゼーレ」の真の関係性、つまりゲンドウたちがゼーレ(のシナリオ)をどう思っているのかが、いつまでたってもよく見えてこないということが、じれったくもあり興味深くもあるのだが、ともかくゼーレによる「人類補完計画」が「エヴァ」の物語の中心に位置しているらしいことは誰の目にも明らかなことだろう。だが、ではその「人類補完計画」とは如何なる計画なのかというと、これまたいつまでたってもはっきりとしない。それどころか、どう見ても「人類」にとって好ましからざる展開になっているのに、ゲンドウと冬月は平然と「ここまではゼーレのシナリオのまま」と宣ったりもしていた。
だが『Q』には、やっと「ゼーレのシナリオを書き換える」という台詞が出てくる。そしてゲンドウはゼーレの長老たち全員に一種の「引退」を強いてあっけなく消去してしまう。しかしそれでもゼーレの「人類補完計画」とゲンドウの「人類補完計画」の違いは結局よくわからないままなのだった(私には)。ともあれ、最終的に「人類補完計画」はゲンドウの個人的な野望へと収斂してゆく。冬月は「ゲンドウは自分の願いを叶えるために、あらゆる犠牲をはらっている」と言う。その「願い」とは何なのか? ゲンドウはその答えをあっさりと口にする。「もうすぐ会えるな、ユイ」と。
「人類補完計画」というワードはSF作家コードウェイナー・スミスの連作「人類補完計画」に由来する。スミスの「人類補完計画」の原語は「instrumentality」であり、何らかの道具や手段となるもの、媒介組織、代行機関というような意味である。また、そこには「神との仲立ち」という宗教的な含意も込められている。「instrumentality」を「人類補完計画」と訳したのは、スミス作品の翻訳を多く手掛けた伊藤典夫である。「エヴァ」の「作者」はここから用語を拝借したことを認めている。つまり実際にはコードウェイナー・スミスではなく翻訳家伊藤典夫のワードセンスによるものと言えるのだが、ともかく重要なのは「人類補完」という語の持つ引力である。「人類」を「補完」する? それは「救済」とも「回復」とも違う。文字通りに取るならば、それは「足りないものを補って完全にする」ということである。スミス=伊藤を離れて「エヴァ」における「人類補完計画」を問題にするならば、つまり「人類」に欠けている要素は何であり、それを補うことによって完全な状態になるというその完全さとは如何なる状態なのか、という話になるわけだが、「エヴァ」シリーズは『シン』に至って、この「人類の補完」を碇ゲンドウの妻ユイとの再会という私事に完全に変換してしまう。ユイは物語の最初の時点ですでに亡くなっており、設定上は「二〇〇四年没、享年二十七」。シンジは母親のことを覚えていない。ユイの旧姓は綾波である(らしい)。彼女は冬月が京都の大学で教鞭を執っていた頃の教え子のひとりであり、その縁でゲンドウと知り合って恋愛し結婚し妊娠し、シンジを産んだ。ゲンドウとは同僚でもあり、エヴァ開発中の事故で死亡したとされていたが、実際にはエヴァに魂を取り込まれて一体化し、初号機の制御システムとして存在し続けている(この事実は『Q』ではじめて判明する)。綾波レイは綾波ユイをモデルとするクローンのシリーズの名称であり、レイが何体も培養(?)されている様子はテレビシリーズでも描かれていた。『Q』にはもとの綾波レイ(それもすでにクローンであった可能性が高いが)の代わりにまったく同じ容姿の「アヤナミレイ(仮称)」が登場し、『シン』では「そっくりさん」とも呼ばれる。アスカはレイ(仮称)を「初期ロット」という渾名で呼ぶが、どうやら「アヤナミシリーズ」とともに式波・アスカ・ラングレーの「シキナミシリーズ」もあるらしいことが語られもする(では真希波・マリ・イラストリアスの「マキナミシリーズ」もあるのか、ということになるのだが、それは後で検討する)。
「人類補完計画」に話を戻そう。『破』の物語を「色々あってサードインパクト(実際にはニアサード)が起こってしまう」と纏められるとしたら、『Q』の物語は「更に色々あってフォースインパクトが起こってしまう」と纏めることが出来るだろう。『シン』のゲンドウの言葉を借りれば、セカンドインパクトは「海の浄化」、サード・インパクトは「大地の浄化」、そしてフォースインパクトは「魂の浄化」を齎すものだった(ファーストインパクトは「使徒」が生まれるきっかけとなった隕石の地球への衝突を指す)。更に『シン』では「アディショナルインパクト」が惹き起こされ、ゲンドウの「人類補完計画」は、それをもって完遂することになる。だが、その話に向かうのはまだ早い。
十四年後の『Q』では、すでに述べたようにNERVとWILLEの対立の構図上で物語が進められる。ニアサードインパクトを経てフォースインパクトを惹き起こそうと目論むゲンドウと、全人類のためにそれをなんとか阻もうとするミサトたちの対立である。シンジは最初、WILLEの管理下に置かれる。彼はニアサードインパクトのトリガーとなった人物として危険視され、もう二度とエヴァに乗るなと言い渡されて首に「DSSチョーカー」を装着される。シンジがWILLEの命に叛いてエヴァに乗り込もうとしたらチョーカーが発動して死に至るのだ。だがシンジはヴンダーを急襲してきたNERV側のエヴァMark.09を操縦するレイ(実はクローンのレイ(仮称))に導かれてNERV本部に戻る(このあたりの優柔不断さがいかにもシンジである)。シンジはそこで渚カヲルとも再会し、彼とともにエントリープラグが二つある新型エヴァ第13号機に乗ることをゲンドウに命じられる。シンジは最初は拒否するが、カヲルがシンジのDSSチョーカーを外して自分の首に付け替えたことに感じ入って一緒に第13号機に乗ることを決意する。『Q』の後半ではシンジとカヲルがレイ(仮称)と共にセントラルドグマ(サードインパクトの爆心地)の最深部に降り立ち、『破』のラスト、つまり十四年前からそこに留め置かれたままだった第2使徒リリスとエヴァMark.06に刺さった二本の槍を抜くかどうかのやたらと複雑怪奇な物語展開となる。あまりにもややこし過ぎるので説明は省くが、ともかく色々あってフォースインパクトが開始されてしまう。ゲンドウの奸計によってそのトリガーにされたカヲルは自ら犠牲となりDSSチョーカーを起動させてシンジの目の前で無惨に爆死する。フォースインパクトは駆けつけたアスカとマリの働きもあって途中で停止するが、地上に帰ったシンジはカヲルを死なせてしまったこと、フォースインパクトを起こしてしまったことに絶望し、完全な意志阻喪状態に陥る。ここまでが『Q』のストーリーである。
『シン』でもNERVとWILLEの戦いは続いており、その範囲は世界規模に及んでいる(映画はパリ市街地の場面から始まる)。『破』のラストでシンジはレイ(仮)とともにアスカに連れられて荒野を歩き始めていたが、三人は偶然にかつての同級生、二十八歳になった相田ケンスケと遭遇し、ニアサードインパクトを生き延びた人々が住む「第3村」へと招かれる。そこにはやはり大人になった元同級生、鈴原トウジと(学級委員長だった)ヒカリ夫妻と、その娘ツバメも居た。『シン』の前半は「第3村」でのシンジたちの生活が描かれる。シンジは自分を責めるあまりやる気を喪ったままで、誰かと話すこともなければ、食事も碌に採ろうとしない。そんな彼に友人たちとその家族は温かく接するが、シンジは歩み寄る気配さえ見せない、シンジはアスカとともにケンスケの家に仮住まいすることになるが、やがて一人で出ていってしまう。一方、レイ(仮)は鈴原家に居候しつつ、村の人たちと触れ合っていく。前述のように彼女は綾波レイその人ではなく、そのクローンであり、そのことを本人も自覚している。レイ(仮)は綾波レイの「そっくりさん」ではあるが、別人格なのだ。体調の変化を自覚した彼女は「わたしはNERVでしか生きられない」と独白する。
私は何者なのか、という問いは「エヴァ」シリーズ全編を貫いている。『シン』前半では、それがレイ(仮)の物語として描かれる。レイ(仮)は第3村で人間が持つ基本的な感情をひとつひとつ学んでいく。彼女が村の女性たちと田植えをするシーンはこの映画の中では例外的に牧歌的な雰囲気を醸している。村のおば(あ)ちゃんたちに、そろそろ「そっくりさん」も変だから何か名前をつけるといいのじゃないかと言われたレイ(仮)は、家出してからNERV第二支部の跡地で無為に過ごしていたシンジに会いに行き、自分に名前をつけてほしいと頼む。最初、シンジは「名前といっても君は綾波じゃないし」と困る(だが彼はレイ(仮)を「アヤナミ」と呼んでいる)のだが、後になってシンジは、綾波は綾波だ、他に思いつかないよ、と言う。その頃になるとシンジは自責と懊悩から少しずつ回復しており、他人への態度も以前よりは柔和なものに変化している。だが、この会話の直後、レイ(仮)は「初期ロット」であるがゆえの活動限界に達し、あっけなく自壊してしまうのだ。
「エヴァ」シリーズに当初から潜在していたが、「新劇場版」以降、前にも増して全面に押し出されてきたテーマは、運命という主題である。ここでいう「運命」とは、最初から定められていた、という意味だ。私は何者なのか、という問いは、私は如何なる役割なのか、という問いと同義である。この世界=物語において、私の果たす役割とは何か? シリーズを通じて、どれだけ意想外の出来事や未曾有の悲劇が出来しても、その後すぐさま、実はこうなることは始めから決まっていたのだ、何もかもなるべくしてなったことなのだ、などとされるのは、たとえまるでそうは思えなかったとしても、登場人物たちの運命にはそれぞれに明確な機能があり、それらが有機的に絡み合うことで物語が展開しているのだ、すべてはシナリオ通りなのだということを強調するためである。それはつまり、このすべてが何らかの目的に沿って進められているのだということ、何もかもがひとつのありうべき結末へと向かっているのだということである。では、その目的とは、その結末とは、いったい何なのか?
だが、ここにはやはり疑問符を付しておかねばならない。『シン』は「新劇場版」の、そして「エヴァ」シリーズ全編の真の「完結編」となることが予告されており、実際にそのようなものになっている。だが、その「完結」のありさまは、どの時点で確定していたのだろうか。そもそも最初のテレビシリーズでは、あの第25話と最終第26話が「作者」にとって望まざる終わりになってしまったーー作業工程の致命的な遅れによってアニメーションが間に合わなくなり、結果として過去回の使い回しや静止画、実写、絵コンテなどが全面的に使用される異常な展開となり、ストーリー的にも破綻していると思われても仕方のないようなエンディングになってしまったーーがゆえに「劇場版」という仕切り直しの必要が生じたのだった。だがそれでもうまく終われなかったので、「新劇場版」が始まったのだ。「エヴァ」が四半世紀以上の時間をかけて、いわば遠心軌道的に『シン』で語られる結末に向かってきたのだとして、そのいわばトゥルーエンドは、いちばん最初からそのようなものとして構想されていたのだろうか? おそらくそうではない。もちろん私は何も知らない。だがしかし、シナリオの最後のページが何度も書き改められてきたことは間違いない。『シン』の結末は、試行錯誤の何度目かだったのであり、事と次第によってはまたもややり直しになる可能性だってあったのだ。だがそれはトゥルーエンドになった。いや、トゥルーエンドにされたのである。
あるいは、こう言ってもいいかもしれない。「エヴァ」の「作者」は、庵野秀明は、最初のテレビシリーズでも、「劇場版」でも、「新劇場版」でも、毎回同じことをやろうと試みたのだ。にもかかわらず、どうしてか、どうしても、うまく終われなかったのであり、何故うまく終われなかったのかを一言でいうならば、そこに時間というものが存在していたからなのだ。庵野秀明は、『新世紀エヴァンゲリオン』放映終了時に三十六歳、「新劇場版」開始時に四十七歳、『シン・エヴァンゲリオン』完成時に六十歳。彼は何度もトゥルーエンドを目指し、失敗し、やり直し、また失敗し、その間に年齢と経験を重ねて、そして遂に、この果てなきトライアルを無理矢理にでも終わらせることにしたのだ。だから、先の問いはこう書き換えねばならない。「エヴァ」を今度こそ完全に終わらせるために選び取られた結末、最後である(もうこの続きはないと宣言する)がゆえに「シン=真=トゥルー」になることを強引に決定づけられた結末、その「新」にして「真」なる結末が意味するものとは、いったい何なのか?
繰り返す。それ以前から何度となく匂わされてはいたものの、『シン』の終盤に至ってもはや隠す気もなく大々的に露呈される真実とは、結局のところ「人類補完計画」とは「ユイの復活」もしくは「ユイとの再会」を激しく希求した碇ゲンドウが人類と地球環境を丸ごと巻き込んでやってのけた極私的でエゴイスティックな一大プロジェクトだったのだということである。これはけっして矮小化ではない。逆である。ゲンドウはユイへの愛惜の想いを極限まで増幅し拡大してみせたのである。ゲンドウにとっては、ユイという一個の存在はユイ以外のすべての存在と完全に釣り合っている。今あるこの世界に唯一足らないのがユイ、つまり「人類」を「補完」するものとは「ユイ=妻」なのだ。逆にいえば、ユイさえ還ってきてくれるなら、人類など滅びても一向に構わない、ということである。なんという話だろうか。「度を超した愛妻家」とは、そういう意味である。
ところでしかし、これはあくまでも「碇ゲンドウの物語」である。では、その「息子」である「碇シンジの物語」はどうなのか?
5。カヲルとアスカとミサト
「シンジの物語」を語る(読む?)ためには、何人かの登場人物について補足しておかなくてはならない。
渚カヲルは、おそらく「エヴァ」シリーズの中でも最も謎に満ちた存在だろう。彼はテレビシリーズの後半から登場していたが、ゼーレからNERVに送り込まれたフィフスチルドレン=EVAパイロット、だが実は使徒(しかも「第17使徒タブリス」にして「第1使徒アダム」)でもあった彼は、善悪や敵味方の判別がどこまでも曖昧になり渾然一体となっていく「エヴァ」の世界を象徴していると言える。すでに述べたように『Q』でシンジはカヲルとNERV本部で再会し友情を深めるが、カヲルは自らの命を犠牲にしてフォースインパクトを食い止める。そのことでトラウマを負ったシンジが立ち直るまでが『シン』の前半の物語だった。
テレビシリーズの時点からカヲルはいうなればシンジの「完璧な鏡像/双子」として設定されていた。常に冷静で超然としていて、自分の役割を十全に理解して行動するカヲルはシンジにとって憧憬の対象であると同時に(何故かはよくわからないが)素直に心を開ける人物である。だが、そんなカヲルの正体(?)が実は戦うべき敵=使徒であり、しかも最終的に非業の死を遂げてしまうことで、シンジははかり知れないショックを受ける。『Q』でカヲルはシンジをピアノの連弾に誘う。ピアノを弾いたことがないシンジは躊躇うが、「生きていくためには新しいことを始める変化も大切」だとカヲルは言う。二人がピアノを弾く場面の親密さには微妙に同性愛的な気配が漂う。あるとき、夜空を見上げながらシンジが、子どもの頃から星を見ると安らぐ、自分という存在などどうでもよく思えて落ち着くのだと言うと、カヲルは「変化を求めず虚無と無慈悲な深遠の世界を好む、君らしいよ」と微笑む。このようにカヲルはシンジのすべてを肯定し、受け入れてくれる。カヲルは「僕は君と会うために生まれてきたんだね」とさえ言う(実際その通りなのだ。そういうキャラクターとして召喚されたのだから)。ともにエヴァ第13号機に乗ることになった際、カヲルはシンジに「いつも君のことしか考えてない」と言う。二人は手を握り合う。レイにもアスカにも(ある意味ではミサトにも)シンジは疑似的で微温的な恋愛感情を抱いてきたが、彼の理想の恋人に成り得たのは実のところ渚カヲルなのである。だが、だからこそカヲルは途中で姿を消さなければならない。DSSチョーカーの発動によって絶命する前に、カヲルは「シンジ君は安らぎと自分の場所を見つければいい。縁が君を導くだろう」と告げる。カヲルの台詞には常に予言や託宣としての意味がある。そして確かに『シン』は、碇シンジが縁に導かれて安らぎと自分の場所を見つけるまでの物語なのである。
式波・アスカ・ラングレーは、以前は惣流・アスカ・ラングレーという名前だった。テレビシリーズと「新劇場版」で最も設定が変更されたのが彼女だろう。「式波」という新たな姓が「綾波」と対にするために選ばれたことは明白である。「式」と「綾」。「新劇場版」における最大の変更点は、アスカもレイと同様、クローンを前提とする一種の人造人間「シキナミシリーズ」だとされる点である。したがって惣流時代にはあったアスカの母親とのエピソードは無くなっている。『シン』にはアスカが食事も睡眠も本当は必要ないらしいことを窺わせる場面もある。彼女は自分を「リリンもどき」と言う(「リリン」は人間のこと)。アスカがシンジのことを気に懸けるレイ(仮)に対して、私たちはヒトの枠を超えぬよう非効率な感情を持たされている。あなたたちアヤナミシリーズは「第三の少年」(レイ、アスカに続く第三番目のEVAパイロットということだが、それ以外の含意もあるのかもしれない)すなわち碇シンジに好意を抱くように設計されている、ただそれだけのことなのだ、その感情はNERVに仕組まれたものに過ぎないのだ、といったことを言う場面があるが(これに対してレイ(仮)は「それでもいい」と答える)、追って明らかにされる先の事実を踏まえると、それはそのままアスカ自身にも当て嵌まる。
だが、この決定的と言ってよい違いを除けば、アスカの性格設定は一貫している。一時はシンジの恋人の最有力候補だったこともあるアスカは『破』から十四年後、相変わらずエヴァに乗り、WILLEの一員としてマリを従えて戦闘に従事している。だが今の彼女は左目に眼帯をしており、その顔には凶相ともいうべき表情が浮かんでいる。それでも勝ち気さの裏に繊細さや脆さを隠し持っているところや、ふとした瞬間に垣間見える優しさは変わっていない。第3村に居る間、アスカは特に何もしていない。レイ(仮)に「仕事はしないの?」と問われた彼女は「あんたバカ? ここは私の居るところじゃない。守るところよ」と答える。そしてアスカが村を去ることになった時、シンジは自分も一緒にWILLEに戻ると言うのである。
『シン』の長い長いクライマックスの途中で、戦闘中のアスカは最後の手段としてエヴァの「裏コード」を発動させ、自ら使徒化することによってATフィールドを中和する。それは彼女が「リリンもどき」でさえなくなること、アスカという存在の消滅(精確にはユイとエヴァ初号樹の関係と同じエヴァとの魂的融合?)とイコールである。つまりカヲルと似た運命を辿るのだが、しかし後でもう一度述べるように、カヲルもアスカも、最後の最後には救済されることになる。いや、あれが「救済」と呼ぶべきことなのかどうか、今もって私には判断出来ないのだが。
葛城ミサトは、『破』まではゲンドウの部下だったが、『Q』になるとNERVと対立するWILLEの司令官になっている。ストーリー全体からすると傍系のエピソードにも映るが、ことのほか重要に思えるのは、彼女が加持リョウジとの間に息子を設けていたという事実である。先述のように加持は自分の命と引き換えにサードインパクトを止めた(『Q』に加持は登場せず、このことは『シン』で初めて明らかにされる)。それは身重のミサトを庇ってのことであったらしいことが『シン』では語られる。ミサトと加持の息子は父親と同じ「加持リョウジ」と名づけられたが、ミサトは自分が母親であることを隠し、リョウジをWILLEの支援組織KREDITに預けた。リョウジは両親を知らぬまま成長し、相田ケンスケの紹介でシンジと出会い、二人は悪手を交わす。後になってミサトはその時の写真を受け取り涙する。シンジは「すごくいい奴だった。少ししか話してないけど、僕は好きだよ」とミサトに言う。
このエピソードが何故、重要に思えるのかといえば、ミサトがユイを除く主要登場人物の中で、ただひとり「母」になるからである。「新劇場版」に出てくる「母」は、あとは鈴原ヒカリだけなのだ。そもそも「エヴァ」は「父と息子の物語」であり「夫と妻の物語」でもあるが、「母と息子の物語」「父と母(=親)の物語」という面は希薄である。すでに見たようにユイは「ゲンドウの妻」としての存在感は「エヴァ」の世界を律するほどに強固だが、一方で「シンジの母」としてのそれは、やや不自然とも思われるほどに弱い。それだけに、とりわけテレビシリーズでは生活の上でもシンジの保護者=母親代わりでもあったミサトが母になることには、おそらく表面に現れている以上の意味がある。それは彼女が「シンジの(擬似的な)母」から「リョウジの(本物の)母」に変わってしまうということなのだから。かくしてシンジは、ユイという実の母も、ミサトという仮の母も失い、いわば母でもあり得る妻を求めなくてはならなくなるのである。
こうして、マリが登場する。
6。マリとは何者か?
真希波・マリ・イラストリアスは、「新劇場版」の『破』で初めて登場した、まったく新しいキャラクターである(ただし『序』の時点で登場自体は予告されていた)。誰の目にも明らかなことだと思うが、マリこそ「エヴァ」を終わらせるための最大の鍵である。アスカが「コネメガネ」と呼ぶように、マリはイギリス出身で、NERVのユーロ支部から何らかの肝入りでEVAパイロットとして配属されてきた。長身、巨乳、メガネという、これまでの「エヴァ」には居なかったタイプの女性である。『Q』では天地真理の「ひとりじゃないの」(一九七二年)を、『シン』では佐良直美の「世界は二人のために」(一九六七年)を鼻歌で唄っている。驚いたときに「アジャパー」と言う。つまり妙に「昭和感」のある人物なのだが、その理由の説明は特にない。
『破』ではアスカのライバルになりそうな雰囲気もあったが、『Q』ではほぼアスカの部下と言える扱いになっている。マリには他の登場人物のような性格的な陰影やネガティヴな要素が全くと言っていいほど存在していない。また、エヴァに乗ること、使徒や(のちには)NERVと戦うことへの不安や葛藤も、その言動からはまるで感じられない。彼女は与えられた条件、自分の置かれた状況において、可能な限りポジティヴで楽天的な態度を貫いており、もちろんあとで触れるようにシリアスな一面もありはするのだが、その軽やかさと無邪気さは「エヴァ」の世界では明らかに異色なものだと言える。マリはシンジを「ワンコくん」と呼ぶ。彼女がシンジに顔を寄せて彼の体臭をかぐ描写が何度かあるが、それは最終的に重要な意味を帯びることになる。以前から知っていたわけでもないはずなのに、マリは最初からシンジに(いくぶん「からかい上手」的な感じではあるものの)妙に好意的であり、『Q』の終わりでシンジが行方不明になったときも「どこにいても必ず迎えに行くから、待ってなよ、ワンコくん」と呟くし、アスカがシンジを責めたあとには「君はよくやってるよ、エラいよ、ワンコくん」などと慰める。だがシンジの方は、少なくとも最初の内は、あまりピンと来ていないように見える。『破』そして『Q』までは、マリは「エヴァ」の世界において、どこか浮いているようにさえ思える。
いったいマリとは何者なのか。多くの観客が気づくだろうが、『Q』でマリは何度か(その時点では)不可解な口の利き方をする。碇ゲンドウのことを、ごく自然な感じで「ゲンドウ君」と呼ぶのだ。いかに「コネメガネ」とはいえ彼女は一介のEVAパイロットに過ぎないはずである。ゲンドウに君づけは年齢的にも合わない(もっともマリの年齢にかんする言及は作中にはないが)。どういうことなのか。この疑問に一定の答えが与えられるのは『シン』が後半に入ってからである。実はマリはゲンドウやユイと同じく京都の大学での冬月のの教え子のひとりだったのだ。コネメガネの「コネ」は、おそらく冬月のコネなのである。
本論では、基本的に「エヴァ」シリーズのアニメ以外の関連作やスピンオフについては触れない方針を取っているが、やはりこれだけは記しておかねばなるまい。貞本義行によるコミック版『新世紀エヴァンゲリオン』の単行本最終巻に当たる14巻が『Q』公開後ほどなくして出版されたのだが、そこには書き下ろしの短編「夏色のエデン」が収録されている。舞台は一九九八年の京都の大学、飛び級をして十六歳で冬月教授の「形而上生物学第一研究室」に所属している「マリ」は同じ研究室の先輩「ユイ」に慕情を寄せている。物語の冒頭でイギリスへの留学の話題が出てくるので、それをそのまま受け取るなら、これは『破』で登場する以前のマリのエピソードということになる。「夏色のエデン」に即すなら、一九九八年に十六歳だったマリの生年は一九八二年ぐらい。「新劇場版」ではテレビシリーズの「ファーストインパクトから十五年後の二〇一五年」という時代設定は単なる「ファーストインパクトから十五年後」に変更されているが(繰り返すが『Q』と『破』の間に「二〇一五年」は過ぎてしまった)、二〇一五年にマリは三十三歳。それから十四年後には四十七歳ということになる。もちろん、こんな計算には何の意味もない(それに「夏色のエデン」のユイは最初から「碇ユイ」であり、ゲンドウは「六分儀ゲンドウ」と呼ばれている。おそらく世界線が別なのだ)。
意味があるのは、マリがシンジの父ゲンドウを君づけで呼べる存在、その意味では(年齢差はあれど)シンジの母ユイと同等の立場なのだということである。つまり真希波・マリ・イラストリアスは、ゲンドウの妻であり、シンジの母であるユイ、物語の最初から不在であり、にもかかわらずすべての物語の作動因でもあり、ゲンドウがゼーレから奪取して私有化する「人類補完計画」の核心であるユイの代補として投入されたのである。もっとはっきり言えば、マリはシンジの新にして真の恋人、シンジの妻、シンジの子を産む母となるために、ただそのためだけに「作者」によって、庵野秀明によって創造、いや、捏造され、いわば正真正銘の「最後の使徒」として、颯爽と「エヴァ」の世界に送り込まれたのだ。
『シン』の後半に冬月がマリを「イスカリオテのマリア」と呼ぶ場面がある。「イスカリオテのユダ」と「マグダラのマリア」を合体させた、これまた意味性に満ち満ちたワードだが、そこからどれほど膨大な蘊蓄や豊饒な参照系が導かれるにせよ、それはただのブラフに過ぎない。ひとつだけ確かなことは、マリがやってこなければ「エヴァ」はけっして終われなかっただろうということである。これは『シン』を観終わった者ならば誰もが首肯するに違いない、歴然たる事実である。父ゲンドウが妻ユイを取り戻し、息子シンジが妻マリを得るまでの物語、それが『シン・エヴァンゲリオン』なのだ。そして遡行的に「エヴァ」という巨大なサーガの大団円も、この構図へと収束することになる。
では、あらためて問おう。これはいったい何なのか? この終わりが意味するものは何か? 結局のところ、これはどんな物語だったのか? そして、本当にこれでよかったのか?
7。エヴァに乗らないしあわせ
碇ゲンドウは「世界を滅ぼすのは簡単だが、世界を造り直すのは難しい」と言った。碇シンジは「エヴァに乗って世界を変えるんだ」と言った。では世界は造り直されたのか、世界は変わったのだろうか?
確かに変わる。だが、どのように?
『シン』の終盤、ゲンドウは「すべての始まり、約束の地、ひとの力ではどうにもならない運命を変えることができる唯一の場所」であるところの「ゴルゴダオブジェクト」で、彼の「人類補完計画」の最終段階としての「アディショナルインパクト」を起こそうとする。そこは「マイナス宇宙」であり、LCLによって人間に認知可能な仮想世界が形成されているとされる。父は息子に「私の妻、お前の母」も、ここにいたのだと告げ、初号機を渡せば母に会えると言う。
アディショナルインパクトはゴルゴダオブジェクトでしか起こすことが出来ないとゲンドウは言う。そこで登場する最後のエヴァが「エヴァンゲリオンイマジナリー」である。名前の通り、それは「虚構と現実を等しく信じる生き物、人類だけが認知できる」「想像上の、架空のエヴァ」である。エヴァ初号機の希望の槍と13号機の絶望の槍が互いにトリガーとなり、「虚構と現実が同一化する」ことによって「自分の認識=世界を書き換える」のがアディショナルインパクトである(らしい)。ミサトはそれを食い止めるべく急造された「第三の槍」を携えて独りマイナス宇宙へと赴き、そこで殉死を遂げるだろう。
もちろん私は、ここでも「考察」に踏み込むつもりはない。重要な点は、これ以降の『シン』が、ある意味でテレビシリーズの最終二話にも似た内面世界に没入してゆくということである。ゲンドウは「マイナス宇宙」を「記憶の世界」とも呼ぶ。記憶とは事実としての過去のことではない。それはどうしても想像で補うしかない。だからエヴァイマジナリーは、おそらくエヴァアナムネーシスでもあるのだろう。その場所は「人類のフィジカルもメンタルもひとつに溶け合った世界」であり「浄化された魂だけの世界」であり、そして「ユイと私が再会できる、やすらぎの世界」なのだとゲンドウは呟く。人間嫌いで、けっして裏切ることのない知識とピアノだけが友の代わりだった若きゲンドウを変えたのがユイだった。彼女は彼の子を妊娠し、名前は「男だったらシンジ、女だったらレイ」にしたいと言った。親の愛情を知らない自分が親になることへの不安もユイが消し去ってくれた。生まれたのは男の子で、だからシンジと名づけられた。だがユイはその後、不幸な事故で死んで(?)しまった。ゲンドウはシンジを「私への罰」と捉え「子どもに関わらないことがユイへの贖罪」だと考え、つらく当たった。それでもシンジをNERVに呼び寄せてエヴァに乗せたのは「ユイの再構成にシンジが必要か否か」わからなかったからだとゲンドウは言う。「ただユイの胸で泣きたかった、ただユイの傍にいることで自分を変えたかった」と嘆くゲンドウは、それまでの非情で冷酷なイメージを一変させ、人間的な脆さを露わにしている。
「私は私の弱さゆえにユイに会えないのか」と自問するゲンドウに、そこにずっと一緒にいたシンジは「弱さを認めないからだと思うよ」と答える。そう、これまでのシンジは過去のゲンドウなのであり、だから未来のシンジはこれまでのゲンドウになるかもしれなかったのだ。だがシンジが変わったことで、ゲンドウも救われることになる。ミサトの死を受け止めてみせたシンジに、ゲンドウは「大人になったな」と言う。以前なら考えられなかったことだが、父は息子に「すまなかった」とさえ口にする。ゲンドウの物語は、「そこにいたのか、ユイ」という一言で終幕となる。おそらくゲンドウの「人類補完計画」は失敗に終わった。だが、彼の願いは叶えられたのだ。
突然、もういないはずの渚カヲルが現われて「ここからは僕が引き継ぐよ」と宣言する。カヲルはシンジに「イマジナリーではなく、リアリティで立ち直っていたんだね」と言う。ここから『シン』は「エヴァ」の登場人物たち、それぞれの最後の物語を語り始める。エヴァに乗ることだけが自己承認の手段だったアスカ。シンジは彼女に「アスカはアスカだ」と言う(これはアヤナミレイ(仮)への「綾波は綾波だ」と同型の台詞である)。僕を好きだと言ってくれてありがとう、とシンジはアスカに言う。「僕もアスカが好きだったよ。さよなら、ケンスケによろしく」。第3村でアスカはケンスケの家に居候していたが、シンジのこの言葉は二人が同居人以上の関係になり得る可能性を示唆している。「今度は君の番だ、カヲル君」とシンジは言う。カヲルがシンジの理想像であることはすでに述べたが、ここでシンジは「カオル君は父さんと似てるんだ」と言う。そして「もう泣かない」と約束し、カヲルは「そうか、君はもう成長してたんだね」と応じる。そこにやはり死んだはずの加持リョウジが現われ、カヲルを「渚司令」と呼んで「あなたはシンジ君をしあわせにしたかったのではなく、それによってあなたがしあわせになりたかったんです」と指摘する。加持は「葛城と一緒に老後は畑仕事でもどうですか?」とも言う。こうして生きているひとも死んでいるひとも、皆が皆、救いを与えられてゆく。次はもちろん綾波レイである。もうひとりの綾波だったレイ(仮)は(第3村で)自分の居場所を見つけた、だから君も、ここではない場所でしあわせを見つけてほしい、とシンジは言う。「ここではない場所のしあわせ」、それは「エヴァに乗らないしあわせ」である。
エヴァに乗らないしあわせ、これこそ「エヴァ」シリーズを閉じる魔法の呪文である。シンジは言う。「僕もエヴァに乗らない生き方を選ぶよ、時間も世界も戻さない、ただエヴァがなくてもいい世界に書き換えるだけだ」。それは「世界の新たな創世=ネオン・ジェネシス」と呼ばれる。長い長い物語の、今度こそ最後の大団円が、遂にやってくる。「そうか、この時のためにずっと僕の中にいたんだね、母さん」とシンジは言う。「父さんは母さんを見送りたかったんだね、それが父さんが願った神殺し」とシンジは言う。そして、あの決定的な一言が口にされる。さようなら、すべてのエヴァンゲリオン。
エヴァに乗らないしあわせの世界とは、エヴァが存在しない世界、いや、エヴァだけが存在していなかったことにされた世界のことである。シンジが言うように、時間も世界も戻されるわけではない。ただ、エヴァ以外ののあらゆるものたちが、エヴァが存在したせいでその存在を無くしてしまった者たちも含めて、何もかも回復され、回復ということさえ消去される。エヴァを忘却した世界、それはつまり、これまでのすべての物語が完璧に忘れ去られた世界である。だが、それまでのすべての物語によって齎された主人公の成長と成熟は忘却も消去もされていない。こうして碇シンジは、十四年+十四年、すなわち二十八歳の青年に変身するのである。『シン』の真のラストシーン、駅ホームのベンチで恋人マリと待ち合わせたシンジの声は、緒方恵美から神木隆之介に変えられている。二人は手に手を取って駅を出て、街へと、外へと、駈け出してゆくだろう。その光景は、アニメではなく、ほとんど実写に見える。
これが『シン・エヴァンゲリオン劇場版』の、そして「エヴァンゲリオン」シリーズ全編の結末である。登場人物たちが次々と現れる展開は、確かにテレビシリーズの最終二話を彷彿とさせる。最後にエヴァのいない世界が現出するところも同じである。だが、あのときはシンジが煩悶と懊悩の果てに「僕はここにいてもいいんだ」という自己肯定に辿り着き、皆から一方的に「おめでとう」と言われて「ありがとう」と返す、という極端に強引な終わらせ方であったのに対し、今回はむしろシンジのほうが登場人物たちに「ここにいてもいい」のだと祝福し、そのことによって自分が大人になったことを証明する、という終わりになっている。この違いはやはり重要である。マリがかいだシンジの体臭は、大人の男のものになっている。あたかも彼女は、その変化を証立てるためにのみ登場したかのようだ。マイナス宇宙に彼女が出て来ないのは、そこで問題にされ得るような内面を最初から持っていないからである。何故ならマリは、イマジナリーではなく、リアリティの側の存在であるからだ。
ビルドゥングス・ロマンとしての「エヴァ」は、かくして幕を閉じた。テレビシリーズから四半世紀、三十五歳だった庵野秀明は今では還暦を超えている。まさかこれほど長く掛かるとは思ってもみなかっただろう。だがおそらくは、いや、間違いなく、これだけの時間が流れたからこそ、あのような結末になったのだ。
碇シンジは、成熟の年齢に達したのだろうか? それが何歳のことであれ、『シン』の結末が示しているのは、そして「エヴァ」のすべての結末が示しているのは、答えはイエスだということだろう。冬月は「自分と同じ喪失を体験させるのは、息子のためか、碇」と言っていた。それはもっぱら綾波レイのことを指していたのだと思われるが、実際にはレイの(アスカの? ミサトの? カヲルの?)代わりに真希波マリが投入されたことによって、父ゲンドウと同じ致命的なまでの喪失は鮮やかに回避され、息子シンジの世界は補完されることになる。言い換えるならそれは、シンジがマリのような大人の女性と結ばれるに相応しい大人の男性へと成長を遂げた、ということである。最後の出動の前に、アスカはシンジに「私がなぜあんたを殴ろうとしたか、わかる?」と問いかける(そういう場面があったのだ)。シンジは、自分で責任を負いたくなくて、何も決めなかったからだ、と答える。でも今はそうではない、ということがシンジの態度からは窺える。それを聞いたアスカは、自分よりも遅れてではあるが、いつの間にかシンジも大人になっていたことを理解する。
考えるべきは、このように他の登場人物たちからも承認され、彼自身も自覚的な碇シンジの「成熟」が、冬月の言うような「喪失」によって齎されたのではないとするなら、いったい何が彼を大人にしたのか、ということである。『シン』の結末に至る「エヴァ」のすべての物語をあらためて辿り直してみても、この疑問に対する明確に説得的な解答は得られない。まさに、いつの間にか、としか言いようがないのだ。敢て率直に述べてしまうなら、この問いへの答えは要するに、碇シンジよりも先に庵野秀明が大人になっていたから、ということ以外にはない。そして、それは紛れもない事実なのだ。だが繰り返しになるが、シンジが遂に「成熟」を迎えた、ようやく真の意味で「大人」になったということは、彼が「大人」の女性であるマリを獲得したことが示されるラストシーンから遡行的に導かれるのであって、その逆ではない。ここには明らかに一種のパラドックスが覗いている。シンジがマリと恋愛関係を結ぶに至るプロセスは、まったく描かれることがない。いや、それを描くわけにはいかないのだ。何故ならば、そこにはプロセスなど存在していないからである。レイがシンジに好意を抱くようにあらかじめプログラミングされていたのだとするなら、マリはそうではないと誰に言えるのか(マキナミシリーズ?)。だがしかし、この当然の疑念が検討されることは、もはやけっしてないだろう。もう「エヴァ」は完結してしまったからだ。私たちはただ、あの終わりを、すべての終わりとして、そのまま受け入れるしかない。そして実際のところ、あの結末は、これ以上ないほどに完璧なハッピーエンドだったのではあるまいか?
こうしてひとまず、私の『シン・エヴァンゲリオン』論は幕を閉じる。だがもちろん、考えてみたいことはまだまだ沢山残っている。遠からず私は私の「庵野秀明論」を再起動することになるだろう。それは庵野という一個人の問題に留まらず、戦後日本に宿り、或る一貫性を保ちつつも刻々と変化してきた時代や社会や国家などなどの心性を、稀代の表現者である「庵野秀明」と、その(「エヴァ」以外も含む)作品群を通して、あらためて問い直す作業になるはずだ。それは一風変わった「文芸評論」になるであろうと予告しておく。キーワードは、もちろん「成熟」である。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
