数学の偉人と歴史
●古代エジプトの測量。
●前625-前546 タレス
哲学者、数学者
万物の根源(アルケー)は水だと説いた。
タレスの定理(半円に内接する角は直角である)。

● 前582-前496 ピタゴラス
52歳からピタゴラス学派(ピタゴラス教団)を設立。整数のみを信じ、無理数を信じなかった。秘密主義で戒律を破れば海に沈められた。
・ピタゴラスの定理(三平方の定理)
a^2+b^2=c^2

・10は完全な数とした。1+2+3+4=10で、これらを使い三角形を描けるからである。この図形をテトラクテュスと呼ぶ。

・ピタゴラス音律。弦の長さが整数比(3:2)だと和音になる。
・名言「万物は数である」。コスモス(秩序)という語を宇宙という意味で用いた最初の例。また哲学(フィロソフィア)という語を最初に用いた。
● 前323-283 アレクサンドリアのエウクレイデス(ユークリッド)
『原論(ユークリッド原論)』…ユークリッド幾何学。五つの公準が原則。
● 前287?-前212 (シラクサの)アルキメデス
浮力、てこの原理、アルキメデス機械
・アルキメデスの原理。王が職人に金の王冠を作らせた。王は銀を混ぜているのではと疑い、アルキメデスに証明を求めた。アルキメデスは風呂に入ると水が溢れ出すことから浮力の原理を発見し、天秤に金塊と王冠を吊るして水に沈め、純金の密度を計測した。
・アルキメディアン・スクリュー。王は大型の船を造らせた。浸水した水を掻き出すために螺旋状の円筒を回転させる方法を施した。
・アルキメデスの鉤爪。てこの原理を利用し、船の転覆をはかる装置。
・アルキメデスの熱光線。太陽光熱を複数のレンズで反射させ、一点に集めることで船を炎上させる装置。
・取り尽くし法を駆使して円周率を求めた。
・『砂粒を数えるもの』…宇宙を埋め尽くすのに必要な砂粒の個数を計算した。10^63よりも少ない。
212 第二次ポエニ戦争にてローマ軍に殺害される。(将軍はアルキメデスを殺害しないよう兵士に命じたが、兵士が名前を聞いても無視しため殺害されたという。最期の言葉は「図を壊すな」)。

● 83頃-168頃 クラウディオス・プトレマイオス
150 『アルマゲスト』…天動説
トレミーの定理

● 200頃-284頃 ディオファントス
代数学の父
『算術』…全13巻からなるが、戦禍にさらされ6巻のみ残った。フェルマーはこの本の余白に最終定理などを書き込んだ。
・ディオファントスの墓碑にある一次方程式の問題
「一生の1/6は少年時代だった。また、一生の1/12はあごひげを生やした青年だった。さらに一生の1/7を独身として過ごしてから結婚し、 その5年後に子供が生まれた。その子供は父より4年前に父の半分の年齢でこの世を去った」。


A. 84歳
● 598-665 ブラフマグプタ(インド)
628『宇宙の始まり』…0の概念を発明
● 800-850 フワーリズミー(アラビア)
アルゴリズムの語源
● 1170-1250 レオナルド・フィボナッチ(伊)
フィボナッチ数列(黄金比)
1202 『算盤の書』アラビア数字をヨーロッパに輸入
◆15c-17c 計算師の活躍。計算を早めるために様々な記号が考案された。
● 1473-1543 ニコラウス・コペルニクス(ポーランド)
天文学者
1543『天体の回転について』…地動説を基に天体観測を行った。
● 1501-1576 ジェロラモ・カルダーノ(伊)
確率論の父。
1545『偉大なる術(アルス・マグナ』
三次方程式の解を初めて発表し、虚数の概念を提唱した。
1663『サイコロあそびについて』
名言
「ギャンブラーにとっては、全くギャンブルをしないことが最大の利益となる」。
◆ 1517 マルティン・ルターの『95ヶ条の論題』。宗教改革のはじまり。
● 1550-1617 ジョン・ネイピア(スコットランド)
1614 ネイピアの対数
1618 ネイピア数…自然対数の底
● 1564-1642 ガリレオ・ガリレイ(伊)
天文学、物理学
1589 ピサの斜塔での実験。落下の法則を発見。
1597 ケプラー宛の手紙で地動説を支持する表明。
1609 望遠鏡を改造し、天体観測を行う。
1610 『星界の報告』。木製の3つの衛星を発見。ガリレオ衛星と呼ばれる。
1613 『太陽黒点論』
1616 第一回目の裁判で有罪判決。以後地動説を唱えないよう命じられる。教皇庁はコペルニクスの地動説の書を閲覧禁止にする。
1632『天文対話』…地動説の解説。
1633 第ニ回目の裁判で再び有罪判決、異端を認める。終身刑を言い渡されるが、直後に減刑される。名言「それでも地球は動く」。
1638 『新科学対話』
● 1571-1630 ヨハネス・ケプラー(独)
天文学
1596 『宇宙の神秘』…コペルニクスの地動説を支持。
1609 ケプラーの法則…惑星の楕円軌道。
● 1596-1650 ルネ・デカルト(仏)
1637『方法序説』…コギト・エルゴ・スム、デカルト座標
1641『省察』
1644『哲学原理』
1649『情念論』
● 1607-1665 ピエール・ド・フェルマー(仏)
裁判官
1670「フェルマーの最終定理」。彼の読んだディオファントス著『算術』の余白に書き込まれていた、x^n+y^n=z^nとなる3以上の自然数の組み合わせは存在しないという予想。フェルマーの死後、『算術』の余白に書き込みありの『算術』を息子が出版したことで彼の問うた数学的難問の数々が世に明るみに出た。最終的に証明に至らずに残った難問がフェルマーの最終定理であった。

◆ 1618-1648 三十年戦争(旧教vs新教)
● 1620-1674 ジョン・グラント(英)
商人。統計学の父。
1662『死亡表に関する自然および政治的観察』、ペティと共著。
ペスト禍に見舞われたロンドンで、教会の過去60年分の死亡表を統計的に分析した。
ウィリアム・ペティは友人。
● 1623-1662 ブルーズ・パスカル(仏)
1640『円錐曲線試論』(パスカルの定理)
1642-52 機械式計算機の製作
1655『パスカルの三角形』
1656-57『プロヴァンシアル』…匿名でジャンセニスムを擁護
1669『パンセ』…人間は考える葦である、パスカルの賭け(神の存在証明)
パスカルの原理(流体力学)、確率論


● 1632-87 ウィリアム・ペティ(英)
1690『政治算術』
経済学に初めて統計学的な手足を取り入れた。グラントの友人。
● 1642-1727 アイザック・ニュートン(英)
1665-1666 ペストの流行で大学閉鎖になり研究に没頭した。
・流率法(後の微分積分学)…ライプニッツと先取権をめぐり論争
・万有引力(後のニュートン力学)
・プリズムでの分光の実験、光の粒子説、光のスペクトル…ロバート・フックと論争
1671 『無限級数の解析』『流率の級数について』…微分積分法
1672 王立協会会員
1668 ニュートン式望遠鏡
1669 ケンブリッジ大学の教授になる
1687『自然哲学の数学的諸原理(プリンキピア)』
・ニュートン力学(古典力学、万有引力の法則)
・ニュートンの運動3法則(慣性の法則、運動方程式、作用反作用の法則)
・実証科学の方法論
1690『ダニエル書と聖ヨハネの黙示録の預言についての研究』…カトリック教会の堕落した800年+1260年=2060年に終末が来ると預言
1699 王立造幣局長官
1703 王立協会員会長
1704『光学』
1727 死去
1728『改訂古代王国年代学』
1754『二つの聖句の著しい変造に関する歴史的記述』…三位一体論の否定
錬金術による水銀の使用が判明している
● 1646-1716 ゴットフリート・ライプニッツ(独)
1684 微分の確立
1686 積分の確立
※ニュートンの盗作と疑われた論争したが、ニュートンとは独立して発見したものと認められている。
1685『形而上学序説』
1710『弁神論』(神義論)…神の義とこの世に悪が存在する理由について。
1714『モナドロジー』…モナド論
● 1656-1742 エドモンド・ハレー(英)
1693 統計学を用いて生命保険制度を創設
1705 1758年に彗星が来ることを預言し的中させる
● 1690-1760 クリスティアン・ゴールドバッハ(プロイセン)
1742 ゴールドバッハ予想
彼がオイラーに宛てた書簡による。
4以上の全ての偶数は、二つの素数の和で表すことができる。
現在も未解決。

● 1700-1782 ダニエル・ベルヌーイ
流体力学、統計学、確率論
● 1702-1761 トーマス・ベイズ(英)
ベイズの定理…条件付き確率。後にラプラスはベイズの定理を数式で定義し、ベイズ統計学の基礎を作った。
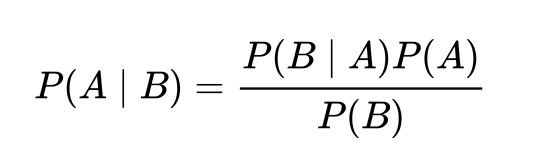
● 1707-1783 レオンハルト・オイラー(スイス)
計算の天才。盲目になっても計算を続けた。
1736 「ケーニヒスベルクの七つの橋問題」(一筆書き可能か)を幾何学的に説いた。これが位相幾何学(トポロジー)の始まりと見なされている。
1753 フェルマーの最終定理は、n=3の場合は存在しないことを証明
・オイラーの等式、e^iπ+1=0
「人が息をするように、鳥が空を飛ぶように、オイラーは計算をする」と評される。
● 1736-1813 ジョゼフ・ルイ・ラグランジュ(伊)
1788『解析力学』…ラグランジュ力学…ニュートン力学を再定式化した解析力学。
● 1749-1827 ピエール・シモン・ラプラス(仏)
1799-1825『天体力学概論』
1812『確率の解析的理論』…ラプラスの悪魔
1814『確率の哲学的試論』…古典的確率論
ベイズの定理を数式で定義し、ベイズ統計学の基礎を作った。
● 1759-1823 ウィリアム・プレイフェア(英)
エンジニア、政治学者
統計グラフの発明
1786 折れ線グラフ、面グラフ、棒グラフ
1801 円グラフ
● 1768-1830 ジョセフ・フーリエ(仏)
1822『熱の解析的理論』
フーリエ変換

● 1775-1856 ボーヤイ・ファルカシュ(ハンガリー)
非ユークリッド幾何学の提唱者の一人であるボーヤイ・ヤーノシュの父親。
彼は平行線公準の研究をしたが証明できなかった。
息子はこれを反駁できないものとした。
1832年、彼は息子の論文を自著の付録に付けたが、ガウスは公表しなかった。
● 1776-1831 ソフィ・ジェルマン(仏)
女性のため偽名を用いてガウスらと文通していた。
1825 フェルマーの最終定理はn=5の時に成り立つことを証明。
1839 n=7の時も成り立つことを証明。
● 1777-1855 カール・フリードリヒ・ガウス(独)
9歳 算数の授業で教師が1から100までの数字を全て足せ」という問題を出したところ、101×50=5050と数秒で答えた。
1796 コンパスと定規のみで正17角形の作図法を発見。
1801『ガウス整数論』
1809『天体運行論』…最小二乗法
1811 複素数平面(ガウス平面)
1827『曲面の研究』…微分幾何学、ガウス曲率
◆ 1789-1799 フランス革命
● 1789-1857 オーギュスタン・ルイ・コーシー(仏)
解析学。フランスのガウス。
ニールス・アーベルやエヴァリスト・ガロアの論文の審査を引き受けながらその論文を紛失した。
● 1792-1856 ニコライ・ロバチェフスキー(露)
非ユークリッド幾何学の提唱者。
1829 『幾何学の新原理並びに平行線の完全な理論』(双曲線幾何学)
◆ 1793 メートル法の制定
● 1802-1860 ボーヤイ・ヤーノシュ(ハンガリー)
非ユークリッド幾何学の提唱者の一人。
ボーヤイ・ファルカシュの息子。
父の反対にめげずに父の平行線公準の研究を継ぎ、父の著書の付録に自分の論文「空間論」を掲載してもらう。
しかしガウスに評価されず、研究をやめてしまった。
● 1802-1829 ニールス・アーベル(ノルウェー)
1824 アーベル-ルフィ二の定理…5次以上の方程式は代数的に解けないことを発見。
1828 楕円関数
● 1811-1832 エヴァリスト・ガロア(仏)
ガロア理論(群論)の論文が二度も紛失させられた(コーシー、フーリエにより)ことで失望し、政治活動を強め、悪態をついて投獄される。女性関係のトラブルで決闘を申し込まれ、遺書に理論の着想が書き残される。決闘により21歳で死去。
● 1815-1864 ジョージ・ブール(英)
ブール代数(ブール論理)…コンピュータ科学の基礎
● 1821-1894 パフヌティ・チェビシェフ(露)
確率論の基礎を確立。
1867 チェビシェフの不等式…確率論の定理。
● 1823-1891 レオポルト・クロネッカー(独)
カントールの集合論を攻撃し、人格非難までした。
「自然数は神の作ったものだが、他は人間の作ったものである」
● 1826-1866 ベルンハルト・リーマン(独)
1854 リーマン幾何学(非ユークリッド幾何学)
1859 リーマン予想
素数の分布について。現在も未解決。
● 1831-1879 ジェームズ・クラーク・マクスウェル
1864 古典電磁気学
● 1831-1916 リヒャルト・デデキント(独)
1855 ガロアのガロア理論の最初の講義を行う。
1872 『連続性と無理数』…デデキント切断。実数論の基礎づけ。
1888 『数とは何かそして何であるべきか』…鎖。自然数論の基礎づけ。
● 1845-1918 ゲオルク・カントール(独)
1874 集合論、対角線論法で無限の存在を証明
1877 カントール、連続体仮説を提示
● 1848-1925 ゴットロープ・フレーゲ(独)
1879『概念記法』、述語論理、記号論理学(数理論理学)
● 1854-1912 アンリ・ポアンカレ(仏)
位相幾何学(トポロジー)
1904 ポアンカレ予想

ヒルベルトの形式主義に反対して直観主義を支持した。
● 1857-1936 カール・ピアソン(英)
数理統計学
● 1862-1943 ダフィット・ヒルベルト(独)
1900 ヒルベルト・プログラム(ヒルベルトの23の問題)、形式主義
● 1871-1953 エルンスト・ツェルメロ
1908 集合論の公理化
● 1872-1970 バートランド・ラッセル(英)
1901 ラッセルのパラドックス
フレーゲの記号論理学について矛盾を指摘
1903 タイプ理論
1911-13 ラッセルとホワイトヘッド、『プリンキピア・マテマティカ(数学原理)』
◆ 1875 国際度量衡連盟が設立される
● 1879-1955 アルベルト・アインシュタイン(独)
物理学
1905 特殊相対性理論
1915-16 一般相対性理論
● 1881-1966 ブラフワー(オランダ)
数学基礎論における直観主義。
◆ 1884 万国子午線会議が開かれる
● 1887-1920 シュリニヴァーサ・ラマヌジャン(インド)
3500以上もの定理を発見
タクシー数
● 1890-1962 ロナルド・フィッシャー(英)
推計統計学(推計学)の確立者。
1930 『自然選択の遺伝学的理論』…突然変異と自然選択説を融合、総合説の成立。
● 1891-1965 アドルフ・フレンケル
1922,1925 ツェルメロの公理系を改良、公理的集合論(ZF)の確立
◆ 1897〜 国際数学者会議(ICM)
第1回はスイスのチューリッヒで開催しれた。4年に一度開催される。開会式では、フィールズ賞、ネヴァンリンナ賞(2022〜、IMUアバカス・メダルに改称)、ガウス賞、チャーン賞が授与される。
● 1903-1987 アンドレイ・コルモゴロフ(露)
1933『確率論の基礎概念』…公理的確率論
● 1903-1957 ジョン・フォン・ノイマン(オーストリア・ハンガリー)
1944『ゲームの理論』…経済学の原理を数学で説明する。ゲーム理論。
ノイマン型コンピュータ
京都に原爆を落とそうと考えていた
● 1906-1978 クルト・ゲーデル(オーストリア・ハンガリー)
1930 一階述語論理の完全性定理
1930 第一不完全性定理、第二不完全性定理
これによりヒルベルト・プログラムは崩壊
1940 カントールの連続体仮説は反証も証明もできない
● 1906-1998 アンドレ・ヴェイユ(仏)
哲学者シモーヌ・ヴェイユは妹
1935 架空の数学者団体ブルバキを結成し、『数学原論』(1939)を刊行する。
1949 ヴェイユ予想
● 1909-1984 スタニスワフ・ウラム
マンハッタン計画に従事、水爆の発案者
モンテカルロ法…シュミレーションを乱数で行う手法
● 1909-1945 ゲルハルト・ゲンツェン(独)
1934 シークエント計算
1935 自然演繹
● 1912-1954 アラン・チューリング(英)
同性愛者、無神論者、アスペルガーの疑い
1936 論文『計算可能な数について』、チューリングマシン考案。コンピュータの原理の発明とと言える。
1938 ブレッチリー・パーク(のHut8)にてナチス・ドイツ軍のエニグマ(暗号機)の解読に従事。
1940 暗号解読機「ボンブ」を発明し、ドイツ軍の暗号解読に成功する。解読された機密情報はウルトラと呼ばれた。ドイツ軍は暗号が解読されているとは知らずにイギリス軍の掌の上で戦い続け、イギリス軍を勝利に導いた。
1941 同僚のジョーン・クラークと婚約するが結婚には至らなかった。
1950 チューリング・テスト(イミテーション・ゲーム)を考案。ある機械が人間的かを判定するテスト。
1952 チューリング・パターン。反応拡散系。自然や生物が作り出す模様の仕組みを説明する理論。
1952 関係を持った男娼が、泥棒にチューリングの自宅を荒らすよう画策したことで、同性愛が発覚し、同性愛容疑で逮捕され、離職、女性ホルモン治療を受けさせられる。
1954 青酸カリで自殺と断定される。齧りかけのリンゴが落ちていた。
◆ 1914-1918 第一次世界大戦
● 1916-2001 クロード・シャノン
1948 情報理論
情報理論の父
● 1917-1998(日) 岩澤健吉
1959 岩澤理論
この理論がフェルマーの最終定理の証明に貢献した。
● 1927-1958(日) 谷山豊
● 1930-2019(日) 志村五郎
1955 谷山・志村予想
「全ての楕円曲線はモジュラーである」
この理論がフェルマーの最終定理の証明に貢献した。
● 1928-2014 アレクサンドル・グロタンディーク(独)
スキームの考案による代数幾何学の大幅な書き直し。
1960代『代数幾何学原論』
講義の際誤って57を素数の例として出し、「グロタンディーク素数」と呼ばれた。
グロタンディーク宇宙
エタール・コモホロジーの発見によるヴェイユ予想への貢献。
● 1928- ヴォルフガング・ハーケン(独)
1976 四色定理を証明
● 1934-2007 ポール・コーエン
1963 ZFC(公理的集合論+選択公理)と連続体仮説は独立であることを証明。
● 1935- ニコラ・ブルバキ(数学者団体による架空のペンネーム)
1939『数学原論』…集合論の上に現代数学を打ち立てることを目標にする。
◆ 1936 フィールズ賞設立
メダルにはアルキメデスの肖像が彫られている。
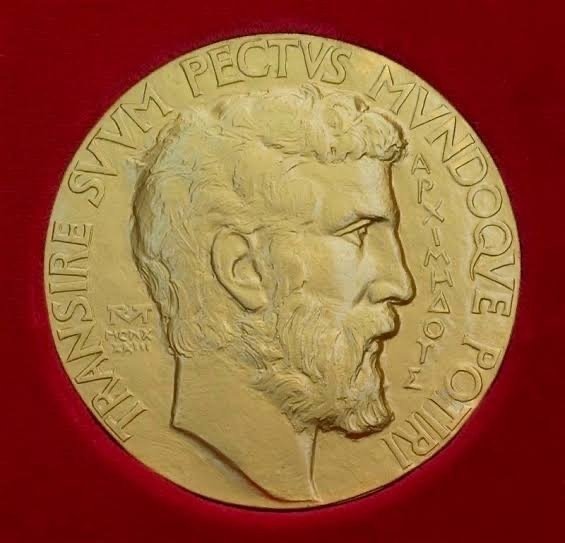
● 1940- ソール・クリプキ(米)
分析哲学、論理学
1972『名指しと必然性』様相論理、クリプキ意味論(可能世界意味論)
● 1944-(独) ゲルハルト・フライ
フライ曲線
1984 背理法により、谷村・志村予想が証明されればそれはフェルマーの最終定理が証明されたことも意味することを発見。
● 1944- ピエール・ドリーニュ(ベルギー)
1974 ヴェイユ予想を証明
● 1953- アンドリュー・ワイルズ(英)
1986 フェルマーの最終定理の研究を開始し、引きこもる。
1993 フェルマーの最終定理の証明を発表。しかし査読で不備が見つかり、一度手放した岩澤理論を使って証明を完成できた。
1995 査読を通り、証明を完成させる。
● 1948- ディビッド・マッサー(英)
● 1954- ジョゼフ・オステルレ(仏)
1985 ABC予想

● 1957- ナレンドラ・カーマーカー(インド)
1988 カーマーカーのアルゴリズム(カーマーカー法)…線形計画問題の多項式時間解法の理論化。特許を取得している。
● 1966- グリゴリー・ペレルマン(露)
2002、2003 ミレニアム懸賞問題のポアンカレ予想を証明
2006 フェールズ賞を辞退
2010 ミレニアム賞を辞退
現在はマスコミを避けてスウェーデンでキノコ狩りをしている。
● 1969- 望月新一
京都大学教授
2012 ABC予想を証明する、宇宙際タイヒミュラー理論を発表
2020 長期の査読を経て論文が掲載される
◆ 2001 アーベル賞設立
ニールス・アーベルにちなむ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
