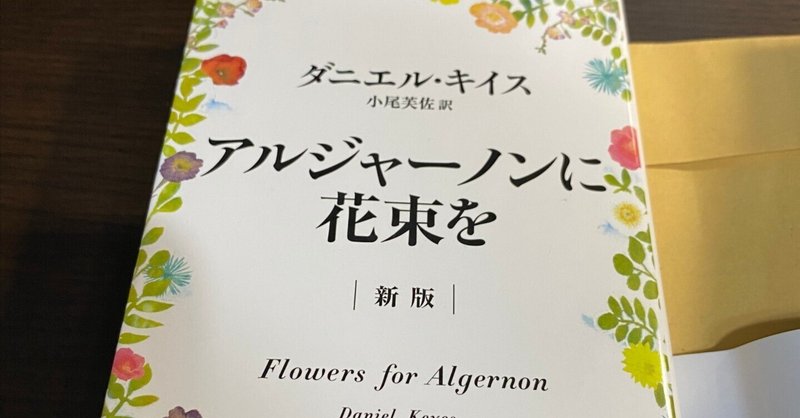
『アルジャーノンに花束を』感想
定期的に耳にするこの作品。
先日SNSでバズっていて、この際だから手にしてみたいと古本屋で探し続けていた作品を、ついこの間新宿の書店で見つけた。
あらすじも知らずに完全初見で読み始めた訳だが、前提知識皆無で読めたことは、結論として非常に良かったと思う。一行目からの異様な書き出し、手術成功の如何など、序盤から先を予想し裏切られを繰り返し、刺激を受けながら読むことが出来た。
やはり一番ショッキングだったのは、「アリス」が「キニアン先生」に戻ってしまう学校での場面。場面展開の示唆が丁寧に描かれ、ある程度推測をしながらページをめくっていけるこの作品の中で、このシーンは大きな衝撃を受けた。
半分までは4日ほどに分けて少しずつ読み進めていたが、半分から先は平日のド真ん中にも関わらず一気に読み切ってしまった。
本当に良い作品だったと思う。
最近のアニメ作品は導入やキャラ設定に新鮮さを感じられても、回が進むにつれ自然と「ああ、あの作品の系譜か」となることが本当に多い。
この作品のテーマは僕の脳内ライブラリにはなかったので、全く新しい経験だった。
それでいてチャーリィと自分が重なる場面も多く、主人公の考えや在り方が独り歩きしていかなかった点も嬉しい。
また他人の感想を漁る中で、これがいわゆるSFジャンルの作品であることに初めて気付いた。構成の妙によるものか、心理描写の巧みさによるものか、決して突飛で非現実的な話には見えなかった。
満足した豚か、不満足な人間か。
「知的障害の自分も確かに人間だった」と主張するこの作品においてこの言葉を引き合いに出すのは不適切極まりない。
とは思うが、私が常に思考を巡らせているこのテーマと本作品は、個人的に切っても切り離せない。
常に私は後者でありたいと考えている。劣等感に苛まれ続けるとしても、現状に甘んじて日々を過ごすような存在ではいたくない。
そしてチャーリィも同じ考えを持っていた。
優しくて素直だった、友達にも恵まれていた昔のチャーリィに戻るのは怖いと彼は言っていた。
「結局は素直で明るく優しいのが一番」、そんな美辞麗句を跳ね除けるのがこの作品の好きなところだ。
結局のところ持たざる者は哀れであり、そこは徹底して生まれながらに不平等で救いは無い。
理解も浅いままに自分の中だけでグルグルと回っているミルの言葉。
いずれしっかり誰かと話し合ってみたい。
最近は専らアニメとビジネス本ばかりだったので、小説を読む楽しさを久しぶりに思い出した(本当に久しぶりで、下手したら10年以上ぶりかもしれない)。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
