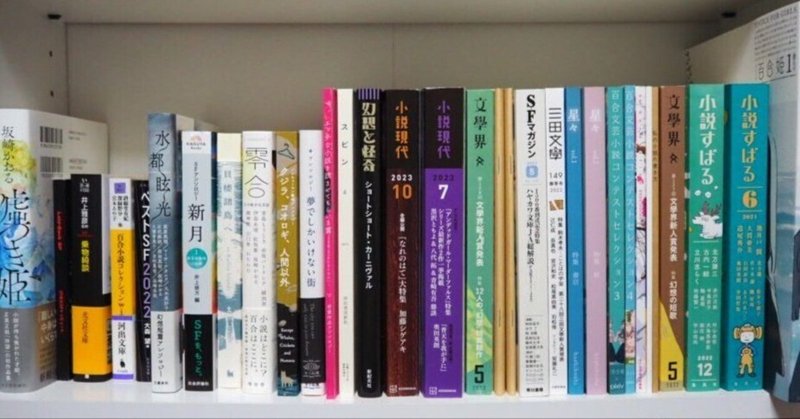
さかさ近況㊳
『嘘つき姫』発売から一週間ほど経ちました
おかげさまで、多くの方に手にとってもらえている。毎日感想が読めるなんて、最高じゃあないですか…
インタビューや書評もぽつりぽつり出ている。
お好みの作品が人それぞれなのもうれしい。その中でも、書き下ろしの「私のつまと、私のはは」が評価されているのもうれしい。これは、初めは雑誌のスピン用に書いたのだが、理由は細かく書かないがボツになったものだ(その後「ニューヨークの魔女」を書いた)。それを大幅に書き直し、正直かなりよくなっている。あのとき止めていた編集長はさすがだと思う。ちなみに作者的には、この作品集の中では「日出子の爪」がお気に入りである。
ありがたいことだが、ポジティブな感想が出ているうちは、「知ってる人」か「本をよく読む人」だけで、「ふだんあんまり読まない人」とかにも届いてほしいなあとも思う。読めばぜってー面白い!と、いつも思っているので、いかに手にとってもらえるか、がこれからの課題になるだろう。Please read it, Obama.
とはいっても、売り上げばかりが指標になるのは健康的によろしくないのも事実だ。みんなゆるゆるやってこうぜ。しょせんは文学の話だ…。
最近読んだもの、見たもの
併読していて、あまり読めていないのだが。
まずは松樹凛『射手座の香る夏』(東京創元社)が、予想にたがわず面白かった。松樹さんの作品はいくつか読んできたが、よい意味で理屈っぽいなと思った。アイデアやガジェットとしての理屈もそうだし、物語の整合性という意味での理屈としてもそうだ。だから、スパン、と決まるし、それを下支えする文章力があるから、エモーショナルに展開できる。私はこれができない(作者もふわふわしてるから…)。完成度、という点では表題作の「射手座の香る夏」が秀でていたが、個人的には「さよなら、スチールヘッド」が好み。少年少女の脱出劇みたいな話が好きなんで…。
冬乃くじ『猫の上で暮らす一族の話』(惑星と口笛ブックス)も読んだ。再読がほとんどだったが、こうして通して読むことで、「愛」がテーマなのではないか、と思った。「ハッピー・バースデー」でのイボ太郎への眼差し、「サトゥルヌスの子ら」の母への思い、「ある授業」の(おそらく)失われたであろう人への回顧。「愛憎」と書きたくなるが、不思議と「憎」は感じない(物語上はあるが)。みなどこか終着駅に座り、淡々と今までの人生を振り返っているような語り口で、短編集ながら、長い誰かのモノローグを聞いているような気分になった。こういうタイプの作品を書ける作家は少ないかもしれない。逆を言えば、「こうでない」冬乃作品も読みたいなあと思った。
大原鉄平「森は盗む」(小説トリッパー2024年春季号)も面白かった。設計士として働く「私」の視点から、腕は確かだが手癖の悪い大工の「よっちゃん」との関係を描く物語。まず、主人公自身が実際の建物を建てるわけでなく、「パソコンのディスプレイの中」だけでしか家を建てないという設定がよかった。建物の資材としての「森」、「檻」の対比としての「家」、人々の大切なものだけを盗む「よっちゃん」。それらを見つめる私は架空の「家」をつくる。この配置のバランスが見事で、非常に巧みだった。この均衡が見事だからこそ、最後のカタルシスがとてもよく効いたのだろう。人によっては、このバランスの良さが鼻につくのかもしれないが、私はとてもうまい作家だと思った。相川英輔「魔法をさがして」(スピン/spin7号)も、短いながら佳品だった。「魔法が使える」父親の言葉を信じた主人公が、自身の「魔法」を探す話。『青い鳥』を連想する、上質な童話のような世界観であった。草野理恵子「あしたば」(Call Magazine vol.55)は、よくわからないなあと思ったけど、わからないが心地よい詩。あしたばの葉はギザギザだなあと思いながら、ぴょんぴょん跳ねるウサギとあたたかい石を思うだけで、どうも安心する。笛宮ヱリ子「あとかた」(Call Magazine vol.54)も、ちょっとこわいけど、そんなに嫌な気持ちにならない話。こういう身体の話は好みです。
人文書系では、ヘンリー・ペトロスキー/池田栄一訳『本棚の歴史』(白水社)がべらぼうに面白かった。文字通り、本棚の歴史を書いたもの。当たり前の話だけど、今の表紙が合って小口があって…みたいな本のつくりは初めからではなく、最初は巻物だったわけだから、そのころ「本棚」ってあったんだろうかと気になったので読んだのだが、ほええという驚きがいっぱいあって面白い。本棚は書見台の発展という知見は興味深い。すごく面白かったので、そのうちそういう小説が出るでしょう…。そして、このヘンリー・ペトロスキーという人は建築土木史専門なのですが、『フォークの歯はなぜ四本になったのか』「ゼムクリップから技術の世界が見える』(以上、平凡社ライブラリー)など、とても興味をそそられるタイトルのものが多い...。
多川精一『戦争のグラフィズム 回想の『FRONT』』(平凡社)もよかった。戦中につくられた『FRONT』という雑誌の製作過程を、実際に携わった人間が回顧するもの。軍の広報雑誌のような立ち位置ながらも、当時の最新技術を追い求め、そして内部の人間は左翼的思想の持ち主が多く、特高にも目をつけられていた、というアンビバレントな状況が興味深い。これももっと調べたい内容だ。
***
欲張りはしないので、一億部ぐらい売れるよう、みなさんどうぞよろしくお願いいたします。
