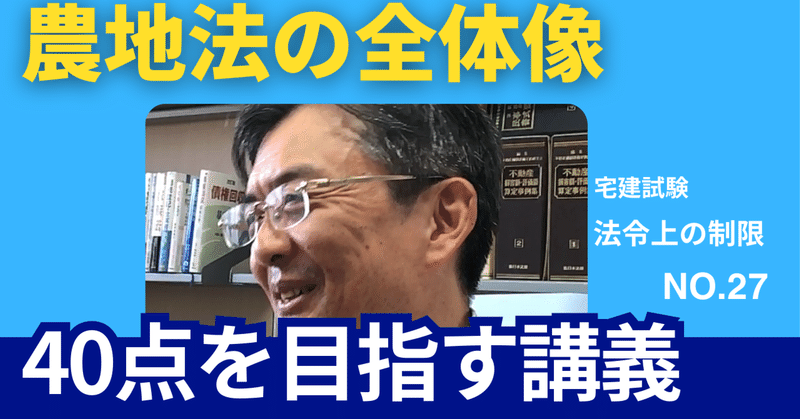
40点を目指す講義NO.27 農地法の全体像
今回の内容は、YouTubeで視聴できます。
1.農地法の概要
農地法の全体像を把握する際のポイントは、農地法の目的と手段を意識することです。
(1)農地法の目的
農地法の目的は、自国の食糧自給のために農地等を確保することです。
要するに、農地を確保して、自国の食糧を確保することです。
食糧を輸入に頼りすぎると、何らかの事情で外国から食糧が入ってこなくなった場合、日本国民の生活、生存に危機的な状況をもたらすことになります。なので、自国の食糧自給率をある程度は確保しておく必要があり、農地を保護しているわけです。
(2)農地法の目的を達成するための手段
手段として、
①農地等の処分の制限
例えば、農地の用途が変わる転用(農地を宅地にするとか)、農地等の処分の際、原則として、許可制をとることによって、農業をまじめにやらない人に農地が譲渡されること、あるいは、農地の減少を防いでいます。
許可なく移転登記がなされた場合も、当該処分は無効となります。
また、許可なく転用したら、原状回復義務を負います。
②農地等の賃借人の保護
農地を借りて耕作をしている賃借人が、安心して農業に打ち込めるようにするための手段が用意されています。
例えば、
・農地等の賃貸借は、その登記がなくても、農地等の引渡しがあれば、その農地等についての物権を取得した第三者に対抗することができます(農地法第16条)。
・農地等の賃貸借契約の解除などを行うには、原則として、都道府県知事の許可が必要です(農地法第18条)。
をしています。
平成25年問題21
農地法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 農地の賃貸借について法第3条第1項の許可を得て農地の引渡しを受けても、土地登記簿に登記をしなかった場合、その後、その農地について所有権を取得した第三者に対抗することができない。
2 雑種地を開墾し、現に畑として耕作されている土地であっても、土地登記簿上の地目が雑種地である限り、法の適用を受ける農地には当たらない。
3 国又は都道府県等が市街化調整区域内の農地(1ヘクタール)を取得して学校を建設する場合、都道府県知事等との協議が成立しても法第5条第1項の許可を受ける必要がある。
4 農業者が相続により取得した市街化調整区域内の農地を自己の住宅用地として転用する場合でも、法第4条第1項の許可を受ける必要がある。
解説
選択肢1は、誤りです。
農地の賃貸借については、農地を借りて耕作をしている賃借人が、安心して農業に打ち込めるようにするため、賃借権の登記がない場合でも、引渡しが対抗要件となります(農地法第16条)。
つまり、農地の賃借人は、引渡しさえ受けていれば、登記がなくても、その後に農地の所有権を取得した者に対して、賃借権を対抗することができます。
(3)農地等の処分の制限について
処分制限の処分には、3つのタイプがあります。
①権利移動
②転用
③転用目的の権利移動
①権利移動(農地法第3条)
権利移動とは、使用・収益権の移転や設定のことを言います。
権利移動では、耕す人が変わるということになります。
使用・収益権の移動の例としては、農地の売却や贈与、その他にも競売も権利移動です。
売買予約は権利移動には含まれませんが、予約完結権を行使をして所有権を取得する場合は権利移動に含まれます。というのは、完結させる意思表示によって、その段階で、売買契約と同じ効果が生じるからです。
次に、使用・収益権の設定・移転の例としては、地上権、永小作権、賃借権、使用借権、質権があります。
担保である不動産質権については、不動産質権者がその不動産を支配し、原則として使用・収益できるからです。
これに対し、質権と同じ担保である抵当権の設定・移転は、権利移動に含まれません。というのは、抵当権設定者自身が抵当権設定後もそのまま使用・収益できるからです。
但し、抵当権が実行されて、その所有者が変更する場合には、許可が必要です。
以上のところのポイントは、農地は誰が使えるのかという点にあります。
②転用(農地法第4条)
農地の用途が変わることです。
例えば、自分の持っている農地をつぶして宅地にすることです。
③転用目的の権利移動(農地法第5条)
これは、権利移動と転用のミックス型です。
例えば、農家のAが、持っていた農地をBに売り、Bがそれを宅地にすることです。
以上の3つのタイプがありますが、②と③は、転用を含むので、農地がなくなることから、食糧生産という観点からは、その結果が重大です。なので、②と③は、①より厳しい規制が必要になります。
平成21年問題22
農地法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 土地区画整理法に基づく土地区画整理事業により道路を建設するために、農地を転用しようとする者は、法第4条第1項の許可を受けなければならない。
2 農業者が住宅の改築に必要な資金を銀行から借りるため、自己所有の農地に抵当権を設定する場合には、法第3条第1項の許可を受けなければならない。
3 市街化区域内において2ha(ヘクタール)の農地を住宅建設のために取得する者は、法第5条第1項の都道府県知事等の許可を受けなければならない。
4 都道府県知事等は、法第5条第1項の許可を要する農地取得について、その許可を受けずに農地の転用を行った者に対して、必要な限度において原状回復を命ずることができる。
解説
選択肢2は、誤りです。
農地法でいう「権利移動」とは、農地を使用・収益する権利を設定・移転することを意味しています(農地法第3条第1項、第5条第1項)。
ここでいう「権利」とは、所有権、地上権、賃借権、使用借権などを指します。ここでは、農地の使用・収益者が変わる場合を規制の対象としています。では、抵当権はどうかというと、抵当権を設定したとしても、農地の使用・収益者が変わるわけではありません。債権者が農地を耕作するわけでなく、使用・収益者は、従前通りです。したがって、抵当権の設定については、3条や5条の許可は不要です。
2.用語の定義
(1)農地
農地とは、耕作、つまり、耕して作物を作る目的に供される土地を言います(農地法第2条第1項)。
農地か否かの判断は、何によってするのか。
客観的な土地の事実状態で行います。
例えば、現実に肥料を施して、農作物を作ったりするようなところか否かで農地か否かを判断します。
登記簿上の地目が、「雑種地」とかになっていて、「田」、「畑」ではなくても、客観的な土地の事実状態で農地か否かを判断します。
では、休耕地や休閑地は、農地か?
休耕地とは、人で不足等の何らかの事情で、作物の栽培を休止している田畑のことです。
休耕地とみなされるためには、農業休止はあくまでも一時的なものであり、田畑も耕作者がいれば即時に栽培が可能な状態で、所有者も農業を継続する意志を持っている必要があります。
この休耕地において、1年以上栽培がおこなわれず、耕作の見通しが立っていない場合には、休耕地ではなく、耕作を放棄したものとみなされます。これを「耕作放棄地」と言います。耕作放棄地とみなされた土地は、通常の農地よりも高い税率の固定資産税がかかってきます。
休閑地とは、その土地の力の回復のため、耕作を休止した耕地を言います。
耕地は、何年か連続して使用すると、地力が減退して収穫量が減少します。このようなときは、一般に休閑地にクローバーなどのマメ科の牧草をまき、家畜の放牧などを行って地力の回復を増進させます。
以上、休耕地と休閑地は、いずれも再び耕すことが予定されていますので、農地になります。
では、家庭菜園をしている土地は、農地か?
家庭菜園は、食糧事情への貢献度が低いため、農地として扱う必要はないと言われています。
平成13年問題23
農地法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 現況は農地であるが、土地登記簿上の地目が「山林」である土地を住宅建設の目的で取得する場合には、農地法第5条の許可を要しない。
2 農地法第3条又は第5条の許可を要する農地の権利移転について、これらの許可を受けないでした行為は、その効力を生じない。
3 市街化区域内の農地を耕作目的で取得する場合には、あらかじめ農業委員会に届け出れば、農地法第3条の許可を要しない。
4 農地法第4条の許可を受けた農地について、転用工事に着手する前に同一の転用目的で第三者にその所有権を移転する場合には、改めて農地法第5条の許可を要しない。
解説
選択肢1は、誤りです。
農地か否かの判断は、客観的な土地の事実状態で行います。登記簿上の地目は関係ありません。現況が農地であれば、その農地を守る必要があります。よって、現況が農地である土地を住宅建設の目的で取得する場合には、農地法第5条の許可が必要です。
同じような問題が、平成20年問題24、平成24年問題22、平成25年問題21でも出題されています。
(2)採草放牧地
採草放牧地とは、農地以外の土地で、主として耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるものを言います。
牧草地をイメージしてください。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
