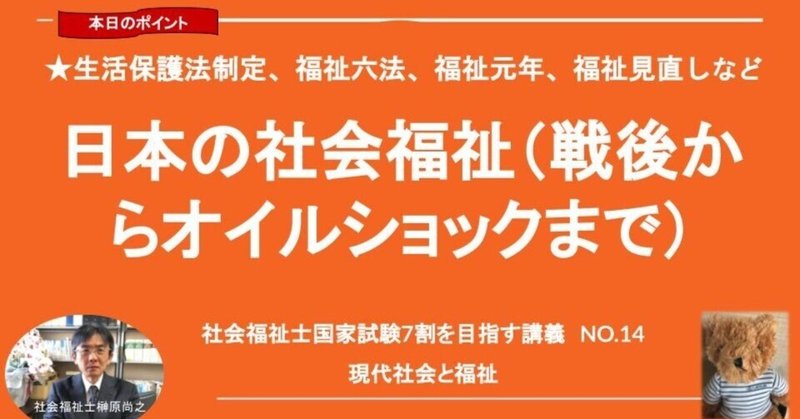
7割を目指す講義NO.14 日本の社会福祉(戦後からオイルショックまで)
1.日本の戦後直後
日本の社会福祉に関する戦後の動きを確認します。
1945年8月15日に、第二次世界大戦が終結しました。日本は敗戦を迎え、6年ほど連合国軍総司令部(GHQ)の占領下に置かれます。戦後改革の一環として、民主化と非軍事化を基調とした福祉改革が始まるわけです。
戦後の動きについては、3点の重要なところがあります。
1つは、GHQに占領政策をされている日本がどのように救貧対策を行っていくのかということを尋ねられたものとして、「救済福祉に関する覚書」というものがあります。
これは、1945年12月8日付けで出ました。
これは、GHQからの質問書で、救済に関する方針について尋ねられたものです。
日本政府は、1945年12月31日に、「救済福祉に関する件」にて、これに回答するわけです。その内容は、基本的には、戦前というか、戦争時にやっていた天皇を中心とした、これまでの救済対策と何ら変わることのない慈恵的救済対策をしていくとの回答でした。
日本政府は、「救済福祉に関する件」という形で、このように回答をしたわけですが、これは、戦前と同様の救済対策をしますとの回答だったので、GHQからは、これではダメだということで、突き返されるわけです。
そこで、1946年に、GHQから「社会救済に関する覚書」というものが示されます。これが、SCAPIN775になります。
SCAPIN775では、いわゆる慈善的救済、つまり、日本がこれまで行ってきた慈恵的救済を排除するための3つの原則を示したものになります。
この中で示された原則が、
①扶助の国家責任の原則
②保護の無差別平等の原則
③最低生活保障の原則(保障する最低限度の生活は健康で文化的生活水準であること)
こういう3つの原則になります。
日本では、この原則を踏まえて、1946年、昭和21年に、旧生活保護法が成立しました。
旧生活保護法は、救護法、母子保護法等の公的扶助に関する法律が一本化されたものになります。
ところが、この法律は、いまだ慈恵的救済という面が色濃く残存するもので、いくつか不備があったために、1950年、昭和25年に改正され、新生活保護法になりました。
不備の1つは、保護の基準が、いわゆる勅命、つまり、天皇の命令によって保護の基準が決められていた点です。
ここから先は
¥ 110
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
