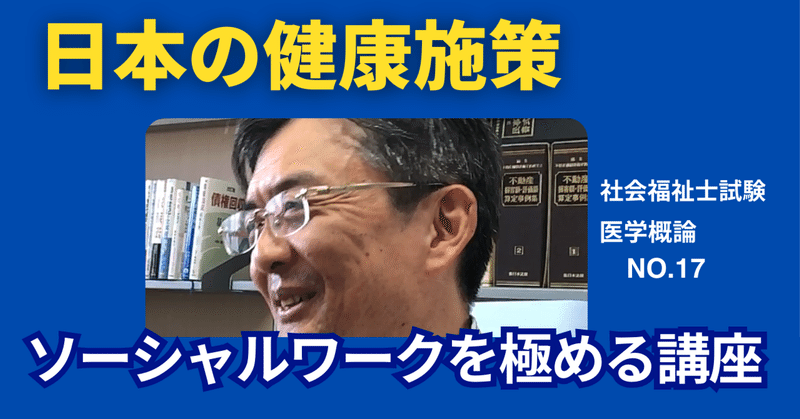
医学概論NO.17 ソーシャルワークを極める講座 日本の健康施策
今回の内容は、YouTubeで視聴できます。
1.日本の健康施策
日本における健康施策を見ていきます。
日本においては、世界の動向を受けて、健康作り運動として、2000年に厚生労働省が、健康日本21を示しました。
ただ、その前に一つ押さえておきたい運動があります。
8020運動です。
(1)8020運動
8020運動とは、 1989年(平成元年)より厚生省と日本歯科医師会が推進している「80歳になっても20本以上自分の歯を保とう」というスローガンを掲げた運動のことになります。
8020運動の歌もあります。小学校の時に毎日歯磨きの時間に「8020 8020 何のことだかわかるかな・・・」というメロディーが流れていたと思います。
この8020運動は、妊産婦を含めて、乳幼児から亡くなるまでの全てのライフステージ(全年齢層を対象)で健康な歯を保つことが大事だとして、それを目標にしています。
2003年に健康増進法が施行されます。この健康増進法が、「健康日本21」を中心とする健康づくり施策を推進する法的基盤になりました。
「健康日本21」においては、歯科関係では、「国民の健康の増進の目標に関する事項」の中に「歯の健康」の目標として、8020達成者率等が位置付けられています。
第28回第3問の選択肢
日本における健康施策に関する問題で、「8020運動は、 乳幼児を対象としない。」〇か✖か
この選択肢は、誤りです。
8020運動は、全年齢層、つまり、妊産婦を含めて、乳幼児から亡くなるまでの全てのライフステージで健康な歯を保つことが大事だと言っています。ですから、この8020運動は、乳幼児を対象としています。
(2)健康日本21
次に、「健康日本21」に移ります。
健康日本21は、「21世紀における国民健康づくり運動」とも呼ばれます。
それまでの早期発見・早期治療に重点を置いた健診等の対策に加え、生活習慣の改善による発症予防を推進し、健康寿命を延伸し、すべての国民が健やかで活力ある社会にするために、2000年に始まったのが、健康日本21になります。
「健康日本21」ですが、厚生労働省が、21世紀における国民健康づくりというものを運動としてスタートさせたものになります。
健康日本21の特徴は、具体的な数値目標を定めて、一定期間運動し、最終的に評価をしていくという点にあります。ここの部分が、それまでの健康づくり対策である第1次・第2次国民健康づくり対策とは異なる点になります。
厚生労働省の資料より

そして、この運動を法制化して推進するため、2002年に健康増進法という法律が公布されております。
健康増進法においては、禁煙の規定があります。
すなわち、学校、病院、行政機関、児童福祉施設等の第一種施設は、敷地内禁煙になっています(第29条)。ただし、屋外喫煙所は設置可能です。
また、国、都道府県、市町村、多数の者が利用する施設(敷地を含む。)及び旅客運送事業自動車等の管理権原者その他の関係者は、望まない受動喫煙が生じないよう、受動喫煙を防止するための措置の総合的かつ効果的な推進を図るため、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければなりません(健康増進法第26条)。
そして、特に受動喫煙を防止するための措置については、最近の改正があったので、要注意です。
2020年4月1日から改正健康増進法が完全施行されています。
すでに、2019年7月から、学校、病院、行政機関、児童福祉施設などの第一種施設は、屋外喫煙所の設置を除いて、敷地内禁煙になっています。
それ以外の多数の者が利用する施設(第二種施設)は、2020年4月以降より、健康増進法の基準(これは、換気扇を取り付ける、喫煙室を仕切りで囲う、空気清浄機を設置するという基準です。)を満たした喫煙専用室以外は、原則禁煙となっています(第29条)。
ただし、2020年4月1日時点で営業している飲食店で、資本金5000万円以下、客席面積100㎡以下の場合には、保健所に届出書を出せば、従来通り飲食しながら喫煙が可能になります。
また、多数の者が利用する施設を管理する者が喫煙場所を設置する際には、望まない受動喫煙を生じさせることがない場所とするよう配慮しなければなりません(第27条第2項)。
この配慮義務の具体例としては、喫煙場所を設ける場合には、施設の出入口付近や利用者が多く集まるような場所には設置しないこと等です。
このように、喫煙者には肩身の狭い状況になっています。昔は、大学とかで、教授が煙草をふかしながら、授業をしたりしていました。今では、想像できないかもしれませんが、昔は煙草をぷかぷかしながら、講義をするというのが普通でした。しかし、現在は、健康増進法で禁止されています。
第23回第4問の選択肢
健康に関する問題で、「我が国の健康増進法においては、学校、体育館、病院、劇場その他、多数の者が利用する施設を管理する者は受動喫煙を防止するための措置を講ずるよう努めることが定められている。」〇か✖か
この選択肢は、正しいです。
健康増進法第26条に規定されています。
多数の者が利用する施設(敷地を含む。)等の関係者は、望まない受動喫煙が生じないよう、受動喫煙を防止するための措置の総合的かつ効果的な推進を図るため、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければなりません。
あと、健康増進法による規定の内容として、もう一つ押さえておいて欲しい事項があります。
それは、市町村による健康増進事業の実施です(第19条の2)。この実施は、努力義務になっています。
主な事業内容としては、健康手帳の交付、健康教育、健康相談、各種検診等があります(健康増進法第17条第1項)。
では、どのような検診が対象になっているか?
歯周疾患、骨粗鬆症、がん、肝炎ウイルス等になります(健康増進法施行規則第4条の2)。
第28回第4問の選択肢
日本における健康施策に関する問題で、「歯周疾患検診は、 健康増進法に基づき実施されている。」〇か✖か
この選択肢は、正しいです。
創作問題
「骨粗鬆症検診の実施は、健康増進法に基づくものである。」〇か✖か
この選択肢は、正しいです。
健康日本21では、成人病の一次予防を重視し、健康寿命、つまり健康上の問題がない状態で日常生活を送れる期間を延ばして、生活の質を向上させるという運動が展開されています。
つまり、健康日本21は、一次予防である生活習慣病の予防と二次予防である早期発見、早期治療を行い、健康寿命を伸長させることを狙いとしています。このあたりは、アルマ・アタ宣言のプライマリ・ヘルス・ケアを意識しています。
そして、国民の保健医療水準の指標となる具体的な目標を設定して、その目標を達成するための運動の評価に基づく健康増進事業を推進するようになりました。
つまり、栄養から始まって、運動、休養、ストレス、タバコ、アルコール、癌、歯周病、糖尿病の9項目を挙げて、知識の普及と個人レベルの対応から社会環境まで具体的な目標値をあげています。
そして、「個人」の健康づくりを支援するための社会環境づくりも、この時に考えられるようになりました。
その上で、厚生労働省は、この国民健康づくり運動を各都道府県単位、各市町村単位で進展させています。
このあたりは、オタワ憲章のヘルスプロモーションを意識しています。
第33回第3問の選択肢
健康の概念と健康増進に関する問題で、「「健康日本21」は、一次予防を重視している。」〇か✖か
この選択肢は、正しいです。
健康日本21では、生活習慣病等の発症を予防する「一次予防」に重点が置かれています。
第26回第3問の選択肢
健康に関する問題で、「健康寿命とは、 介護を受けたり病気で寝たきりになったりせずに自立して生活できる期間をいう。」〇か✖か
この選択肢は、正しいです。
健康日本21ですが、すでに、2011年10月に健康日本21評価作業チームによる最終評価というのが出されています。
この最終評価では、全体の約60%が一定の改善がみられ、15パーセントが悪化したという報告がなされています。
そして、この報告を受けて、2013年度からは新たに健康日本21(第二次)がスタートしています。運動期間は、2013年度から2022年度までです。
健康日本21(第二次)については、国民に広く知られるようになった成人病などに関して、二次予防である早期に発見して早期に直しましょうというのではなく、そもそもそのようなものにかからないようにしましょうという一次予防に重点を置き、生活習慣病の発症や重症化に至らないように健康を支え、守るための社会環境の整備にも力を入れていくという点が特徴的です。
この健康日本21(第二次)では、国民の健康の増進に関する国の基本的な方針(方向)が示されています。
具体的には、
①健康寿命の延伸(えんしん これは伸ばすという意味です。)と健康格差の縮小
②糖尿病等の生活習慣病の発症予防と重症化予防の徹底
③こころの健康等を推進することで社会生活を営むために必要な機能の維持及び向上をする
④健康を支え、守るための社会環境の整備
⑤生活習慣病の予防等の観点から、栄養、食生活、身体活動・運動、休養、飲酒、喫煙、歯・口腔(こうくう)の健康に関する生活習慣及び社会環境の改善
が示されています。
第33回第3問の選択肢
健康の概念と健康増進に関する問題で、「健康増進法は、生活習慣病対策を含まない。」〇か✖か
この選択肢は、誤りです。
健康増進法においては、食生活、喫煙、身体活動・運動、歯の健康保持など生活習慣病対策について定められている箇所があります。
第33回第3問の選択肢
健康の概念と健康増進に関する問題で、「健康増進は、一次予防には該当しない。」〇か✖か
この選択肢は、誤りです。
健康増進は一次予防に該当します。健康増進を図ることで、病気を防ぐなどの予防(一次予防)となります。
第28回第3問の選択肢
日本における健康施策に関する問題で、「「健康日本21」 (第二次) には、 アルコール摂取に関する項目は含まれていない。」〇か✖か
この選択肢は、誤りです。
健康日本21(第二次)では、国民の健康の増進に関する国の基本的な方針(方向)の一つとして、生活習慣病の予防等の観点から、栄養、食生活、身体活動・運動、休養、飲酒、喫煙、歯・口腔(こうくう)の健康に関する生活習慣及び社会環境の改善が挙げられています。この中には、飲酒も含まれています。
今見てきたように、健康寿命の延伸を基本方針とする健康日本21(第ニ次)ですが、健康寿命の延伸のために、ロコモティブシンドローム対策の一つとしてロコモティブシンドロームの認知度を高めることが目標とされています。
ロコモティブシンドロームは、運動器症候群とも言いますが、からだを動かすのに必要な運動器に障害が起こり、「立つ」「歩く」といった動作が困難となり、寝たきりになる危険性が高くなる症状をいいます。
要するに、運動器の障害により要介護になるリスクの高い状態のことを指します。
ロコモティブシンドロームの予防の一つには、筋力の維持が大切になります。その中でも特に下肢の筋肉の減少は大きく現れます。そこで、筋力を維持するためには、ウオーキングやランニングのような持続的なトレーニングに加えて、「スクワット」のような動作を行うトレーニングに取り組むのがよいと言われています。
また、健康日本21(第二次)の基本方針に出てくる飲酒ですが、「健康日本21(第二次)の推進に関する参考資料」によると、健康日本21(第二次)における飲酒に関する目標は、以下の3つです。
一つ目として、生活習慣病の発症リスクを高める量を飲酒している者の減少
二つ目として、未成年者の飲酒をなくすこと
三つ目として、妊娠中の飲酒をなくすこと
です。
ここでは、未成年者の飲酒防止が含まれている点は注意が必要です。
そして、健康日本21(第二次)の基本的方針の①から⑤までの関係にもふれておきます。
①健康寿命の延伸(えんしん これは伸ばすという意味です。)と健康格差の縮小
②糖尿病等の生活習慣病の発症予防と重症化予防の徹底
③こころの健康等を推進することで社会生活を営むために必要な機能の維持及び向上をする
④健康を支え、守るための社会環境の整備
➡「地域のつながりの強化」を目指し、自分と地域のつながりが強い方だと思う割合が全世代で65%に達することを目標とする。
⑤生活習慣病の予防等の観点から、栄養、食生活、身体活動・運動、休養、飲酒、喫煙、歯・口腔(こうくう)の健康に関する生活習慣及び社会環境の改善
①から④までの基本的な方向を実現するため、⑤の改善が重要であるとされています。
すなわち、①健康寿命の延伸(えんしん)と健康格差の縮小、②糖尿病等の生活習慣病の発症予防と重症化予防の徹底、③こころの健康等を推進することで社会生活を営むために必要な機能の維持及び向上をする、④健康を支え、守るための社会環境の整備の実現のために、⑤生活習慣病の予防等の観点から、栄養、食生活、身体活動・運動、休養、飲酒、喫煙、歯・口腔(こうくう)の健康に関する生活習慣及び社会環境の改善が重要であるとされているわけです。
そして、これに従って、各都道府県と各市町村は、健康増進計画の策定をしています。
なお、2022年10月に、健康日本21(第二次)の最終評価が公表されました。その評価の中で、悪化している項目には、「メタボリックシンドロームの該当者および予備群の減少」、「睡眠による休養を十分とれていない者の割合の減少」、「生活習慣病の発症リスクを高める量を飲酒している者の減少」などがあります。悪化しているということは、減少していないということです。
健康日本21は、2024年度(令和6年)からは、健康日本21(第三次)として開始されています。
健康日本21(第三次)の実施期間は、2024年度~2035年度になります。
健康日本21(第三次)は、すべての国民が健やかで心豊かに生活できる持続可能な社会の実現を目標として、その基本的な方向として、下記の4項目の取り組みを進めるとしています。
・個人の行動と健康状態の改善(運動習慣者の増加など)
・社会環境の質の向上(居心地が良く歩きたくなるまちなかづくりに取り組む市町村数の増加など)👈ここは、健康日本21(第二次)の段階で、社会環境の整備を目標としていたところ、健康日本21(第三次)では、次なる段階として、社会環境の質を目指すということです。
・ライフコースアプローチを踏まえた健康づくり(20歳未満の飲酒をなくすなど)
以上の3つを推し進め、結果として、
・健康寿命の延伸と都道府県ごとの健康格差の縮小
を目指す。
*ライフコースアプローチについて
現在の健康状態はこれまでの自らの生活習慣や社会環境などの影響を受ける可能性があり、子ども(次世代)の健康にも影響を及ぼす可能性があります。 このことからすると、胎児期から高齢期にいたるまでの人の生涯を経時的(時間の経過的)に捉えた健康づくり(ライフコースアプローチ)の観点を取り入れると有効です。このような個人の特性をより重視しつつ健康づくりを行うことが、すべての国民が健やかで心豊かに生活できる持続可能な社会の実現に繋がります。
山梨県の資料より


健康寿命は増加傾向にあります。
厚生労働省の資料より

この我が国における健康づくり運動の変遷の流れをある程度理解しておいてください。
その際、健康づくりの3要素(栄養、運動、休養)の視点をもつとよいと思います。
健康な毎日を過ごすためには、栄養、運動、休養の3つの要素が大切です。
そして、お互いが関連しあっているため、どれかひとつだけを意識すればいい訳ではありません。
上の図を前提にして、付け加えておきますと、第1次国民健康づくりの段階においては、健康づくりの3要素(栄養、運動、休養)のうち、栄養に重点をおいた健康増進事業を推進していたという点です。そして、第2次国民健康づくりの段階になると、運動に重点をおいて、運動習慣の普及に重点をおいた健康増進事業を推進していました。
では、健康づくりの3要素のうちの休養についてはどうなっているのか?
第3次国民健康づくり(健康日本21)の具体的な数値目標の1つとして、栄養、運動の他に休養についても意識的に取り入れられています。
第26回第3問の選択肢
健康に関する問題で、「「健康日本21」(第二次)の基本的な方針は、 活力ある社会の実現のために高齢者の死亡率を減少させることである。」〇か✖か
この選択肢は、誤りです。
選択肢にあるように、高齢者の死亡率を減少させるのではなく、 一次予防を推進して健康寿命の延伸を図ることが健康日本21(第二次)の基本的な方針とされています。
第31回第4問の選択肢
健康に関する問題で、「「健康日本21(第二次)」の基本的方向は、平均寿命の延伸である。」〇か✖か
この選択肢は、誤りです。
「健康日本21(第二次)」の基本的方向としては、①健康寿命の延伸と健康格差の縮小等があります。選択肢では、平均寿命の延伸とありますが、正しくは、健康寿命の延伸です。
ちなみに、厚生労働省のまとめによると、2024年の日本人の平均寿命は、女性87.09歳、男性81.05歳となっています。平均寿命とは、0歳時点で何歳まで生きられるかを統計から予測した「平均余命」のことです。わかりやすくいえば、特定の人が生きられるおおよその年齢となります。これに対し、健康寿命は、WHOが2000年に公表した概念になります。意味としては、人の寿命において、健康上の問題で日常生活を制限されることなく生活を送ることのできる期間のことをいいます。ここでいう「日常生活の制限」とは、介護や病気などを指し、自立して元気に過ごすことができない状態を指します。
第30回第3問の選択肢
世界保健機関( WHO )の活動に関する問題で、「健康寿命とは、健康上の問題で制限されることなく仕事ができる期間と定義した。」〇か✖か
この選択肢は、誤りです。
健康寿命は、意味としては、人の寿命において、健康上の問題で日常生活を制限されることなく生活を送ることのできる期間のことをいいます。選択肢は、制限されることなく仕事ができる期間とありますが、制限されることなく「生活」を送ることができる期間が正しいものとなります。仕事ができる期間のみを指す概念ではありません。
第33回第3問の選択肢
健康の概念と健康増進に関する問題で、「健康寿命とは、平均寿命を超えて生存している期間をいう。」〇か✖か
この選択肢は、誤りです。
健康寿命とは、人の寿命において、健康上の問題で日常生活を制限されることなく生活を送ることのできる期間のことです。つまり、健康上の問題によって、日常生活が制限される事無く生活できる期間の事を言います。平均寿命を超えて生存する期間ではありません。
(3)健康づくりのための身体活動基準2013
厚生労働省は、健康日本21(2000年から2012年度)の推進に資するように、2005年、健康づくりと生活習慣病予防のために、新しい標語を作りました。
厚生労働省の資料より

新しい標語というのは、「1に運動、2に食事、しっかり禁煙、最後にクスリ」というものです。
しかし、このようなかけ声だけではなかなか運動を推進できないものです。そこで、厚生労働省は、具体的でわかりやすい運動指針を策定することにしました。
つまり、厚生労働省では、2005年8月に「運動所要量・運動指針策定検討会」を設置し、約1年をかけて、運動所要量を決め、これに基づいて、具体的でわかりやすい運動指針を作成しました。
これが、「健康づくりのための運動基準2006・運動指針2006」になります。
なお、この運動基準・運動指針では、基本的に健康な成人の方を対象としています。ですから、持病のある方は、かかりつけの医師に相談して、安全に運動を実施するようにしましょうと呼びかけています。
第24回第3問の選択肢
「健康づくりのための運動指針2006」に関する問題で、「この運動指針では、生活習慣病の患者を対象としている。」〇か✖か
この選択肢は、誤りです。
健康づくりのための運動指針2006は、生活習慣病予防のための安全で有効な運動を広く国民に普及させることを目的として、生活習慣病を予防するための身体活動量・運動量及び体力の基準値を示したものになります。ですから、この運動指針では、基本的に、健康な成人の方を対象としています。
その後、2013年度から始まった健康日本21(第二次)を推進する取り組みの一環として、「健康づくりのための運動基準2006・運動指針2006」が改定されました。
2013年に「健康づくりのための身体活動基準2013」「健康づくりのための身体活動指針(アクティブガイド)」が策定されています。
厚生労働省の資料より

この健康づくりのための身体活動基準2013は、子供から高齢者までの全年齢を対象にして、運動だけでなく、生活活動も含めた「身体活動」全体に着目することの重要性を掲げたものになります。
ここでいう「身体活動」とは、安静にしている状態よりも多くのエネルギーを消費する全ての動作を指します。
この身体活動には、2つあります。
運動と生活活動です。

運動とは、スポーツ等の、特に体力の維持・向上を目的として計画的・意図的に実施し、継続性のある身体活動
生活活動とは、日常生活における労働、家事、通院・通学などの運動以外の活動
この運動と生活活動の二つを合わせたものが、身体活動になります。
第24回第3問の選択肢
「健康づくりのための運動指針2006」に関する問題で、「体力の維持・向上を目的として計画的・意図的に実施するものを「生活活動」という。」〇か✖か
この選択肢は、誤りです。
生活活動とは、身体活動のうち、運動以外の活動で、職業活動上のものや家事、通院・通学なども含むものになります。
体力の維持・向上を目的として計画的・意図的に実施するものは、身体活動のうち、運動を指します。
運動は「強さ」と「時間」を正しく設定して行うことが大切になってきます。
そこで、「健康づくりのための身体活動基準2013」では、身体活動の強度を「メッツ」という単位で表します。
また、身体活動量を「メッツ」に実施時間(時)をかけた「メッツ・時」で示し、身体活動の種類ごとに、どのくらいの時間をかけて実施すれば健康づくりのための目標に達するかを自分で計算できるようにしています。
そして、「身体活動基準2013」では、身体活動の基準を世代(18歳未満、18歳~64歳まで、65歳以上)で分けて、その目標(基準範囲)を設定しています。

また、すべての世代共通の方向としては、
・身体活動の目標を「今より少しでも増やす」
例えば、10分多く歩くとかです。
・運動の目標を「運動習慣をもつようにする。(30分以上・週2以上)」
というものになっています。
ここでは、世代のうち、18歳から64歳における身体活動量の目安を見ていきます。
身体活動量の目安は、身体活動・運動と生活習慣病との関係を示す内外の文献から生活習慣病予防のために必要な身体活動量、運動量の平均を求めて設定したものです。
例えば、散歩など普通に歩く(普通歩行)ことが、3メッツ程度の強度の身体活動になります。
メッツという単位ですが、メッツはその運動が安静時の何倍に相当するかで表す単位になります。そして、この数字と時間を掛け合わせた数字が活動量になります。
ちなみに、1メッツは、安静時の活動の強度を指します。
例えば、座って安静にしている状態が、1メッツです。そして、3メッツは、その運動が安静時の3倍に相当するという意味になります。
第24回第3問の選択肢
「健康づくりのための運動指針2006」に関する問題で、「身体活動量は、活動の強度を意味するメッツ(Mets)を用いて「メッツ✖時」で表す。」〇か✖か
この選択肢は、正しいです。
メッツは、その運動が安静時の何倍に相当するかで表す単位になります。この数字と時間をかけ合わせた数字が活動量になります。
では、身体活動量の目標について確認します。

18~64歳の世代の身体活動の目標は、3メッツ以上の強度の身体活動を毎日60分(=1週間に23メッツ・時)行うことです。
1メッツ・時=1エクササイズ
1週間に、23エクササイズが、身体活動量の目標になります。
身体活動によるエネルギー消費量(kcal)は、メッツ✖時間(h)✖体重(kg)で推定することが可能です。
例:体重50kgの人が、30分の歩行(3メッツ)を行った場合のエネルギー消費量は、3(メッツ)✖0.5(h)×50(kg)=75kcalと推定できます。
身体活動量を増加させることでリスクを低減できるものとしては、糖尿病、循環器疾患、がん、ロコモティブシンドローム、認知症が挙げられています。
なお、「健康づくりのための身体活動基準 2013」を見直し、「健康づくりのための身体活動・運動ガイド2023」が策定されています。
第24回第3問の選択肢
「健康づくりのための運動指針2006」に関する問題で、「身体活動の量は、「運動」の量で決定される。」〇か✖か
この選択肢は、誤りです。
身体活動の量は、運動と生活活動の活動強度と時間によって算出されます。
第24回第3問の選択肢
「健康づくりのための運動指針2006」に関する問題で、「健康づくりのための身体活動量の目標は、週10エクササイズ(Ex)以上である。」〇か✖か
この選択肢は、誤りです。
身体活動量の目標ですが、3メッツ以上の身体活動を1週間に23メッツ・時行うことです。これをエクササイズの単位で表しますと、1メッツ・時=1エクササイズになるので、週23エクササイズになります。よって、週10エクササイズ以上としている選択肢は誤りとなります。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
