
トレーニングいらず!全く新しい速読/読書術 DUAL BRAIN READING WORKSHOP CLASS No4:DBRの理論①(DBRが生まれた背景)
こんにちは、いまでもカナディアンです。
前回のCLASS No3はいかがだったでしょうか?
前回はDBRの衝撃の効果についてをお話ししました。
まずは、振り返りです。
CLASS No3:DBRの衝撃の効果 まとめ
1.DBRの読書スピード
2.DBRが当たり前になった人の世界観
3.どんな人でも実践可能なDBR
いかがでしょうか?
今回のCLASS No4ではDBRの理論①についてお話しします。
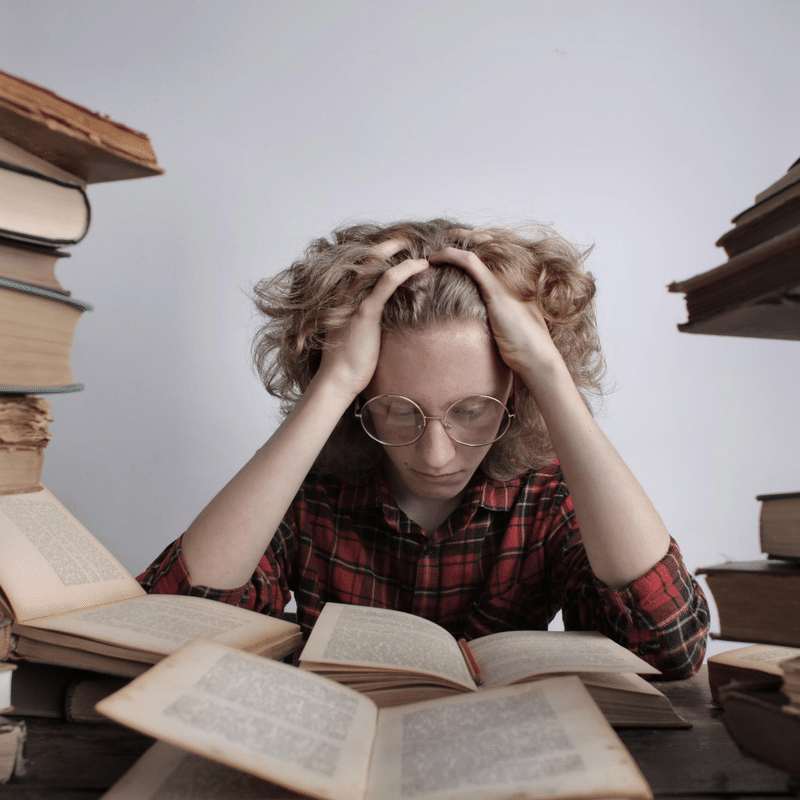
1.赤点が8つ!? 絶望的な状況からそれのヒントは生まれた。。。
では、早速DBRの理論の話をさせていただきます。
DBRの特徴を2つだけ上げると以下のようになります。
1.私(いまでもカナディアン)が高校時代~大学時代に組み上げた完全オリジナルの速読/読書術
2.右脳(イメージ)と左脳(ロジック)を組み合わせたハイブリット型の速読/読書術
となります。
まず、1についてお話ししようと思います。
そもそもですが、あなたはどうして私がオリジナルの速読/読書術を作り上げたと思いますか?
普通に考えれば、「本を速く、たくさん読みたかったから」となるかもしれません。
実は、それは全く違います。
なぜなら、この速読/読書術の原型をくみ上げた当時、私は全く本を読んでいなかったからです。
では、なぜ速読/読書術を作り上げることになったのでしょうか?
その理由は読書とは全く異なる理由によるものでした。
それは…
受験勉強
というよりも
追試対策
です。
当時、私が通っていた高校は地方の高校でありながら、全国でも結構名の知れた進学校でした。
定期テストの内容は難関大学の過去問のコピペの詰め合わせで、3年生の頃の定期テストや実力テストの内容ははっきり言って、範囲が限られてはいるものの現実の入試問題よりも難しいものでした。
そのようなテストを毎回受けていたのですが、当時の私は家庭や学校の事情で体力的にも精神的にも疲れ果てており、不登校になっておりました。
その結果、定期テストの日程を勘違いしてしまい、なんと8科目もの赤点を取ってしまいました。
難関大学の過去問題よりも難しい定期テストで8科目も赤点を取ってしまうのは、はっきり言って致命的です。
普通に勉強していては、とても追試を全科目クリアはできません。
困った私は知恵を振り絞り、どうにかして追試を全科目合格できるよう考えました。
その結果、私が取ったやり方は、参考書や問題集の解説と答えを重要度で分け、その箇所だけ暗記していくという方法でした。
つまり、解説や答えを読むのを諦め、とにかく「見る」。
そして、「見た」内容を受重要度に応じて分類して、重要度の高い順番から暗記していく。
という試験対策を行いました。
そして、まさにこのやり方が的中しました。
圧倒的に素早く解説書と問題集を読みこなすことができるようになり、
シンプルに必要なところだけ何度も見て暗記するため、暗記の効率が格段に上がりました。
その結果、成績が停滞していた自分はあれよあれよと成績が伸び、最終的には志望校の直前模試で科目別ではありますが偏差値82をたたき出し、見事逆転合格することができました。

2.ただの序章にすぎなかつた大学受験
「やった!なんとか合格できた!」
という喜びもつかの間。
入学後に更なる問題が生じました。
私が入学した大学は授業は基本的に英語で行われており、
海外のような卒業することが大変な大学でした。
そのため、入学後にすぐに始まる1年生向けゼミでは、最初の授業までの課題が800ページの専門書2冊に関するレポートを提出。
さらに、他の授業でも毎週200~300ページの内容を読み、課題を提出するものでした。
しかも、それらの文献はすべて英語で書かれています。
大学に入るまで、一度も海外に行った事すらなく、読書もほどんどしてこなかった私にとってはとてもやり切れるものではありません。
実際、このような課題の量についていけない学生は多く、当時でも2年以内に3割の学生が退学するような大学でした。
せっかく苦労して入学した志望大学、もちろん退学するわけにはいきません。
高校の勉強で知恵を振り絞った経験を大学入学後、また同じようにすることになりました。
そこで役立ったのが、また受験で学んだ内容でした。
特に、高校現代と小論文の内容です。
この内容を高校時代に自ら編み出した暗記術と組み合わせることで、高速で大量の文献を読みこなそうとしたのです。
そして、これがまたもやうまくいきました。
入学してからすぐに大学でも高い成績を出し続けることができました。
課題の量に圧倒されている同学年の学生を横眼にです。
その結果、学内の成績上位リストの常連になることになり、給付型(返済不要)の奨学金の支給対象にも選ばれました。
さらに、授業の勉強も効率的にできたため、研究だけでなく、バイトも、社会活動も、留学も様々な活動を積極的に行える時間を捻出できるようになりました。
ですので、私の学生生活は本当に充実したものとなりました。
帰国後に書いた卒論も、大量の資料をたったの1週間で調べ上げ、4日でテキスト化、3日で編集。
なんと、普通の学生が数か月かけて書き上げる卒業論文をたったの2週間で書き上げることができました。
それで余った時間も社会活動に費やすことができ、学問だけでは学べない体験をたくさんすることができました。

このように、私オリジナルの速読/読書術であるDBRは私が当時抱えていた課題に対して、自分の持っている知識をベースに試行錯誤で形作っていったものです。
実際、本を全然読んだことがなかった当時の普通の高校生である私が、普通に高校で学べる内容をもとに組み上げたものです。
そのため、簡単な知識で始められるメソッドとなりました。
だからこそ、前回紹介したようにほとんど読書をしたことがない人でも、ルールを覚えるだけで、3倍も読書スピードが上がったわけです。
ですので、実践的であり、オリジナルのものです。
いかがでしょうか?
DBRが即効性のあり、誰ども効果が出る速読/読書術であることを納得いただけたのではないでしょうか?
次回はDBRの理論の続編 実際のDBRの実践法について入っていきたいと思います。
3.CLASS No4:DBRの理論①(DBRが生まれた背景)まとめ
1.赤点が8つ!? 絶望的な状況からそれのヒントは生まれた。。。
2.ただの序章にすぎなかつた大学受験
DUAL BRAIN READING(DBR)を是非体験してみたい方はこちらへご連絡ください。
頂いた資金は障害者の自立支援への活動に使わせていただきます
