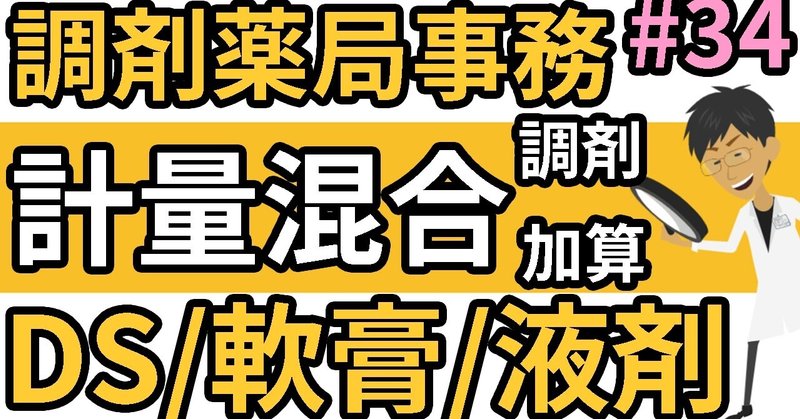
#34調剤薬局事務 調剤料の加算②計量混合調剤加算とは?算定要件や点数を処方例を使って薬剤師が解説☆
調剤薬局事務 資格・独学・勉強お役立ちCH - tyouzaiCHです。
▼以下の文章は動画内容を文字おこししたものです。
///////////////////以下、動画内容////////////////////////////
皆さんこんにちは、チャンネル運営者のSATOUです。

今回は調剤料の加算項目②として計量混合調剤加算について、お伝えしていきます。
それで、もしかすると薬局によっては「計量混合加算」と少し略して使っていることがあるかもしれませんが、一応、正式名称が計量混合調剤加算となっておりますのでこの動画では正式名称で統一してお話していきます。
それでは早速本編に入りましょう!
計量混合調剤加算とは?
漢字を見てもらうとイメージしやすいかと思いますが、計量混合調剤加算とは?【2種類以上の「医薬品」を『計量』して、かつ、『混合』した場合に算定できる】点数となります。
それで、ここで定義されている「医薬品」は薬価基準に収載されている必要があります。
次に図を見ていただきたいのですが、、、
図

計量混合調剤加算は、区分が内服薬、頓服薬、外用薬の場合に算定することができます。
また、備考欄とその右側にある点数の欄にあるように、薬の形、剤形ごとに点数が決まっており液剤は35点、散剤、顆粒剤は45点、軟・硬膏剤は80点です。
ここに記載されている以外の剤形、例えば錠剤やカプセル剤、注射剤などは計量混合調剤加算の算定は出来ませんので注意が必要です。
点数の部分についても、一応、( )内の点数は予製剤を使った時の点数で左側の点数の100分の20、つまり5分の1の点数となっています。
予製剤については自家製剤加算の時と同じ考え方ですので、もし必要な方は#33の動画も確認して見て下さい。
それと、レセプト記載時に必要な略号は赤丸の部分です。
最後に計量混合調剤加算は「1調剤につき」算定する点数です。
特に実務においては1調剤についての理解が中途半端ですと計量混合調剤加算を複数算定できる場合などに迷ってしまいますので「1調剤」についてはきちんと理解しておいた方が良いと思います。
以上、ここまでが計量混合調剤加算の基本的な概要、全体像になります。
それで、算定要件のもう少し細かな部分についてもいくつか知っておいた方が良いと思いますので処方例を見ながら確認していきましょう!
計量混合調剤加算
(処方例)
処方例1)
パントシン散20% 1g
【般】酸化マグネシウム 1g
1日3回毎食後 14日分(※混合)
はじめに処方例1をご覧ください。
最初に薬の名前を見て剤形を判断できれば良いのですが、上段のパントシン散20% 1gの場合は散剤の「散」という記載から粉薬であることがわかります。
それで、下段の一般名で酸化マグネシウム 1g も結論を言えば粉の薬なのですが、、、もしかすると薬の名前から剤形が判断できない場合もあるかもしれませんのでそういった場合の考え方をお伝えします。
まずは、用法の部分を見ますと内服薬であることがわかります。
次に薬剤名の右側にある投与量の単位をみますと1gとなっていますので、ここから散剤や顆粒剤といった粉薬であることがわかります。
このgという単位は他に外用薬の場合にも使われますが、その場合も用法を見れば外用薬であることがわかりますのでもしも剤形の判断に迷った時には用法と投与量の単位の部分に注目するとほとんど解決できますので是非覚えておいてもらえればと思います。
それで、処方例1の場合、2種類の粉薬を計量して混合すると考えますので、、、
先ほどの点数表に戻りまして、、、
内服薬で散剤・顆粒剤の計量混合調剤加算ということで45点を算定します。
自家製剤加算の内服薬とは違って投与日数にかかわらず、1調剤につき一律45点となっていますのでご注意ください。
(処方例2)
○○液1% 3mL
× ×液2% 5mL (※混合)
咳発作時屯用 5回分
続いて、処方例2を見ていきましょう。
こちらの処方例は○○液1%と××液2%という、どちらも液体の薬、液剤を計量して混合した場合とします。
一応、用法の部分も確認しますと「頓服薬」であることがわかります。
点数表に戻りまして、、、
区分が頓服薬で剤形が液剤になりますので表にある通り35点を算定することができます。
それで液剤について、補足ですが液剤の場合、区分が内服薬でも処方例のような頓服薬でも、また外用薬でも全て同じ点数の35点となっております。
(処方例3)
リンデロン-VG軟膏0.12% 10g
アズノール軟膏0.033% 20g
(※上記混合)
1日3回 痒い所に塗布
次に処方例3を見ていきましょう!
こちらの処方例では薬剤名から剤形が軟膏であることがわかります。
また、そもそも軟膏なので外用薬ということがわかりますが、一応、用法の塗布という記載からも外用薬であることがわかるかと思います。
それで、2種類の軟膏を計量し混合したものとしますので点数表を確認しますと、、、
外用薬の軟膏剤ですので計量混合調剤加算は80点を算定することができます。
それで、例えば予製剤を使った場合は80点の右側にある( )内の16点を算定します。表には抜けていたのですが、計量混合調剤加算の予製剤の略号は(予)となっております。
ここまで、処方例1では散剤、つまり粉薬と粉薬の混合について、処方例2では液剤と液剤、処方例3では軟膏剤と軟膏剤といった形でそれぞれ混ぜ合わせる前の薬剤と混合調剤した後の薬剤の剤形は同じ剤形でした。
ご覧のように原則的には計量混合調剤加算の場合、調剤する前と調剤した後で剤形の変化はありませんが、特殊な例があるので最後にそちらをお話して今日の動画を閉めようと思います。
・特殊な例
ドライシロップ(DS)と液剤(シロップ剤)を混合する場合
(処方例4)
クラリスドライシロップ10%小児用 1g
ムコダインシロップ5% 6mL
1日3回 毎食後 7日分(※混合)
処方例4ではドライシロップ剤とシロップ剤を混合した場合の例となります。
処方例1-3の場合との大きな違いとしては
DSという粉薬とシロップ剤という液剤を混合することで調剤後の完成品は液剤となりますので調剤した前と後で剤形に変化があることです。
それで、厚生労働省から出されている「調剤報酬点数表に関する事項」によりますと
”ドライシロップ剤を液剤と混合した場合は、計量混合調剤加算を算定するものとする。”
という、記載がありましたので特殊な例として計量混合調剤加算の算定が認められているようです。
先ほど見て頂いた通りDSとシロップ剤を混合調剤した場合の完成品は液剤になります。ですので点数表を見返しますと、、、
一番上の液剤の欄を参照していただいて35点を算定することができます。
それで、前回の動画#33で似たような処方例についてお話したのですが覚えていらっしゃるでしょうか?
//////////#33処方例/////////
Rp1)
A細粒 0.5g
B液 5mL
1日2回朝夕食後 3日分(混合する)
(A、B両成分を含有する液剤は薬価基準に収載されておらず、ABの混合は配合変化などの問題がないものとする)
//////////////////////////////////
ご覧のように#33の処方例でも粉薬と液剤の混合についての処方例ですが、こちらは自家製剤加算の算定例としてお話してきました。
それで、今回の動画でお話した処方例に戻って確認しますと
同じ粉薬でもドライシロップと液剤の場合は計量混合調剤加算になるよー
ということを覚えておいてもらえると良いかと思います。
少し紛らわしい所だったので補足させてもらいました。
計量混合調剤加算については
もう少し細かなところまでお話したいこともあるのですが、ひとまず基本事項は以上とさせて頂きます。今後もし必要と感じた場合はまた別の動画でお話しようと思います。
このチャンネルのでは調剤薬局事務の初心者の方に向けてこれからも情報をお伝えしていきます。動画に良い所があればグッドボタン、チャンネル登録もお願いいたします。
それでは、最後までご視聴いただきありがとうございました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
