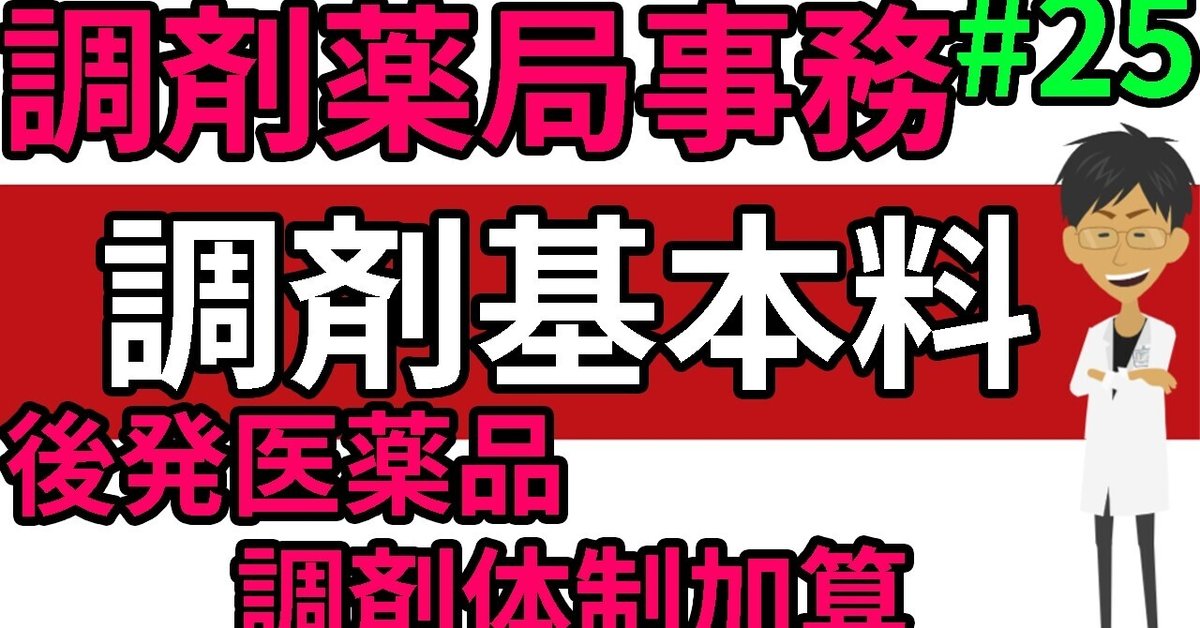
#25調剤報酬の算定☆調剤基本料の加算項目☆調剤薬局事務向け
▼以下の文章は動画内容を文字おこししたものです。
////////////////////////以下、動画内容/////////////////////////////////////////////
皆さんこんにちは、チャンネル運営者のSATOUです。
今回の動画は調剤基本料の加算項目の①として「地域支援体制加算」
加算項目の②として「後発医薬品調剤体制加算」についてお話します。
また、前回の動画#24の中でお話した調剤基本料の基本点数について補足点があったのでお話します。
途中で調剤基本料の算定例として例題を出しますので復習として一緒に問題を解いてみましょう!
どれも大切な項目だと思いますので是非最後までご視聴下さい。
それでは早速いってみましょう!
まずは、調剤基本料のおさらいです。
調剤基本料=基本点数+加算項目
調剤基本料はご覧の通り基本点数と加算項目の合算により計算することとなります。
それで、今日お話するのは加算項目の方で加算項目としては、、、

地域支援体制加算と、、、

後発医薬品調剤体制加算について見ていきます。
それで、調剤基本料の加算項目については先ほどもお話した通り「地域支援体制加算」と「後発医薬品調剤体制加算」があるのですが
まずは、今現在多くの薬局で算定していると思われる「後発医薬品調剤体制加算」の方からお話していきます。
・後発医薬品調剤体制加算について
後発医薬品調剤体制加算を算定する上でのポイントとしては2つあります。
①処方箋の受付1回につき算定する
一つ目は処方箋の受付1回につき算定するということで、こちらは調剤基本料の基本点数と同じ考え方になります。
②届出した薬局のみ算定可能
二つ目のポイントは、後発医薬品調剤体制加算を届出した薬局が算定できる点数であるということです。
こちらは、後発医薬品を使っている薬局であれば勝手に算定してよいというわけではなく、それぞれの薬局がある地方厚生局に届出することで算定することができます。。。。
・調剤報酬点数表(後発医薬品調剤体制加算)
それでは、実際に後発医薬品調剤体制加算の調剤報酬点数表を見ていきましょう!

ご覧のように後発医薬品調剤体制加算の種類としては1~3の3種類に分類されています。
それで、種類の右側にあるのが調剤報酬明細書に記載する時にも使われる「略号」で、その右側に点数がそれぞれ書かれています。
ご覧のように点数は上から下にいくほど点数が高くなっています。
この点数が高くなる要因としては、備考欄にありますように後発医薬品の調剤数量の割合が高いほど加算点数が高くなってきます。
つまり、国としてはジェネリックを沢山つかう薬局ほど高い加算点数を算定して良いということです。
それで、備考欄にある後発品の調剤数量の割合について、、、
大まかな所だけ説明しますと、、、
・直近3ヶ月の後発医薬品の調剤数量を元に計算
・カットオフ値が50%以上
このような基準を元に計算することで割合を算出します。
カットオフ値については、「後発医薬品がある先発医薬品+後発医薬品」が全医薬品の調剤数量に占める割合のことですが、こちらは今のところ気にしないで大丈夫かと思います。
例えば、2021年4月の後発医薬品の調剤数量の割合を求めるときは
2021年の1月、2月、3月のデータを元に計算します。
今、保険薬局に勤務している方でしたらレセコンを使うことですぐに今現在の自分の薬局の後発医薬品の調剤数量の割合を知ることができると思います。
それで、この割合が75%以上なら後発医薬品調剤体制加算1を届出することで加算点数を算定できますし80%以上なら後発医薬品調剤体制加算2、85%以上なら後発医薬品調剤体制加算3をそれぞれ届出することで加算項目を算定することができます。
少し実務的な話になりますが、例えば2021年の4月はジェネリックの調剤数量割合が79.9%で後発医薬品調剤体制加算1を算定している薬局でもジェネリックの調剤数量が増えて5月のジェネリックの調剤数量割合が80.5%になれば後発医薬品調剤体制加算2を届出することで加算点数が変更になるといった場合もありえます。
以上が後発医薬品調剤体制加算についてです。続いて
調剤基本料の加算項目の①として「地域支援体制加算」について

こちらのポイントとしては、、、
表の備考欄にもありますように・処方箋の受付1回につき算定できる点数
・地域医療に貢献する体制がある保険薬局で基準を満たせば算定可能
で、2021年現在ですと38点が算定できます。
地域支援体制加算については以上の大まかな概要
だけ抑えておけば問題ないかと思っています。
正直な所、地域支援体制加算は算定するための要件、基準が厳しいと個人的には思っていまして僕の薬局では算定できておりません。
ですので、あまり偉そうなことは言えませんが、僕が勉強した範囲で大枠についても軽く触れておこうと思います。
・地域支援体制加算の算定要件について
2020年の調剤報酬改定後の算定要件の大枠ですが
・全ての薬局に共通する要件
・調剤基本料1を算定する薬局の要件
・調剤基本料1以外を算定する薬局の要件
以上のように分かれています。
・全ての薬局に共通する要件としては、先ほどの表、こちらのの基準という場所に記載されているように「24時間調剤および在宅業務に対応できる体制」「麻薬の調剤ができること」「医薬品の備蓄が1200品目以上ある」ことなどが挙げられます。
その他にも、薬局の開局時間に関すること、管理薬剤師の勤務時間に関すること、調剤従事者等の資質向上に関すること、など多くの規定があります。
それで今回の動画では地域支援体制加算の算定要件については概要に留めます。
理由としては、先ほどの例でご覧いただいた基準はほんの一部でとにかく情報量が多いです。
また個人的には算定要件が結構複雑で初心者向けではないと感じているからです。資格試験や実務においても地域支援体制加算の算定要件まで必要かなーと疑問に思いますので今回は概要に留めますが
もしかすると人によっては知識として知っておきたいという方や実務の上で必要性を感じる方もいるかもしれませんので、地域支援体制加算の算定要件についてわかりやすく説明されているサイトを動画の概要欄でご紹介します。
必要な方は、そちらでご確認ください。
URL
https://note.com/ryuuta/n/n1845129c1787
以上、ここまでが地域支援体制加算についてお話してきました。
・調剤基本料の加算項目(その他)
それで、調剤基本料の加算項目としては今回お話してきた「後発医薬品調剤体制加算」「地域支援体制加算」の他にも・時間外加算・休日加算・深夜加算といった処方箋の受付日時によって算定できる項目もあります。
こちらについてはまた別の動画で詳しく説明しようと思います。
・調剤基本料の算定例
今までの動画でお話した内容を元に調剤基本料の算定例を見ていきますと。
(例題)
調剤基本料2、地域支援体制加算、後発医薬品調剤体制加算3を届け出している保険薬局の調剤基本料は( )点である。(2021年現在)
このような問題があったとして、一緒に問題を解いていきましょう!
時間のある方は動画を一時停止して問題を解いてみて下さい。。。
それでは回答です。
まず、調剤基本料2の点数は調剤報酬点数表の基本点数の部分から確認します。

・調剤基本料2はご覧のように点数が26点、略号は(基B)赤丸の部分になります。
続いて、地域支援体制加算の点数表を見ていきます。

地域支援体制加算は点数が38点、略号は赤丸の部分(地支)になります。
最後に後発医薬品調剤体制加算の表をみますと

後発医薬品調剤体制加算の3は点数が28点、略号は赤丸の部分(後C)です。
以上をまとめると
・調剤基本料2(基B)26点
・地域支援体制加算(地支)38点
・後発医薬品調剤体制加算3(後C)28点
(2021年現在)
それぞれの点数を足し算すると
26+38+28=92点です。
ですので(例題)の答えは。。。 92点 となります。。。。
調剤報酬明細書の調剤基本料の欄への書き方は
上段に各略語を記載して。。。
下段に合計点数である「92」を記載することになります。
以上、ここまでが調剤基本料の加算項目についてお話してきました。
調剤基本料のおさらい、補足
それで、最後に調剤基本料の簡単なおさらいと補足についてお話させてください。
・調剤基本料のおさらい
調剤基本料=基本点数+加算項目
前回の動画で調剤基本料は基本点数と加算項目を合算したものであることをお話してきました。
それで、基本点数には5種類あって加算項目については今日の動画でお話した内容となります。
それで、基本点数の部分で前回お話しなかった内容について簡単に触れますと
調剤基本料の基本点数
"調剤基本料について、同一患者から異なる医療機関の処方箋を同時にまとめて複数枚受け付けた場合、2回目以上の受付分については所定点数の100分の80に相当する点数を算定する。"
という規定が2020年の調剤報酬改定後に新設されました。
どういうことかと言いますと、2つ以上の医療機関から複数枚の処方箋を受け付けたときに2枚目以降の処方箋が減額されるということです。
たとえば、A病院とBクリニックの処方箋を一緒にもってきた場合は、以前は調剤基本料×2回の算定でしたが、今回の改定によりBクリニックの基本料だけ20%分安くなります。
例えば調剤基本料1を届出している薬局の場合、基本点数が42点なのでA病院の1枚目はそのまま42点でB病院の2枚目については42点×0.8=34点となり2枚目は8点(80円)マイナスになります。自己負担割合が3割ですと20~30円安くなる計算です。
ここの部分を前回の動画で話すべき内容が抜けていたので今回補足させていただきました。
最近、調剤報酬算定について僕自身も一生懸命勉強しているのですが、なかなか理解が進まず内容がまとまらなかったり、皆さんにお伝えした方が良いと思う内容も多くなったりで動画作成の時間がかかってしまっています。
定期的に動画投稿が出来なくなってきており本当に申し訳ないのですが、これからも少しずつでも勉強を進めて動画でお話していこうと思っています。
もしかすると、なかなか時間がなくて勉強できない視聴者さんもいるかもしれませんが、少しずつでも一緒に頑張りましょう。
それでは今回は以上です。
最後までご視聴いただきありがとうございました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
