
附論 ― 冊子の内容と記述手法の問題 ―
浄土真宗本願寺派勧学・司教有志の会から「新しい領解文(浄土真宗のみ教え)」に対する声明の第7弾の附論が発表されました。
附論 ― 冊子の内容と記述手法の問題 ―
このたび公開された総合研究所冊子(以下、「冊子」と呼ぶ)について、一部では「学問的に厳正に立論された満井論文」などと評価し公言する人もいるようであるが、率直に言って、この冊子の内容は、「論文」と呼ぶに値するものではない。
この冊子は、一見すると様々に論を展開しているように見え、それを証明しているかのように先学の文章を多く引用して、「議論の余地はない」などと断言している。しかし、声明(七の一)~(七の四)において指摘したように、この冊子は、その制作意図からして浄土真宗の根幹から大きく逸脱しており、その内容も辻褄合わせの説明に終始する支離滅裂なものとなっている。しかも、その強引な主張を正当化するために、先学の文章を前後の文脈をまったく無視して利用している点については道義的にも問題であり、きわめて杜撰である。こうした手法で作られた冊子を、本願寺派の総合研究所の名のもとに公開することは、本願寺派の教学研究への信頼を失墜させ、ひいては、仏教そのものの魅力まで失わせかねない。
この冊子を公にした研究所所長(当時)の満井秀城氏には、研究所発行の本冊子の内容全体に責任がある。本附論では、声明(七の四)に【問題三】として指摘した、先学の文章を冊子が恣意的に引用している点について、以下、冊子の本論Ⅰ・Ⅱに引用されている文章ごとに、その問題を簡潔に指摘しておく。
Ⅰ.仏教の思想的歴史
本論「Ⅰ」の項目においてもきわめて恣意的かつ独断的な論が展開されているが、その?において冊子制作者は、龍樹菩薩が「初期仏教以来の縁起説を空・無自性の思想によって解釈し、大乗仏教の思想的基盤を構築した」(五頁)とし、その直後には「縁起によって空および無自性を基礎づけた」と述べている。この冊子を読む者からすれば、両者の内容は矛盾していると見えてもおかしくないものであるが、そのことに対して必要な説明を欠いているのは、冊子制作者自身の理解が十分ではなく、曖昧もしくは混乱しているからであろう。
まず基礎的なことを確認しておくが、初期仏教以来の縁起説にしても、龍樹菩薩が空・無自性によって解釈した縁起説にしても、あるいは空・無自性を基礎づけた縁起説にしても、「本来一つ」ということを認める縁起説ではない。当然ながら、「本来一つ」ということを理由として諸法が縁起すること、あるいは仏の救いが実現することを説くものでもない。
そして龍樹菩薩の空・無自性の説示についても、あらゆる存在を(迷いと悟りというように)分別して「二つ」とする考えを否定すると同時に、あらゆる存在の根源を「本来一つ」とする考えを否定するものである。したがって、煩悩とさとりを「本来一つ」などと単純に理解することは、初期仏教はもとより、龍樹教学としてもありえない。付言すれば、「私の煩悩と仏のさとりは本来一つ」などという理解の根拠となる文言は、初期仏教はもとより、龍樹教学としても存在せず、また、仏に帰依する者のとる表現としてはきわめて不適切だと思われる。
さらに冊子は、難解な龍樹菩薩の『中論』第二十四章「四諦の考察の章(観四諦品)」第十八偈・第十九偈をその直後に原文とともに引用しているが(ただし第十八偈の原文におけるpracaks maheという冊子の表記は、pracaksmaheの誤り ※Sの下に・あり)、この引用についても何の説明もない。この二偈は、仏教の歴史を通して実に多岐にわたって解釈されてきている。大乗仏教における縁起と空性の理解や、両者の関係については、以後の中観派の学説に対する瑜伽行唯識学派からの批判を無視しては語れないが、冊子の引用手法を見る限り、ただ龍樹菩薩の難解な偈頌のみを示し、その権威をもって読む者を威圧しようとするかのような意図を感じるばかりである。このような短絡的で稚拙な内容をもって「議論の余地はない」とするなど許容されるはずもない。
《中村元博士の文章》
(2)の①では、「縁起・空について」(五頁)の説明として、現象世界においては生滅変化しているが「高い立場から見るとただ偉大なる一つの理(ことわり)があるだけで、生じても滅してもいません」(六頁)という中村元博士の言葉を引用し、その直後に「仏の智慧によって見れば、この現象世界はただ空なる真実があるだけの境地なのであろう」(同)という結論じみた文章を置いている。
もし冊子が、仏からみれば私たちの煩悩具足の現実も「ただ空なる真実があるだけ」だから、「そのまま救う」という弥陀のよび声が成立しているのだと主張しているのであれば、それこそ序論において満井氏が、「『本来一つだから、そのまま救われる』と理解すると、とんでもない事態になる」と注意喚起している危険思想そのものである。冊子全体として思想的に整合性が取れておらず、理解に苦しむところである。
《藤田宏達博士の文章》
(2)の②では、『無量寿経』に「注意すべき叙述も見出される」(六頁)として、『無量寿経』に空思想の影響がみられるという藤田宏達博士の文章を引用している。しかし空思想の影響がみられるということは「空だから弥陀の救済が成立する」という冊子の主張とはまったく関係がなく、根拠とはならない。もし冊子が、「私の煩悩と仏のさとりは本来一つゆえ」に「そのまま救う」という弥陀のよび声となったという理屈を正当化したつもりで、ここに藤田博士の文を引用しているのならば、あまりにも不適切かつ乱暴な仕方である。
《梶山雄一博士の文章》
(2)の③では、梶山雄一博士の著書『大乗仏教の誕生「さとり」と「廻向」』を引用し、「回向(廻向)」について触れている。最初に述べておかなければならないのは、仏教、特に大乗仏教の「回向」の思想は、「私の煩悩と仏のさとりとは本来一つゆえ」を根拠とするものではないということである。両者が「本来一つ」であるならば、「回向」そのものは不要である。また「回向」が、「そのまま救う」の「そのまま」ということの論理的根拠にはならないことについては言うまでもない。その意味で、満井氏自身がいう「本来一つゆえ」が「弥陀のよび声」にかかるという不可解な解説ともまったく無関係である。ここにも冊子全体としての思想的な不整合があるようである。冊子制作者は、本当に『大乗仏教の誕生「さとり」と「廻向」』の内容を理解しているのだろうか。
簡略ではあるが、梶山博士の論旨を確認しておきたい。冊子では梶山博士の文章を
・・・・・・一見対立している二つのもの、たとえば煩悩とさとりは、ともに空であるから、本質的には不二である。(中略)・・・・・・
として、「本質的には不二である」に続く文章を意図的に省略しているが、引用元の著書では、
・・・・・・本質的には不二である。業報によって生死流転すること、つまり輪廻と、業報輪廻からの解放である涅槃との二つも、区別できない、不二のものである。
と述べられているとおり、梶山博士の論旨は「二而不二」を述べるものである。端的にいえば、「空」とは「本来一つ」という短絡的な思想ではない。空をそのように理解するのはまったく誤りである。
《中村元博士の文章》
(2)の④では、中村博士の言葉を引用し、何の説明もないまま、「つまり、空の故に対立項は不二であり、自他平等が意識され、慈悲(愛)が平等に注がれるのである」(八頁)というだけである。冊子の文章は、もしかすると、中村博士の「自分の身を相手の立場に置いて考える」という説明を承けたものであるかもしれない。しかし、この中村博士の説明は、「二而不二」ということ、つまり、自と他の二つの平等、すなわち不二ということを述べているのであり、「私の煩悩と仏のさとりとは本来一つ」ということではない。「本来一つ」であるならば、慈悲(愛)が注がれる必要もない。そして「本来一つ」であるならば誰が誰に慈悲(愛)を注ぐのであろうか。冊子全体に通じて言えることであるが、空に関して「本来一つ」という言葉で表現できていると理解して論旨が展開されているところが大きな誤りなのである。
Ⅱ.廻向の出どころ
続く本論「Ⅱ」では「廻向の出どころ」として、先学の文章が羅列的に引用されているだけであり、いずれも先学の論述意図を無視し、都合の良いように断章取義している。
(1) 他力廻向法の根源
《村上速水和上の文章》
(1)の①では、「他力廻向法の根源」を示すものとして村上速水和上の文を引用しているが、この文章は「廻向」について述べているものではなく、衆生の成仏の可能性として、「空無自性」あるいは「生仏一如」について言及されているにすぎない。変化することのない固有の実体があれば、凡夫は永遠に凡夫のままであり、仏と成ることは理論上、不可能だからである。それも「他力救済が可能となるためには、生仏一如にして無自性である義が許されるべき」(八頁)と述べられているように、他力の法義においても、大乗で説かれる「生仏一如」「無自性」の思想は認めるべきことを示されたものであり、決して「生仏一如」「無自性」という思想から、直接、弥陀の救済が成立すると言われているのではない。それは、この村上和上の論述そのものが、
しかし生仏本来平等であるならば、何故に仏は慈悲心を起し、衆生を憐憫するのであろうか。
という問いから展開されていることからも明らかである。ただ「生仏一如」、つまり本来平等というだけであれば、慈悲を起こす必要も、救う必要もないからである。
なお、村上和上は、右の問いをうけつつ、仏が衆生を見そなわすには「生仏平等」と見る側面と、迷いと悟りが「雲泥の如く」異なっていることを見る側面とがあるとし、救済の悲願の起こされるまさしき理由は後者にあることを指摘されている(『同』一七五頁~一七六頁)。
要するに、村上和上の文章は、「本来一つゆえ そのまま救う」という趣旨を示されたものでは決してない。
《梶山雄一博士の文章》
(1)の②では、梶山博士の文章を引用しているが、この文章も、本来は「二而不二」あるいは「不一不二」ということを述べたものである。そして、この引用もまた梶山博士の論旨を無視した仕方が行われている。冊子は、
梶山氏も「(a)回向の思想は、空の論理なくして成り立たない」と言われ、さらに「(b)空の思想は必然的に不二の思想に導いていく(中略)一見対立している二つのもの、たとえば煩悩とさとりが、ともに空であるから、本質的に不二である」と念を押されている。
というが、実際の梶山博士の説明は、(a)と(b)の順序が逆であり、「念押し」などされていない。この「本質的に不二である」という梶山博士の言葉をもって「本来一つゆえ」という一行を正当化したいのであろうが、それは「空の思想」に対する誤った理解である。梶山博士の文章を自身の主張のために利用しているに過ぎない。
(2) 煩悩菩提体無二
この一段では、冒頭に親鸞聖人の『高僧和讃』から曇鸞讃の一首が引用されている。
本願円頓一乗は 逆悪摂すと信知して
煩悩・菩提体無二と すみやかにとくさとらしむ
この和讃では、「円頓一乗」という天台宗の用語がみられる。「煩悩即菩提」に通じる「煩悩・菩提体無二」という用語も同様であり、これは当時流行していた天台本覚思想において頻繁に用いられた用語である。比叡山で天台教学を学ばれた親鸞聖人は、当然そのことを知っておられたわけであるが、留意すべきは、親鸞聖人がこれら天台教学の用語を、曇鸞大師の教えを讃嘆するために用いておられる点である。
これは親鸞聖人が、「円頓一乗」「煩悩・菩提体無二」という用語を、曇鸞大師の『往生論註』に説かれている本願の救済を通して、はじめて意味をもつ言葉として扱われたことを意味している。換言すれば、本願の救済を離れるならば、これらの言葉はみな空虚な概念に過ぎないということである。ご和讃に「本願円頓一乗」と示され、その本願によって「煩悩・菩提体無二と すみやかにとくさとらしむ」と讃嘆されている所以である。
しかし、冊子は「煩悩・菩提体無二」という言葉を「私の煩悩と仏のさとりは本来一つ」の意味とした上で、煩悩とさとりがともに空であり本質的に不二ゆえに、仏の側からは「そのまま救う」という慈悲が成立するとし、「空からの招き・よびかけ」として阿弥陀仏の救いを位置付けている。
当然のことながら、本願の救済を通して「煩悩・菩提体無二」という言葉を意味づけていかれた親鸞聖人のご和讃と、「煩悩・菩提体無二」を根拠として本願の救済を位置付けようとする冊子の説明とは、まったく逆の論理である。冊子制作者は、本願の真実性に基づいて法義を顕された親鸞聖人のおこころを理解していないと言うほかない。
《村上速水和上の文章》
(2)の①②では、村上和上の文章を引用しているが、これらの文章も、親鸞聖人と同じく、ともに本願のはたらきをもって大乗仏教の至極とされるものである。よって「本来一つゆえ」という一行とは、何のかかわりもない。
《梯實圓和上の文章》
(2)の③では、梯和上の文章を引用しているが、声明(七の四)に言及している通り、梯和上の講義の意図をまったく無視してその一部を切り取ったものである。しかも、この冊子の内容とどのような関係があるのかも、一行も説明されていない。
冊子に引用された箇所は、そもそも「『無分別智』と『無分別後得智』」という項目の内容であり、言葉を超えた一如の領域をさとる「無分別智」のみを語られたものではない。したがって、引用箇所の直後には、
「空」といっても何もないということではなく、無限の豊かさを持っているということなのです。無限に豊かであるから言葉にかからない。言葉で表現できたら嘘になります。そういう嘘になる世界を嘘にならないようにコントロールしていく言葉、それが「無分別後得智」という特別な智慧なのです。こういう智慧をもって仏は説法をされるわけです。
と続いており、言葉をもってはたらきかける「無分別後得智」という智慧の重要性を講義されている。そして『仏説無量寿経』をその無分別後得智の具現として位置づけ、「それが一句となって私たちに届いているのが『南無阿弥陀仏』なのです」(『法界に遊ぶ』四一頁)として講義を結ばれている。梯和上の講義とこの冊子の内容とは、まったく関わりがない。
《中村元博士の文章》
(2)の④では、中村博士の「救う主体も空、救われるものも空、さらに救われて到達する境地も空」であり、「区別されず、分つことのできないもの」であるという言葉を引用しつつ、
したがって、勧学寮が「同意」し、ご門主が発布されたご消息に示されている「新しい領解文」にあるように、私の煩悩と仏のさとりは本来一つゆえ「そのまま救う」 が弥陀のよび声と、われわれはいただくのである。
と結んでいるが、なぜ「したがって」と続いているのか、意味不明である。救うものと救われるものがともに空であることが、どのような意味で、本来一つゆえ「そのまま救う」という論理に繋がるのであろうか。ただ「空」であり「区別できない」というだけであれば、そもそも仏がさとる必要もなければ、衆生を救う必要もないのである。むしろ『仏説無量寿経』に、
一切の法は、なほ夢・幻・響きのごとしと覚了すれども、もろもろの妙なる願いを満足して、かならずかくのごときの刹を成ぜん。法は電・影のごとしと知れども、菩薩の道を究境し、もろもろの功徳の本を具して、受決してまさに仏となるべし。諸法の性は、一切、空無我なりと通達すれども、もっぱら浄き仏土を求めて、かならずかくのごときの刹を成ぜん。
とあるように、諸法は「空」「無我」であると見通しながら、なお「空」に執われることなく、仏のさとりを求めつづけ、衆生への慈悲を起こしつづけるところにこそ、大乗菩薩道がある。私の煩悩と仏のさとりがともに「空」であり「区別できない」から、「そのまま救う」という慈悲が成り立つというごとき短絡的な論理は、大乗仏教の思想としてありえない。
端的にいえば、救うものと救われるものがともに「空」であるということと、冊子がいう「空だから阿弥陀仏の救いが成り立つ」ということは、まったく話が違うのである。
《桂紹隆博士の意見》
(2)の⑤では、インド大乗仏典に関する緻密な文献研究を専門とする桂紹隆博士の意見が記されている(冊子一一頁)。この二段落からなる⑤の内容は、どの部分が桂博士の発言なのか明瞭に示されてはいないが、前段と後段における敬語表現の有無から、少なくとも「新しい領解文」について解説している後段の内容は、桂博士の発言ではないことが分かる。しかし冊子制作者は、その後段の最後に(注23)を付して、桂博士の指導に対する謝辞を述べており、あたかも⑤の二段落すべてが桂博士の発言に基づいているかのような印象操作を行っている。
前段のなかで、桂博士は「煩悩即菩提」という漢訳の語について、インド仏典には唯識論書である『大乗荘厳経論』と『摂大乗論』に各一箇所、わずか二箇所の用例のみであることを指摘している。この二つの論書については、桂博士の恩師、長尾雅人博士の緻密な研究成果があり、それらの資料を含む懇切丁寧な指導が桂博士から冊子制作者になされたはずだが、それについては簡素な(注22)があるだけである。それ以外で、前段のなかで桂博士の見解が含まれていると考えられるのは、以下の箇所のみである。
それらの梵語原文を見ると、表現は「煩悩即菩提」とはなっていないが、趣旨は同じであるという。桂氏は結論として、梶山氏のように「空思想」に基づいて「煩悩即菩提」と解釈することは十分可能であるが、文献学的には唯識論書中の「煩悩即菩提」にも注目する必要があるといわれている。
まず留意すべきは、桂博士は「煩悩即菩提」という漢訳の説示を「空」の思想をもって解釈することは可能であると発言されているのであり、「新しい領解文」の「私の煩悩と仏のさとりは本来一つゆえ」という一行について、言及されているわけではないということである。
さらに問題は、波線部分の「梶山氏のように」という言葉である。この文章を読めば桂博士が「梶山博士が言ったように「煩悩即菩提」を「空思想」に基づいて解釈することは可能である」と発言したように読める。しかし、冊子が引用している梶山博士の著書『大乗仏教の誕生「さとり」と「廻向」』には、一箇所も「煩悩即菩提」という語はみられない。そもそも「煩悩即菩提」という語は、桂博士が指摘するようにインド仏典では唯識論書の二箇所しかない。つまり、「空思想」を確立した龍樹菩薩を開祖とする中観学派の論書にはないのである。したがって、龍樹研究の第一人者であった梶山博士が「煩悩即菩提」という説示を「空思想」で解釈し、まして「煩悩と菩提(さとり)が本来一つ」という意味であると説明することなどあるはずもないのである。すなわち、この波線部分の記述は桂博士の発言ではなく、冊子制作者があたかも桂博士の発言であるかのように見せるために挿入したものに他ならない。
ちなみに上記の唯識論書における「煩悩即菩提」の意味について要点だけ説明しておく。両論書では、その説示は異なる文脈の中にあるが、いずれも「煩悩を転じて菩提を得る」という、いわゆる「転迷開悟」を意図するものである。このことが、桂博士の「趣旨は同じ」という指摘である。決して「私の煩悩と仏のさとりは本来一つ」などといった内容ではない。むしろ、煩悩と菩提はまったく異なるが、如来の智慧と慈悲を拠りどころとして大乗菩薩道を実践するならば、煩悩を転じて菩提を得ることができるという、成仏の可能性を示すものである。
その転迷開悟のために「聞・思・修」による成仏道が、仏説である大乗経典を根拠として論書で体系化され、さまざまな学派や宗派が生まれるのである。そうして生まれたどの教えも「私の煩悩と仏のさとりは本来一つ」だから成仏できるというような短絡的なものではない。むしろ仏教の歴史の中では、そのような安易な理解こそ、かえって仏の智慧と慈悲を否定するものであり、危険思想に陥るという指摘が繰り返しなされている。
以上のように、桂博士は、決して冊子のように「私の煩悩と仏のさとりとは 本来一つゆえ」という理由をもって、阿弥陀仏の救いを説明できると意見されているわけではない。桂博士や梶山博士の学恩を受けた多くの方々は、両博士が「私の煩悩と仏のさとりとは 本来一つゆえ」という一行の内容を仏教思想として認めたかのような印象操作をしている⑤の内容に、強い憤りを覚え、深い悲しみを抱いておられるであろう。
【補記】
(2)の⑤《桂紹隆博士の意見》についての基本的な問題点は示し終えたが、今後の不毛な議論を避けるため、「煩悩即菩提」という漢訳の表現について、桂博士が『大乗荘厳経論』と『摂大乗論』の二箇所にあるとし、その梵語原文について「趣旨は同じである」と指摘してくださっている点について、述べておきたい。
まず、『大乗荘厳経論』の該当箇所は、第十三章「随修品」第十二偈の世親釈に引用される経文の一部である。梵語原文は「煩悩と菩提は同一(一つ)である」(「本来」ではない点に留意)という意味であるが、文脈的には、この説示には仏・如来の深い意趣(密意)があるのであって、単純に「同一」と理解してはならないと誡めている箇所である。
また、『摂大乗論』の該当箇所は第十章「果智分」の中の偈文であり、仏のあり方(仏身)は「不可思議」であることの説示における一句である。『摂大乗論』の漢訳は四本あり、その中の一本が「煩悩即菩提」と漢訳している。しかし、有名な玄奘訳の当該箇所は「煩悩成覚分」、つまり「煩悩が覚分(菩提)と成る」という意味であり、残る二つの漢訳も玄奘訳とほぼ同じ内容である。この『摂大乗論』の梵語原文は散逸して現代に伝わっていないが、他の梵語文献に引用されており、そこから回収・復元される梵語原文もチベット訳も、玄奘訳と同じ意味である。
いずれにしても「煩悩と菩提が本来一つ」という意味ではなく、まして「私の煩悩と仏のさとりとは本来一つ」などということでは決してない。冊子制作者は、指摘された該当箇所を確認し、漢訳の「煩悩即菩提」の説示内容と意図をどのように検討し理解して、この冊子にしたのだろうか。もし検討したのならば自分に不都合な部分を無視したことになるし、検討すらしていないのならば極めて礼を失した行為というよりほかはない。
以上、この冊子に引用されている先学の文章の本来の論述意図を確認するとともに、冊子の引用手法が、いかに恣意的で悪質なものであるか、その一端を示した。
あえて冊子制作者の意図を推し量れば、仏の智慧とは空の体得であり、法蔵菩薩の修行も阿弥陀仏の救済もすべては空の原理に貫かれているという印象を、読み手に与えようとしているのかも知れない。
しかし冊子が述べるところの空の理解は、すでに述べてきたように誤りである。その上「空からの招き・よびかけ」などと述べ、煩悩具足の凡夫を「そのまま救う」という阿弥陀仏の慈悲が空から起ると主張しているようであるが、この重大な一点についての聖教上の文証は存在しない。すなわち、どれほど印象操作を繰り返しても論証にはならず、ただ不快な読後感を与えるだけである。
このような内容の冊子が総合研究所から出され、全寺院へ送付されたことは、本願寺派の教学研究そのものへの信頼を失墜せしめるものである。そして、引用された先学に教えを受けた人たちは、恩師の業績をこのような稚拙な文章に利用され、強い憤りと深い悲しみの声を上げている。この冊子が先学の業績を傷つけるだけではなく、その学恩を大切にする方々をも傷つけていることを、冊子の制作責任者である満井氏(現勧学寮員)は知るべきである。
最後に
声明(七)を結ぶにあたり、この総合研究所発行の冊子に対する勧学寮の対応について、言及しておきたい。
これまで述べてきたとおり、この冊子の内容は、学問的にも道義的にも許されないものであるが、冊子は結論において、
あらためて言いうることは「私の煩悩と仏のさとりは本来一つゆえ」の一行は、勧学寮の同意があるように浄土真宗の法義として、また仏教思想史的にも問題はなく、序論でも述べたように議論の余地はないといえる。
と主張している。このように稚拙な内容をもって全国の寺院へ発送され、「議論の余地はない」と断言して、各地の僧侶・門信徒の戸惑いや不安の声を封じ込めようとしている冊子について、勧学寮はどのように考えているのであろうか。勧学寮は、この冊子によって、さらなる混乱の渦中に巻き込まれていることを自覚しているのだろうか。
現在に至るまで、勧学寮はこの冊子について沈黙したままである。浄土真宗の根本的立場を無視し、辻褄合わせの説明のために聖教の御文を扱い、自己正当化のために先学の文章までも恣意的に利用するこのような冊子を、はたして勧学寮は、ただ黙認するのであろうか。
勧学寮は、ご門主の唯一の諮問機関として、浄土真宗本願寺派という宗門の宗意安心を護る最高機関である。まさにその一点においてこそ、現在に至るまで全国の僧侶・門信徒からの信頼が得られ、その権威が保たれてきた機関なのである。もし、この総合研究所冊子の内容に対して、適切な見解を示し、その指導力を発揮することができないのであれば、もはや現在の勧学寮は、その機能を失っていると言われても仕方がない。
思えば、二〇二二年十二月十九日、勧学寮がご消息「新しい領解文(浄土真宗のみ教え)」の文案について「同意」をしたその時点から、本願寺派宗門の未曽有の混乱は始まっている。そしてご消息「新しい領解文」が発布され、その解説文を公開して以来、勧学寮は宗門の混乱を収めるために、何らの具体的対応をなしておらず、この総合研究所冊子についても、沈黙し続けている。現在の勧学寮は、これまでの勧学寮が得てきた信頼も権威も失墜させていると言わざるを得ず、宗意安心を護るというその根本的な職責をも果たせていないようである。まことに悲しいことであり、私たちは深く失望しているのである。
称名
二〇二四年 五月 二十日
浄土真宗本願寺派 勧学・司教有志の会
代表 深川 宣暢(勧学)
森田 眞円(勧学)
普賢 保之(勧学)
宇野 惠教(勧学)
内藤 昭文(司教)
安藤 光慈(司教)
楠 淳證(司教)
佐々木義英(司教)
東光 爾英(司教)
殿内 恒(司教)
武田 晋(司教)
藤丸 要(司教)
能仁 正顕(司教)
松尾 宣昭(司教)
福井 智行(司教)
井上 善幸(司教)
藤田 祥道(司教)
武田 一真(司教)
井上 見淳(司教)
他数名







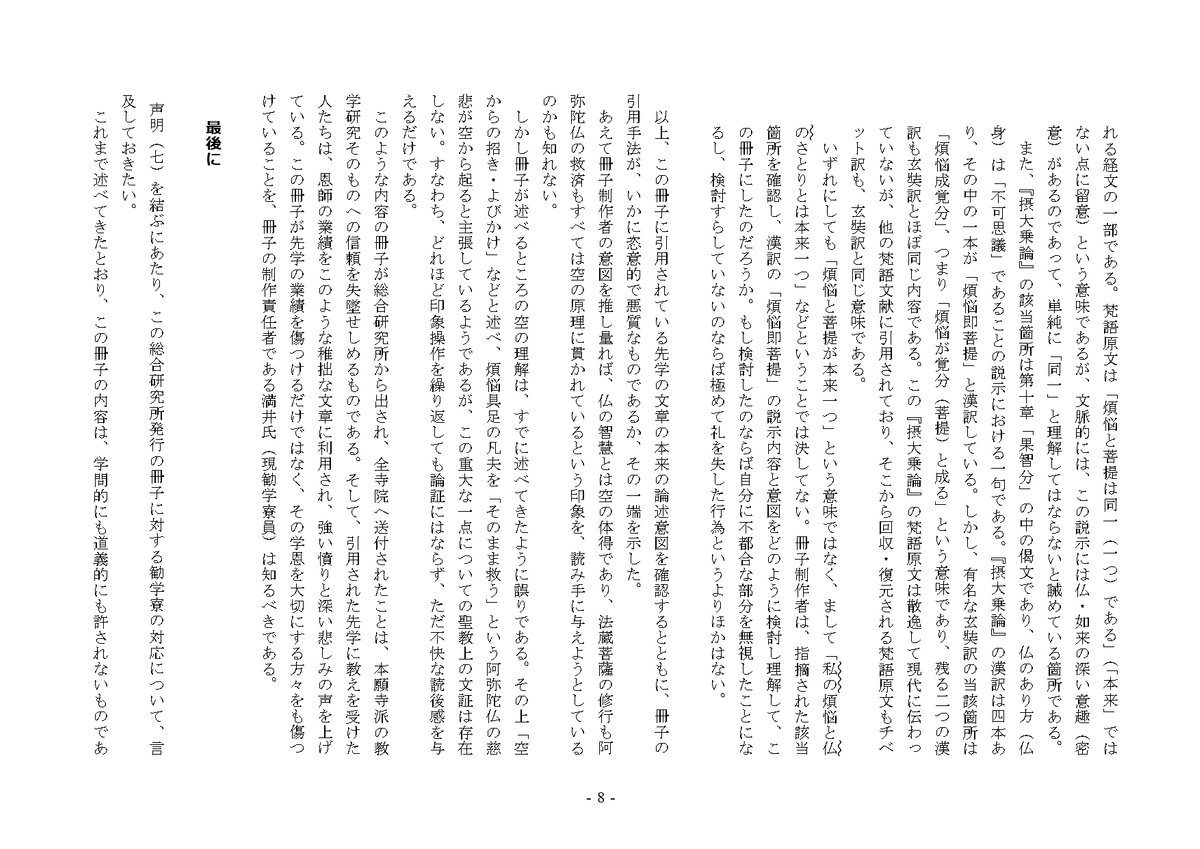

いただいた浄財は、「新しい領解文を考える会」の運営費に活用させていただきます。
