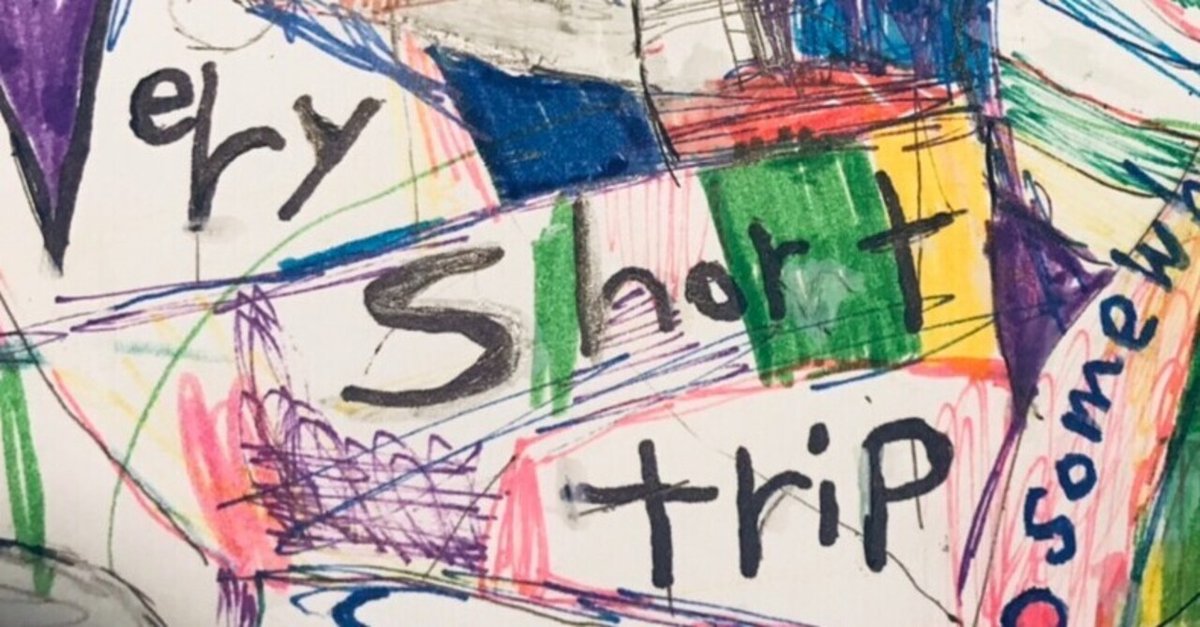
ベリーショートトリップ〜たまにどこかに行っている〜
9 湯行黙浴、養生訓
彼岸が過ぎ、いつの間にか朝夕肌寒くなった。
季節の変わり目のせいか、あるいは例の注射を打ったせいからか、それは知らないが、ここしばらくの間どうもすっきりしない。不調とまではいかないが、今月は不規則な生活もたたり、間があれば臥せっていた。
連休の1日目は昼過ぎに座布団を枕にして横になるといつの間にか日が暮れていた。何度も目は覚めるが、ふてくされたように起き上がらずにまた眠りに潜り、気がつけば夜中の0時。そこで起きてもすることがなく、床に入りまた明け方までうつらうつらする。夜勤のサイクルが体から抜けず、いつも仮眠状態で熟睡を味わったことがない。要するに慢性の時差ぼけ状態なのだ。
いくつか対処療法はあり、その一つが入浴である。
ここのところ、シャワーばかりで、しばらく湯船に浸かっていなかった。
午前5時。のそのそと起き上がり、風呂場に向かう。窓が濃いブルーに変わり、かすかな光がステンレスの浴槽に反射している。
風呂は旧式のガス釜いわゆるバランス釜というやつで点火にコツがいる。まずハンドルをグルグル回し火種を起こす。ハンドルが回転する度に火打石のようにパチパチと火花が散る。次に点火操作つまみを種火の位置にして種火に引火させる。そのまましばらく引火させ、引火した状態で、つまみを本火の位置に回すと着火する。しかし、種火引火の時間が短いと本火に着火せず消えてしまい、また火種を起こさなければならない。だいたい10秒くらいで着火するが、寒いとなかなか着火しない。今日は2回目で着火。着火とともにつまみをシャワーから出湯に切り替えると、ようやく蛇口からお湯が出て、白みかけた浴室に湯気が立ち込めた。
寝すぎで頭痛がする。湯が溜まる間、バター茶を淹れて待つことにした。いつしか読んだチベットの紀行文に出てきて試して以来、体調が思わしくないときはコーヒーよりもこのバター茶を飲むようにしている。体が温まって良い。といっても本格的なものではなく、市販のティーパックを鍋でグツグツ煮出し、小さじ一杯の砂糖に牛乳に岩塩をひとつまみ、最後にバターをひとかけ沈めだけである。バター茶をゆっくり二杯飲み終えた頃、湯が溜まった。
さて、抗時差ぼけ入浴療法とは単に風呂に入るだけなのだが、いわゆる湯治と同じく、1日に何度も入るのである。まさに湯行と言っていい。
熱めの湯に10分ぐらい浸かり、2、3時間たったらまた入る。6時にまず一回目。その後8時、10時、12時前と午前だけで4回は入った。
湯に長く浸かるのが苦手でまさにカラスの行水のため、繰り返し入るうちにだんだん退屈になり、いろんな入り方をした。頭まで潜り、膝を抱え、まるで胎児のような格好で息をこらえながら沈んでみたり、風呂の蓋を頭の上に被せサウナ状態にして汗をかいてみたり、追い炊きをし、耐えられるだけの熱さまで熱したところで冷水を浴びたり、要するに暇なのである。
昼食に蕎麦を茹でて食べたあと、だいぶふやけて軽くなった体を横たえるとまた少し眠気が襲ってきた。楽にはなったが、どうもあと一息というところでしっくりこない。
このまま午後も入り続けてもあまり変化はなさそうだ。
(やはり行くしかないか)
と思いっていたら少し眠ったらしい。
目が覚め、ここまできたらトドメの湯行として温泉に行くことに決めた。
◉
遠刈田温泉は以前、夜勤が明けるとよくその足で行っていた湯場であるが、1時間近くかかり、最近はその気力もなく足が遠のいていた。
しかし、本物の温泉は効力が全く違う。温泉は成分で効能はさまざまあるが、私の体に一番合っていてよく行くのは蔵王の青根温泉である。ただ効力からすれば同じく蔵王の麓にある遠刈田温泉の方が上だ。
タオル一本を持って車を走らせること1時間。遠刈田に着く。
ところでこの遠刈田には公衆浴場が二つある。温泉街の中心にある神の湯と少し離れたところにある寿の湯である。運営は同じだが、この二つの浴場は暗黙のルールというかある区分けが敷かれている。
大きめの神の湯はいわば観光客向けであり、小さめの寿の湯は地元人向けでなのだ。しかし、そうした案内はどこでにもなく、自然と客層がそういう風に分かれている。なぜそうなるかというと、寿湯は地元人向けだけあって相当に熱く、まず入れない。泉質はほぼ同じだが、神の湯は水足して冷ましてある。それでも熱めの方で、初めて来た観光客などは熱い熱いと言いながら入るぐらいの温度である。寿の湯はそれよりも熱く43℃〜45℃。熱い湯が好きな強者でないと入りたくても入れないのだ。また神の湯が自動入浴券なのに対し、寿湯は入り口に未だに番台があり、お金を直接払うという希少な銭湯形式で、どこか奥ゆかしい格式めいたものを感じさせる。
そんなこともあり、神の湯の客層と寿の湯の客層は違うわけであるが、具体的にどう違うかといえば、神の湯の客は腹の出た親父がよく洗い場で寝転んでいたり、脱衣所にびちゃびちゃに濡れたまま上がってきたり、湯船につかったかと思えば、プールのようにそのまま浮かんでみたりする人たちがいる。一方、寿の湯は、まず、浴場で会ったら必ず挨拶をしなければならない。また、桶などを使ったら元の位置に戻し、湯船でもゆっくり静かに浸かる。上がる時にはお先しますといい、体をよく拭いてから上がる。という具合だ。これは誰がそうしろと言ったことではなく、子供が親を真似るように自然とできた風気なのだろう。
では神の湯が風気の乱れた荒れた湯場であるかといえばそうでもない。またに例に挙げた人がいるのはた仕方なく大抵の人はお行儀よく入っている。寿の湯に比べたらゆるい感じというところだろうか。
そういえば、神の湯がゆるいながらも秩序を保っている理由を思いだした。かつて夜勤明けで開店間際に神の湯に行っていた時いた名物爺さんの事である。神の湯は観光客向けではあるが、朝は地元人も入りに来ている。その一人に入り口近くでいつも体を洗っている頭がスキンヘットのガリガリに痩せた90ぐらいの爺さんがいた。その爺さん、ずっと体を洗っている。どんだけ洗うんだというくらい洗っている。骨と皮だけのような体をもうなくなるくらい洗っている。やがて入り口から人が入ってくる。その人が何気なくそのまま戸を閉めて入ってこようとするその時、入り口の戸がピッチっと最後まで閉まりきらなかったとする。するとその爺さんここぞとばかりにすかさず
「戸ー閉めでげ!コノーー!!!」
と怒鳴りつけるのだった。
何も知らない客は突然のことで震え上がったようにそわそわとしながら入り口に戻り、わずかに閉まりきらなかったとを閉め直す。
桶を使ったまま戻さなければ
「おげ戻せコノー!!」とまた怒鳴りつける。
ヨボヨボ爺さんなのに、かなり迫力があり、怒鳴られた方がそれなりのおっさんであっても大概はそわそわしてまう。
あの爺さんは多分、湯の神の化身だったのかもしれない。あるいは、いつもずっと身体を洗いながら、湯場の秩序を守る、湯守。だいぶ前のことだからもういなくなっているだろう。あんな風に怒鳴る爺さんというのはもはや天然記念物のように見つけるのが難しい。
あいにく、今日はこのご時世でどちらの湯も開店が16時からとなっていた。最近は若者向けの洒落たお店が並んでおり、温泉街も幾分賑わっている。
16時寿の湯へ入る。
3人ほど地元人らしき人と挨拶を交わす。白熱球の薄灯に湯船が見えないほどに湯気がたちこめている。
強大な地熱の威力を放つ湯に体を沈め、しばし、湯行。そして、黙浴。
5分浸かるのがやっとである。
骨まで染みるような湯に感服し「お先します」と言ってあがった。これで養生完了である。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
