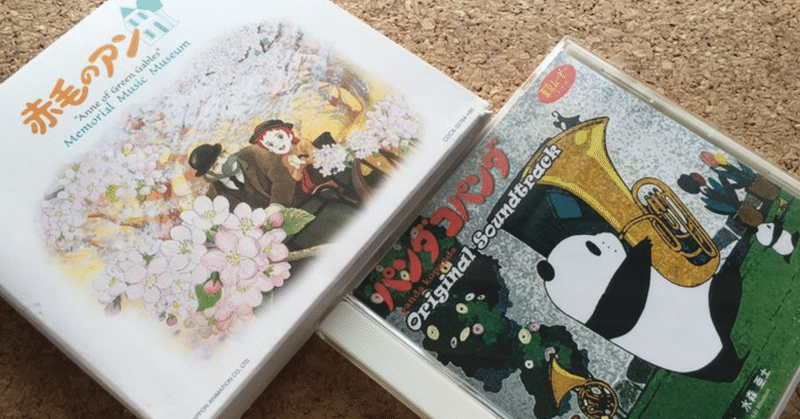
TVアニメ『赤毛のアン』についていくつかのこと
いましがた、『赤毛のアン』のことをTwitterのTLで目にしたので、検索してみるとどうやら細田守監督が『世界一受けたい授業』というテレビ番組で「絶対に観てほしい5つのアニメ」の中に『赤毛のアン』を挙げていたということだった(他は『エースをねらえ!('79年公開の劇場版)』『機動戦士ガンダム』『銀河鉄道999('79年公開の劇場版)』『ルパン三世 カリオストロの城』とのこと)。
これもいい機会だろうと感じたので、過去にTwitterやTumblrで書いたことをまとめて以下に転記した。
2017年5月3日。NHKで20時から『発表!あなたが選ぶアニメ ベスト100』という番組が放送されていた。これはまったく偶然なのだけれど、その日の昼間に『母をたずねて三千里』1話の「マルコ横顔長回し」超絶テンションのカットと、直前にいきなりインサートされる「俯いたマルコ主観に母親の顔がフレームインしてくる」驚嘆すべきレイアウトのカットを見ていた際に、「日本アニメのテレビシリーズでナンバーワンってなんだろう?」という会話があって、コンマ0.2秒で「そりゃ『赤毛のアン』でしょ」と私は答えた。放送された番組でのランキングは残念ながら記憶にない。
余談だが、上に書いた《『母をたずねて三千里』1話の「マルコ横顔長回し」超絶テンションのカットと、直前にいきなりインサートされる「俯いたマルコ主観に母親の顔がフレームインしてくる」驚嘆すべきレイアウト》はYouTubeの日本アニメーション公式チャンネルで観ることができる。20分15秒〜21分30秒まで。きちんと冒頭から観て、そして前後の繋がりも意識すると異様な緊張感が感じられるかと思う。レイアウトやカットを意識して観たときは度肝を抜かれた。
『母をたずねて三千里』第1話「いかないでおかあさん」
こんな長回しのFix(カット尻にT.U.があるとはいえ)、画面が保つ・成立すると絵コンテ上で確信するその判断力。成立させたのは作画と声の演技だけでなく、長回しで横顔を見せられる人物の「主観」が直前に一瞬入るからではないか。そして長回し直後、マルコが俯いた顔をパッと上げる美しく完璧なアクション!正面からマルコを捉えるカメラは先ほどまで母がいた場所にある!
(注:実際にはT.U.トラックアップではなく映像用語としてはズームアップなのですが、一般的なアニメの撮影用語としてT.U.という言葉を使用しています)
閑話休題。
2010年に『赤毛のアン』が編集され劇場作品『赤毛のアン グリーンゲーブルズへの道』として公開した際に、宣伝用特番かなにかのインタビューで高畑勲監督が「(企画制作準備中に)日本語でしゃべらせたときにどんな仕草でやればいいのかわからなくて」といったようなこと(正確な引用ではありません)を語っていて、そこから考えるの!?と絶句した記憶がある。
テレビアニメ『赤毛のアン』1話はマシューが駅からアンを家に連れて行く馬車で揺られる「だけ」の話。それで信じられないくらい面白い。2話はマリラが家に来たアンに驚く「だけ」。3話はマリラがアンを帰らせるために馬車に乗せて揺られる「だけ」。それで震えるほど感動する。信じ難いが本当だ。アンが馬車に揺られながら身の上話をしてゆくと、ある地点で「ああ、マリラの表情が変わったなあ」と思ったらそのあとに「馬車が向きを変える」カットがちゃんと入っている。
映画『かぐや姫の物語』では高畑勲監督が「原典を読んでみても、主人公のかぐや姫ってなにを考えてるのか、わからん」(要約)から作品づくりがスタートしている。『赤毛のアン』でも「アンがわからなかった」(要約)という意味の発言をしている。
高畑勲監督作品の凄みは自身が共感する人物または代弁者を作品中にあからさまには設定しない部分だと思っている。『赤毛のアン』での高畑勲はアンでもマリラでもマシューでもない。共感ベースで語る部分がとても少ない。だからこそ多くの人にとって映すものが違う鏡となる。物語作品でそれを徹底するのはとんでもないことだ。
【2016年4月6日、高畑勲監督の訃報を受けて】
今日は映画『ホーホケキョ となりの山田くん』サントラ盤から「ケ・セラ・セラ」と、映画『かぐや姫の物語』サントラ盤から「天人の音楽I、II」を繰り返し聴いている日だった。どちらも憂いなどこの世にないかのように眩しすぎるほど明るく、だからこそ恐ろしくもある、生についての曲と、死についての曲。 私が『かぐや姫の物語』を観ている最中に涙を拭ったのは、月からの一行が人間たちやかぐや姫の想いなど一向だにせずノーテンキなユルユルと愉しげなサンバのような音楽でやってくるところだった。極楽浄土から阿弥陀如来が来て横からのウェストショットになって音が掻き消え、「Mmーー」と上の階で回る洗濯機みたいな音だけが微かに聞こえる。そうだよね、こうでなくっちゃいけないよね、とその圧倒的な演出の正確さに、恐怖にも近い畏怖の念を覚えて涙が頬をつたったのだった。
テレビアニメ『赤毛のアン』のサントラ盤からは、この2曲を聴く。
誰かが わたしを つれてゆくのね
白い花の道へ 風のふるさとへ
もえる雲の下へ なみだつ みずうみへ つれてゆくのね
(『赤毛のアン』オープニング曲「きこえるかしら」歌:大和田りつこ/作詞:岸田衿子/作曲:三善晃)
はしっても はしっても おわらない 花の波
みずうみは遠く もえるくもは もっと遠く
花の中で 一日は終わる さめない夢みたいに
(『赤毛のアン』エンディング曲「さめない夢」歌:大和田りつこ/作詞:岸田衿子/作曲:三善晃)
このOP曲とED曲は、歌詞が対になっているのだ。開幕では「誰かが迎えに来て、自分を花の道や雲の下や湖へと連れて行ってくれる」と高らかに歌い上げるのだけれど、閉幕ではそれが一転し、花の波は走っても走っても終わらず、湖は遠く、雲はもっと遠く、そこに辿り着けぬまま一日は終わる。
〈現代音楽作曲家の三善晃がTVアニメ主題歌を初めて手がけたことが注目されて、当時の新聞に、優れた歌だが高級すぎて子供には難解なのでは、などという記事が載った。私はそんな批判は何の意味もないと思った〉
CD『コロムビア サウンド アーカイブス シリーズ 赤毛のアン 想い出音楽館』(日本コロムビア)ブックレットに掲載された高畑勲「赤毛のアン、音楽の思い出」より
テレビアニメ『赤毛のアン』は第1話から最終話までOPとEDが繰り返し、こう歌い続ける。どこかに幸せな楽園がありそこへ誰かが連れて行ってくれるのではなく、未来への希望を胸に何処かを目指し自身で道を歩き日々を過ごすその過程こそに幸せがあるのではないか、と。その日々は、まるで覚めない夢かのように。
絶望の淵で座り込んでいたアンに、マシューやマリラや友人たちとの日々が与えたのは──そして同時に、アンの姿がマシューやマリラや友人たちに見せたのは──希望を抱き歩き続ける力だ。望みは天に、歩みは地に。
「神は天にいまし すべて世はことも無し」(テレビアニメ『赤毛のアン』最終話タイトルより)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
