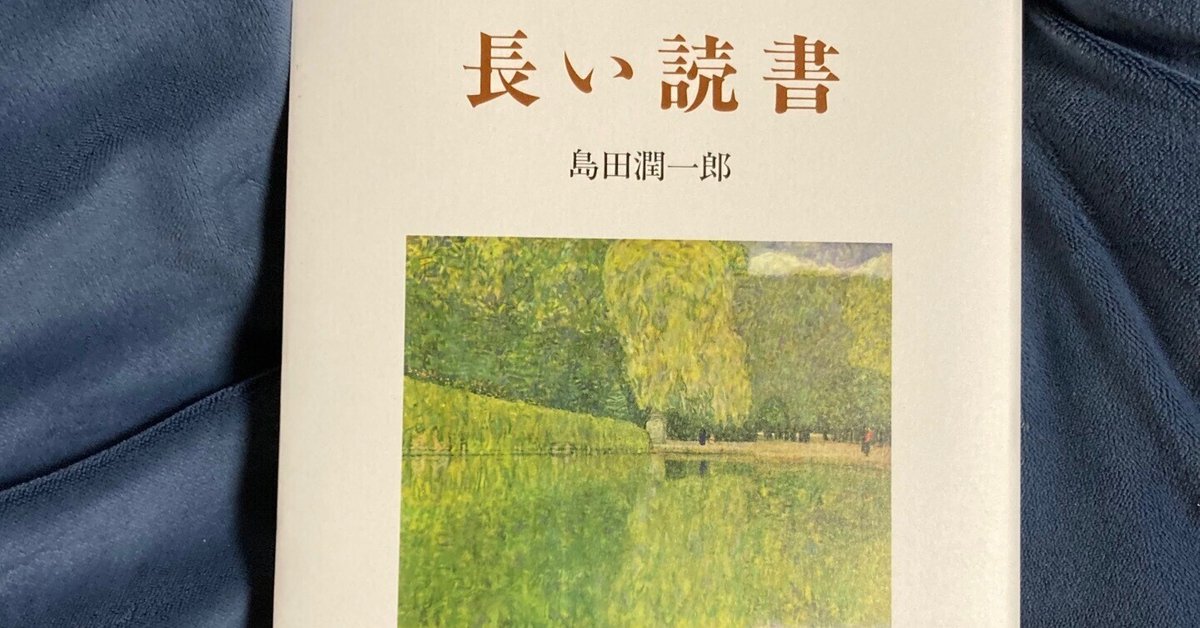
『長い読書』を読んで
朝起きてコインランドリーで洗濯物を済ませたあと、隣町の〈珈琲館〉まで歩いた。昨晩、職場からの帰りに丸善日本橋で買った『長い読書』をわたしは読みはじめた。
1頁読む毎に何かをおもいだす、不思議なエッセイ集だ。
ハイパーリンクの張り巡らされたコスモス(宇宙)へと連れ去られる。 そこでは万物が照らし合っている。 万物照応。 ひとつの想起が別の想起を生んでは著者自身も予想のつかない衝突をくりかえしている。
感化の力はつよい。読み手であるわたしの意識の底にある鍵穴に鍵が差し込まれる。そこに鍵穴があったことにまず驚いているじぶんがいる。解像度の高い想起のスイッチが押され、想起乱れ打ちの一種の確変モードが始まる。 なにを見てもなにかを思い出してしまう。
たとえば、卒業以来会っていない中学の同級生のO君のこと。たとえば、20歳の頃にプルーストの『失われた時を求めて1「スワン家のほうへ 1
』(岩波文庫)を読んだところで続きを読むのをやめたこと。たとえば、地元にある〈たらば書房〉で10年前にクレジオの『調書』を買って読んだこと。
脳内のスクリーンで繰り広げられる「記憶の編集劇」ともいうべき事態は自動筆記みたいなもので、じぶんでも止めることはできない。想起はじぶんのなかで起こっているのに、その様子を一歩引いて眺めているじぶんがいる。 恒星の間をわたしは飛行していく。インターステラー。
思い出された情景の数々。読み終える頃には頭の中で本が1冊分出来上がりそうな勢い。でも想起は生まれたそばから露と消えていく。だから、本書の後ろにわたしにだけ見えているもう1冊の書物は永遠に架空の存在のままだろう。二重露光。埋もれ木。生まれなかった本も含めて本だとおもう。
なんでそう考えたのかはわからない。でも、実際にあったこと9割と島田さんが想像して書いたこと1割でこの文章ができていたらいいな、とおもった。
それからそれから、いま思い出せるのは、家に帰ったらこの本をW. G. ゼーバルト『移民たち』と須賀敦子『コルシア書店の仲間たち』のあいだに差しておこうとふとおもったことだ。それ以外のことは忘れてしまったみたいだ。
全体の3分の1読んだところで本を閉じてわたしは店を出た。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
