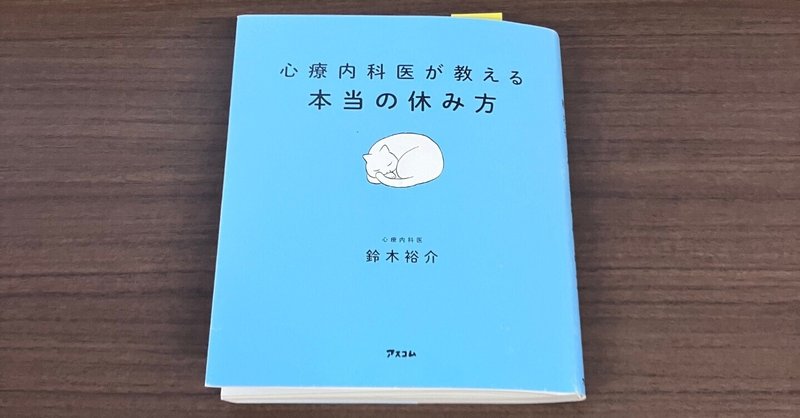
トラウマ関連の読書記録⑭「休みたい」
心の底から心身をゆっくりと休めたい
この本がトラウマ治療に関連があるのか?と言われると、ちょっとよくわからない。ただ、「しっかりと休めない」というのはトラウマを持っている人にありがちだし、本の中にポリヴェーガル理論やトラウマについても書いてあるので関連があると考えた。
今の私が考える目下最大のテーマの1つは「ちゃんと休みたい、リラックスしたい」である。という訳で、トラウマ治療界隈(ってどこだ)で話題になっていたこの本を読まない訳にはいかなかった。
私たちがどれだけ疲れているか、そしてそれを自覚していないか
この本の前半は、ストレッサーの種類やストレスが体に及ぼす影響、仕組みなどが丁寧に説明されている。人の身体はストレスを誤魔化すようにできていること、身体に出る症状のサイン、コミュニケーションでの疲れ、過剰適応、解離などなど。
他者のニーズを満たすのではなく、自分のニーズ、自分の身体のニーズに気づくこと、そして応えること。
休むのには勇気がいる。他者のニーズばかりを満たそうとするのは、安心したいからだ。そうするとどんどん自分のニーズがわからなくなっていく。休むことに罪悪感や自己否定もある。悪循環に嵌まっていく。
とってもわかる。私は休みたいし自分のニーズを満たしたいし、そうする必要がある。
疲れというのがそもそも自覚しにくいことなのだということも実感としてよくわかる。私の場合はトラウマが影響しているせいもあるのだろうと思う。
ポリヴェーガル理論と自律神経のバランス調整
この本は「休みたいけど休めないよね、わかるよ」ということだけを書いているのではなかった。メインは(私には)お馴染みのポリヴェーガル理論と、自律神経の調整だった。ポリヴェーガル理論の説明はとてもわかりやすい。もちろんわかりやすくしているため、理論については端折っている部分もあるだろうけど、これぐらいで十分だと思う。
交感神経と副交感神経、背側迷走神経系と腹側迷走神経系、そして闘争・逃走モードと凍り付きモードについて書いてあるが、闘争・逃走モードを「炎のモード」、凍り付きモードを「氷のモード」と表現してあってわかりやすい。そして、人は安全・安心を感じることでちゃんと休めて癒しを得ることができるが、そのためには自律神経の調整を行う腹側迷走神経系を優位にすることが必要になってくる。
思春期の子どもがなりがちな「起立性調節障害」についても書いてあるが、まさに自律神経のバランスが崩れた結果なのだとわかる。
動けない自分を受け入れることができるか
まずは、自分の自律神経が「炎のモード」なのか「氷のモード」なのかを自覚することから始まる。ただし、どちらの状態もそれ自体が「悪いこと」ではない。
ちなみに「氷のモード」は背側系の自律神経が優位になっている時に入り、引きこもったりシャットダウンしたりする。でもこれを、避けないといけない悪い事態だから何とかしなくてはと焦ったり否定することは全く意味が無い。
「ここで、私が提案したいのは『背側系に入っていることの必要性を理解し、その状態を積極的に肯定していく』ということです。」
「危機をやりすごして自らの身を守り、エネルギーを節約し、回復に向かうために必要なプロセスなのです。」
こんな状態になっていたら、じっくり休むしかなくなるし、それが一番の近道になるのだろうと思う。でもこれを自分自身で受け入れられずに自己否定に陥ることが多い。
自律神経のバランスを取るためにできること
この本の後半は「正しい休養行動を取る具体的な方法」が書いてある。
コーピング、腹側迷走神経を刺激するエクササイズなどはすぐに使えそうだ。実際に毎日朝晩やっているが、なかなかいい。
そして、自分の身体の内側の感覚である「内受容感覚」について。心臓がドキドキするとか、胃がきゅっとなる感じなどの身体の感覚のことである。内受容感覚は感情の根源にあるもので、幸福感や安心感に直結している。全身からの内受容感覚を脳で受け取って「私が私であるという感覚」が生まれているらしい。内受容感覚を感じる練習も載っている。
それからリソースについても書いてある。安全・安心のもととなるもので、どんなささいなものでもいい。自分の周りのリソースを探して集める。
これはSE(ソマティック・エクスペリエンシング)でセラピストにも言われたことだ。
最後に「BASIC Ph」について書いてあった。これは私も初めて知った。自分自身に合ったコーピングを理解するための概念として紹介されている。
治療もセルフケアも大事にしたい
私の「休みたいのに休めない」は、トラウマ由来もあると思うので、治療が進めば少しずつ変わっていくだろうと思っている。多分。
ただ、この本に書いてあるような自分自身へのケアも地道にやっていきたい。
「休めない私はダメだ」とは思わないのだけど、とにかく疲れたなあという気持ちが最近大きくなっている。これまでは気づかなかったのかもしれない。この気持ちを尊重したい。
わかりやすくて優しくて、とてもいい本だった。あっという間に読んだけど、本に書いてあったことはちゃんと入ってきた感覚がある。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
