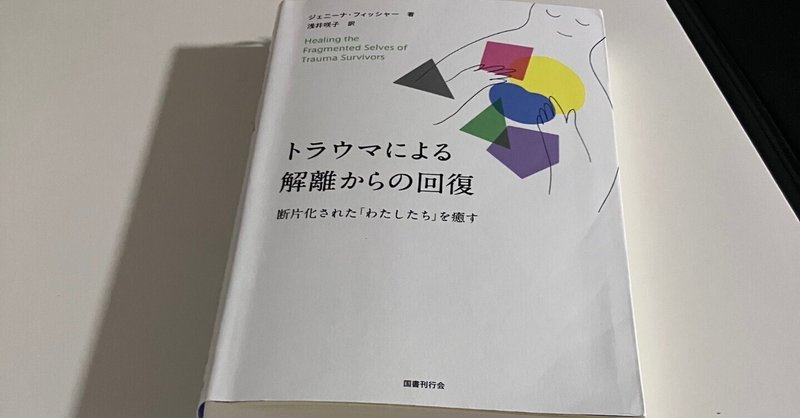
トラウマ関連の読書記録②「トラウマによる感情の断片化」
ずいぶんと遠くまで来てしまった
当初、私は家族に関する困りごとがあり、びっくりするぐらい不安が大きい自分のことをどうにかしたいと思っていた。私が変われば状況も変わるのではないかとも思っていた。そして、ネットで知った某講座を受講した。
結論から言えば、心理学でよくある知識を使う、素人の高額な講座だった。今の時点での私には、その講座でのことは全く何も残っていない。否定はしないし、あれが必要な人もいるのだろうけれど、私としては最初からカウンセリングや治療を受けていたらよかったと思う。知識って本当に大事だ。
ただ、あの時の私の気持ちや自己に対する意識の状態では、あの講座が精いっぱいだったのだとも思う。
アダルトチルドレンという概念を自分のこととして考えるようになって、ようやくカウンセリングを受けることにした。自分のために大学院で心理学の講座をいくつか受けるようになった。そして、トラウマ治療について知った。
アダルトチルドレンというのは、「状態」のことなのだなと思う。
幼少期に機能不全家庭でトラウマを受けた子のことをそう呼ぶのだと。
トラウマというのは、生死にかかわるような大きな出来事とは限らない。両親に話を聞いてもらえなかったとか、一人ぼっちだったとか、そういうこともトラウマになる(生死にかかわるようなトラウマは「ビッグT」、そうではないものは「スモールt」と呼ぶらしい)。
そして、トラウマを受けた脳がどのように記憶をして、その子が生き延びるためにどのように機能するかということが神経科学の面から研究されてきた。脳や体にトラウマは記憶されて残っているらしい。
ここまでの流れは、私にとってはかなりしっくりくるものであった。
ショートカットでたどり着けるものならそうしたかったけど、1年かかってしまった。でもたどり着いたのだから十分だ。
とりあえず、ここに細々と残しておこうと思う。
トラウマによるパーツ
「断片化」とは、パーツのことである。
構造的解離理論と神経生物学モデルを融合させてセラピーを行い、クライアント自身がトラウマのパーツを癒していくようにする。
この本では解離性障碍の重篤な事例なども多く載っており、「いや私はここまでじゃないけど…」という感じにはなった。そういう意味では、事例については自分に寄せて読むことがなかなか難しかったように思う。でもそれを差し引いても、読んでよかったと思える本だった。自分で愛着を育てていくということ、置き去りにされた子どもの自分に気づいて共感し、寄り添うことがどれだけ大事なのか改めてわかった。
人はとにかく、うまく生き残るためにいろんな手を使って適応しようとする。子どもも同じだ。
幼少期の脳は右脳が優勢らしい。詳細はこの本の中できちんと説明されているので省くが、幼少期の右脳での経験は左脳とは独立している。
左脳は経験と情報を表すために言葉を使い、左脳にふだんの日常を送る自己がいる。一方右脳は言語を持たず、事実のままオリジナルを保存する。感情は両方の脳で経験されるが、左脳でのみ言語化される。脳梁を介して左右の脳の情報のやり取りが行われないと左脳は右脳の記憶を持つことができない。そして、脳梁は20歳ぐらいに完成する。しかも虐待やネグレクトを受けた場合は、脳梁は通常より未発達になるのだそうだ。右脳は置いてきぼりだ。
子どもは防衛反応を使って自分の安全を確保する。辛い出来事に対しては心理的な距離を取り、本能的に「パーツ」として分離する。右脳に感情を分離したパーツを作り、そのパーツが子ども自身が生き延びるための役割を引き受ける。一方左脳では「通常の子どもとしての発達」をして、何とか日常を送ろうとする。
子どもの辛かったままの自分が、今も右脳に分離されて「その時の辛いまま」で生き続けている。まだまだピチピチしている。ちなみにパーツは1つだけとは限らない。複数の場合の方が多いのだろう。怒り、悲しみ、愛着の欲求、たたかう、逃げる…いろんなパーツが、子ども時代の辛い時に役割を果たしてくれていたのだ。
このパーツたちに左脳の自分(大人で日常を送っている私自身)が気づき、受け止めて気持ちを通わせ癒していく、というのが目的となる。
パーツは統合され無くなる訳ではないらしい。左脳の私自身がパーツを有効に前向きに役立てることができるようになる、とあった。
ちょっと何言ってるかわからない感じかもしれないが、本を読めばわかると思う。
ちなみに、「パーツ」はインナーチャイルドのことなのだろうと思う。左脳=大人の自分、右脳=インナーチャイルドという話も聞いたことがある。たぶんスキーマ療法の「脆弱な子どもモード」や「懲罰的ペアレントモード」も同じことなのかなと感じている。
そして、どれも同じことを言っている。「傷ついた子どもの自分を受け止めて対話し、癒していく」ということだ。
次世代への連鎖を止められる
パーツたちに気づき、気持ちに共感し受け止めて癒していくと「安定型愛着」を獲得できるとある。つまり、親に愛されて育った子どもと同様の安定した愛着を持てるようになるという。
「健全な内的愛着を構築することによって、人間は潜在記憶や過去の物語を変容させられるので、獲得した安定型愛着が次世代にも伝わるのです。それによりトラウマを世代間で連鎖させずに、安定型愛着の世代間伝搬を通して新しい遺産を伝授していけるのです。」
これは非常にうれしい。私は絶対に世代間連鎖だけは止めたいと思っている。他の何を置いても、それだけは何とかしたい。だからこんなに必死になっているというのもある。こんなのを子どもに引き継ぐなんて真っ平ごめんだ。
個人的には、「獲得した安定型愛着」って最強では?と思っている。
「なんか知らんが小さい頃親に愛されて育てられた」という安定型愛着もいいけれど、それだって何かしらのトラウマや傷がゼロな訳ではない。そんなに能天気な人間はいない。そして、彼らは自分の中を知らないままだ。
一方で自分の中の傷つきや苦しみに目を向けて受け止めて、自分の中と深く繋がって獲得した安定型愛着は、酸いも甘いも知ってるぜという感じがするのだ。私の中は私が育てる。
というか、私がこれでいいじゃんと思っているのだからこれでいい。最高だ。
ナラティブはどこまで必要か
この本の中で何度も言われるのは「トラウマを詳細に語ることは不要」ということだ。幼いパーツたちの経験してきたことやトラウマの歴史の感覚や概要だけが必要となる。
過去の記憶を語り尽くすことが、トラウマの治療になるわけではないのだと。
この本にある解離性障碍などの重篤な例だと、そういった出来事を語るだけでも圧倒されてパーツが活性化してしまい、自己破壊などの行動に出ることがあるらしい。とても危険だ。
前までのトラウマ治療はあれもこれも全部語り尽くしてください、というスタンスだったが、それは不要とのこと。
ただ、語ることで癒されたり気づいたりすることも多くあると思う。特に私のような、多少の症状はあるものの「生きづらい」というのが主訴の場合は、記憶を思い出すことは辛いけれどそれ以外には特に支障は無い。
最初は「自分はあんなことされた、こんなこと言われた、やっぱりひどかったんだうちの親は」「私は周りの幸せそうな子とは違ってた」みたいなところから入るのではないか。自己憐憫と被害者意識の沼。
その沼にドップリ浸かってから、沼を抜け出して次の一歩を進めるのではないかなと思う。
しかしこの沼は、予想よりも生暖かくて案外居心地がいい。ただ、その沼に浸かったままだとどこにも進めないわけだけど。
なにはともあれマインドフルネス
この本にも重要なこととしてマインドフルネスが出てきた。
もう必須という感じだ。とにかくマインドフルネスを身に付けろ。
自分の中をマインドフルに見つめることができれば、もうこっちのものという感じがする。
どこを見ても何を読んでも必ず出てくるマインドフルネス。身に付けることができたら財産になる。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
