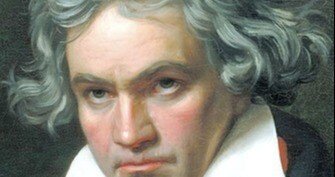#Beethoven

ベートーヴェン:ヴァイオリンソナタ第8番 ト長調 Op.30-3(Beethoven:Violin Sonata No.8 in G major, Op.30 No.3 )
00:00 I. Allegro assai 06:49 II. Tempo di minuetto, ma molto moderato e grazioso 13:52 III. Allegro vivace 公開者情報. Pandora Records/Al Goldstein Archive 演奏者. Paul Rosenthal, violin ; Edward Auer, piano 著作権 EFF Open Audio License 備考 Performed 1982. Seattle: Lakeside School ベートーベンの『ヴァイオリンソナタ第8番 ト長調 Op.30 No.3』は、彼が1801年から1802年にかけて作曲した三つのヴァイオリンソナタの一つです。この三作品は一緒にOp.30として出版されました。特に第8番は、このシリーズの中で最も軽やかで親しみやすい作品とされています。 ### 構成 ソナタは以下の四つの楽章から構成されています: 1. **アレグロ・アッサイ** - この楽章は活発で明るいムードで始まり、ヴァイオリンとピアノが華やかな対話を繰り広げます。 2. **テンポ・ディ・メヌエット, ma molto moderato e grazioso** - 第二楽章はメヌエットとして書かれていますが、伝統的なメヌエットよりもゆったりとしたテンポで、非常に優雅な雰囲気を持っています。 3. **アレグロ・ヴィヴァーチェ** - 第三楽章は軽快なスケルツォで、このソナタの中でも特に明るく元気な部分です。ベートーヴェンらしいユーモアが感じられる楽章です。 4. **アレグロ・ヴィヴァーチェ** - 最終楽章も高速なテンポで、技術的に要求されるパートが多いです。ピアノとヴァイオリンが見事な技巧を披露しながら、作品を力強く締めくくります。 ### 解説 Op.30 No.3は、ベートーヴェンが初期から中期にかけてのスタイルの変化期に作曲された作品の一つです。この作品では、彼独特の音楽言語と表現の幅の広がりが見られます。特に、この時期のベートーヴェンの作品には、古典派音楽の形式を踏襲しつつも、その枠組みを超えた音楽的探求が見られ、後のロマン派音楽への道を示唆しています。 このソナタでは、ベートーヴェンの作曲技法の特徴であるモチーフの発展や対位法の技術、豊かな和声言語が随所に見られます。また、ヴァイオリンとピアノの間の対話や、楽章を通じてのアイデアの展開が見事に描かれており、ベートーヴェンの室内楽作品の中でも特に親しみやすい作品とされています。 全体として、ヴァイオリンソナタ第8番は、ベートーヴェンの作曲技術と音楽的表現の豊かさを示す素晴らしい例であり、彼のソナタ作品の中でも特に人気のある作品の一つです。 チャンネル登録 https://www.youtube.com/channel/UCqAFiZznfr5Y7wgfV_sOiGQ Walk Into Siena コミュニティ https://www.youtube.com/@WalkIntoSiena/community ベートーヴェン 再生リスト https://youtube.com/playlist?list=PLTtHiFCVwL1zT3TDzCFkYRGchw_08y2KG ベートーヴェン「ヴァイオリンソナタ」 再生リスト https://www.youtube.com/playlist?list=PLTtHiFCVwL1z8Amf6sxbhe-ICQdPQT4Us クラシック全般 再生リスト https://youtube.com/playlist?list=PLTtHiFCVwL1yxp2hTQ64gcreupYj8u6jd #ベートーヴェン #ヴァイオリンソナタ第8番 #ト長調 #Op30の3 #Beethoven #ViolinSonataNo8 #Op30 #No3

ベートーヴェン:弦楽三重奏曲第4番 ハ短調 作品9-3(Beethoven:String Trio in C minor, Op.9 No.3)
00:00 I. Allegro con spirito 05:42 II. Adagio con espressione 13:51 III. Scherzo: Allegro molto e vivace 16:49 IV. Finale: Presto パスキエ・トリオ 1950年代録音 Pasquier Trio Recorded on 1950s ベートーヴェンの弦楽三重奏曲第4番 ハ短調 Op.9-3は、有名な古典音楽の作品の一つです。この作品は、ベートーヴェンが初期に作曲した弦楽三重奏曲の一つであり、同じくOp.9に属する「弦楽三重奏曲第1番」「弦楽三重奏曲第2番」を含む三曲から成り立っています。 弦楽三重奏曲とは、ヴァイオリン、ヴィオラ、チェロの三つの弦楽器で演奏される楽曲であり、古典音楽の中でも非常に重要なジャンルの一つです。また、この曲はベートーヴェン初期の作品としては非常に重要な位置を占めています。 この曲は、ハ短調で書かれており、雰囲気には暗さや悲しさが感じられます。しかし、ベートーヴェンの音楽にはいつものように力強さや情熱も感じられます。演奏時間は約25分ほどであり、三つの楽章から構成されています。 この作品は、ベートーヴェンの音楽の中でも非常にクラシックな様式を持ち、時代背景から見ても非常に特徴的な作品です。また、弦楽器の音色や調和、リズムやメロディーの美しさなど、音楽的な魅力を持ち合わせています。 今でも、多くの音楽愛好家に愛され、演奏されるこの作品は、ベートーヴェンの音楽を知る入門的な作品としてもお勧めです。 Beethoven's String Trio in C minor, Op.9 No.3 is one of the composer's most celebrated chamber works. As the final work in his Opus 9 set of string trios, it showcases Beethoven's remarkable ability to blend technical proficiency with emotional depth. The String Trio in C minor is scored for violin, viola, and cello, and consists of four movements. The first movement, marked Allegro con spirito, is a stunning display of Beethoven's signature style. Full of dramatic contrasts and virtuosic solos, it sets the tone for the rest of the piece. The second movement, Adagio con espressione, is a lyrical and introspective aria-like melody, full of expressive nuance and harmonic richness. The third movement, Scherzo: Allegro molto e vivace, is a playful and energetic scherzo with syncopated rhythmic motives that drive the music forward. The final movement, Finale: Presto, is a frenetic and intense tour-de-force that showcases Beethoven's ability to write technically demanding music that never loses sight of its emotional content. Even within Beethoven's vast catalogue of chamber music, the String Trio in C minor stands out as a masterpiece of the genre. Whether played in concert halls or private salons, it continues to captivate audiences with its emotional power and technical brilliance. ベートーヴェンの弦楽三重奏曲第4番 ハ短調 Op.9-3は、ヴァイオリン、ヴィオラ、チェロのための三重奏曲の一つとして、1797年から1798年頃に作曲されました。この作品はOp.9の三つの弦楽三重奏曲の中で最も人気があり、演奏される機会も多いです。 Op.9の三重奏曲は、ベートーヴェンが若く、まだウィーンに滞在して間もない時期の作品ですが、彼の才能と革新性が光る作品群となっています。特に第3番は、その構造や発展、そして感情の深さから、ベートーヴェンが後に弦楽四重奏曲や交響曲で示すであろう傾向の萌芽を感じさせるものとなっています。 この三重奏曲の構成は以下のようになっています: 1. Allegro con spirito 2. Adagio con espressione 3. Scherzo: Allegro molto e vivace 4. Finale: Presto この作品は、情熱的で激しいハ短調の部分と、美しい旋律を持つ中間部分が交錯することで、ベートーヴェンらしいダイナミックな構造を持っています。特に第1楽章は、音楽の激しい感情と緻密な構築が感じられる部分であり、ベートーヴェンの革新的な手法が窺えます。 全体として、この三重奏曲はクラシック期の形式とロマン派の感情の融合が見られる作品で、ベートーヴェンの中期への移行を予感させるものとなっています。 ベートーヴェンの弦楽三重奏曲第4番 ハ短調 Op.9-3に関する追加情報: 1. **歴史的背景**: Op.9の三重奏曲群は、ベートーヴェンがウィーンに定住した初期に書かれました。この時期、ベートーヴェンはまだ若く、ウィーンの社交界や音楽界での地位を築こうとしていました。Op.9の三重奏曲は、その技術と情熱で、彼の作曲家としての才能を確固たるものとした証となります。 2. **作品の特徴**: - 第1楽章は緊張感と情熱に満ちており、激しい表情が特徴です。 - 第2楽章は歌心に富む美しい旋律が印象的です。 - 第3楽章のスケルツォは軽やかで躍動感に満ちており、ベートーヴェンのユーモアのセンスも垣間見られます。 - 第4楽章は高速で終始駆け抜けるような楽章で、技巧とエネルギーが際立っています。 3. **受容**: 当時のウィーンの音楽愛好家や評論家たちは、この三重奏曲を高く評価しました。特にハ短調の三重奏曲は、その情熱的な構造と深い感情から注目を浴びました。Op.9の三重奏曲は、ベートーヴェンがウィーンの音楽界での地位を確立する助けとなりました。 4. **後世への影響**: ベートーヴェンのこの時期の作品は、後のロマン派の作曲家たちに大きな影響を与えました。情熱的で緻密な構造は、後の世代の作曲家たちによって模倣されるとともに、新たな音楽的探求のヒントとなりました。 総じて、Op.9-3のハ短調三重奏曲は、ベートーヴェンの音楽的発展の重要なステップであり、彼の作品の中でも特に価値のあるものとして認識されています。 Walk Into Siena チャンネル登録 https://www.youtube.com/channel/UCqAFiZznfr5Y7wgfV_sOiGQ Walk Into Siena コミュニティ https://www.youtube.com/@WalkIntoSiena/community ベートーヴェン 再生リスト https://youtube.com/playlist?list=PLTtHiFCVwL1zT3TDzCFkYRGchw_08y2KG クラシック全般 再生リスト https://youtube.com/playlist?list=PLTtHiFCVwL1yxp2hTQ64gcreupYj8u6jd #ベートーヴェン #弦楽三重奏曲第4番ハ短調 #作品9の3 #Beethoven #StringTrio #Op9 #No3

ベートーヴェン:ヴァイオリンソナタ第7番 ハ短調 作品30-2(Beethoven:Violin Sonata No.7 in C Minor, Op. 30, No.2)
00:00 I. Allegro con brio 07:16 II. Adagio cantabile 16:03 III. Scherzo: Allegro 19:22 IV. Finale: Allegro - Presto 演奏者 Corey Cerovsek (violin) Paavali Jumppanen (piano) 公開者情報 Boston: Isabella Stewart Gardner Museum 著作権 Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives 3.0 ベートーベンのヴァイオリンソナタ第7番 ハ短調 Op.30-2は、ドイツの作曲家、ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーベンによって作曲されたバイオリンソナタのひとつです。この作品は、1802年に完成され、ヴァイオリニスト、ロドルフ・クレーツェツァーに献呈されました。 ベートーベンのヴァイオリンソナタ第7番は、ハ短調で書かれており、その悲壮的な音楽が特徴的です。この作品の第1楽章は、力強く重厚な主題から始まり、感情的な展開を見せます。第2楽章は、より静かで美しいメロディーを持つアンダンテです。第3楽章は、ハンガリー的なリズムやメロディーが特徴的なスケルツォであり、第4楽章は、情熱的なフィナーレを迎えます。 ベートーベンのヴァイオリンソナタ第7番は、独特な音楽性とともに、演奏家にとっても高度な技術を要する作品です。また、ベートーベンが自分の感情や思いを込めて作曲したとされるこの作品は、聴衆に力強い感動を与える作品として知られています。 ベートーベン:ヴァイオリンソナタ第7番 ハ短調 Op.30-2は、ヴァイオリンとピアノのための魅力的な作品であり、ベートーベンの音楽を愛する人々にとっては、必聴の作品と言えます。 Beethoven: Violin Sonata No.7 in C Minor, Op. 30, No.2, also known as the Second Sonata in C Minor, is a masterpiece composed by Ludwig van Beethoven between 1801 and 1802. It is the second of three violin sonatas in the Op. 30 collection. The work consists of four movements, and it is considered to be one of Beethoven's most technically challenging pieces for the violin. The first movement, Allegro con brio, opens with a dramatic and intense theme that sets the tone for the entire piece. The second movement, Adagio cantabile, is a slow and lyrical movement that showcases the violinist's ability to express emotion through the instrument. The third movement, Scherzo: Allegro, is a fast and playful section that features quick notes and intricate rhythms. The final movement, Finale: Allegro, is a high-energy conclusion to the piece, marked by syncopated rhythms and strong dynamics. What makes this sonata truly remarkable is not just its technical difficulty, but also the depth of emotion that Beethoven was able to convey through the music. The C minor key signature provides a sense of tension and darkness, which is reflected throughout the piece in the form of unpredictable harmonies, sudden shifts in dynamics, and unexpected melodic turns. Today, Beethoven's Violin Sonata No.7 remains a cornerstone of the classical violin repertoire and is often performed in concert halls around the world. Its mix of technical virtuosity and emotional depth continues to inspire generations of musicians and music lovers alike. ベートーヴェンのヴァイオリンソナタ第7番 ハ短調 Op.30-2は、彼の全10曲あるヴァイオリンソナタの中の一つで、1801年から1802年にかけて作曲されました。この時期はベートーヴェンが進行する難聴に直面し、個人的な危機を経験していた時期でもありますが、彼の音楽にはその苦悩が表れることなく、むしろ革新的な要素が多く取り入れられています。 Op.30には他にも2つのヴァイオリンソナタ(第6番、第8番)が含まれており、第7番はその中でも特に人気があり、多くの演奏家によって演奏されています。 このヴァイオリンソナタ第7番は、以下の4つの楽章からなります: 1. Allegro con brio 2. Adagio cantabile 3. Scherzo: Allegro 4. Finale: Allegro - 第1楽章は、伝統的なソナタ形式で、情熱的な主題と対照的な第二主題が展開されます。 - 第2楽章は、詩的で深い感情の表現が見られるもので、ベートーヴェンの中期の作品に特有の深みと内省的な性格を持っています。 - 第3楽章は、軽快なスケルツォで、中央部にはトリオが置かれ、その後スケルツォが戻ってきます。 - 第4楽章は、リズミックな主題が特徴的で、そのエネルギッシュな音楽が楽章全体を通して展開されます。 このソナタは、ヴァイオリンとピアノのためのデュオとしての均等な役割を強調しており、どちらの楽器も独立して重要な役割を果たしています。ベートーヴェンのヴァイオリンソナタは、以降のヴァイオリンとピアノのための室内楽作品に多大な影響を与えました。 **1. バックグラウンド:** ベートーヴェンは1801年から1802年にかけてOp.30の3つのヴァイオリンソナタを書きました。この時期は彼の難聴が進行していることを実感し始め、それが後の人生や音楽にどれほどの影響を及ぼすかに深い不安を感じていました。しかし、この3つのソナタでは、彼の苦悩や危機を乗り越える意志が感じられるとともに、彼が音楽言語をさらに革新しているのを確認することができます。 **2. 構造と特徴:** - Op.30の3つのソナタは、それぞれ異なるキーで書かれていますが、第7番のハ短調はこの中で最もドラマティックで情熱的です。 - ピアノとヴァイオリンは、ともに音楽的な対話を持ちながら、それぞれの楽器の個性を活かした独立した声を持っています。この点が、ベートーヴェンのヴァイオリンソナタが特に注目に値する理由の一つです。 **3. 受容:** このソナタは公開当初から評価が高く、その後もヴァイオリンソナタの中で特によく演奏される作品の一つとなっています。ヴァイオリニストやピアニストの間でも、この作品の深さや情熱、そして技術的な挑戦が評価されています。 **4. 影響:** ベートーヴェンのヴァイオリンソナタは、後の作曲家たちに大きな影響を与えました。特に彼のようにピアノとヴァイオリンを対等なパートナーとして扱うアプローチは、19世紀のロマン派の作曲家たちに引き継がれ、新しいヴァイオリンソナタの形成に寄与しました。 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 ヴァイオリンソナタ第7番(ヴァイオリンソナタだいななばん)ハ短調 作品30-2 は、ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェンが作曲したヴァイオリンソナタ。 概要 前後に連なる第6番や第8番とともに、1802年頃に作曲されたと推定されるヴァイオリンソナタである。出版は1803年。第6番、第8番とともにロシア皇帝アレクサンドル1世に献呈されており、この経緯から3曲とも通称「アレキサンダー・ソナタ」とも呼ばれている。 作曲推定年である1802年は、10月に「ハイリゲンシュタットの遺書」が認められるなど、ベートーヴェンにとってはある意味で追い込まれた年ではあったが、その一方で「英雄」の作曲が始められるなど、いわゆる初期から中期への転換に差し掛かる時期でもあった。第7番は前作第6番のイ長調、後作第8番のト長調のような明朗な調とは違い、厳しい調であるハ短調で書かれている。この「作品30」の3曲から、ベートーヴェンのヴァイオリンソナタはモーツァルトの影響を脱し、独自の境地を築くこととなる。 曲の構成 全4楽章、演奏時間は約26分。 第1楽章 アレグロ・コン・ブリオ ハ短調、4分の4拍子、ソナタ形式。 第2楽章 アダージョ・カンタービレ 変イ長調、2分の2拍子、複合三部形式。 第3楽章 スケルツォ:アレグロ ハ長調、4分の3拍子。 第4楽章 フィナーレ:アレグロ - プレスト ハ短調、2分の2拍子、ロンドソナタ形式。 Walk Into Siena チャンネル登録 https://www.youtube.com/channel/UCqAFiZznfr5Y7wgfV_sOiGQ Walk Into Siena コミュニティ https://www.youtube.com/@WalkIntoSiena/community ベートーヴェン 再生リスト https://youtube.com/playlist?list=PLTtHiFCVwL1zT3TDzCFkYRGchw_08y2KG クラシック全般 再生リスト https://youtube.com/playlist?list=PLTtHiFCVwL1yxp2hTQ64gcreupYj8u6jd #ベートーヴェン #ヴァイオリンソナタ第7番 #作品30の2 #Beethoven #ViolinSonataNo7 #Op30No2

ベートーヴェン:弦楽三重奏曲第3番 ニ長調, Op.9-2(Beethoven:String Trio in D major, Op.9 No.2)
00:00 I. Allegretto 11:02 II. Andante quasi allegretto 12:15 III. Menuetto: Allegro 16:29 IV. Rondo: Allegro 演奏者 Musicians from Marlboro (String Trio) 公開者情報 Boston: Isabella Stewart Gardner Museum 著作権 Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 ベートーヴェンの弦楽三重奏曲第3番 ニ長調, Op.9-2は、ドイツの作曲家ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェンが作曲した弦楽三重奏曲の一つです。この曲は、1797年に作曲され、Op.9というシリーズの中の2番目の曲です。 この曲は、ヴァイオリン、ヴィオラ、チェロのために書かれており、3つの楽器が同等に扱われ、美しい旋律や複雑なリズム、豊かな和声が特徴です。また、この曲の演奏には、3人の演奏家が密接に協力し、一つのアンサンブルとして同調する必要があります。 この曲は、ベートーヴェンが若き日に作曲した作品の一つであり、当時の音楽界に大きな影響を与えました。また、この曲は、後のベートーヴェンの作品にも影響を与え、彼の発展に大きな役割を果たしたとされています。 弦楽三重奏曲第3番 ニ長調, Op.9-2は、古典派音楽の中でも重要な作品の一つであり、現代の音楽愛好家にも愛され続けています。是非、一度聴いてみることをお勧めします。 Ludwig van Beethoven, one of the greatest composers of all time, has left us with a remarkable legacy of music. One of his most remarkable pieces is the String Trio in D major, Op.9 No.2. This work is one of a set of three string trios, and was composed in 1798–99, shortly after the First Symphony. The String Trio in D major is a masterpiece of chamber music, and is a testament to Beethoven's ability to create magnificent works for small ensembles. The piece consists of four movements – Allegretto, Andante quasi allegretto, Menuetto – Allegro, and Rondo – that demonstrate the composer's mastery of form and structure. The opening movement, Allegretto, is a light-hearted and charming piece with a lively theme that is introduced by the violin, answered by the cello, and then imitated by the viola. The second movement, Andante quasi allegretto, is more introspective, with a melancholic melody played by the viola and accompanied by the violin and cello. The third movement, Menuetto – Allegro, is a dance-like piece that is both rhythmic and playful. Finally, the concluding Rondo is lively and exuberant, with a catchy refrain that is repeated throughout the movement. Walk Into Siena チャンネル登録 https://www.youtube.com/channel/UCqAFiZznfr5Y7wgfV_sOiGQ Walk Into Siena コミュニティ https://www.youtube.com/@WalkIntoSiena/community ベートーヴェン 再生リスト https://youtube.com/playlist?list=PLTtHiFCVwL1zT3TDzCFkYRGchw_08y2KG ベートーヴェン「ピアノソナタ」再生リスト https://youtube.com/playlist?list=PLTtHiFCVwL1wx8p370mNaQ7Ap00CYMRmH&si=ZJyq2TWV_K9qt4Ir クラシック全般 再生リスト https://youtube.com/playlist?list=PLTtHiFCVwL1yxp2hTQ64gcreupYj8u6jd #ベートーヴェン #弦楽三重奏曲第3番ニ長調 #Op9の2 #Beethoven #StringTrio #Op9No2

ベートーヴェン:弦楽三重奏曲第2番 ト長調 Op.9-1(Beethoven:String Trio in G major, Op.9 No.1)
00:00 I. Adagio - Allegro con brio 09:44 II. Adagio ma non tanto e cantabile 16:37 III. Scherzo: Allegro 21:30 IV. Presto 演奏者 Musicians from Ravinia's Steans Music Institute (ensemble) 公開者情報 Boston: Isabella Stewart Gardner Museum 著作権 Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives 3.0 ベートーヴェンという名前は、音楽史上に残る偉大な作曲家として知られています。彼が生み出した数多くの作品の中でも、その中でも「弦楽三重奏曲第2番 ト長調 Op.9-1」は、特に名高い作品の一つです。この曲は、ヴァイオリン、ビオラ、チェロの3つの楽器を使った室内楽曲で、全3曲からなる「弦楽三重奏曲集Op.9」の中の第一番の作品になります。 この弦楽三重奏曲は、ベートーヴェンが26歳の時に作曲されました。当時の彼は、既に音楽において非常に優れた才能を持っており、この作品でもその才能を実証しています。この曲は、美しい旋律や巧みなリズム、そして三つの楽器が絡み合って生み出す深い響きが特徴的で、聴き手を魅了する作品となっています。 また、この曲は、3つの楽器が同等に重要な役割を果たすことが要求され、楽器の独奏のように扱われることがあります。そのため、演奏者にとっても非常に難易度が高く、才能が要求される作品となっています。 以上のように、「弦楽三重奏曲第2番 ト長調 Op.9-1」は、ベートーヴェンの代表作の一つであり、音楽史上においても非常に高い評価を受けている作品です。音楽好きなら、ぜひこの曲を聴いてみてください。 ベートーヴェンの弦楽三重奏曲第2番 ト長調 Op.9-1は、彼の早期の作品であり、1797年から1798年頃に書かれました。Op.9には3つの弦楽三重奏曲が含まれており、これらの作品はベートーヴェンの室内楽作品としての才能を強く示しています。以下はOp.9-1に関する簡単な解説です。 - **編成**: ヴァイオリン、ヴィオラ、チェロ - **構成**: 以下の4つの楽章で構成されています。 1. **Allegro con brio**: ヴィヴァートで始まる典型的なソナタ形式の楽章。ヴィヴァートのテーマが繰り返され、発展的な中間部を経て、再現部で元のテーマに戻ります。 2. **Adagio ma non tanto e cantabile**: 美しいメロディが特徴的な楽章で、ベートーヴェンの感受性と深い表現力が際立っています。 3. **Scherzo: Allegro**: この曲のスケルツォは、軽やかでリズミックで、途中のトリオ部分が挿入されています。 4. **Presto**: 速めのテンポで始まり、勢いよく進行する楽章。ソナタ形式に基づいており、ベートーヴェンの技巧とエネルギッシュな性格が感じられます。 Op.9の三重奏曲は、ベートーヴェンが室内楽作品を真剣に取り組んだ証とも言えます。これらの作品は、彼が後に弦楽四重奏曲やピアノ三重奏曲で展開していくスタイルや技巧の前触れを感じさせます。Op.9-1のト長調の三重奏曲は、明るくて活力に満ち、ベートーヴェンの青春期のエネルギーと熱意を感じさせる作品です。 ベートーヴェンの弦楽三重奏曲第2番 ト長調 Op.9-1の背景や作品の詳細 1. **受け入れられた背景**: Op.9の三重奏曲は、当時のウィーンの音楽愛好家たちによく受け入れられました。これらの作品が成功したことで、ベートーヴェンはウィーンの音楽界での地位を確固たるものとしました。 2. **献呈**: この三重奏曲セットは、重要なパトロンであり友人でもあったアンドレアス・キルヒバッハ伯爵に献呈されています。 3. **技巧と構築**: ベートーヴェンは、三つの楽器の間で音楽的な対話を織り成すことに成功しています。彼は各楽器の特性と可能性を最大限に活かしており、それがこの三重奏曲の魅力の一部となっています。 4. **比較**: Op.9の三重奏曲は、モーツァルトやハイドンの影響を受けているとしばしば指摘されますが、ベートーヴェンはこれらの作品で独自の音楽的言語と発展の方向を確立しました。 5. **後の作品への影響**: Op.9の三重奏曲は、ベートーヴェンが後に執筆する室内楽作品、特に弦楽四重奏曲やピアノ三重奏曲に大きな影響を与えました。 ベートーヴェンは自身のキャリアの中で多くのジャンルの作品を書きましたが、室内楽作品では彼の深い感受性や革新的な発想が特に際立っています。Op.9の三重奏曲は、彼の早期の室内楽作品として、後の成熟期の作品への橋渡しの役割を果たしています。 From Wikipedia, the free encyclopedia The three String Trios, Op. 9 were composed by Ludwig van Beethoven in 1797–98. He published them in Vienna in 1799, with a dedication to his patron Count Johann Georg von Browne (1767–1827). They were first performed by the violinist Ignaz Schuppanzigh with two colleagues from his string quartet. According to the violinist and conductor Angus Watson, these were probably Franz Weiss on viola and either Nikolaus Kraft or his father Anton on cello. Each of the trios consists of four movements: Op. 9 No. 1: Adagio – Allegro con brio String Trio No. 3 in G major, Op. 9 No. 1 I. Adagio - Allegro con brio II. Adagio ma non tanto e cantabile III. Scherzo – Allegro IV. Presto Walk Into Siena チャンネル登録 https://www.youtube.com/channel/UCqAFiZznfr5Y7wgfV_sOiGQ Walk Into Siena コミュニティ https://www.youtube.com/@WalkIntoSiena/community ベートーヴェン 再生リスト https://youtube.com/playlist?list=PLTtHiFCVwL1zT3TDzCFkYRGchw_08y2KG クラシック全般 再生リスト https://youtube.com/playlist?list=PLTtHiFCVwL1yxp2hTQ64gcreupYj8u6jd #ベートーヴェン #弦楽三重奏曲第2番ト長調 #Op9の1 #Beethoven #StringTrio

ベートーヴェン:ヴァイオリン・ソナタ第4番 イ短調 作品23(Beethoven:Violin Sonata No.4 in A minor, Op.23)
The Violin Sonata No. 4 of Ludwig van Beethoven in A minor, his Opus 23, was composed in 1801, published in October that year, and dedicated to Count Moritz von Fries. It followed by one year the composition of his first symphony, and was originally meant to be published alongside Violin Sonata No. 5, however it was published on different sized paper, so the opus numbers had to be split. Unlike the three first sonatas, Sonata No. 4 received a favourable reception from critics. From Wikipedia, the free encyclopedia 00:00 I. Presto 07:20 II. Andante scherzoso, più allegretto 16:19 III. Allegro molto 演奏者 Corey Cerovsek (violin) Paavali Jumppanen (piano) 公開者情報 Boston: Isabella Stewart Gardner Museum 著作権 Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives 3.0 https://imslp.org/wiki/IMSLP:Creative_Commons_Attribution_Non-commercial_No_Derivatives_3.0 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 ヴァイオリンソナタ第4番 イ短調 作品23 は、ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェンが1800年から1801年にかけて作曲したヴァイオリンソナタ。作曲者のヴァイオリンソナタとしては4作目のもので、初めての短調ソナタである。 概説 第1番 ニ長調、第2番 イ長調、第3番 変ホ長調と、ヴァイオリンの明るい響きを前面に押し出した作品群の後の激しい曲風である。ただ(小規模な)3楽章作品の形式は未だ守っており、この頃のピアノソナタが4楽章で管弦楽編曲をにらんだものとは事情が異なる。ヴァイオリンソナタはヴァイオリンとピアノとの調和の妙が一つの目的であり、ピアノ即ちオーケストラという作者の考えとは相違がある。この作品では後の第9番「クロイツェル」と同じ調性でヴァイオリンに演奏簡単なイ短調を選んでいる。 曲の構成 第1楽章 プレスト イ短調、8分の6拍子、ソナタ形式。 冒頭からピアノの主和音にのって、ヴァイオリンの重音が一気呵成に進められる。 第2楽章 アンダンテ・スケルツォーソ・ピウ・アレグレット イ長調、4分の2拍子、ソナタ形式。 室内楽に適した暖かい響きの中間楽章。ベートーヴェンの古典派作家としての一面を見せる優美な曲想である。冒頭におどけた舞踏を思わせるシンコペーションがヴァイオリン、ピアノの掛け合いで奏でられる。ソナタ形式でありこの点でも古典派作者の作である。 第3楽章 アレグロ・モルト イ短調、2分の2拍子、ロンド形式。 自由なロンド形式で書かれており、第1楽章同様に速いテンポが特徴的。 Walk Into Siena チャンネル登録 https://www.youtube.com/channel/UCqAFiZznfr5Y7wgfV_sOiGQ Walk Into Siena コミュニティ https://www.youtube.com/@WalkIntoSiena/community ベートーヴェン 再生リスト https://youtube.com/playlist?list=PLTtHiFCVwL1zT3TDzCFkYRGchw_08y2KG ベートーヴェン ピアノ協奏曲 再生リスト https://youtube.com/playlist?list=PLTtHiFCVwL1wBLC-eEetKFd__1S5alEa5 クラシック全般 再生リスト https://youtube.com/playlist?list=PLTtHiFCVwL1yxp2hTQ64gcreupYj8u6jd #ベートーヴェン #ヴァイオリンソナタ第4番 #作品23 #Beethoven #ViolinSonataNo4 #Op23

ベートーヴェン:ピアノ協奏曲第4番 ト長調 作品58(Beethoven:Piano Concerto No.4, Op.58)
From Wikipedia, the free encyclopedia Ludwig van Beethoven's Piano Concerto No. 4 in G major, Op. 58, was composed in 1805–1806. Beethoven was the soloist in the public premiere as part of the concert on 22 December 1808 at Vienna's Theater an der Wien. 00:00 I. Allegro moderato 17:53 II. Andante con moto 22:59 III. Rondo: Vivace 演奏者 Debbie Hu (piano) University of Washington Symphony Orchestra (orchestra) https://music.washington.edu/ensembles/university-washington-symphony-orchestra 公開者情報 Pandora Records/Al Goldstein Archive http://www.ibiblio.org/pandora/HOMEPAGE.html 著作権 EFF Open Audio License https://imslp.org/wiki/IMSLP:EFF_Open_Audio_License 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 ピアノ協奏曲第4番 ト長調 作品58は、ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェンが遺したピアノ協奏曲のひとつ。 概要 『ピアノ協奏曲第3番ハ短調』を完全な形で書き上げられてから最初に演奏された翌年にあたり、またベートーヴェン唯一のオペラ作品『フィデリオ』の元となった作品『レオノーレ』初稿の初演が行われた年でもある1805年に作曲に着手、翌1806年に完成させている。 オーケストラを従えてピアノ等の独奏楽器が華々しく活躍する協奏曲はピアニスト等の独奏楽器を奏でるプロ演奏家にとって自身の腕前を披露するのに適したものとされていたこともあり、従来の協奏曲ではオーケストラは伴奏役に徹するのが常で、実際の作品では、例えば冒頭部分に於いて、オーケストラが前座宜しく先にメロディを奏でていると後から独奏楽器が、まるで花道上に現れ歩みを進める主役の如く、やおら登場し華々しく歌い上げることが多いのであるが、進取の気風に満ちていたベートーヴェンは当楽曲でいきなり独奏ピアノによる弱く柔らかな音で始めるという手法を採り入れた。これは聴衆の意表を突く画期的なものとされ、驚きと感動をもたらしたと伝えられている。 更にベートーヴェンは伴奏役に徹しがちなオーケストラとピアノという独奏楽器を“対話”させるかのように曲を作るという手法も採り入れている。作曲当時使われていたピアノは現在流通しているものと比べて音量が小さく、それでいてオーケストラと対等に渡り合えるようにすべく、独奏ピアノの側にあっては分散和音やトレモロを駆使して音響効果を上げる一方、オーケストラの側にあっては楽章により登場楽器を限定したりしている《第1楽章ではティンパニとトランペットを参加させず、第2楽章は弦楽合奏のみに限定》。 当楽曲は完成の翌年・1807年の3月にまずウィーンのロプコヴィッツ侯爵邸の大広間にて小規模オーケストラを使って非公開ながら初演され、翌1808年の12月22日に同じくウィーンに所在するアン・デア・ウィーン劇場に於いて公開による初演を行っている(1808年12月22日のベートーヴェンの演奏会)。何れもベートーヴェン自身がピアノ独奏を務めているが、かねてから自身の難聴が進行していたこともあり、当楽曲が自身のピアノ独奏により初演された最後のピアノ協奏曲となった。 なお当楽曲は、ベートーヴェンの最大のパトロンであり、また彼にピアノと作曲を学んだともいわれるルドルフ大公に献呈されている。 楽器編成 独奏ピアノ、フルート1、オーボエ2、クラリネット2、ファゴット2、ホルン2、トランペット2、ティンパニ、弦5部 曲の構成 全3楽章で構成されており、演奏時間は36分《第1楽章20分、第2楽章6分、第3楽章10分》。 第1楽章 Allegro moderato ト長調 4/4拍子 協奏的ソナタ形式。前述のように「運命の動機」を含む穏やかな主題がピアノ独奏でいきなり奏されると、オーケストラはロ長調によりそれに応え、新鮮な印象を受ける。 カデンツァはベートーヴェン自身により2種類が書かれている。一つは100小節あり、多くのピアニストはこちらを演奏している。もう一つは50小節あり、マウリツィオ・ポリーニやアルフレート・ブレンデル、パウル・バドゥラ=スコダ等が演奏した録音により確認することが出来る。この他、ブラームス、クララ・シューマン、ゴドフスキー、ブゾーニ、メトネル、フェインベルクなどの名だたるピアニスト・コンポーザーたちがカデンツァを書いている。 第2楽章 Andante con moto ホ短調 2/2拍子 自由な形式。オーケストラが低音に抑えられた弦のユニゾンだけとなり、即興的で瞑想的な音楽を歌うピアノと、淡々と対話を続ける。 第3楽章 Rondo Vivace ト長調 2/4拍子 ロンド形式。ト長調であるが、主題はハ長調に始められる。 カデンツァはベートーヴェン自身により1種類書かれ、35小節ある。ヴィルヘルム・バックハウス作によるドラマティックで技巧的なカデンツァも有名。他に有名な所ではヨゼフ・ホフマン、エドウィン・フィッシャー、ヴィルヘルム・ケンプ、ルービンシュタインも独自の演奏をも時に用いていた。ヤン・パネンカは少しアドリブを入れて弾くが、その様なピアニストは現代にも時々見られる。 幻の初演改訂版 一般には1806年完成時の楽譜が出版されている。1808年の公開初演時にはさらに手を加えて演奏したとされていたが、その楽譜は長らく公にされていなかった。しかし、写譜屋が作成していた写譜の中の作曲者による注釈を元にして、音楽学者のバリー・クーパーが「改訂版」として復元に成功した。ロナルド・ブラウティガム独奏、アンドルー・パロット指揮のノールショピング交響楽団演奏によるCDが2009年にBISから発売されている。 Walk Into Siena チャンネル登録 https://www.youtube.com/channel/UCqAFiZznfr5Y7wgfV_sOiGQ Walk Into Siena コミュニティ https://www.youtube.com/@WalkIntoSiena/community ベートーヴェン 再生リスト https://youtube.com/playlist?list=PLTtHiFCVwL1zT3TDzCFkYRGchw_08y2KG ベートーヴェン ピアノ協奏曲 再生リスト https://youtube.com/playlist?list=PLTtHiFCVwL1wBLC-eEetKFd__1S5alEa5 クラシック全般 再生リスト https://youtube.com/playlist?list=PLTtHiFCVwL1yxp2hTQ64gcreupYj8u6jd #ベートーヴェン #ピアノ協奏曲第4番 #作品58 #Beethoven #PianoConcertoNo4 #Op58

ベートーヴェン:ヴァイオリン・ソナタ第3番 変ホ長調 作品12-3(Beethoven:Violin Sonata No 3 in E flat major, Op.12 No.3)
From Wikipedia, the free encyclopedia The Violin Sonata No. 3 of Ludwig van Beethoven in E-flat major, the third of his Opus 12 set, was written in 1798 and dedicated to Antonio Salieri. It has three movements 00:00 I. Allegro con spirito 08:16 II. Adagio con molto espressione 14:25 III. Rondo: Allegro molto 演奏者 Corey Cerovsek (violin) Paavali Jumppanen (piano) 公開者情報 Boston: Isabella Stewart Gardner Museum 著作権 Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives 3.0 ヴァイオリンソナタ第3番 変ホ長調 作品12-3 は、ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェンが1797年から1798年にかけて作曲した3曲のヴァイオリンソナタの1曲。他の2曲(第1番、第2番)とともに3部作として師であるアントニオ・サリエリに献呈された。ピアノに高度なアルペッジョ・半音階などを盛り込んでおり、新奇さを出している。 曲の構成 第1楽章 アレグロ・コン・スピーリト 変ホ長調、4分の4拍子、ソナタ形式。 冒頭からアルペッジョの華やかな展開。6連符が多くリズムに変化をつけている。 第2楽章 アダージョ・コン・モルト・エスプレッシオーネ ハ長調、4分の3拍子、三部形式。 穏やかな中間楽章。ピアノ左手部に3連符を使って単調さを避けている。 第3楽章 ロンド:アレグロ・モルト 変ホ長調、4分の2拍子、ロンド形式。 Walk Into Siena チャンネル登録 https://www.youtube.com/channel/UCqAFiZznfr5Y7wgfV_sOiGQ Walk Into Siena コミュニティ https://www.youtube.com/@WalkIntoSiena/community ベートーヴェン 再生リスト https://youtube.com/playlist?list=PLTtHiFCVwL1zT3TDzCFkYRGchw_08y2KG クラシック全般 再生リスト https://youtube.com/playlist?list=PLTtHiFCVwL1yxp2hTQ64gcreupYj8u6jd #ベートーヴェン #ヴァイオリンソナタ第3番 #作品12の3 #Beethoven #ViolinSonataNo3 #Op12No3

ベートーヴェン:ピアノソナタ第23番ヘ短調 作品57「情熱」Beethoven Piano Sonata No 23 In F Minor, Op 57 "Appassionata"
In this video, we'll be playing Ludwig van Beethoven's Piano Sonata No. 23 in F minor, Op. 57known as the Appassionata. This sonata is a famous work for piano and has been considered a great example of the Romantic Period. If you're a fan of Beethoven's music, then this video is a must-watch. We'll be playing the sonata using the original piano key notation and providingclear explanations of each note and passage. So whether you're a beginner or an experienced pianist, this video is a great resource for learning about Ludwig van Beethoven's Piano Sonata No. 23 in F minor, Op. 57known as the Appassionata! 00:00 I. Allegro assai 17:27 II. Andante con moto 31:37 III. Allegro ma non troppo - Presto 演奏者 Frederic Rzewski piano / @fredericrzewski7628 公開者情報 Frederic Rzewski, 2001. 著作権 Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 備考 Rzewski's comments These file(s) are part of the Werner Icking Music Collection. 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 ピアノソナタ第23番ヘ短調 作品57は、ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェンが作曲したピアノソナタ。『熱情(アパショナータ)』という通称により有名で、ベートーヴェン中期の最高傑作のひとつとして名高い。 概要 ベートーヴェンの創作期は実り多い中期に入っていた。交響曲では第3番(英雄)、ヴァイオリンソナタでは第9番(クロイツェル)、ピアノソナタでは第21番(ヴァルトシュタイン)といった傑作が次々生み出され、ベートーヴェンの作風は大きな転換点を迎えていた。一方、彼の難聴は悪化の一途をたどっており、その絶望から1802年にはついにハイリゲンシュタットの遺書を書くに至っている。 そうした中、このピアノソナタは歌劇『フィデリオ』に並行する形で作曲された。『フィデリオ』のスケッチに混ざる形でこの作品の楽想が書きつけられており、作曲の開始は1804年であったことがわかる。1805年4月18日に出版社へ宛てた書簡には曲の完成の目途について語られており、同年夏ごろの『フィデリオ』完成に近い時期に全曲が出来上がったものと考えられる。アントン・シンドラーは1806年の夏にマルトンヴァーシャール(ハンガリー語版)で全曲が一気に書き上げられたとしており、またフェルディナント・リースは1803年にデープリングでベートーヴェンがこの曲を作曲している場に居合わせたと主張しているが、いずれの証言にも疑問の余地が残る。作曲者は同じ頃に交響曲第5番(運命)にも取り掛かっており、この交響曲の4つの音からなる有名な「運命の動機」はこのソナタの第1楽章でも重要な役割を果たす。 楽譜は1807年2月にウィーンの美術工芸社から出版され、フランツ・フォン・ブルンスヴィック伯爵に献呈された。このときの表紙にはピアノソナタ第54番 作品57という番号が付されたが、研究者らの努力にもかかわらずこの番号が何を根拠に定められたのかは明らかになっていない。なお、『熱情』という副題は1838年にハンブルクの出版商クランツがピアノ連弾用の編曲版の出版に際してつけたものであるが、これが通称となり今日までそのまま通用している。 ベートーヴェンは当時この曲の草稿を携えて移動することが多く、そうした中で生まれた1806年秋のエピソードとして次の話が伝えられている。カール・アロイス・フォン・リヒノフスキー侯爵の城からウィーンに帰る途中、ベートーヴェンは突如雨に降られ、持っていたこの曲の原稿を濡らしてしまった。その原稿を優れたピアニストであったマリー・ビゴーに見せたところ、彼女は初見で完全に弾いてしまったのである。ベートーヴェンは大変喜び、出版後の原稿を彼女に贈った。この自筆楽譜は現在パリ音楽院に保存されている。 曲は燃えるような激しい感情を寸分の隙もない音楽的構成の中に見事に表出しており、ベートーヴェンの最高傑作のひとつに数えられる。カール・チェルニーはこの作品について「強大かつ巨大な計画をこの上なく完璧に遂行したもの」と表現した。ピアニストらは劇的な情熱が現れる中にも正確なリズムを維持するよう説いており、演奏には非常に高度な技術が要求される。作曲者自身もこの曲の出来に満足するとともに内容を気に入っていたらしく、当時は他のジャンルにおいて引き続き旺盛な創作をみせたにもかかわらずピアノソナタには4年のあいだ手をつけなかった。石桁真礼生は、本曲の各楽章を「苦悶・静かな反省・勝利の歌」と評している。なお、ベートーヴェンは1803年にエラール製のピアノを贈られており、この楽器によって拡大された音域が曲中で存分に活用されている。 本作は第21番(ヴァルトシュタイン)、第26番『告別』と並んでベートーヴェンの中期ピアノソナタを代表する作品であり、第8番『悲愴』、第14番(月光)と合わせてベートーヴェンの三大ピアノソナタとされることもある。 演奏時間 約21-25分。 楽曲構成 第1楽章 Allegro assai 12/8拍子 ヘ短調 ソナタ形式。序奏を置かず、弱音による主題の提示に始まる。主要主題はいずれも5対1の鋭い付点リズムであり、第1主題は分散和音の下降動機(C-A♭-F)と旋律的動機(C-D-C)の二つから構成される(譜例1)。これらの動機は全楽章の主題に用いられている。主題はすぐに反復されるが、この際ナポリの六度が用いられ、この音程関係も全曲を通じて用いられることになる。 第2楽章 Andante con moto 2/4拍子 変ニ長調 変奏曲形式。威厳を湛えた穏やかな主題と、3つの変奏およびコーダからなる。主題は単純な旋律ながらも美しい譜例4で、前段、後段のそれぞれ8小節が各々繰り返される。 第3楽章 Allegro ma non troppo - Presto 2/4拍子 ヘ短調 ソナタ形式。開始から強い減七の和音が打ち鳴らされる。導入部の音型が発展し、譜例5の第1主題が姿を現す。ここでも主題の内にナポリの六度の関係が用いられている。 ピアノソナタ第23番が使用された作品など 楽曲 「ベートーヴェンの主題による変奏曲」作品133:ハンガリー出身のピアニスト・作曲家ステファン・ヘラーが第2楽章の主題により作曲。本作を含むベートーヴェンの作品の他に、モーツァルト、ショパン、シューマン作品のモチーフを織り込んだ大作。 アンダンテ・コン・モト - フレデリック・ジェフスキーのピアノ作品 映像作品 西部警察 PART-III - 第13話「追跡!1825日」(1983年7月10日放映)にて、小林昭二演じるチョーさん(南長太郎)の回想場面で第1楽章の終結部分が使用される。 SP 警視庁警備部警護課第四係 鳥人戦隊ジェットマン - 敵である次元戦団バイラムの幹部であるマリアが演奏している。 神童 (映画) 少女に何が起ったか リングにかけろ ルパン三世 (TV第2シリーズ) 贖罪の奏鳴曲 世紀末の詩 ゴールデンカムイ 第一期 第九話「煌めく」 ニシン場の親方宅での会話シーン。鶴見篤四郎中尉(声:大塚芳忠)が第1楽章主題提示部を演奏。 チャンネル登録 / @WalkIntoSiena ベートーヴェン再生リスト https://youtube.com/playlist?list=PLTtHiFCVwL1zT3TDzCFkYRGchw_08y2KG ベートーヴェン「ピアノソナタ」再生リスト https://youtube.com/playlist?list=PLTtHiFCVwL1wx8p370mNaQ7Ap00CYMRmH ベートーヴェン の7大ピアノ・ソナタ集 再生リスト https://youtube.com/playlist?list=PLTtHiFCVwL1xEY24t4_5KF0rgQSVYgejm クラシック全般 再生リスト https://youtube.com/playlist?list=PLTtHiFCVwL1yxp2hTQ64gcreupYj8u6jd #ベートーヴェン #ピアノソナタ第23番 #作品57 #情熱 #Beethoven #PianoSonataNo23 #Op57 #Appassionata

ベートーヴェン:ピアノソナタ第14番嬰ハ短調 作品27 2 『幻想曲風ソナタ』(Sonata quasi una Fantasia)
The Piano Sonata No. 14 in C-sharp minor, marked Quasi una fantasia, Op. 27, No. 2, is a piano sonata by Ludwig van Beethoven. It was completed in 1801 and dedicated in 1802 to his pupil Countess Giulietta Guicciardi. The popular name Moonlight Sonata goes back to a critic's remark after Beethoven's death. The verbatim translation would actually be "Moonshine Sonata". The piece is one of Beethoven's most popular compositions for the piano, and it was a popular favourite even in his own day. Beethoven wrote the Moonlight Sonata in his early thirties, after he had finished with some commissioned work; there is no evidence that he was commissioned to write this sonata. From Wikipedia, the free encyclopedia 00:00 I. Adagio sostenuto 07:09 II. Allegretto 09:32 III. Presto agitato (P)サンソン・フランソワ 1963年4月29日~30日録音 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 ピアノソナタ第14番嬰ハ短調 作品27-2 『幻想曲風ソナタ』("Sonata quasi una Fantasia")は、ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェンが1801年に作曲したピアノソナタ。『月光ソナタ』という通称とともに広く知られている。 概要 1801年、ベートーヴェンが30歳のときの作品。1802年3月のカッピによる出版が初版であり、ピアノソナタ第13番と対になって作品27として発表された。両曲ともに作曲者自身により「幻想曲風ソナタ」という題名を付されており、これによって曲に与えられた性格が明確に表されている。 『月光ソナタ』という愛称はドイツの音楽評論家、詩人であるルートヴィヒ・レルシュタープのコメントに由来する。ベートーヴェンの死後5年が経過した1832年、レルシュタープはこの曲の第1楽章がもたらす効果を指して「スイスのルツェルン湖の月光の波に揺らぐ小舟のよう」と表現した。以後10年経たぬうちに『月光ソナタ』という名称がドイツ語や英語による出版物において使用されるようになり、19世紀終盤に至るとこの名称が世界的に知られるようになる。一方、作曲者の弟子であったカール・チェルニーもレルシュタープの言及に先駆けて「夜景、遥か彼方から魂の悲しげな声が聞こえる」と述べている。このように『月光ソナタ』の愛称と共に広く知られる以前より人々の想像を掻き立て、人気を博した本作であったが、ベートーヴェン自身はそのことを快く思っていなかったとされる。なお、後述の尋常小学校の物語が引用されることがあるが、作り話である。 曲は伯爵令嬢ジュリエッタ・グイチャルディに献呈された。ベートーヴェンはブルンスヴィック家を介した縁で自らのピアノの弟子となったこの14歳年少の少女に夢中になる。1801年11月16日に友人のフランツ・ベルハルト・ヴェーゲラーへ宛てた書簡には次のようにある。「このたびの変化は1人の可愛い魅力に富んだ娘のためなのです。彼女は私を愛し、私も彼女を愛している。(中略)ただ、残念なことには身分が違うのです」。その後、グイチャルディはヴェンゼル・ロベルト・フォン・ガレンベルクと結婚してベートーヴェンのもとを去っていく。この献呈は当初から意図されていたわけではなく、グイチャルディにはロンド ト長調 作品51-2が捧げられるはずであった。しかし、ロンドをヘンリエッテ・リヒノフスキー伯爵令嬢へ贈ることが決まり、代わりにグイチャルディへと献呈されたのがこのソナタであったようである。なお、ジュリエッタはアントン・シンドラーの伝記で「不滅の恋人」であるとされている。 曲の内容は『幻想曲風ソナタ』という表題が示すとおり、伝統的な古典派ソナタから離れてロマン的な表現に接近している。速度の面では緩やかな第1楽章、軽快な第2楽章、急速な第3楽章と楽章が進行するごとにテンポが速くなる序破急的な展開となっている。また、形式的にはソナタ形式のフィナーレに重心が置かれた均衡の取れた楽章配置が取られ、情動の変遷が強健な意志の下に揺るぎない帰結を迎えるというベートーヴェン特有の音楽が明瞭に立ち現われている。 本作はピアノソナタ第8番『悲愴』、同第23番(熱情)と並んで3大ピアノソナタと呼ばれることもある。 演奏時間 約15-16分。 楽曲構成 ピアノソナタ第14番の手稿譜。画像をクリックして他のページを参照可能。 第1楽章 Adagio sostenuto 2/2拍子 嬰ハ短調 三部形式。『月光の曲』として非常に有名な楽章である。冒頭に「全曲を通して可能な限り繊細に、またsordinoを使用せずに演奏すること」(Si deve suonare tutto questo pezzo delicatissimamente e senza sordino.)との指示がある。「sordino(弱音器)」とは「ダンパー」のことを指すとされ、冒頭の指示は現代のピアノにおいては「サステインペダルを踏み込んだ状態で」と解釈される。 序奏に続いてA主題が提示される。途切れることのない3連符の上に出される符点リズムの旋律は、葬送と関係するという見方もある。 中間部が譜例2から始まるとやがて旋律的要素は影をひそめ、3連符の音型が緩やかに弧を描きつつ高音へ昇って降りきたり、その後譜例2の再現を行い、その途中からはホ長調でA主題の旋律が始まり、譜例3(B主題)も続いて嬰ハ長調(?)で再現される。3連符の動きが約2オクターブの音域を行きつ戻りつする中、低音部で譜例2のリズムが繰り返されるコーダを経て、最弱音で楽章を閉じる。アタッカの指示があり、休みを置かずにただちに次の楽章に移る。 第2楽章 Allegretto 3/4拍子 変ニ長調 複合三部形式。スケルツォもしくはメヌエットに相当する楽章であるが、いずれであるとも明記されていない。暗い両端楽章の間にあって効果的に両者を繋ぐ役割を果たしており、フランツ・リストはこの楽章を「2つの深淵の間の一輪の花」に例えた。レガートとスタッカートが対比される譜例4により開始される。 譜例4が変奏され、なだらかな中間楽節が出ると譜例4が回帰して主部を結び、中間以降が繰り返される。トリオは二部形式で前後半が各々反復される。前半はアクセントが強調されて重々しく奏される。 後半はピアニッシモで始まった後に再びアクセントが強調されるが、最後は穏やかに結ばれる。反復後にアレグレット・ダ・カーポで主部に戻る。 第3楽章 Presto agitato 4/4拍子 嬰ハ短調 ソナタ形式。ピアノソナタ第14番としては、第3楽章のみソナタ形式となっている。堅牢な構築の上に激情がほとばしり、類稀なピアノ音楽となった。急速に上昇するアルペッジョからなる譜例6の第1主題は、第1楽章の3連符の動機を急速に展開させたものである。頂点のスフォルツァンドでダンパーが解放される。 第2主題には、短調のソナタ形式としては珍しく、属調の嬰ト短調で現れ、第1主題と対照的に流麗な旋律である。 第2主題が変奏して繰り返された後、経過句の部分にナポリの6の和音が結構長く使われ、続いて譜例8が出されて緊張感が高まる。 高まった緊張がコデッタでしばし和らぎ、提示部の繰り返しとなる。展開部はまず第1主題に始まって、まもなく嬰ヘ短調による第2主題へと接続される。主題は低音部に移され、徐々に勢いを落としてピアニッシモに落ち着く。途中で、一瞬ト長調に転調するが、すぐに嬰ヘ短調を呼び戻し、嬰ハ短調の属和音まで突進する。 再現部は第1主題の再現後に経過句を省略して(推移無し・確保無し)、主調のままの嬰ハ短調で第2主題(譜例7)の再現を行い、譜例8もこれに続くが、譜例8の途中の部分からは、旋律が提示部と同じ形ではなくちょっとした変奏が求められている。コーダは規模の大きな堂々たるもので、まず譜例6に始まり減七の和音がフェルマータを付されて引き伸ばされる。続いて譜例7が扱われると、およそ3オクターブを駆け巡るアルペッジョが吹き荒れる。カデンツァ風のパッセージを経て一度アダージョに落ち着くものの、すぐさま元のテンポに復帰して提示部コデッタに現れた旋律を出す。最後は両手のユニゾンでアルペッジョを奏し、フォルテッシモの主和音が全曲に終止符を打つ。 「月光の曲」 ウィキソースに月光の曲の原文があります。 日本では戦前の尋常小学校の国語の教科書に、「月光の曲」と題する仮構が読み物として掲載されたことがあった。 この物語は19世紀にヨーロッパで創作され、愛好家向けの音楽新聞あるいは音楽雑誌に掲載された。日本では、1888年に積善館より出版された英語テキスト『New national readers』第5巻およびその日本語訳『ニューナショナル第五読本直訳』の12章に「BEETHOVEN'S MOONLIGHT SONATA」(第十二課 「ベトーブン」ノ月光ノ「ソナタ」)として掲載された。その後、1892年に上梓された小柳一蔵著『海外遺芳巻ノ一』に『月夜奏琴』という表題で掲載されている。『月夜奏琴』を口語調に書き直したものが『月光の曲』である。 あらすじ ベートーヴェンが月夜の街を散歩していると、ある家の中からピアノを弾く音が聞こえた。良く見てみるとそれは盲目の少女であった。感動したベートーヴェンはその家を訪れ、溢れる感情を元に即興演奏を行った。自分の家に帰ったベートーヴェンはその演奏を思い出しながら曲を書き上げた。これが「月光の曲」である。 ベートーヴェン再生リスト https://youtube.com/playlist?list=PLTtHiFCVwL1zT3TDzCFkYRGchw_08y2KG ベートーヴェン「ピアノソナタ」再生リスト https://youtube.com/playlist?list=PLTtHiFCVwL1wx8p370mNaQ7Ap00CYMRmH ベートーヴェン の7大ピアノ・ソナタ集 https://youtube.com/playlist?list=PLTtHiFCVwL1xEY24t4_5KF0rgQSVYgejm #ベートーヴェン #ピアノソナタ第14番嬰ハ短調 #作 品27 #幻想曲風ソナタ #Beethoven #SonataquasiunaFantasia

ベートーヴェン:ピアノソナタ第1番 ヘ短調 作品2-1
In this video, we'll be discussing Ludwig van Beethoven's Piano Sonata No. 1 in F minor, Op. 2 No. 1. This sonata is a classic example of the Romantic era, and is known for its flowing and melancholic melodies. We'll be discussing the composition, dynamics, and interpretation of this sonata, so be sure to check it out! 00:00 I. Allegro 04:01 II. Adagio 08:59 III. Menuetto: Allegretto 12:21 IV. Prestissimo 演奏者 Paul Pitman (piano) 公開者情報 Palo Alto: MusOpen 著作権 Creative Commons Attribution Share Alike 3.0 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 ピアノソナタ第1番 ヘ短調 作品2-1は、ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェンが1795年に完成したピアノソナタ。 概要 1792年11月、ベートーヴェンが故郷のボンを後に音楽の都ウィーンへ赴いたのはフランツ・ヨーゼフ・ハイドンに師事するためであった。しかしハイドンの施した指導はベートーヴェンの期待に応えるものではなく、ヨハン・バプティスト・シェンクがハイドンの誤りを多数指摘するに至って野心溢れる若き作曲家の不満は膨れ上がった。やがて彼は「ハイドンからは何も学ぶところはなかった」とさえ口にするようになる。その後ハイドン門下を飛び出してヨハン・ゲオルク・アルブレヒツベルガーやアントニオ・サリエリらに師事したベートーヴェンであったが、1795年にハイドンがイギリスへの演奏旅行から帰国すると同年に完成した3曲のピアノソナタをかつての師に献呈したのである。この3曲が作品2としてまとめられ、翌1796年にウィーンのアルタリアから出版された。 様々に性格が異なる楽曲を同時期に生み出していくスタイルは、それまでの時代の作曲家にはあまり見られなかったベートーヴェンの創作上の特徴であるが、作品2の3曲も三者三様の個性に彩られており既に作曲者らしさが前面に出てきている。本作はその中でも劇的、悲劇的に書かれており、後年の作風を強く予感させる内容となっている。調号として4つの変化記号が並ぶヘ短調という調性はアマチュア音楽家にとって譜読みが難しいこともあり、当時の鍵盤楽器作品では敬遠されがちであった。そうした中でヘ短調を採用した第1番のソナタには、自作曲を演奏するピアニストとして聴衆により強い印象を残そうというベートーヴェンの野心が窺われる。また、ピアノを管弦楽的に扱う傾向も既に現れている。 ベートーヴェンのピアノソナタには選帝侯ソナタなどのボン時代の習作も含まれるが本作の習熟度には遠く及ばない。芸術家ベートーヴェンのピアノソナタはこの作品に始まり、以降晩年に至るまで32曲にわたって連なっていくことになる。音楽史上欠くことのできないこれら作品群はピアノ音楽の新約聖書と称えられ、その歩みはベートーヴェンの作曲様式の変遷を写し出すのみならずピアノ音楽発展の系譜そのものであるということができる。 演奏時間 約17分半-19分。 楽曲構成 第1楽章 Allegro 2/2拍子 ヘ短調 ソナタ形式。楽章は簡潔ながらも巧みに構築されており、高い構成力が既に示されている。曲はアルペッジョが駆け上がる第1主題に開始する。モーツァルトの交響曲第25番の第1楽章や、交響曲第40番の第4楽章としばしば比較されるこの主題は、マンハイム楽派の影響を色濃く映し出している。 第2楽章 Adagio 3/4拍子 ヘ長調 展開部を欠くソナタ形式。穏やかな第1主題は1785年に作曲されたピアノ四重奏曲 WoO 36-3の第2楽章からの転用である。 第3楽章 Menuetto, Allegretto 3/4拍子 ヘ短調 メヌエットと明示されて形式もメヌエットのそれに沿っているが、楽想はスケルツォのような雰囲気を漂わせる。4声体書法を用いて謎めいた主題が提示される。 第4楽章 Prestissimo 2/2拍子 ヘ短調 ソナタ形式。3連符の伴奏の上に強烈に出される第1主題に始まる。非常に強い印象をもたらす楽想であり、フランツ・シューベルトのピアノソナタ第11番などもこの楽章の影響下にあると思われる。 #ベートーヴェン #ピアノソナタ第1番 #作品2の1 #PianoSonataNo1 #Beethoven

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第10番 変ホ長調「ハープ」作品74
In this video, we'll be playing Ludwig van Beethoven's String Quartet No. 10 in E-flat major, Op. 74, on the harpsichord. If you're a fan of classical music, then you'll love this video! We'll be playing the amazing String Quartet No. 10 by Ludwig van Beethoven on the harpsichord. This work is full of beautiful melody and is sure to please any classical music fan! 00:00 I. Poco adagio - Allegro 09:17 II. Adagio ma non troppo 18;47 III. Presto 24:00 IV. Allegretto con variazioni 演奏者 Borromeo String Quartet (String Quartet) 公開者情報 Boston: Isabella Stewart Gardner Museum 著作権 Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 弦楽四重奏曲第10番変ホ長調Op.74は、ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェンによって1809年に作曲された弦楽四重奏曲である。第1楽章の随所に現れるピッツィカートの動機から、「ハープ」という愛称を持つ。ベートーヴェンは金字塔ともいえる3曲の巨大な作品群「ラズモフスキー弦楽四重奏曲」を作曲したあとは、作品の規模は縮小し、代わりにロマン的な情緒やのびのびとした感情をたたえる作風へと変化した。この曲はまさしくそのように、いくらか自由な気持ちで作曲されたものである。 曲の構成 第1楽章 Poco Adagio-Allegro 気まぐれな序奏に始まる。主部はソナタ形式で、第1主題は和音の連打によって始まるが、その後は極めて旋律的な第1主題が第1ヴァイオリンとヴィオラによって歌われる。そしてすぐに前述のピッツィカートによる推移部が現れる。但し第2主題は経過的なものである。展開部は内声はトレモロを刻み、両外声が絡み合いながら進む。再現部は定型どおりであるが、コーダは第1ヴァイオリンのアルペッジョの伴奏の下にピッツィカートであとの三つの楽器が掛け合う充実したものとなっている。 第2楽章 Adagio ma non troppo 変イ長調、ロンド形式。様々な美しい旋律群が豊かな和声や装飾に彩られている。 第3楽章 Presto-Piu presto quasi prestissimo スケルツォ、ハ短調。同じトリオが2回ある。 いわゆる「運命の動機」のようなもの(厳密には違う)によって支配されている。 トリオはハ長調。2小節単位で6/8拍子の要領で弾くという指示がある。チェロとヴィオラに現れる2本の旋律がポリフォニックに展開する。 第4楽章 Allegro con Variazioni 変奏曲。主題と6つの変奏、コーダからなる。意外にも、ベートーヴェンが弦楽四重奏曲の最終楽章に使用した変奏曲として唯一のものである。主題は同じ動機が繰り返される。ここでは晩年に見られるような主題の性格を変えていく性格変奏ではなく、装飾によるものである。 #ベートーベン #弦楽四重奏曲第10番 #ハープ #作品74 #StringQuartetNo10 #Beethoven

ベートーベン:弦楽四重奏曲第8番 ホ短調「ラズモフスキー2番」Op.59-2
This video is about the string quartet No. 8 in E minor, Op. 59, No. 2 by Ludwig van Beethoven. This quartet is one of the most famous and well-known compositions by Beethoven. In this video, I'm playing the quartet and explaining the different parts of the piece. 00:00 I. Allegro 10:51 II. Molto adagio 27:08 III. Allegretto 36:17 IV. Finale: Presto ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 1951年録音 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 弦楽四重奏曲 第8番 ホ短調 作品59-2(げんがくしじゅうそうきょく だい8ばん ホたんちょう さくひん59-2)は、ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェンが1806年に作曲した弦楽四重奏曲。ベートーヴェンはラズモフスキー伯爵によって弦楽四重奏曲の依頼を受けた。そのようにして作曲された3曲の弦楽四重奏曲はラズモフスキー伯爵に献呈され、ラズモフスキー四重奏曲という名で親しまれるようになった。これはその2曲目に当たるのでラズモフスキー第2番と呼ばれる。 概要 これらの3曲は作品18の6曲とは作風・スケールなどによって大きな隔たりを持つ。形式の拡大、徹底した主題労作や統一、またロシア民謡の採用もみられ、今までにない異例の長大さを示す。それはもはや室内楽の規模ではなく、交響的な音世界を表現している。この第2番はその中でもいくらか小規模なものであり、全楽章がソナタ形式であった第1番に比べると、第2楽章に緩徐楽章、第3楽章にスケルツォ、第4楽章にロンド・ソナタ形式というように簡潔なソナタの形となっている。3曲のなかで唯一短調を採り、形式が圧縮された内省的なものである。 曲の構成 第1楽章 Allegro ホ短調、8分の6拍子。ソナタ形式。第1主題は和音連打に始まり、線的で断片的な旋律が続く。第1主題の提示の後、それがすぐにナポリ調のヘ長調で繰り返される点は、ベートーヴェン中期の特徴も一つである。展開部と再現部の繰返し指定がある。 第2楽章 Molto Adagio 深い感情をもって ホ長調、4分の4拍子。ソナタ形式。チェルニーは、この楽章はベートーヴェンが星のきらめきを想像して書いたと伝えている。和声的な第1主題と、いくらか律動的な第2主題からなり、それはどちらも非常に感慨深いが、ここでも主題労作の技法は有効的に用いられている。途中に「運命」の動機が現れ、展開部で繰り返される。 第3楽章 Allegretto ホ短調、4分の3拍子。スケルツォ。主部はリズミカルであり、Maggiore(ホ長調)の中間部はロシア民謡の旋律が使われている。なおその旋律は後にムソルグスキーがオペラ「ボリス・ゴドゥノフ」において、リムスキー=コルサコフが『皇帝の花嫁』第1幕第3場で、チャイコフスキーが『マゼッパ』第3幕の前奏曲(「ポルタヴァの戦い」)で、アントン・アレンスキーが弦楽四重奏曲第2番第3楽章で、ラフマニノフがピアノ連弾のための6つの小品第6曲で、それぞれ使用した。 第4楽章 Presto ホ短調、2分の2拍子。ロンドソナタ形式。主題はホ短調であるが、明確にハ長調によって開始され、ユニークである。よって第1主題の再現の際には必ずハ長調への解決が導かれる。第2主題はロ短調を採るが、全体はきわめてコンパクトに有機的にまとめられ、無駄がない。コーダはPiu Prestoとなり加速し、力強くホ短調のまま終わる。 #ベートーヴェン,#Beethoven,#StringQuartet,#ラズモフスキー2番,#作品59の2,#弦楽四重奏曲第8番

ベートーヴェン:ピアノ協奏曲第1番 ハ長調, Op.15
In this video, we'll be playing Ludwig van Beethoven's Piano Concerto No. 1 in C major, Op. 15. This famous piece is one of the most popular and well-known piano concertos in the world, and is sure to bring a burst of energy to your performance! If you're interested in learning how to play this piano concerto, or just want to add some energy to your performances, be sure to check out this video! We'll give you a step-by-step guide on how to play this piece well, and we'll also include a performance of the concerto for you to listen to and learn from! 00:00 I. Allegro con brio 15:25 II. Largo 24:22 III. Rondo. Allegro scherzando 演奏者 DuPage Symphony Orchestra (orchestra) Barbara Schubert (conductor) 公開者情報 DuPage, IL: DuPage Symphony Orchestra 演奏者 Ching-Yun Hu (piano) 著作権 Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 備考 Performed 12 May 2012 in Wentz Concert Hall. From archive.org 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 ピアノ協奏曲第1番ハ長調作品15は、ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェンが遺したピアノ協奏曲の一つ。 概要 ハイドンの下で本格的に作曲を学ぶべく1792年にボンからウィーンに居を移したベートーヴェンが、1800年に交響曲第1番を発表する以前に当楽曲を書いている。 ボンに居住していた頃からウィーンに引っ越して間もない時期にかけてベートーヴェンは都合3曲のピアノ協奏曲を作曲している。ボン時代からウィーン時代にかけて作曲され、後に「ピアノ協奏曲第2番」となる”2つ目のピアノ協奏曲”の後に当楽曲(”3つ目のピアノ協奏曲”)は完成されているが、出版に際しては逆に当楽曲が第2番より先に出版されたことから、「ピアノ協奏曲第1番」として世に送り出される結果となった。 1795年3月に初稿が完成し、初演は同月29日にウィーンのブルク劇場に於いて、作曲者自身のピアノ独奏とサリエリの指揮により初演された模様。その後当楽曲は改訂されることになり、交響曲第1番が初演された1800年4月2日の演奏会に於いてその改訂された当楽曲が併せて披露され、翌1801年、更に手が加えられた上で出版するに至った。 楽器編成 フルート1、オーボエ2、クラリネット2、ファゴット2、ホルン2、トランペット2、ティンパニ、弦五部 曲の構成 3楽章からなる。全曲で約35分。 第1楽章 Allegro con brio ハ長調 4/4拍子 協奏的ソナタ形式。ピアノソナタ第21番「ヴァルトシュタイン」にもつながる明朗快活な楽章。主題は溌剌としたC音の連打と上昇音階。 モーツァルトの影響が強いものの、中間部で遠隔調の変ホ長調を採用する点にロマン的な萌芽が認められる。しかしカデンツァは作者のもの(3曲残され、1曲は未完成)、カール・ライネッケのものもあるが、いずれも第3番と同様に奏者に任せる伝統的な形になっている。本来演奏者の自由であるカデンツァにまで作曲者の強い意思を貫くのは第5番「皇帝」においてである。 再現部の前のピアノの独奏移行部は非常に演奏が困難であるが、演奏の際には多くの場合、右手のみのオクターヴでのグリッサンドで演奏される。 172小節目右手3拍めのf6#は自筆譜では#が書かれておらずf6となっているが、意図して当時のピアノの音域に合わせたものか単純な書き損じなのかは不明である。ただし、再現部のフレーズと照らし合わせて#で演奏した方が調性的にも自然なため初版からf6#で記譜されている。アンドラーシュ・シフの様にf6で弾くべきと主張する演奏家もいる。 第2楽章 Largo 変イ長調 4/4拍子 三部形式。落ち着いた緩徐楽章。随所にピアノの華麗な音階進行を取り入れている。フルートとオーボエが休みで、クラリネットが活躍する。 第3楽章 Rondo Allegro ハ長調 2/4拍子 ロンドソナタ形式。楽しげなロンド。独奏と管弦楽との掛け合いがにぎやかな演出をしている。ベートーヴェン自身の作曲したカデンツァが第457小節、第485小節に置かれているが、2番目のものは大半で演奏されない。 最後のベートーヴェン特有のティンパニの連打は史上最初の打楽器ソロの難解なパッセージである。 #ベートーヴェン,#ピアノ協奏曲第1番,#作品15,#Op15,#Beethoven