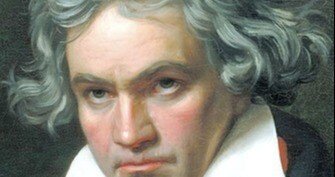#ヘ

ベートーヴェン;ヴァイオリンソナタ第2番 イ長調, 作品12-2
00:00 I. Allegro vivace 06:44 II. Andante, più tosto. Allegretto 11:43 III. Allegro piacevole 1947年12月17日にヤッシャ・ハイフェッツ(Vn)とエマニュエル・ベイ(P)によって録音されました。録音地はハリウッドのRCAスタジオです。 ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェンの『ヴァイオリンソナタ第2番 イ長調 作品12-2』は、ベートーヴェンが若い頃に作曲した一連のヴァイオリンソナタの中の一つです。この作品も『ヴァイオリンソナタ第1番』と同様に、1797年から1798年にかけて作曲され、1798年に出版されました。ヴァイオリンソナタ第1番、第2番、第3番を含む作品12の3曲は一緒に出版され、これらはベートーヴェンが作曲した最初のヴァイオリンソナタであり、彼の室内楽作品の中でも重要な位置を占めています。 ヴァイオリンソナタ第2番は、以下の3楽章から構成されています: 1. 第1楽章 Allegro vivace(アレグロ・ヴィヴァーチェ) 2. 第2楽章 Andante, più tosto Allegretto(アンダンテ、それよりはむしろアレグレット) 3. 第3楽章 Allegro piacevole(アレグロ・ピアチェヴォーレ) この作品は、軽快で明るい性格が特徴です。第1楽章の「Allegro vivace」は、活気に満ちた開始部で始まり、技術的にも表現的にも要求される部分が多くあります。第2楽章「Andante, più tosto Allegretto」は、より詩的で、柔らかなメロディが特徴です。そして第3楽章「Allegro piacevole」は、楽し気で親しみやすいフィナーレを提供し、作品全体を明るく締めくくります。 ベートーヴェンは、このソナタを通じてヴァイオリンとピアノ間の対話を重視しています。両者は対等なパートナーとして扱われ、ベートーヴェンの室内楽における新たな対話の形式を示唆しています。彼のヴァイオリンソナタは、後の作品へと続く彼の音楽的探求の早期の例を提供しており、特にヴァイオリンとピアノのためのレパートリーにおいて革新的な貢献をしています。 チャンネル登録 https://www.youtube.com/channel/UCqAFiZznfr5Y7wgfV_sOiGQ Walk Into Siena コミュニティ https://www.youtube.com/@WalkIntoSiena/community ベートーヴェン 再生リスト https://youtube.com/playlist?list=PLTtHiFCVwL1zT3TDzCFkYRGchw_08y2KG ベートーヴェン「ヴァイオリンソナタ」 再生リスト https://www.youtube.com/playlist?list=PLTtHiFCVwL1z8Amf6sxbhe-ICQdPQT4Us クラシック全般 再生リスト https://youtube.com/playlist?list=PLTtHiFCVwL1yxp2hTQ64gcreupYj8u6jd #ベートーヴェン #ヴァイオリンソナタ第2番 #イ長調, #Op12の2

ベートーヴェン:ヴァイオリンソナタ第8番 ト長調 Op.30-3(Beethoven:Violin Sonata No.8 in G major, Op.30 No.3 )
00:00 I. Allegro assai 06:49 II. Tempo di minuetto, ma molto moderato e grazioso 13:52 III. Allegro vivace 公開者情報. Pandora Records/Al Goldstein Archive 演奏者. Paul Rosenthal, violin ; Edward Auer, piano 著作権 EFF Open Audio License 備考 Performed 1982. Seattle: Lakeside School ベートーベンの『ヴァイオリンソナタ第8番 ト長調 Op.30 No.3』は、彼が1801年から1802年にかけて作曲した三つのヴァイオリンソナタの一つです。この三作品は一緒にOp.30として出版されました。特に第8番は、このシリーズの中で最も軽やかで親しみやすい作品とされています。 ### 構成 ソナタは以下の四つの楽章から構成されています: 1. **アレグロ・アッサイ** - この楽章は活発で明るいムードで始まり、ヴァイオリンとピアノが華やかな対話を繰り広げます。 2. **テンポ・ディ・メヌエット, ma molto moderato e grazioso** - 第二楽章はメヌエットとして書かれていますが、伝統的なメヌエットよりもゆったりとしたテンポで、非常に優雅な雰囲気を持っています。 3. **アレグロ・ヴィヴァーチェ** - 第三楽章は軽快なスケルツォで、このソナタの中でも特に明るく元気な部分です。ベートーヴェンらしいユーモアが感じられる楽章です。 4. **アレグロ・ヴィヴァーチェ** - 最終楽章も高速なテンポで、技術的に要求されるパートが多いです。ピアノとヴァイオリンが見事な技巧を披露しながら、作品を力強く締めくくります。 ### 解説 Op.30 No.3は、ベートーヴェンが初期から中期にかけてのスタイルの変化期に作曲された作品の一つです。この作品では、彼独特の音楽言語と表現の幅の広がりが見られます。特に、この時期のベートーヴェンの作品には、古典派音楽の形式を踏襲しつつも、その枠組みを超えた音楽的探求が見られ、後のロマン派音楽への道を示唆しています。 このソナタでは、ベートーヴェンの作曲技法の特徴であるモチーフの発展や対位法の技術、豊かな和声言語が随所に見られます。また、ヴァイオリンとピアノの間の対話や、楽章を通じてのアイデアの展開が見事に描かれており、ベートーヴェンの室内楽作品の中でも特に親しみやすい作品とされています。 全体として、ヴァイオリンソナタ第8番は、ベートーヴェンの作曲技術と音楽的表現の豊かさを示す素晴らしい例であり、彼のソナタ作品の中でも特に人気のある作品の一つです。 チャンネル登録 https://www.youtube.com/channel/UCqAFiZznfr5Y7wgfV_sOiGQ Walk Into Siena コミュニティ https://www.youtube.com/@WalkIntoSiena/community ベートーヴェン 再生リスト https://youtube.com/playlist?list=PLTtHiFCVwL1zT3TDzCFkYRGchw_08y2KG ベートーヴェン「ヴァイオリンソナタ」 再生リスト https://www.youtube.com/playlist?list=PLTtHiFCVwL1z8Amf6sxbhe-ICQdPQT4Us クラシック全般 再生リスト https://youtube.com/playlist?list=PLTtHiFCVwL1yxp2hTQ64gcreupYj8u6jd #ベートーヴェン #ヴァイオリンソナタ第8番 #ト長調 #Op30の3 #Beethoven #ViolinSonataNo8 #Op30 #No3

ベートーヴェン:序曲『コリオラン』(Ouvertüre zu „Coriolan“)作品62
イーゴリ・マルケヴィチ指揮 ラムルー管弦楽団 1959年録音 ベートーヴェンの「序曲『コリオラン』作品62」は、1807年に作曲され、同年のプライベートなコンサートで初演されました。この曲はシェイクスピアの『コリオレーナス』ではなく、ハインリヒ・ヨーゼフ・フォン・コリンの同名の悲劇に基づいています。そのため、音楽はドラマティックであり、劇的な情緒が豊かに表現されています。 序曲は、C短調で書かれており、強い情緒的な緊張感と激しい動きが特徴です。曲は、力強い和音で始まり、コリオランの葛藤を表現しています。この葛藤は、コリオランが故郷ローマを攻撃しようとする一方で、母親と妻の訴えに心動かされるというものです。 作品は、主に二つの主題で構成されています。第一主題は、強いリズムと力強い動きを持ち、コリオランの戦闘的な性格を示しています。対照的に、第二主題は、より穏やかで抒情的であり、彼の家族への愛を表現しています。 序曲は、力強いクライマックスに向かって進行し、最終的には突然終わることで、コリオランの悲劇的な運命を暗示しています。この終結部は、コリオランが自らの命を絶つというドラマの結末を象徴していると考えられています。 ベートーヴェンの「コリオラン」序曲は、その強烈な感情表現と劇的な構成で、今日でも広く演奏される名作として知られています。 ベートーヴェンの「序曲『コリオラン』作品62」は、1807年初頭に作曲された演奏会用序曲です。この作品は、ベートーヴェンの友人であるウィーンの宮廷秘書官兼法律家・詩人ハインリヒ・ヨーゼフ・フォン・コリンの戯曲『コリオラン』に触発されて作曲されました。この戯曲は、古代ローマの英雄コリオランの物語を描いており、彼がローマに進攻するものの、妻と母の献身的な忠告により祖国側に戻り、最終的に殺されるという悲劇的な展開があります。 楽器編成には、フルート2、オーボエ2、クラリネット2、ファゴット2、ホルン2、トランペット2、ティンパニ、弦五部が含まれています。 この曲は、アレグロ・コン・ブリオ、C短調、4分の4拍子で、ソナタ形式を採用しています。ベートーヴェンらしい打撃的な激しい冒頭部から始まり、暗く行動的な第1主題が続きます。この主題は、傲慢かつ情熱的なコリオランの性格を表現しています。第2主題は、より柔らかく、主人公の妻の心情を反映しているとされています。曲は悲劇的な色合いを強めながら進行し、最終的には息も絶え絶えの第1主題で終わります。 ベートーヴェンの「序曲『コリオラン』作品62」に関して、さらに詳細な情報を提供します。この序曲は、ベートーヴェンが古代ローマを舞台にした話であるコリンの戯曲『コリオラン』を見た際の感動によって作曲されました。この戯曲は、祖国に追放された主人公コリオランが隣国の軍隊を率いて復讐を試みるが、最終的に断念し、その後殺されるという悲劇的な結末を迎えます。 音楽的には、「序曲『コリオラン』」は演奏会用序曲であり、エグモントのような舞台音楽ではありません。この曲は、悲劇の題材を反映して常に悲壮感を伴います。美しく伸びやかな旋律も登場し、これはコリオランの妻の登場を暗示している可能性があります。また、コリオランの葛藤や軍隊の進軍をイメージさせる箇所もあり、これらは曲の終盤の聴きどころとなっています。 このように、この曲はベートーヴェンの感情的な深さと音楽的な独創性が融合した作品として、今日でも多くの人々に感銘を与え続けています。 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 序曲『コリオラン』(Ouvertüre zu „Coriolan“)作品62は、ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェンが1807年に作曲した演奏会用序曲。 作品について この序曲は1807年の初め頃に作曲された演奏会用序曲で、恐らくごく短期間で完成したとされる。ベートーヴェンの友人で、ウィーンの宮廷秘書官を務め、また法律家で詩人でもあったハインリヒ・ヨーゼフ・フォン・コリン(英語版)による、古代ローマの英雄コリオラヌスを主人公にした戯曲『コリオラン』を見たときの感動が、作曲の動機となったという。物語は、古代ローマで大きな勢力を持っていたが政治上の意見の相違で追放されたコリオランが、隣国の将軍となり大軍とともにローマへの進攻に参加するものの、妻と母の献身的な忠告で再び祖国側についたので殺されてしまうというものである。献身的な妻が出てくるという点で、ベートーヴェン唯一のオペラ『フィデリオ』との類似が見られる。 この曲が書かれた1807年にベートーヴェンは、交響曲第4番、第5番、第6番の3つの交響曲やピアノ協奏曲第4番、ヴァイオリン協奏曲などを作曲したが、こうした多忙な中でこの序曲が一気に書かれたという。特に第5交響曲の第1楽章とは同じハ短調、アレグロ・コン・ブリオである他、動機の執拗な展開など類似点が多く見出せる。曲はコリンに献呈された。 楽器編成 木管楽器:フルート2、オーボエ2、クラリネット2、ファゴット2 金管楽器:ホルン2、トランペット2 その他:ティンパニ、弦五部 構成 アレグロ・コン・ブリオ、ハ短調、4分の4拍子。ソナタ形式。 ベートーヴェンらしい打撃的な激しい冒頭部で始まる。すぐに暗いが行動的な感じの第1主題が続く。この主題は傲慢かつ情熱的な主人公の性格を表現しているといわれている。(この主題はハイドンの交響曲第39番ト短調の第1楽章第1主題に似ている)第2主題は主人公を憂える妻とも比せられる柔らかいものだが、緊張は持続されたままで、再び第1主題をベースに悲劇的な色を濃くしていく。第1主題の動機が伴奏に回っている中そのまま展開部に移行する。展開部は提示部のコデッタと類似したもので、ベートーヴェンの交響曲のそれよりは変化に乏しいものの力強く劇的である。冒頭の打撃を迎えて再現部に入る。再現部はほぼ型どおりに進むが、突然切れてコーダとなる。コーダは第2主題で始まり、提示部と同じ展開で悲劇色を強めたのち、冒頭の打撃が堰き止めるように三たび立ち現れ、そのあと息も絶え絶えとなった第1主題で曲は終わる。 Walk Into Siena チャンネル登録 https://www.youtube.com/channel/UCqAFiZznfr5Y7wgfV_sOiGQ Walk Into Siena コミュニティ https://www.youtube.com/@WalkIntoSiena/community ベートーヴェン 再生リスト https://youtube.com/playlist?list=PLTtHiFCVwL1zT3TDzCFkYRGchw_08y2KG ベートーヴェン『交響曲集』 再生リスト https://www.youtube.com/playlist?list=PLTtHiFCVwL1wpquw9OxqNkW04ZYODRzFE クラシック全般 再生リスト https://youtube.com/playlist?list=PLTtHiFCVwL1yxp2hTQ64gcreupYj8u6jd #ベートーヴェン #序曲 #コリオラン #Ouvertürezu #Coriolan #作品62

ベートーヴェン:交響曲第1番 ハ長調 作品21
00:00 I. Adagio molto - Allegro con brio 09:23 II. Andante cantabile con moto 16:13 III. Menuetto: Allegro molto e vivace 20:11 IV. Adagio - Allegro molto 演奏者 Pittsburgh Symphony Orchestra (orchestra) William Steinberg (conductor) 公開者情報 Command, 1964. CC 11024 SD. 著作権 Public Domain - Non-PD US, Non-PD EU 備考 Source: Internet Archive ベートーヴェンの交響曲第1番 ハ長調 作品21は、バロン・ゴットフリート・ファン・スヴィーテンへの献呈作品で、1801年にHoffmeister & Kühnel of Leipzigから出版されました。作曲が完了した正確な時期は不明ですが、フィナーレのスケッチは1795年から存在していることがわかっています。 交響曲は以下の4つの楽章から構成されています: 1. **第1楽章**: - 序奏に続く第一主題はハ長調の調性を強く確立させ、モーツァルトの交響曲第41番の第1楽章に似た力強い旋律が見られます。この第1主題(C-G-H-C)の動機は全楽章にわたって使用され、統一感を与えています。 2. **第2楽章 (Andante cantabile con moto)**: - ソナタ形式の緩徐楽章で、冒頭はフーガ風に開始されます。2番フルートは休止します。 3. **第3楽章 (Menuetto, Allegro molto e vivace)**: - 複合三部形式で、メヌエットと題されているものの、"Allegro molto e vivace"のテンポ指定からスケルツォの性質が強く、早くも後の大作に見出されるような革新性を示しています。 4. **第4楽章 (Adagio - Allegro molto e vivace)**: - 序奏付きソナタ形式で、序奏のヴァイオリンの旋律は秀逸と言われています。G音から始まる上行フレーズが繰り返し提示され、その後は1オクターブ上のG音まで達し、この1オクターブの上行音形とそれに続く旋律が第1主題としての役割を果たします。このような断片的な動機が発展して主題が生まれる処理は、後の交響曲第5番や交響曲第9番の第1楽章冒頭でも見られます。序奏の後の主部はロンド風で、ハイドン的な楽しさに満ちています。第1主題は、第1楽章の副主題(C-E-G-F-E-D-C)の完全な逆行である。 また、ボストン交響楽団のエリッヒ・ラインスドルフ指揮による録音では、ベートーヴェンが交響曲の冒頭で誤ったキーを使い、風のセクションを過剰に使用すると強調されています。これは、「クラシック」な作曲家と比較して異なる場所にあります。 ベートーヴェンの交響曲第1番は、古典派の伝統に基づいていながらも、その新しい要素が含まれており、後の交響曲に向けての道を開いています。以下は、既に提供した情報に含まれていない、この作品に関するいくつかの追加的な観点です: 1. **時期と背景**: - 交響曲第1番はベートーヴェンの初期の作品であり、古典派の伝統に基づいていますが、それでもベートーヴェンの個性が見られます。 2. **形式と構造**: - ベートーヴェンは古典的な四楽章の形式を採用していますが、各楽章において独自の方法でこれを拡張または変更しています。たとえば、第3楽章は伝統的なメヌエットではなく、より速く活発なスケルツォとして作曲されています。 3. **影響**: - 交響曲第1番は、ベートーヴェンが後の交響曲でさらに探求するいくつかの音楽的アイデアを紹介しています。これには、動機の発展と再帰、および楽章間の関連性が含まれます。 4. **楽器編成**: - この交響曲は、フルート、オーボエ、クラリネット、ファゴット、ホルン、トランペット、ティンパニ、および弦楽器で演奏されます。 5. **評価**: - 交響曲第1番は、批評家や聴衆から広く賞賛されており、ベートーヴェンの交響曲の中で重要な地位を占めています。 これらの点は、交響曲第1番がベートーヴェンの音楽的進歩において重要な位置を占めていることを示しています。それは古典派の伝統を尊重しながらも、新しい音楽的表現と形式の探求を促進しました。 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 交響曲第1番 ハ長調 作品21(こうきょうきょくだい1ばん ハちょうちょう さくひん21)は、ベートーヴェンが1799年から1800年に作曲した自身1曲目の交響曲である。ピアノソナタ第8番「悲愴」や七重奏曲、6つの弦楽四重奏曲などともに、ベートーヴェンの初期の代表作として知られている。 ベートーヴェンの交響曲のうち、第1番、第2番はベートーヴェンの「初期」の作品に含まれ、第1番もハイドン、モーツァルトからの影響が強く見られるが、既にベートーヴェンの独自性が現れている[1]。 作曲の経緯 ベートーヴェンは当初ピアニストとして生計を立てていたこともあり、初期の作品はピアノソナタ、ピアノ三重奏曲、ピアノ協奏曲など、主にピアノに関する作品が中心を占めている。一方で、この時期には弦楽四重奏曲、七重奏曲などの作曲も経験しており、これによってベートーヴェンは室内楽曲の書き方も学ぶことになる。 これらの作曲を経験することによって、ハイドン、モーツァルトら古典派の作曲技法を吸収し、自らの技術として身につけている。 交響曲第1番は、ここで学んだ技術の総集編として作曲されたものと考えられている。 この作品はゴットフリート・ファン・スヴィーテン男爵に献呈された。 初演 1800年4月2日、ウィーンのブルク劇場にて、ベートーヴェン自身の指揮により初演された。 ブルク劇場での初演はプログラムの最後に組み込まれた。 完全な2管編成を要求するこの曲は初演時に「軍楽隊の音楽」と揶揄されたという。 楽器編成 編成表 木管 金管 打 弦 フルート 2 ホルン 2 ティンパニ ● 第1ヴァイオリン ● オーボエ 2 トランペット 2 他 第2ヴァイオリン ● クラリネット 2 他 ヴィオラ ● ファゴット 2 チェロ ● 他 コントラバス ● 曲の構成 演奏時間は約30分。 第1楽章 Adagio molto - Allegro con brio ハ長調 4分の4拍子 - 2分の2拍子 序奏つきのソナタ形式(提示部反復指定あり)。序奏に独創性が認められる。作品の冒頭の和音はその調性における主和音であるべきだが、ここでは下属調の属七の和音が使用されている。その後もなかなかハ長調は確立されず、調性が不安定である。このような処理は、通常の古典派の感覚を逸脱するものである。 序奏に続く第一主題はこれと対比をなし、モーツァルトの交響曲第41番の第1楽章にも似た力強い旋律は、ハ長調の調性を強く確立させている。この第1主題(C-G-H-C)の動機は全楽章に渡って用いられており、統一感を与えている。 第2楽章 Andante cantabile con moto ヘ長調 8分の3拍子 ソナタ形式の緩徐楽章(提示部反復指定あり)。冒頭はフーガ風に開始される。2番フルートは休止。 第3楽章 Menuetto, Allegro molto e vivace ハ長調 4分の3拍子 複合三部形式。メヌエットと題されているが、"Allegro molto e vivace"のテンポ指定からスケルツォの性質が強く、早くも後の大作に見出されるような革新性を示している。 第4楽章 Adagio - Allegro molto e vivace ハ長調 4分の2拍子 序奏付きソナタ形式(提示部反復指定あり)。序奏のヴァイオリンの旋律が秀逸といわれる。G音から始まる上行フレーズが繰り返し提示され、それはだんだん長くされ、最後にはF音に達し属七の和音の響きが形作られ、そこでフェルマータとなる。その次には1オクターブ上のG音まで達し、この1オクターブの上行音形とそれに続く旋律が第1主題としての役割を果たすことになる。このような、断片的な動機が発展して主題が生まれるという処理は、後の交響曲第5番や交響曲第9番の第1楽章冒頭でも見られる。 序奏の後の主部はロンド風で、ハイドン的な楽しさに満ちている。第1主題は、第1楽章の副主題(C-E-G-F-E-D-C)の完全な逆行である。 Walk Into Siena チャンネル登録 https://www.youtube.com/channel/UCqAFiZznfr5Y7wgfV_sOiGQ Walk Into Siena コミュニティ https://www.youtube.com/@WalkIntoSiena/community ベートーヴェン 再生リスト https://youtube.com/playlist?list=PLTtHiFCVwL1zT3TDzCFkYRGchw_08y2KG ベートーヴェン『交響曲集』 再生リスト https://www.youtube.com/playlist?list=PLTtHiFCVwL1wpquw9OxqNkW04ZYODRzFE クラシック全般 再生リスト https://youtube.com/playlist?list=PLTtHiFCVwL1yxp2hTQ64gcreupYj8u6jd #ベートーヴェン #交響曲 #第1番 #ハ長調 #作品21

ベートーヴェン:ピアノソナタ第6番 ヘ長調 作品10-2
Ludwig van Beethoven's Piano Sonata No. 6 in F major, Op. 10, No. 2, was dedicated to the Countess Anne Margarete von Browne, and written from 1796 to 1798. The sonata spans approximately 13 minutes. 00:00 I. Allegro 08:18 II. Allegretto 12:01 III. Finale: Presto 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 ピアノソナタ第6番 ヘ長調 作品10-2は、ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェンが作曲したピアノソナタ。 概要 3曲からなる作品10のピアノソナタのうち第2曲にあたる。確実な作曲年代の同定には至っていないものの、グスタフ・ノッテボームはスケッチの研究から1796年から1798年の夏季に至る期間に全曲が書き上げられたと推定している。出版は1798年9月にウィーンのエーダーから行われ、ブロウネ伯爵夫人アンナ・マルガレーテへと献呈されている。ブロウネ伯爵夫妻は早くからベートーヴェンの庇護者であり、伯爵には作品9の弦楽三重奏曲やピアノソナタ第11番、夫人にも作品10以外にいくつかの楽曲が献呈されている。 ひとまとめとして出版された作品10の3曲であるが、内容的にはそれぞれが際立った特徴を有している。本作は軽快な調子で書かれており、形式的には4楽章のソナタから緩徐楽章を除いた3つの楽章によって構成される。緩徐楽章の省略はベートーヴェンの作品では珍しいことではなく、これ以降も研究されて後年の傑作の誕生へと繋がっていく。本作が内に秘める豊かなユーモアの由来には作曲者が教えを仰いだフランツ・ヨーゼフ・ハイドンの存在が指摘されるが、師の影響に加えて十全に発揮されたベートーヴェン自身の個性もこのピアノソナタに顕れている。 楽曲構成 第1楽章 Allegro 2/4拍子 ヘ長調 ソナタ形式。2つの和音とこれに応答するターン的音型の第1主題により明るく開始される。主題の後半は起伏のある息の長い旋律である。 第2楽章 Allegretto 3/4拍子 ヘ短調 明示されていないが実質的にスケルツォに相当する。当初の構想はメヌエットとトリオであったとされる。パウル・ベッカーらはこの楽章が後年の傑作を予感させる内容を有すると評している。ユニゾンが譜例4を奏して始められる。 第3楽章 Presto 2/4拍子 ヘ長調 単一の材料から成るソナタ形式。ハイドン流の遊び心とバッハ流の対位法を併せ持った楽章とされるが、その音楽にはベートーヴェンの個性が色濃く滲み出ている。まずは主題に声部が順次応答してフーガを思わせるような形で開始する。 Walk Into Siena チャンネル登録 https://www.youtube.com/channel/UCqAFiZznfr5Y7wgfV_sOiGQ Walk Into Siena コミュニティ https://www.youtube.com/@WalkIntoSiena/community ベートーヴェン 再生リスト https://youtube.com/playlist?list=PLTtHiFCVwL1zT3TDzCFkYRGchw_08y2KG ベートーヴェン「ピアノソナタ」 再生リスト https://youtube.com/playlist?list=PLTtHiFCVwL1wx8p370mNaQ7Ap00CYMRmH クラシック全般 再生リスト https://youtube.com/playlist?list=PLTtHiFCVwL1yxp2hTQ64gcreupYj8u6jd #ベートーヴェン #ピアノソナタ第6番ヘ長調 #作品10の2

ベートーヴェン:ピアノソナタ第25番 ト長調 作品79
The Piano Sonata No. 25 in G major, Op. 79, was composed by Ludwig van Beethoven in 1809. It is alternatively titled "Cuckoo" or "Sonatina," and it is notable for its shortness. A typical performance lasts only about nine minutes.The work is in three movements: a fast-paced Presto alla tedesca, a slower Andante, and a lively Vivace. From Wikipedia, the free encyclopedia 00:00 I. Presto alla tedesca 04:16 II. Andante 07:24 III. Vivace 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 ピアノソナタ第25番 ト長調 作品79は、ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェンが1809年に作曲したピアノソナタ。 概要 ひとつ前の第24番とこのピアノソナタが作曲された1809年は、『運命交響曲』(1808年)、『田園交響曲』(1808年)、『皇帝協奏曲』(1809年)などの大作が生み出されていた時期にあたる。一方、ピアノ曲の分野では小品が量産されており、前作同様この曲も小さな規模にまとめられている。ベートーヴェンは1810年7月21日に楽譜出版社のブライトコプフ・ウント・ヘルテルに宛てて「ト長調のソナタには『やさしいソナタ』もしくは『ソナチネ』と名付けて下さい」と書簡で希望を伝えており、初版譜ではそれに従って「ソナチネ」と題された。その名の示す通り、ベートーヴェンのピアノソナタとしては演奏も容易である。 第1楽章にカッコウの鳴き声に似た箇所があることから、このソナタは「かっこう」と呼ばれることがある。楽譜は1810年9月にブライトコプフ社から出版された。曲は誰にも献呈されていない。 演奏時間 約9分半。 楽曲構成 第1楽章 Presto alla tedesca 3/4拍子 ト長調 ソナタ形式。「ドイツ風に」と指定されており、レントラーが意識されている。序奏を置かず、曲は第1主題の提示に始まる。 提示部の反復後、展開部となる。展開部は専ら第1主題の要素が扱われており、手の交差によるパッセージでカッコウの声が繰り返され。再現部は基本に忠実に進められる。なお、再現部の後にもう1度展開部から反復するように指示されている。コーダも短く簡素であり、前打音による主題の装飾が彩りを添え、上昇するアルペッジョで楽章を終える。 第2楽章 Andante 9/8拍子 ト短調 三部形式。メンデルスゾーンによる無言歌集の舟歌を思わせる。ゴンドラの上で二重唱を歌うような主題に始まる。 第3楽章 Vivace 2/4拍子 ト長調 ロンド形式。冒頭から軽快な主題が提示される。この主題はピアノソナタ第30番の冒頭主題と密接に関連している。ロンド主題は譜例5を含む8小節とその後に続く8小節から構成される。 Walk Into Siena チャンネル登録 https://www.youtube.com/channel/UCqAFiZznfr5Y7wgfV_sOiGQ Walk Into Siena コミュニティ https://www.youtube.com/@WalkIntoSiena/community ベートーヴェン 再生リスト https://youtube.com/playlist?list=PLTtHiFCVwL1zT3TDzCFkYRGchw_08y2KG ベートーヴェン「ピアノソナタ」 再生リスト https://youtube.com/playlist?list=PLTtHiFCVwL1wx8p370mNaQ7Ap00CYMRmH クラシック全般 再生リスト https://youtube.com/playlist?list=PLTtHiFCVwL1yxp2hTQ64gcreupYj8u6jd #ベートーヴェン #ピアノソナタ第25番 #作品79

ベートーヴェン:ピアノソナタ第10番 ト長調 作品14 2
The Piano Sonata No. 10 in G major, Op. 14, No. 2, composed in 1798–1799, is an early-period work by Ludwig van Beethoven, dedicated to Baroness Josefa von Braun. A typical performance lasts 15 minutes. While it is not as well known as some of the more original sonatas of Beethoven's youth, such as the Pathétique or Moonlight sonatas, Donald Francis Tovey described it as an 'exquisite little work.' 00:00 I. Allegro 06:04 II. Andante 12:26 III. Scherzo: Allegro assai 演奏者ペ Peter Bradley-Fulgoni (piano) 公開者情報 Peter Bradley-Fulgoni 著作権 Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 備考 Recorded December 2017 in St. Paul's Hall, Huddersfield University (Peter Hill, sound engineer) 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 ピアノソナタ第10番 ト長調 作品14-2は、ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェンが作曲したピアノソナタ。 概要 本作は1798年から1799年にかけて作曲されたものと考えられている。第9番のピアノソナタとともに「作品14」としてまとめられ、1799年12月にウィーンのモロ社から出版され]。両曲ともブラウン男爵夫人ヨゼフィーネ・フォン・ブラウンへと献呈されている。 作品14は比較的小さくまとめられた作品であり、とりわけ演奏も容易で優美な趣を持つ本作は初学者用の教材として用いられることも多い。アントン・シンドラーは作品14の2曲に「男女の対話が認められる」とした上で、「特に第2番目の曲にはこの対話はいっそう明瞭に示されていて、2つの声部の対立は第1番に比べてより明白である」と述べた(そのため、かつて日本ではこのソナタを『夫婦喧嘩』という愛称で呼んでいたが、現在ではこの愛称は廃れている)。同時期に作曲されたであろう第8番『悲愴』と本作との間に見られる性格の差異にベートーヴェンの作曲姿勢が垣間見える。 この作品には作曲者のユーモラスな一面が映し出されており[5]、これほどまでに移り気な性格を示す楽曲も珍しい。エルンスト・フォン・エルターラインのように作品14の価値を低く看做す識者もいる一方で、「非常に美しい小品」と述べたドナルド・フランシス・トーヴィーやシンドラーは高い評価を与えている。 演奏時間 約15分半-16分。 楽曲構成 第1楽章 Allegro 2/4拍子 ト長調 ソナタ形式。第1主題は左手が右手の呼びかけに応えるような譜例1であり、シンドラーが述べたような「男女の対話」を思わせる。 第2楽章 Andante 2/2拍子 ハ長調 変奏曲形式[7]。主題と3つの変奏によって構成されるこの楽章が、ベートーヴェンのピアノソナタに導入された初の変奏曲となった]。おもちゃの兵隊が行進する様を想起させるようなコミカルな主題に始まる)。 第3楽章 Scherzo, Allegro assai 3/8拍子 ト長調 スケルツォと書かれているが、ロンド形式による。主部はヘミオラのリズムを持っており、デニス・マシューズはこれを「(作曲者は)2が3つあることは3が2つあることと同じ」であると見出したのだと表現した。 Walk Into Siena チャンネル登録 https://www.youtube.com/channel/UCqAFiZznfr5Y7wgfV_sOiGQ Walk Into Siena コミュニティ https://www.youtube.com/@WalkIntoSiena/community ベートーヴェン 再生リスト https://youtube.com/playlist?list=PLTtHiFCVwL1zT3TDzCFkYRGchw_08y2KG ベートーヴェン「ピアノソナタ」 再生リスト https://youtube.com/playlist?list=PLTtHiFCVwL1wx8p370mNaQ7Ap00CYMRmH クラシック全般 再生リスト https://youtube.com/playlist?list=PLTtHiFCVwL1yxp2hTQ64gcreupYj8u6jd #ベートーヴェン #ピアノソナタ第10番 #作品14の2

ベートーヴェン:ピアノ・ソナタ 第28番 イ長調 作品101
Ludwig van Beethoven's Piano Sonata No. 28 in A major, Op. 101, was written in 1816 and was dedicated to the pianist Baroness Dorothea Ertmann, née Graumen. This sonata marks the beginning of what is generally regarded as Beethoven's final period, where the forms are more complex, ideas more wide-ranging, textures more polyphonic, and the treatment of the themes and motifs even more sophisticated than before. Op. 101 well exemplified this new style, and Beethoven exploits the newly expanded keyboard compass of the day. 00:00 I. Etwas lebhaft und mit der innigsten Empfindung 04:12 II. Lebhaft. Marschmassig 10:19 III. Langsam und sehnsuchtsvoll 14:31 IV. Geschwind, doch nicht zu sehr, und mit Entschlossenheit 演奏者 Paavali Jumppanen (piano) 公開者情報 Boston: Isabella Stewart Gardner Museum 著作権 Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives 3.0 備考 April 13, 2008. 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 ピアノソナタ第28番 イ長調 作品101は、ベートーヴェンが1815年から1816年にかけて作曲したピアノソナタ。 概要 戦後の混乱、私生活上での失望などにより作曲の筆が進まなくなっていたベートーヴェンであったが、1815年に作品102のチェロソナタ(第4番と第5番)を書き上げ、翌年には歌曲集『遥かなる恋人に』を完成させた。これらに続く形で完成されたのが作品101のピアノソナタである。作曲はほとんどが1816年の夏に行われ、原稿には同年11月の日付が見られる。こうして生まれた本作はベートーヴェンのロマン期・カンタービレ期から後期への橋渡しをする入り口となる作品である。即ち、この作品は第26番『告別』や第27番のソナタのような豊かな歌謡性を備えながら、孤高の境地へと達する後期のスタイルの特質を併せ持ったものである。アントン・シンドラーによると、作曲者自身はこの作品が「印象と幻想」を内に有すると語ったという。 曲はドロテア・エルトマン夫人(旧姓 グラウメン)へと献呈された。メンデルスゾーンやシンドラーも称賛したほどの優れたピアニストであった彼女は、このとき既に10年来のベートーヴェンの弟子であった。夫人の演奏を高く買っていたベートーヴェンは1817年2月23日の書簡で「かねがねあなたに差し上げようと思っていたもので、あなたの芸術的天分とあなたの人柄に対する敬愛の表明になるでしょう。」と書き送ってる。 楽譜の出版は1817年2月、ウィーンのシュタイナーから行われた。ピアニストのアンドラーシュ・シフは、本作と同時期に作曲されたチェロソナタ第5番が構造的に非常に類似していることを指摘している。 演奏時間 約19分。 楽曲構成 第1楽章 幾分速く、そして非常に深い感情をもって Etwas lebhaft und mit der innigsten Empfindung (Allegretto,ma non troppo) 6/8拍子 イ長調 ソナタ形式。形式的には極めて自由でありながら、夢想の中に息づく自然な流れが見事な調和を生み出している。冒頭から譜例1の歌謡的な旋律が属和音で開始される。 第2楽章 生き生きした行進曲風に Lebhaft. Marschmäßig (Vivace alla Marcia) 4/4拍子 ヘ長調 三部形式。シューマンの音楽を予感させるような、付点リズムの跳躍を特徴とした行進曲風の音楽。一転して主題労作的であり、高度な和声法、転調技法で展開され緊張感が高い。第1部全体が冒頭に示される譜例3を素材として構成される。途中、センプレ・レガートとなり、サステインペダルを踏みこんだまま声部が応答しあう個所は印象的な響きをもたらしている。 第3楽章 ゆっくりと、そして憧れに満ちて Langsam und sehnsuchtsvoll (Adagio,ma non troppo,con affetto) 2/4拍子 イ短調 - 速く、しかし速すぎないように、そして断固として Geschwinde, doch nicht zu sehr und mit Entschlossenheit (Allegro) 6/8拍子 イ長調 緩徐楽章を序奏としたフィナーレと見ることができる。序奏部分が第3楽章、ソナタ部分が第4楽章として扱われる場合もある。序奏部全体にわたって弱音ペダルを踏むよう指定されており、寂寥感を湛えた楽想が奏でられる。序奏部は3連符を含む音型から構成される。この部分の最後に置かれるノン・プレストのカデンツァには「少しずつ弦を増やす」と指示されているが、これは当時のピアノでは弱音ペダルの踏み方によって通常3弦を叩くハンマーを順次2弦、1弦と変化させることが出来るほど踏み込みが深くできたことが念頭に置かれており、現代のピアノの弱音ペダルの踏み込みの浅さでは指示通りの演奏は実現不可能である。 Walk Into Siena チャンネル登録 https://www.youtube.com/channel/UCqAFiZznfr5Y7wgfV_sOiGQ Walk Into Siena コミュニティ https://www.youtube.com/@WalkIntoSiena/community ベートーヴェン 再生リスト https://youtube.com/playlist?list=PLTtHiFCVwL1zT3TDzCFkYRGchw_08y2KG ベートーヴェン「ピアノソナタ」 再生リスト https://youtube.com/playlist?list=PLTtHiFCVwL1wx8p370mNaQ7Ap00CYMRmH クラシック全般 再生リスト https://youtube.com/playlist?list=PLTtHiFCVwL1yxp2hTQ64gcreupYj8u6jd #ベートーヴェン #ピアノソナタ第28番 #作品101

ベートーヴェン:ピアノソナタ第7番 ニ長調 作品10-3
Ludwig van Beethoven's Piano Sonata No. 7 in D major, Op. 10, No. 3, was dedicated to the Countess Anne Margarete von Browne, and written in 1798. This makes it contemporary with his three Op. 9 string trios, his three Op. 12 violin sonatas, and the violin and orchestra romance that became his Op. 50 when later published. The year also saw the premiere of a revised version of his second piano concerto, whose original form had been written and heard in 1795. 00:00 I. Presto 05:12 II. Largo e mesto 15:47 III. Menuetto: Allegro - Trio 18:45 IV. Rondo: Allegro 演奏者 Peter Bradley-Fulgoni (piano) http://www.peterbradley-fulgoni.com/page2.htm 公開者情報 Peter Bradley-Fulgoni 著作権 Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 備考 year of recording: 1985 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 ピアノソナタ第7番 ニ長調 作品10-3は、ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェンが作曲したピアノソナタ。 概要 作品10としてまとめられた3曲のピアノソナタのうちの第3曲である。正確な作曲年代はわかっていないものの、3曲とも1795年もしくは1796年から1798年の夏までの期間で作曲されたとされる。1798年にウィーンのエーダー社から出版され、ブロウネ伯爵夫人アンナ・マルガレーテに献呈された。この際、楽譜の表紙には「クラヴサンまたはピアノフォルテのための3つのソナタ」と印字された。これは楽譜の売れ行きを案じた出版社による措置と思われ、作曲者自身は当時既にこの2つの楽器が全く異なるものであると考えていたようである。 作品10の他の2曲(第5番、第6番)が3楽章制を採り小規模であるのに対して、本作は4つの楽章を擁する大規模な音楽となっている。第7番はその3作品の中でも特に優れていると看做されることが多い。ベートーヴェンの弟子であった作曲家のカール・チェルニーは、このソナタを「壮大にして重要な」作品であると評した。とりわけ作曲者がアントン・シンドラーに「悲しんでいる人の心の状態を、さまざまな光と影のニュアンスにおいて描こうとした」と語ったとされる第2楽章は、それまでのベートーヴェンの音楽にはない深刻さを湛えている。この寂寞たる悲劇性を忍び寄る難聴の影と関連付ける意見もある。 演奏時間 約22分半-23分。 楽曲構成 第1楽章 Presto 2/2拍子 ニ長調 ソナタ形式。力を秘めた第1主題がスタッカートのユニゾンで提示されて曲の幕を開ける。この冒頭の4音は楽章全体にわたって使用され、全体を統一するモチーフの役割を果たす。直後には譜例1と対照的なレガートの音型が配されるが、これも4音のモチーフが積み重なって形作られたものである。 第2楽章 Largo e mesto 6/8拍子 ニ短調 ソナタ形式。この「mesto」(悲しげに)と指示された、心を掴む悲劇的な楽章は、音楽史にランドマークを打ち立てたといえる。ベートーヴェンがこの曲を最後にラルゴ楽章を一生ピアノソナタに用いなかったことを受け、パウル・ベッカーは、「ラルゴは最もよい精分を搾取されて、結局ベートーヴェンにより棄てられた」と述べている。重い五重和音が引きずるように歩を進める中で、第1主題の旋律が空虚に揺れる。そういえば後年書かれたピアノソナタ第12番の第3楽章(アンダンテの葬送行進曲)も、重層的な和音が特徴であった。 フォルテッシモの高揚に導かれて現れる印象的な高音部の32分音符の音型は、後年の円熟期における作曲者の書法を予感させる深みに到達している。32分音符の下降音型が第1主題へと接続されて再現部となる。第1主題は短くまとめられ、第2主題も続いて再現される。コーダでは低音で第1主題が奏でられる上で6連符のアルペッジョが鳴り響くが、音量の増大と共に64分音符へと音価を減らして頂点に至る。32分音符の音型と第1主題が順に回想されて、失われたものがどうあがいても取り戻せないとついに悟るように、悲嘆の歩も静かに止まる。 第3楽章 Menuetto, Allegro 3/4拍子 ニ長調 「ソミ」ではじまる典型的な癒し系の主題が歌い始められる。第2楽章で塗り潰され時間が止まった悲壮の闇に、ふと新たな光が差し込んできた感動的な瞬間である。 第4楽章 Rondo, Allegro 4/4拍子 ニ長調 ロンド形式。何かを問うような印象的な主題に始まる。ベートーヴェンはこの動機を用いて憂鬱さを表現したのだとシンドラーが伝えている。壮大なテーマがあるのではなく、上昇する3音符の小さく単純なモチーフが楽章全体を構成している。ベートーヴェンはこのように小さな素材を曲全体に即興的に散らすことをしばしば行ったと、弟子ツェルニーは証言した。 Walk Into Siena チャンネル登録 https://www.youtube.com/channel/UCqAFiZznfr5Y7wgfV_sOiGQ Walk Into Siena コミュニティ https://www.youtube.com/@WalkIntoSiena/community ベートーヴェン 再生リスト https://youtube.com/playlist?list=PLTtHiFCVwL1zT3TDzCFkYRGchw_08y2KG ベートーヴェン「ピアノソナタ」 再生リスト https://youtube.com/playlist?list=PLTtHiFCVwL1wx8p370mNaQ7Ap00CYMRmH クラシック全般 再生リスト https://youtube.com/playlist?list=PLTtHiFCVwL1yxp2hTQ64gcreupYj8u6jd #ベートーヴェン #ピアノソナタ第7番 #作品10の3

ベートーヴェン:ヴァイオリン・ソナタ第6番 イ長調, 作品30-1 (Beethoven:Violin Sonata No.6 in A major, Op.30 No.1)
From Wikipedia, the free encyclopedia The Violin Sonata No. 6 of Ludwig van Beethoven in A major, the first of his Opus 30 set, was composed between 1801 and 1802, published in May 1803, and dedicated to Tsar Alexander I of Russia. 00:00 I. Allegro 07:42 II. Adagio molto espressivo 14:17 III. Allegretto con variazioni 演奏者 Corey Cerovsek (violin) Paavali Jumppanen (piano) 公開者情報 Boston: Isabella Stewart Gardner Museum 著作権 Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives 3.0 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 ヴァイオリンソナタ第6番 イ長調 作品30-1 は、ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェンが1802年に作曲したヴァイオリンソナタ。 概要 ロシア皇帝アレクサンドル1世に献呈された「アレキサンダー・ソナタ」の1曲であり、次作の第7番、次次作の第8番とも異なり、穏やかなゆるさが全曲を覆っている。 もともと最終楽章はクロイツェル・ソナタのそれ、タランテラになる予定であった。作曲者はここに華々しい効果を期待するよりは、次作の華やかにして雄渾な曲想を際立たせようとしたのか、伸びやかな変奏曲楽章をおいている。 曲の構成 第1楽章 アレグロ イ長調、4分の3拍子、ソナタ形式。 16分音符のついた特徴的な主題。オクターヴ奏法とユニゾンが多く、アレグロ楽章として落ち着いた演奏が適切。 第2楽章 アダージョ・モルト・エスプレッシーヴォ ニ長調、4分の2拍子、複合三部形式。 ヴァイオリンが付点リズムで春風駘蕩といった雰囲気を出す。主題はヴァイオリンで導入され、「A - A - A - G - Fis - Fis - Fis - Fis」の単純なもの。中間部は短いながら同主調(ニ短調)に変わり、単調にしていない。 第3楽章 アレグレット・コン・ヴァリアツィオーニ イ長調、2分の2拍子、変奏曲形式。 主題と6つの変奏。ヴァイオリンの「E - A - Cis - Ais - H - H - A - Gis - Fis - Gis - A」の主題をピアノのアルベルティ・バスがささえる。 Walk Into Siena チャンネル登録 https://www.youtube.com/channel/UCqAFiZznfr5Y7wgfV_sOiGQ Walk Into Siena コミュニティ https://www.youtube.com/@WalkIntoSiena/community ベートーヴェン 再生リスト https://youtube.com/playlist?list=PLTtHiFCVwL1zT3TDzCFkYRGchw_08y2KG クラシック全般 再生リスト https://youtube.com/playlist?list=PLTtHiFCVwL1yxp2hTQ64gcreupYj8u6jd #ベートーヴェン #ヴァイオリンソナタ第6番 #作品30-1

ベートーヴェン:ピアノソナタ第19番 ト短調 作品49-1
The Piano Sonata No. 19 in G minor, Op. 49, No. 1, and Piano Sonata No. 20 in G major, Op. 49, No. 2, are short sonatas by Ludwig van Beethoven, published in 1805 (although the works were actually composed a decade earlier in early to mid 1797). Both works are approximately eight minutes in length, and are split into two movements. These sonatas are referred to as the Leichte Sonaten to be given to his friends and students. From Wikipedia, the free encyclopedia 00:00 I. Andante 04:31 II. Rondo: Allegro 演奏者 Paavali Jumppanen (piano) 公開者情報 Boston: Isabella Stewart Gardner Museum 著作権 Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives 3.0 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 ピアノソナタ第19番 ト短調 作品49-1は、ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェンが作曲したピアノソナタ。 概要 このソナタと第20番のピアノソナタは、作品49としてまとめられて1805年1月にウィーンの美術工芸社から出版された。楽想が最初に書き留められたのは1795年から1796年にかけての時期であったと、大英博物館所蔵のスケッチブックを根拠に予想されている。全曲の完成は1798年であると考えられているが、その後ベートーヴェンの弟であるカスパーが独断で出版社にかけあって世に出されたとされる。 作品49の初版譜に記されている「2つのやさしいソナタ(Deux Sonates Faciles)」という題名が示すとおり、曲は内容や演奏の平易なことから弟子の練習曲として書かれたものと思われる。今日においてもピアノ学習者の初歩の教材として頻繁に取り上げられているが、作品49の2曲がたたえる豊かな内容は芸術作品への導入として今なお広く用いられるべきものであるといえる。 楽曲構成 第1楽章 Andante 2/4拍子 ト短調 ソナタ形式。 第2楽章 Rondo. Allegro 6/8拍子 ト長調 Walk Into Siena チャンネル登録 https://www.youtube.com/channel/UCqAFiZznfr5Y7wgfV_sOiGQ Walk Into Siena コミュニティ https://www.youtube.com/@WalkIntoSiena/community ベートーヴェン 再生リスト https://youtube.com/playlist?list=PLTtHiFCVwL1zT3TDzCFkYRGchw_08y2KG クラシック全般 再生リスト https://youtube.com/playlist?list=PLTtHiFCVwL1yxp2hTQ64gcreupYj8u6jd #ベートーヴェン #ピアノソナタ第19番 #作品49の1

ベートーヴェン:ピアノソナタ第30番ホ長調 作品109
Ludwig van Beethoven's Piano Sonata No. 30 in E major, Op. 109, composed in 1820, is the third-to-last of his piano sonatas. In it, after the huge Hammerklavier Sonata, Op. 106, Beethoven returns to a smaller scale and a more intimate character. It is dedicated to Maximiliane Brentano, the daughter of Beethoven's long-standing friend Antonie Brentano, for whom Beethoven had already composed the short Piano Trio in B♭ major WoO 39 in 1812. Musically, the work is characterised by a free and original approach to the traditional sonata form. Its focus is the third movement, a set of variations that interpret its theme in a wide variety of individual ways. From Wikipedia, the free encyclopedia 00:00 I. Vivace ma non troppo 03:36 II. Prestissimo 06:05 III. Andante molto cantabile ed espressivo 演奏者 Ivan Ilić (piano) https://en.wikipedia.org/wiki/Ivan_Ili%C4%87_(pianist)公開者情報 Paris: Ivan Ilić 著作権 Creative Commons Attribution 3.0 備考 Ivan Ilić, piano, recorded by Judith Carpentier Dupont in Paris in April 2003 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 ピアノソナタ第30番ホ長調作品109は、ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェンが1820年に作曲したピアノソナタ。 概要 大作「ハンマークラヴィーアソナタ」を完成したベートーヴェンが続く作品109のピアノソナタに着手したのは1820年の初頭で、これは最後の3つのピアノソナタ(第30番、第31番、第32番)を出版したシュレジンガーとの交渉が行われるよりも前のことであった。曲の原型となったのは小品もしくはバガテルであり、フリードリヒ・シュタルケからピアノ作品集『ウィーンのピアノフォルテ楽派』への楽曲提供を依頼され、既に取り掛かっていた『ミサ・ソレムニス』の仕事を後に回す形で作曲が行われた作品であった。同年4月のベートーヴェンの会話帳には「新作の小品」との記載があり、幻想曲調の間奏曲に中断されるバガテルという楽曲の構成からは、これが作品109の第1楽章となったのであろうことが窺われる。ベートーヴェンの秘書を務めていたフランツ・オリファが、この「小品」をシュレジンガーの求めるソナタの開始楽章にしてはどうかと提案したとされる。結局、シュタルケに提供されたのは11のバガテル 作品119の第7曲から第11曲であった。 ジークハルト・ブランデンブルクは、当初構想されていたのが第1楽章を欠いた2楽章から成るソナタであったとする説を提唱している。第1楽章と他の楽章を結びつける動機要素が、明らかに後になってから付け加えられたものだからである。一方、アレグザンダー・ウィーロック・セイヤーはホ短調のソナタの構想は発展することなく終わり、作品109とは全く関係がないとする立場を取っている。 第3楽章のために最初に書かれたスケッチは6つの変奏を伴う変奏曲であったが、その後9つの変奏に改められ、最終的に6つの変奏に落ち着いた。9つの変奏が設けられていた稿での個々の変奏の性格は、出版された最終稿のものに比べると際立っていないが、ケイ・ドレイファスはその時点で既に「主題の探索と再発見の過程」が示されていると指摘している。 このソナタの完成が1820年の秋であったのか、または1821年になってからであったのかははっきりしていない。1820年9月20日にシュレジンガーに宛てて送られた書簡では、最後の3つのソナタのうち最初の作品の「完成」が近いことが語られている。しかし、ここでの「完成」が意味するところが構想の決定であるのか、送付可能な浄書譜の完成であるのかは不明である。初版譜はベルリンのシュレジンガーから出されたが、作曲者が病床にあり適切な校正を行うことが出来なかったため、数多くの誤植が残されたままだった。作品は当時18歳だったマキシミリアーネ・ブレンターノに献呈されている。1821年12月6日にしたためられた献呈の句には、作曲者がブレンターノ家に抱いていた深い愛着の情が綴られている。 楽曲構成 第1楽章 Vivace, ma non troppo 2/4拍子 ホ長調 ソナタ形式。第1楽章は速度と拍子の異なる楽想をひとつにまとめあげており、当時のベートーヴェンが関心を持っていた挿入節的な構成概念が反映されている。これは同時期に作曲が進められた『ミサ・ソレムニス』やこの後に続くピアノソナタにも見られる特徴である。無駄のない形式の中に込められた曲の内容は幻想的で、それまでのベートーヴェンのピアノソナタには見られなかった柔軟性が示されている。序奏はなく、第1主題が2/4拍子でヴィヴァーチェ・マ・ノン・トロッポで提示される。この第1主題はピアノソナタ第25番の第3楽章の主題との関連を指摘されている。 開始からカデンツを経ないままわずか8小節後に現れる第2主題は、第1主題とうってかわって3/4拍子のアダージョ・エスプレッシーヴォである。 14小節の提示部を終え、曲は第1主題に基づく展開部となる。中音域から長いクレッシェンドを経つつ音量を増して高音域へと昇っていき、クライマックスに達するとそのまま1オクターヴ高く第1主題が再現される。その後ただちに、やや変化を加えられた第2主題の再現が続く。66小節目からはコーダであり、専ら第1主題を扱って最後は静かに楽章を閉じる。 エトヴィン・フィッシャーは、2つの主題の速度記号の落差は外見上だけのものであり、全体が一つの型として作られたかのように即興的に演奏されねばならないと講義している。グレン・グールドはこの第1楽章を高く評価していた。 第2楽章 Prestissimo 6/8拍子 ホ短調 ソナタ形式。第1楽章からは切れ目なく演奏される。楽章中で用いられる素材はフォルテッシモで出される譜例3の第1主題の中に集約されている。 第1主題から導かれる第2主題はロ短調に出されるが、主題の持つ性質によりここでは通常のソナタ形式に見られるような主題間の対比は完全に失われている。 展開部ではまず第1主題のバスの音型がカノン風に処理される。その後静かな推移を見せるが、突如強奏で第1主題が回帰して再現部となる。第2主題はホ短調となって現れ、ごく短いコーダを経て勢いよく終結する。 第3楽章 Andante molto cantabile ed espressivo 3/4拍子 ホ長調 変奏曲形式。主題と6つの変奏からなる。全曲の重心のほとんどはこの第3楽章に置かれており、変奏曲がこれほどの比重を占めたのはベートーヴェンのピアノソナタでは初めてのことであった。 主題: 3/4拍子 「じゅうぶんに歌い、心の底からの感情をもって」(Gesangvoll, mit innigster Empfindung)と付記されている。ゆったりとしたテンポで静かに曲が開始される。3拍子の2拍目に付点音符が置かれることにより、主題にはサラバンドのような性格が与えられている。 第1変奏: 3/4拍子 モルト・エスプレッシーヴォの指示の下、ワルツ様のリズムに乗った歌謡的変奏。曲の雰囲気や主題のテンポは主題から引き継がれ、装飾音が巧みに使われている。 第2変奏: 3/4拍子 主題は16分音符によるモザイク状の音型の中に隠される。さらにこの変奏と対照的な威厳ある変奏が置かれ、2つの性格の異なる変奏が入れ替わりながら進められていく。 第3変奏: 2/4拍子 対位法を駆使したアレグロ・ヴィヴァーチェでのテンポの速い変奏。開始部分の譜例8で示されるパッセージは左右の手を入れ替えて奏され、その後も手の交代が続けられていく。 第4変奏: 9/8拍子 「主題よりいくらか遅く」(Etwas langsamer als das Thema)と指示されている。第3変奏から大きく趣を変え、幻想的な雰囲気をたたえる。2声から4声の声部が対位法を用いてまとめられていく、温かみのある変奏。 第5変奏: 2/2拍子 スタッカートを多用した快活な対位法による変奏。リズムによる推進力に支えられたこの変奏は多声的なコラールのような印象を与える。 第6変奏: 3/4拍子 カンタービレと指定され、まず内声部に主題が奏される。 4分音符で始まったリズムの刻みは8分音符、三連符の8分音符、16分音符、32分音符と細かくなっていき、ついにトリルにまで細分化される。12小節目から両手に現れたトリルは低音部に移され、17小節目からの荒れ狂うアルペッジョを経ると高音で鳴り続けるトリルの上に主題が明滅する。 最後に次第に弱まりながら主題が原型のまま回想され、静かに曲を閉じる。 このように最後に主題がそのまま回想されて終わる変奏曲であるという特徴から、この楽章はバッハの『ゴルトベルク変奏曲』との類似性を指摘されている。 Walk Into Siena チャンネル登録 https://www.youtube.com/channel/UCqAFiZznfr5Y7wgfV_sOiGQ Walk Into Siena コミュニティ https://www.youtube.com/@WalkIntoSiena/community ベートーヴェン 再生リスト https://youtube.com/playlist?list=PLTtHiFCVwL1zT3TDzCFkYRGchw_08y2KG クラシック全般 再生リスト https://youtube.com/playlist?list=PLTtHiFCVwL1yxp2hTQ64gcreupYj8u6jd #ベートーヴェン #ピアノソナタ第30番 #作品109

ベートーヴェン;ピアノソナタ第32番 ハ短調 作品111
From Wikipedia, the free encyclopedia The Piano Sonata No. 32 in C minor, Op. 111, is the last of Ludwig van Beethoven's piano sonatas. The work was written between 1821 and 1822. Like other late period sonatas, it contains fugal elements. It was dedicated to his friend, pupil, and patron, Archduke Rudolf. The sonata consists of only two contrasting movements. The second movement is marked as an arietta with variations. Thomas Mann called it "farewell to the sonata form". The work entered the repertoire of leading pianists only in the second half of the 19th century. Rhythmically visionary and technically demanding, it is one of the most discussed of Beethoven's works. 00:00 I. Maestoso - Allegro con brio ed appassionato 09:18 II. Arietta: Adagio molto semplice e cantabile 演奏者 Peter Bradley-Fulgoni (piano) http://www.peterbradley-fulgoni.com/page2.htm 公開者情報 Peter Bradley-Fulgoni 著作権 Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 備考 recorded in June 2019 at St. Paul's Hall, Huddersfield University: Peter Hill, sound engineer 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 ピアノソナタ第32番 ハ短調 作品111は、ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェンが1822年に完成した、作曲者最後のピアノソナタ。 概要 ベートーヴェン最後のピアノソナタの作曲は、第30番作品109、第31番 作品110と並行する形で進められた。1819年頃にはスケッチに着手しており、1820年9月20日の書簡ではこの曲の作曲を進めている最中であることが報告されている。その後、浄書開始の日付として譜面に1822年1月13日の日付が書き入れられており、この直後に全曲の完成に至ったと思われる。当時のベートーヴェンは『ミサ・ソレムニス』や交響曲第9番などの大作にも取り組んでおり、これら晩年の作品群は同時に生み出されていったことになる。 この曲の完成をもってベートーヴェンは初期より続けてきたピアノソナタ作曲の筆を折る。この曲の後のピアノ作品には『ディアベリ変奏曲』などが続くものの、ピアノソナタが書かれることはついになかった。1822年6月5日付の書簡では次なるピアノソナタが近いうちに出来上がる旨、楽譜出版社のペータースに伝えているが、該当する作品の存在は草稿としても確認されていない。 楽譜は1822年にシュレジンガーから出版された。楽譜の表紙にはルドルフ大公への献辞が掲げられているが、もともとはベートーヴェンと関わりの深かったブレンターノ家のアントニー(1780年-1860年)に贈られる予定だった。しかし、献呈先をどちらとするか両者の間で二転三転した結果、最終的にルドルフ大公へと捧げられることになった。なお、アントニーはピアノソナタ第31番の献呈先としても名前が挙がっていたものの結局同曲は無献辞で出版されており、ようやく『ディアベリ変奏曲』に至って作品の献呈を受けることになる。 他の後期ピアノソナタと同様、この作品もフーガ的要素を含み、非常に高い演奏技術をピアノ奏者に要求する。 また、この曲はベートーヴェンの全ピアノソナタのうち唯一強弱記号としてメゾピアノを使用している曲である。 演奏時間 第1楽章が約9分、第2楽章が約15分である。 楽曲構成 曲はアレグロで対位法的書法を駆使した情熱的なハ短調のソナタ形式と、アダージョで美しいハ長調の変奏曲という、ベートーヴェンが後期ピアノソナタにおいて体現してきたすべての要素を凝縮したかのような対照的な2楽章からな。 第1楽章 Maestoso - Allegro con brio ed appassionato ハ短調 ソナタ形式。序奏を持ち、フーガ的要素を含む。悲愴ソナタや運命交響曲などベートーヴェンのハ短調で書かれた他の作品と同じく、荒々しく熱情的な楽想を持つ。また、減七の和音を多く含む。第1楽章の冒頭、第1小節全体に広がる減七の和音はその一例である。 序奏は低音からのクレッシェンドにより主部へと接続される。第1主題は強奏により威圧的に提示され、まもなく対位法的に扱われていく。 第2主題は変イ長調で現れるが、たちまち細かい音の流れに融解していく(譜例3)。 第2主題のもたらす静寂は長くは続かず、第1主題に基づくコデッタに取って代わられると反復記号によって提示部を繰り返す。展開部では第1主題をフーガ風に扱っていくが、規模はさほど大きなものではない。4オクターヴのユニゾンが強烈に譜例2を奏して再現部となり、続いて第2主題はハ長調となって現れる。第2主題がヘ短調となって低音部で繰り返され、結尾句を経るとコーダとなる。コーダは短いながらも、ディミヌエンドしてハ長調で終止し、第2楽章の変奏曲に溶け込むように巧妙に作られている。 第2楽章 Arietta. Adagio molto, semplice e cantabile ハ長調 (厳格)変奏曲。16小節の主題とそれに基づく5つの変奏からなり、転調を伴う短い間奏とコーダを持つ。16分の9拍子の下、譜例4に示される深みのある主題が穏やかに歌われる。 第1変奏では旋律に一定の律動が伴われ、以後、第3変奏にかけてこの律動が漸次細分化される。 第4変奏になると、32分音符の三連音による律動が低音部及び高音部に出現するが、この律動は非常に重要で、その後の楽曲全体を支配する。第4変奏末尾には間奏部が付されている。長いトリルを伴って主題の断片が現れ、一度ハ短調に転ずると最弱音から息の長いクレッシェンドを形成しつつ第5変奏へと接続される。 最終(第5)変奏より、主題が律動の上に出現する。再び姿を現した主題は名残を惜しむかのように、拡大されて歌われていく。 最後は高音域のトリルを伴いながら主題が回顧され、ハ長調の響きの中、楽曲は静寂のうちに幕を閉じる。 評価 2楽章という際立った対比について、「輪廻と解脱」(ハンス・フォン・ビューロー)、「此岸と彼岸」(エトヴィン・フィッシャー)、「抵抗と服従」(ヴィルヘルム・フォン・レンツ)など、過去にも様々な形容がなされてきた。ベートーヴェン自身は曲が2つの楽章で終わることについて伝記作家のアントン・シンドラーに問われた際、ただ「時間が足りなかったので」とのみ述べたとされる。一方で、トーマス・マンは小説『ファウストゥス博士』の中で作中人物の言葉として「戻ることのない終わり」「ソナタという形式との決別」とし、2楽章が遥かな高みに至るのを聴くとき、聴衆はこのピアノソナタがこれ以上の楽章を必要としないことを自ずと悟るのである、と表現している。 Walk Into Siena チャンネル登録 https://www.youtube.com/channel/UCqAFiZznfr5Y7wgfV_sOiGQ Walk Into Siena コミュニティ https://www.youtube.com/@WalkIntoSiena/community ベートーヴェン 再生リスト https://youtube.com/playlist?list=PLTtHiFCVwL1zT3TDzCFkYRGchw_08y2KG クラシック全般 再生リスト https://youtube.com/playlist?list=PLTtHiFCVwL1yxp2hTQ64gcreupYj8u6jd #ベートーヴェン #ピアノソナタ第32番 #作品111

ベートーヴェン:ホルン・ソナタ ヘ長調, 作品17
In this video, I'm performing the Beethoven Horn Sonata in F major, Op. 17 in 1800. I'm joined by the Calgary Philharmonic Orchestra, conducted by Vladimir Ashkenazy. If you're interested in classical music, then you won't want to miss this performance! The Beethoven Horn Sonata in F major, Op. 17 is one of the composer's most famous pieces, and is a wonderful example of his horn writing. This piece is played on a Hungarian-made horn called the "Basset Horn." If you're a fan of classical music, then you won't want to miss this performance! 00:00 I. Allegro moderato 06:13 II. Poco adagio, quasi andante 07:53 III. Rondo: Allegro moderato (Hr)ジョゼフ・エガー (P)ヴィクター・バビン 1959年3月12日~14日録音 (Hr)Joseph Eger (P)Victor Babin Recorded on March 12-14, 1959 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 ホルンソナタ ヘ長調 作品17は、ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェンが1800年に作曲したホルンとピアノの二重奏曲である。ヴィルトゥオーゾホルン奏者のジョヴァンニ・プントのために書かれた。 概要 プントに触発されたことが作曲のきっかけとなった。本作と同時期の作品にはピアノソナタ第11番や創作主題による6つの易しい変奏曲 ト長調などがあり、本作の性格は後者により近いものがある。曲はプントのソロ、ベートーヴェン自身の伴奏で1800年4月18日にウィーンで初演された。ベートーヴェンの弟子であったフェルディナント・リースの伝えるところでは、驚くべきことにベートーヴェンが作曲にとりかかったのは初演の前日であったという。初演当日、ベートーヴェンは一部記憶を頼りにしつつ、またその場で即興して演奏したとされる。作曲家ベートーヴェンの才能とともに、ごくわずかな時間で演奏の準備を整えたプントの実力の高さを伝えるエピソードである。 ウィーン初演は成功を収め、5月初旬にペシュトにて再演の運びとなった。ベートーヴェンは本作の作曲当時ウィーン以外では知られていなかった。プントとベートーヴェンによるペシュトでの演奏後、ハンガリーの評論家が次のように書いている。「このベートーヴェンとは誰なのか。彼の名前は我々には知られていない。もちろん、プントはよく知られているが。」この演奏会後に両者は仲たがいをしたとみられ、ベートーヴェンは地方公演における共演を拒否してしまう。次に2人が同じ舞台に姿を現したのは1801年1月30日に開催されたホーエンリンデンの戦いでの負傷者のための演奏会であり、ベートーヴェンは本作ではなく、指揮者としてハイドンの交響曲2曲を含むプログラムを演奏したのであった。 この作品はナチュラル・ホルンのために、低音を担当する第2ホルンの語法を用いて書かれている。ベートーヴェンは第1楽章と第3楽章に急速なアルペッジョを取り入れる傍ら、不自然に低いト音を使用している。これらはいずれもプントが専門としていた第2ホルンの奏法の特徴であった。 楽譜の初版は1801年にウィーンで出版された。作品の販路を広げるために、おそらくベートーヴェン自身の手によると思われるチェロソナタへの編曲が行われている。以降は「ホルンまたはチェロとフォルテピアノのためのソナタ」として出版された。ヴァイオリンやフルートのための編曲も行われている。 オーボエ奏者のカール・キム(Carl Khym)によってさらに弦楽四重奏への編曲も行われており、1817年にジムロックから出版されている。 曲はヨゼフィーネ・フォン・ブラウン男爵夫人に献呈されている。 演奏時間 約14分半。 楽曲構成 第1楽章 Allegro moderato 4/4拍子 ヘ長調 曲はホルンが下降音型を示して開始する。これをピアノが受け継ぎ、第1主題を提示する。経過部を終えると遠隔調のホ短調で第2主題が示される。その後、演奏効果の大きなピアノのパッセージを挟み、簡潔なコデッタを置いて提示部の反復となる。展開部は第1主題、第2主題を扱っていき、やがて再現部へと至る。華やかなコーダが置かれて明るく閉じられる。 第2楽章 Poco adagio, quasi andante 2/4拍子 ヘ短調 第2楽章にあたる部分は17小節とごく短い。付点音符のリズムによる主題が奏され、アタッカでフィナーレへと接続される。 第3楽章 Rondo, allegro moderato 2/2拍子 ヘ長調 音程の離れた4音を中心とする主題がロンド主題となる。色彩豊かなホルンパートに流麗なピアノが加わる。ロンド主題はロ短調のものを含む副主題と交代しながら進み、最後はロンド主題を用いたコーダがテンポを落とした後、アレグロ・モルトとなって勢いよく全曲の幕が下ろされる。 / @WalkIntoSiena ベートーヴェン 再生リスト https://youtube.com/playlist?list=PLTtHiFCVwL1zT3TDzCFkYRGchw_08y2KG クラシック全般 再生リスト https://youtube.com/playlist?list=PLTtHiFCVwL1yxp2hTQ64gcreupYj8u6jd #ベートーヴェン #ホルンソナタヘ長調 #作品17