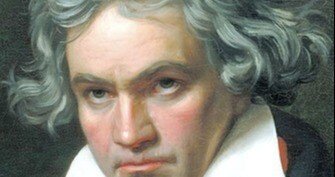#ピアノ

ベートーベン:ピアノ三重奏曲第1番 変ホ長調 Op.1-1
In this video, we'll be playing Ludwig van Beethoven's Piano Trio No. 1 in E-Flat Major, Op. 1, No. 1. This famous piece was written in 1795 and is one of Beethoven's most well-known trios. If you're a fan of classical music, then you'll love this video! We'll be playing the trio and discussing some of the key points of the piece, so that you can understand it better. Be sure to check out the other videos in this series, as they all include different works by some of the most famous classical composers! 00:00 I. Allegro 10:07 II. Adagio cantabile 17:42 III. Scherzo: Allegro assai 22:08 IV. Finale: Presto 演奏者ページ Claremont Trio (Piano Trio) 公開者情報 Boston: Isabella Stewart Gardner Museum 演奏者 Emily Bruskin, violin; Julia Bruskin, cello; Donna Kwong, piano 著作権 Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives 3.0 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 ピアノ三重奏曲第1番変ホ長調 作品1-1は、ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェンが1793年から1795年にかけて作曲したピアノ三重奏曲である。ウィーンで1795年10月で初公演され、第2番、第3番と共にカール・アロイス・フォン・リヒノフスキーに献呈された。 作曲地はボンと推定されている。 演奏時間 約28分 楽曲構成 第1楽章 アレグロ、変ホ長調、4分の4拍子、ソナタ形式。第1主題は、主和音が分散和音で上行するもの。これが少しずつ変化をつけて3回繰り返されてから、なだらかに音階が下行していく。第2主題は変ロ長調。 第2楽章 アダージョ・カンタービレ、変イ長調、4分の3拍子、ロンド形式。ロンド主題はピアノで提示される。最初の副主題は、ヴァイオリンとチェロにより変ホ長調で歌われる。第2の副主題は変イ短調で提示される。 第3楽章 スケルツォ、アレグロ・アッサイ、変ホ長調、4分の3拍子。主題は短前打音を伴ったもの。トリオは変イ長調。弦楽器の和声の上でピアノが主題を歌う。 第4楽章 フィナーレ、プレスト、変ホ長調、4分の2拍子。第1主題はピアノの跳躍音形で始まる。第2主題は変ロ長調で、主和音の分散下行と音階下行をヴァイオリンが奏する。 #ベートーヴェン,#Beethoven,#ピアノ,#ピアノ三重奏曲第1番,#Op1_1

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第14番「月光」 嬰ハ短調 Op.27-2
00:00 I. Adagio sostenuto 06:16 II. Allegretto 08:01 III. Presto agitato 演奏者ページ Jürgen Noll (Piano) 公開者情報 Jürgen Noll 著作権 Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 ピアノソナタ第14番嬰ハ短調 作品27-2 『幻想曲風ソナタ』("Sonata quasi una Fantasia")は、ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェンが1801年に作曲したピアノソナタ。『月光ソナタ』という通称とともに広く知られている。 概要 1801年、ベートーヴェンが30歳のときの作品。1802年3月のカッピによる出版が初版であり、ピアノソナタ第13番と対になって作品27として発表された。両曲ともに作曲者自身により「幻想曲風ソナタ」という題名を付されており、これによって曲に与えられた性格が明確に表されている。 『月光ソナタ』という愛称はドイツの音楽評論家、詩人であるルートヴィヒ・レルシュタープのコメントに由来する。ベートーヴェンの死後5年が経過した1832年、レルシュタープはこの曲の第1楽章がもたらす効果を指して「スイスのルツェルン湖の月光の波に揺らぐ小舟のよう」と表現した。以後10年経たぬうちに『月光ソナタ』という名称がドイツ語や英語による出版物において使用されるようになり、19世紀終盤に至るとこの名称が世界的に知られるようになる。一方、作曲者の弟子であったカール・チェルニーもレルシュタープの言及に先駆けて「夜景、遥か彼方から魂の悲しげな声が聞こえる」と述べている。このように『月光ソナタ』の愛称と共に広く知られる以前より人々の想像を掻き立て、人気を博した本作であったが、ベートーヴェン自身はそのことを快く思っていなかったとされる。なお、後述の尋常小学校の物語が引用されることがあるが、作り話である。 曲は伯爵令嬢ジュリエッタ・グイチャルディに献呈された[1]。ベートーヴェンはブルンスヴィック家を介した縁で自らのピアノの弟子となったこの14歳年少の少女に夢中になる。1801年11月16日に友人のフランツ・ベルハルト・ヴェーゲラーへ宛てた書簡には次のようにある。「このたびの変化は1人の可愛い魅力に富んだ娘のためなのです。彼女は私を愛し、私も彼女を愛している。(中略)ただ、残念なことには身分が違うのです」。その後、グイチャルディはヴェンゼル・ロベルト・フォン・ガレンベルクと結婚してベートーヴェンのもとを去っていく。この献呈は当初から意図されていたわけではなく、グイチャルディにはロンド ト長調 作品51-2が捧げられるはずであった。しかし、ロンドをヘンリエッテ・リヒノフスキー伯爵令嬢へ贈ることが決まり、代わりにグイチャルディへと献呈されたのがこのソナタであったようである。なお、ジュリエッタはアントン・シンドラーの伝記で「不滅の恋人」であるとされている。 曲の内容は『幻想曲風ソナタ』という表題が示すとおり、伝統的な古典派ソナタから離れてロマン的な表現に接近している。速度の面では緩やかな第1楽章、軽快な第2楽章、急速な第3楽章と楽章が進行するごとにテンポが速くなる序破急的な展開となっている。また、形式的にはソナタ形式のフィナーレに重心が置かれた均衡の取れた楽章配置が取られ[12]、情動の変遷が強健な意志の下に揺るぎない帰結を迎えるというベートーヴェン特有の音楽が明瞭に立ち現われている。 本作はピアノソナタ第8番『悲愴』、同第23番(熱情)と並んで3大ピアノソナタと呼ばれることもある。 演奏時間 約15-16分[1][4]。 楽曲構成 第1楽章 Adagio sostenuto 2/2拍子 嬰ハ短調 三部形式[1]。『月光の曲』として非常に有名な楽章である。冒頭に「全曲を通して可能な限り繊細に、またsordinoを使用せずに演奏すること」(Si deve suonare tutto questo pezzo delicatissimamente e senza sordino.)との指示がある(譜例1)。「sordino(弱音器)」とは「ダンパー」のことを指すとされ、冒頭の指示は現代のピアノにおいては「サステインペダルを踏み込んだ状態で」と解釈される。 第2楽章 Allegretto 3/4拍子 変ニ長調 複合三部形式。スケルツォもしくはメヌエットに相当する楽章であるが、いずれであるとも明記されていない。暗い両端楽章の間にあって効果的に両者を繋ぐ役割を果たしており、フランツ・リストはこの楽章を「2つの深淵の間の一輪の花」に例えた。レガートとスタッカートが開始される。 第3楽章 Presto agitato 4/4拍子 嬰ハ短調 ソナタ形式。ピアノソナタ第14番としては、第3楽章のみソナタ形式となっている。堅牢な構築の上に激情がほとばしり、類稀なピアノ音楽となった。急速に上昇するアルペッジョからなる第1主題は、第1楽章の3連符の動機を急速に展開させたものである。頂点のスフォルツァンドでダンパーが解放される。 「月光の曲」 ウィキソースに月光の曲の原文があります。 日本では戦前の尋常小学校の国語の教科書に、「月光の曲」と題する仮構が読み物として掲載されたことがあった。 この物語は19世紀にヨーロッパで創作され、愛好家向けの音楽新聞あるいは音楽雑誌に掲載された。日本では、1888年に積善館より出版された英語テキスト『New national readers』第5巻およびその日本語訳『ニューナショナル第五読本直訳』の12章に「BEETHOVEN'S MOONLIGHT SONATA」(第十二課 「ベトーブン」ノ月光ノ「ソナタ」)として掲載された。 その後、1892年に上梓された小柳一蔵著『海外遺芳巻ノ一』に『月夜奏琴』という表題で掲載されている。『月夜奏琴』を口語調に書き直したものが『月光の曲』である。 あらすじ ベートーヴェンが月夜の街を散歩していると、ある家の中からピアノを弾く音が聞こえた。良く見てみるとそれは盲目の少女であった。感動したベートーヴェンはその家を訪れ、溢れる感情を元に即興演奏を行った。自分の家に帰ったベートーヴェンはその演奏を思い出しながら曲を書き上げた。これが「月光の曲」である。 #beethoven,#ベートーヴェン,#ピアノ,#ピアノソナタ,#第14番「月光」,#月光,#Op.27

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第16番 ト長調 Op.31-1
00:00 I. Allegro vivace 06:29 II. Adagio grazioso 17:37 III. Rondo: Allegretto 演奏者ページ Peter Bradley-Fulgoni (piano) 公開者情報 Peter Bradley-Fulgoni 著作権 Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 備考 recorded in September 2019 at St. Paul's Hall, Huddersfield University: Peter Hill, sound engineer 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 ピアノソナタ第16番 ト長調 作品31-1は、ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェンが作曲したピアノソナタ。 概要 作品31の3曲のピアノソナタ(第16番、第17番、第18番)は1801年に作曲が開始されると、翌1802年に入ってまもなく完成に至ったものとみられている。同年4月22日には作曲者の弟であるカスパールが、楽譜出版社のブライトコプフ・ウント・ヘルテル社と本作の出版に関わるやり取りを開始したことがわかっている。しかしながら、最初の出版はハンス・ゲオルク・ネーゲリの『クラヴサン奏者演奏曲集』に第17番と対にして収められる形で行われた。この際、第1楽章に対しベートーヴェンの意図しない4小節の改変が行われており、これを正す「厳密な改訂版」が1803年にジムロック社より出された。この時点ではまだ本作は第17番と組になっていたが、最終的にカッピが1805年に作品29として出版した版から現在の作品31がひとまとめとなる。 ベートーヴェンは1802年に衰え続ける聴力を苦にハイリゲンシュタットの遺書を書いている一方、同時期にヴァイオリニストのヴェンゼル・クルンプホルツに対して「私は今までの作品に満足していない。今後は新しい道を進むつもりだ」と述べたとカール・チェルニーが伝えている。そうした失意と決意の中で作曲されたこのソナタは、古典的なたたずまいの中に明るい楽想がまとめられたものとなった[5]。 楽曲構成 第1楽章 Allegro vivace 2/4拍子 ト長調 ソナタ形式。右手と左手が16分音符1つ分ずらされた、ユニークな第1主題で始まる。 第2楽章 Adagio grazioso 9/8拍子 ハ長調 第3楽章 Rondo, Allegretto 2/2拍子 ト長調 ロンド形式であるが、ソナタ形式への近接が見られる。4つの声部が書き分けられた譜例6がロンド主題である。 #beethoven,#sonata,#ピアノ,#ソナタ第16番

ベートーヴェン:ピアノソナタ第21番 ハ長調 作品53 『ヴァルトシュタイン』
00:00 Allegro con brio 10:33 Introduzione: Adagio molto (in F major) 24:26 Rondo. Allegretto moderato — Prestissimo 演奏者ページ Paavali Jumppanen (piano) 公開者情報 Boston: Isabella Stewart Gardner Museum 著作権 Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives 3.0 [tag/del] 備考 Oct.12 2008. #beethoven,#ベートーヴェン,#waldstein,#beethovenpiano,#ludwigvanbeethoven#,classicalmusic

ベートヴェン:15の変奏曲とフーガ 変ホ長調 「エロイカ変奏曲」 Op.35
00:00 Introduction 03:07 Theme, Variations 1-14 14:18 Variation 15 18:34 Fugue 10:50 Finale 演奏者ページ Ivan Ilić (Piano) 公開者情報 Paris: Ivan Ilić 著作権 Creative Commons Attribution 3.0 [tag/del] 備考 Pianist Ivan Ilić recorded by Judith Carpentier-Dupont in Paris, July 2005 #wilhelm_kempff,#clifford_curzon,#ludwig_van beethoven,#piano,#beethoven

ベートーヴェン:チェロ・ソナタ第3番 イ長調 Op 69
00:00 1. Allegro, ma non tanto 13:06 2. Scherzo. Allegro molto 18:39 3. Adagio cantabile - Allegro vivace 演奏者ページ Laurence Lesser (cello) Russell Sherman (piano) 公開者情報 Boston: Isabella Stewart Gardner Museum 著作権 Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives 3.0 [tag/del] #ベートーヴェン,#チェロ,#ピアノ,#beethoven,#クラシック

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第5番 ハ短調 Op.10 No.1
00:00 Ⅰ. Allegro molto e con brio 05:06 Ⅱ. Adagio molto 11:56 Ⅲ. Finale (Prestissimo) 演奏者ページ Paavali Jumppanen (piano) 公開者情報 Boston: Isabella Stewart Gardner Museum 著作権 Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives 3.0 [tag/del] 備考 April 22 2007 (concert with Op.7 and the 3 sonatas of Op.10.) #ピアノ,#beethoven,#ベートーヴェン,#ストリートピアノ,#都庁ピアノ,#ラブピアノ

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第28番 イ長調 Op.101
00:00 1. Etwas lebhaft und mit der innigsten Empfindung (Allegretto ma non troppo) 03:49 2. Lebhaft, marschmasig (Vivace alla marcia) 09:12 3. Langsam und sehnsuchtsvoll (Adagio ma non troppo, con affetto) 12:19 4. Geschwind, doch nicht zu sehr und mit Entschlossenheit (Allegro) ピアノソナタ第28番 (ベートーヴェン) https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%94%E3%82%A2%E3%83%8E%E3%82%BD%E3%83%8A%E3%82%BF%E7%AC%AC28%E7%95%AA_(%E3%83%99%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%BC%E3%83%B4%E3%82%A7%E3%83%B3) Piano Sonata No. 28 (Beethoven) https://en.wikipedia.org/wiki/Piano_Sonata_No._28_(Beethoven)#Movements 演奏者 Fritz Jank (piano) 公開者情報 Recorded at Theatro Municipal de São Paulo, February 8, 196 #beethoven,#ピアノ,#ベートーヴェン,#ludwig van beethoven,#beethoven music,#classical music

ベートーベン:ピアノ協奏曲第5番 変ホ長調 作品73 「皇帝」
00:00 I. Allegro 19:35 II. Adagio un poco mosso 36:56 III. Rondo: Allegro ma non troppo ピアノ協奏曲第5番 (ベートーヴェン) https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%94%E3%82%A2%E3%83%8E%E5%8D%94%E5%A5%8F%E6%9B%B2%E7%AC%AC5%E7%95%AA_(%E3%83%99%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%BC%E3%83%B4%E3%82%A7%E3%83%B3) Piano Concerto No. 5 (Beethoven) https://en.wikipedia.org/wiki/Piano_Concerto_No._5_(Beethoven) ベートーヴェン 再生リスト https://www.youtube.com/playlist?list=PLTtHiFCVwL1zT3TDzCFkYRGchw_08y2KG ベートーヴェン ピアノ協奏曲 https://www.youtube.com/playlist?list=PLTtHiFCVwL1wBLC-eEetKFd__1S5alEa5 (P)ヴィルヘルム・バックハウス:クレメンス・クラウス指揮 ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 1953年5月録音 #ベートーヴェン,#ピアノ協奏曲,#皇帝,#クラシック,#ピアノ,#beethoven

ベートーベン:ピアノ協奏曲第3番 ハ短調, Op 37
00:00 I. Allegro con brio 15:14 II. Largo 25:23 III. Rondo – Allegro ピアノ協奏曲第3番 (ベートーヴェン) https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%94%E3%82%A2%E3%83%8E%E5%8D%94%E5%A5%8F%E6%9B%B2%E7%AC%AC3%E7%95%AA_(%E3%83%99%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%BC%E3%83%B4%E3%82%A7%E3%83%B3) Piano Concerto No. 3 (Beethoven) https://en.wikipedia.org/wiki/Piano_Concerto_No._3_(Beethoven) ベートーヴェン 再生リスト https://www.youtube.com/playlist?list=PLTtHiFCVwL1zT3TDzCFkYRGchw_08y2KG ベートーヴェン ピアノ協奏曲 https://www.youtube.com/playlist?list=PLTtHiFCVwL1wBLC-eEetKFd__1S5alEa5 (P)アルフレッド・ブレンデル ハインツ・ワルベルク指揮 ウィーン交響楽団 1961年録音 #ベートーヴェン,#beethoven,#piano concerto,#ピアノ,#クラシック

ベートーベン:ピアノ協奏曲第2番 変ロ長調 Op.19
00:00 I. Allegro con brio 13:40 II. Adagio 23:09 III. Rondo, Molto allegro ピアノ協奏曲第2番 (ベートーヴェン) https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%94%E3%82%A2%E3%83%8E%E5%8D%94%E5%A5%8F%E6%9B%B2%E7%AC%AC2%E7%95%AA_(%E3%83%99%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%BC%E3%83%B4%E3%82%A7%E3%83%B3) Piano Concerto No. 2 (Beethoven) https://en.wikipedia.org/wiki/Piano_Concerto_No._2_(Beethoven) ベートーヴェン 再生リスト https://www.youtube.com/playlist?list=PLTtHiFCVwL1zT3TDzCFkYRGchw_08y2KG (P)ルービンシュタイン クリップス指揮 シンフォニー・オブ・ジ・エア 1956年12月14日録音 #beethoven,#ベートーヴェン,#ピアノ,#classical music,#ludwig van beethoven,#beethoven music

ベートーベン:ピアノ協奏曲第1番 ハ長調 作品15
00:00 I. Allegro con brio 18:47 II. Largo 32:47 III. Rondo. Allegro scherzando ピアノ協奏曲第1番 (ベートーヴェン) https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%94%E3%82%A2%E3%83%8E%E5%8D%94%E5%A5%8F%E6%9B%B2%E7%AC%AC1%E7%95%AA_(%E3%83%99%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%BC%E3%83%B4%E3%82%A7%E3%83%B3) Piano Concerto No. 1 (Beethoven) https://en.wikipedia.org/wiki/Piano_Concerto_No._1_(Beethoven) ベートーヴェン 再生リスト https://www.youtube.com/playlist?list=PLTtHiFCVwL1zT3TDzCFkYRGchw_08y2KG (P)エミール・ギレリス:アンドレ・ヴァンデルノート指揮 パリ音楽院管弦楽団 1957年6月19日~20日録音 #ピアノ,#ピティナ,#beethoven,#ストリートピアノ,#弾いてみた,#ピアノカバー

『ピアノ・ソナタ第31番 変イ長調 Op 110』ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェン
(P)フリードリヒ・グルダ 1953年11月26日録音 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 ピアノソナタ第31番 変イ長調 作品110は、ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェンが1821年に完成したピアノソナタ。 概要 ベートーヴェンの最後のピアノソナタ3作品(第30番、第31番、第32番)は、『ミサ・ソレムニス』や『ディアベリ変奏曲』などの大作の仕事の合間を縫うように並行して進められていった[1]。途中、やがて彼の命を奪うことになる病に伏せることになるが[2]、健康を回復したベートーヴェンは旺盛な創作意欲をもってこの作品を書き上げた[3]。楽譜には1821年12月25日と書き入れられ、これが完成の日付と考えられるものの、その後1822年になってからも終楽章の手直しが行われたとされる[1]。こうして生まれた本作品には前作を超える抒情性に加え[1]、ユーモラスな洒落も盛り込まれており[3]、豊かな情感が表出されている。また、終楽章に記された数々のト書きは、しばしば作曲者を襲った病魔との関連で考察される[2][4]。 1822年2月18日付の書簡からは、このピアノソナタが続く第32番と共に、ベートーヴェンと親交の深かったアントニー・ブレンターノに献呈される予定であったことがわかる[1]。ところが、出版時には楽譜に献辞は掲げられておらず、献呈者なしとなった理由を決定づける証拠も見つかっていないため不明である。[1]。ブレンターノ夫人への献呈が検討される以前には、弟子のフェルディナント・リースへの恩義に報いるために彼に捧げられることになっていたとする説もある[1]。楽譜の出版は1822年7月、シュレジンガー、シュタイナー、ブージーなどから行われた。 作曲者はチェロソナタ第5番にみらるように、後期の作品ではフーガの応用に大きく傾いている。この曲の終楽章は、最後の3曲のピアノソナタの中では最も典型的にフーガを用いたものである。ドナルド・フランシス・トーヴィーは「ベートーヴェンの描くあらゆる幻想と同じく、このフーガは世界を飲み込み、超越するものである」と述べた[3]。 演奏時間 約18分[5]。 楽曲構成 第1楽章 Moderato cantabile molto espressivo 3/4拍子 変イ長調 ソナタ形式[6]。con amabilità(愛をもって)と付記されている。序奏はなく、冒頭から譜例1の第1主題が優しく奏でられる。 ベートーヴェンは譜例2に示される第1主題の後半楽節を好んでおり、自作に度々用いていた。ヴァイオリンソナタ第8番の第2楽章(譜例3)やその他の楽曲にも同じ旋律を見出すことが出来る[5]。また、この旋律がハイドンの交響曲第88番の第2楽章からの借用であるとする意見もある[2]。 第1主題に続いて特徴的なアルペッジョの走句が入り、変ホ長調の第2主題の提示へと移る(譜例4)。 ピアノソナタ第23番と同様提示部の反復は設けられておらず、そのまま展開部へと移行する。展開部はテノールとバスの音域を行き来する左手の音型の上で、転調を繰り返しながら譜例1冒頭2小節の動機要素が8回奏される。続く再現部では第1主題が細かな伴奏音型の上に姿を現し、第2主題は変イ長調となって戻ってくる[5]。コーダでは経過部のアルペッジョが奏でられ、譜例1の断片を回想しつつ弱音で楽章を終える[5]。 第2楽章 Allegro molto 2/4拍子 ヘ短調 三部形式[5]。スケルツォ的な性格を持ち[3]、軽やかな中にも全体的に不気味な雰囲気を漂わせる。第1の部分に使用されている旋律は当時の流行歌から採られている。譜例5は『Unsre Katz hat Katzerln gehabt』(うちの猫には子猫がいた)、続く譜例6は『Ich bin lüderlich, du bist lüderlich』(私は自堕落、君も自堕落)というコミカルなタイトルの楽曲に由来する[3][4][7]。 譜例5と譜例6がそれぞれ反復記号によって繰り返され、曲は中間部へと進む。中間部は下降する音型と上昇するシンコペーションの音型が交差する、譜例7に示される楽想が5回奏されるだけの簡素なものである[3][5]。 中間部が終わると第1部をほぼそのまま再現し、コーダで音量とテンポを落として切れ目なく終楽章へ続く[2][8]。 第3楽章 Adagio, ma non troppo - Fuga. Allegro, ma non troppo 6/8拍子 変イ長調 極めて斬新な構成と内容を備えた終楽章は、規模の大きな変ロ短調の序奏に始まる[5](譜例8)。この部分のベートーヴェンの手稿譜には例外的に数多くの修正の跡が残されており、作曲者が推敲を重ねて書き上げたことが窺われる[4]。レチタティーヴォと明記された楽想は頻繁にテンポを変更しながら進む[9]。この中でタイで繋がれた連続するイ音に作曲者自身が運指を指定している部分は、クラヴィコードで実現可能な演奏効果を想定して書かれたものである[5][9]。 続いて変イ短調の『嘆きの歌』(Klagender Gesang)が切々と歌い始められる(譜例9)。『嘆きの歌』の下降する哀切な旋律線は、バッハの『ヨハネ受難曲』の「Es ist vollbracht」との関連を指摘されている[4][10][11]。 次に変イ長調で3声のフーガが開始される[12]。フーガの主題は第1楽章第1主題に基づくもので[4][13]、この上昇する音列が全曲を統一する役割を果たしている[3]。フーガは自由に展開されてクライマックスを形成する。 盛り上がったところで再び『嘆きの歌』が現れる。「疲れ果て、嘆きつつ」(Ermattet, klagend)と記載されており[9][12]、ト短調で休符によって寸断された途切れ途切れの旋律が歌われる(譜例11)。 クレッシェンドを経て、再度3声のフーガとなる。ベートーヴェンはこのフーガ冒頭にイタリア語で「次第に元気を取り戻しながら」(Poi a poi di nuovo vivente)と記した[9][14]。譜例12の主題は譜例10のフーガ主題の反行によっており[13]、ト長調で開始される。 次第に譜例10の縮小形、拡大系が姿を現すようになり、さらにメノ・アレグロで4分の1の縮小形を出しつつト長調から主調である変イ長調に移行する。同時に、譜例10の主題が堂々とバスに回帰する。その後、対位法を離れて一層大きく歓喜を表しながら、最後に向かって徐々に速度と力を上げていき高らかに全曲を完結させる。 出典 1^ a b c d e f 大木 1980, p. 401. 2^ a b c d Cummings, Robert. ピアノソナタ第31番 - オールミュージック. 2015年2月7日閲覧。 3^ a b c d e f g “Beethoven: The Last Three Piano Sonatas”. Hyperion Records. 2015年2月7日閲覧。 4^ a b c d e “Andras Schiff lecture recital: Beethoven's Piano Sonata Op 110 no 31”. The Guardian. 2015年2月7日閲覧。 5^ a b c d e f g h 大木 1980, p. 402. 6^ 大木, p. 402. 7^ Mauser 2008, p. 148. 8^ von Bülow, Hans. “Score, Beethoven: Piano Sonata No.31 (PDF)”. J. G. Cotta. 2015年2月7日閲覧。 9^ a b c d “Beethoven, Piano Sonata No.31 (PDF)”. Breitkopf & Härtel (1862年). 2015年2月7日閲覧。 10^ Mauser 2008, p. 114. 11^ Kaiser 1979, p. 583. 12^ a b 大木 1980, p. 403. 13^ a b 石桁真礼生『新版 楽式論』、音楽之友社、1966年、P.295-296 14^ 大木 1980, p. 404.

『ピアノソナタ 第26番 変ホ長調 作品81a 『告別』』 ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェン
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 ピアノソナタ第26番 変ホ長調 作品81a 『告別』は、ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェンが1809年から1810年にかけて作曲したピアノソナタ。 概要 本作にはベートーヴェン自身が標題を与えているが、そのようなピアノソナタはこの『告別』と『悲愴』としかない。その背景には彼のパトロン、弟子であり友人でもあったルドルフ大公のウィーン脱出が関係している[1]。 オーストリアは1809年4月9日にナポレオン率いるフランス軍と戦闘状態に陥った。ナポレオンの軍勢は5月12日までにウィーンへと侵攻しており、神聖ローマ帝国皇帝フランツ2世の弟にあたり皇族の身分であったルドルフ大公は5月4日に同市を離れることになる。ベートーヴェンはピアノソナタの第1楽章の草稿に「Das Lebewohl(告別)」と記すとともに「1809年5月4日、ウィーンにて、敬愛するルドルフ大公殿下の出発に際して。」と書き入れた[1]。オーストリアの降伏により同年10月14日に終戦、フランス軍が撤退した後の1810年1月30日にルドルフ大公はウィーンへと戻った。第2楽章の「Die Abwesenheit(不在)」はこの期間のことを示しており、さらに第3楽章には「Das Wiedersehen(再会)」、「敬愛するルドルフ大公殿下帰還、1810年1月30日」と書き込まれている[2]。 この曲を出版したブライトコプフ・ウント・ヘルテル社は各楽章の表題をフランス語に置き換えて"les adieux"、"l'absence"、"le retour"と表記した[2]。親交の深かったルドルフ大公のために作曲されたこのピアノソナタの標題にはベートーヴェン自身もこだわりがあったらしく、「Das Lebewohlはles adieuxとは全く違うものである。前者は心から愛する人にだけ使う言葉であり、後者は集まった聴衆全体に対して述べる言葉だからである。」と手紙で抗議している。ただし、作曲者自身もスケッチ段階では第1楽章の「Das Lebewohl」を取り消して「Der Abschied(別れ)」、第3楽章は「Die Ankunft(到着)」としていたことが分かっている[2]。 出版社へと持ち込まれたのは第24番、第25番のソナタと同じ1810年2月10日であったが、このソナタのみ翌年に作曲者自身による修正を施され[3]、1811年7月に出版された[2]。ルドルフ大公へ献呈[4]。81aとなっている作品番号は、ジムロック社がブライトコプフ社に先駆けて六重奏曲を刊行していたため、ブライトコプフ社が自社の作品番号を混乱させないようピアノソナタを81a、六重奏曲を81bとしたことに由来している[2]。 演奏時間 約16分半[5]。 曲の構成 第1楽章 "Das Lebewohl" Adagio 2/4拍子 - Allegro 2/2拍子 変ホ長調 ソナタ形式[2]。『告別』の副題がつけられている。譜例1に示すとおり序奏の最初の3つの音符には"Lebewohl"と歌詞が与えられており[4]、楽章全体にこのモチーフが配されている[2]。 序奏に続くアレグロの第1主題にはLebewohlの動機が組み込まれており、テヌートで強調されている[6](譜例2)。一方、左手のバスの動きはLebewohl動機の反行形となっている[7]。 Lebewohl動機の反行形に始まる経過部を経ると変ロ長調の第2主題が提示されるが、これも拡大されたLebewohl動機に基づくものである[6](譜例3)。さらに下降する結尾句も同じ動機から構成される[6]。 提示部の繰り返しを終えると展開部となる。小規模な展開部では譜例2の下降する音型が扱われ[6]、これが8分音符2つの単位まで細かく分解されていく[7]。分解された音型からクレッシェンドして再現部となり、譜例2と譜例3が変ホ長調で現れる。コーダではまず譜例2が取り上げられて展開されるが[6]、続いてLebewohl動機と8分音符の走句が組み合わされていく。最後は大公の出立を見送るような情緒を見せつつ楽章を閉じる[7]。なお、ベートーヴェンは楽章の最後から4小節目の2分音符のハ音において、音を持続したままクレッシェンドするという特殊な指示をしている[4][注 1]。 第2楽章 "Die Abwesenheit" Andante espressivo 2/4拍子 ハ短調 2つの主題が繰り返される序奏的性格を持つ楽章[8]。『不在』の副題がつけられており、ドイツ語で「ゆるやかに、表情を込めて」(In gehender Bewegung, doch mit Ausdruck.)と指示されている[4][8]。ハ短調で奏でられる譜例4の第1主題の音型は譜例1の動きと関係している[8]。開始のハ短調に落ち着かず、不安げな様子が表現される[7]。 レチタティーヴォのような経過を経てト長調の第2主題へと移る(譜例5)。 間もなく変ロ短調で第1主題が回帰し、続いてヘ長調で第2主題が再現された後、譜例4の音型を静かに奏でながら終楽章に接続される。 第3楽章 "Das Wiedersehen" Vivacissimamente 変ホ長調 6/8拍子 ソナタ形式[8]。『再会』の副題とともに、ドイツ語による「非常に生き生きとした速度で」(Im lebhaftesten Zeitmaasse)という指示がある[4][8]。和音の一打に続き華麗なアルペッジョの序奏が現れる。第1主題はまず譜例6のように出されるが、主旋律が左手に移されると高音部は装飾的な彩りを添える。 きらびやかな経過部を終えると変ロ長調の第2主題が提示される(譜例7)。第2主題が繰り返される際に現れるフレーズには、同時期に作曲された『皇帝協奏曲』の第3楽章のものと極めて類似したパッセージが用いられている[7]。 勢いのあるコデッタにより結ばれ、提示部の反復に入る。展開部はごく短く、専ら第2主題が扱われる[8]。たちまち細かい分散和音の伴奏に乗ってオクターヴで第1主題が再現され、常法通り第2主題へと進む。コーダではポーコ・アンダンテとなって譜例6を穏やかに回想し、形を変えて繰り返す。最後は元のテンポに戻り、喜ばしく閉じられる。 脚注 注釈 1^ このクレッシェンドは鍵盤楽器では表現不能である。 2^ 譜例中では最後のイ音にかかるタイが省略されている。 出典 3^ a b 大木 1980, p. 384. 4^ a b c d e f g 大木 1980, p. 385. 5^ “Booklet, BEETHOVEN, L. van: Piano Sonatas, Vol. 9 (Biret)”. NAXOS. 2015年4月19日閲覧。 ^6 a b c d e “Beethoven Piano Sonata No.26 (PDF)”. Breitkopf & Härtel. 2015年4月16日閲覧。 7^ ピアノソナタ第26番 - オールミュージック. 2015年4月12日閲覧。 8^ a b c d e 大木 1980, p. 386. 9^ a b c d e “Andras Schiff lecture recital: Beethoven's Piano Sonata Op 81a”. The Guardian. 2015年4月12日閲覧。 10^ a b c d e f 大木 1980, p. 387.