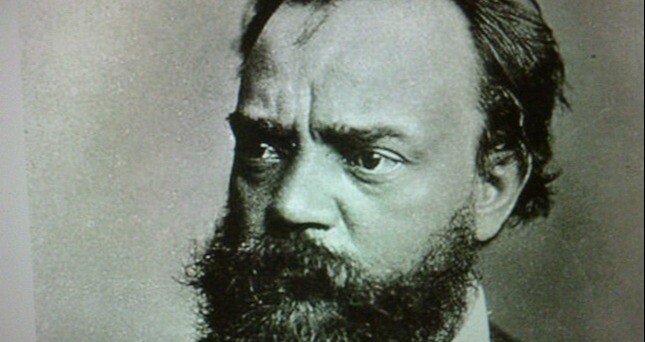#作品95

ドヴォルザーク:交響曲第9番 ホ短調 作品95, B.178
00:00 I. Adagio - Allegro molto 11:06 II. Largo 25:25 III. Molto vivace 32:00 IV. Allegro con fuoco 演奏者 New York Philharmonic (orchestra) Leonard Bernstein (conductor) 公開者情報 New York: Columbia, 1962. MS 6393. 著作権 Public Domain - Non-PD US 備考 Source: Internet Archive ドヴォルザークの交響曲第9番 ホ短調 作品95, B.178は、『新世界より』(From the New World)という愛称で広く知られています。この作品は、チェコの作曲家アントニン・ドヴォルザークによって1893年に作曲されました。ドヴォルザークはこの時、アメリカ合衆国に滞在しており、その経験がこの交響曲に大きな影響を与えています。 ### 楽曲の構成 交響曲第9番は、伝統的な四楽章の構成を持っています: 1. **第1楽章:Adagio - Allegro molto** - 穏やかで神秘的な導入部から始まり、その後エネルギッシュでリズミカルな主部へと移行します。この楽章は、新大陸の広大な自然とアメリカ先住民の音楽の要素を反映しています。 2. **第2楽章:Largo** - この楽章は非常に有名で、穏やかで歌心に富んだメロディが特徴です。特に、コーラングレによる独奏部分は有名で、アメリカの精神的な風景を描写していると言われています。 3. **第3楽章:Scherzo: Molto vivace** - 軽快でダンスのようなこの楽章は、再びアメリカ先住民のリズムとメロディーを思わせる要素が含まれています。活発でリズミカルな部分と、より抒情的なトリオ部分が交互に現れます。 4. **第4楽章:Allegro con fuoco** - 劇的で力強い楽章で、全曲のクライマックスとなります。旋律はアメリカの民謡「スウィング・ロー、スウィート・チャリオット」を思わせる部分があり、交響曲は壮大なフィナーレへと導かれます。 ### 影響と重要性 『新世界より』は、ヨーロッパの伝統に根ざしながらも、アメリカの音楽的素材と風景を取り入れたことで、文化的な架け橋となりました。ドヴォルザークは、アメリカの民俗音楽、特にアフリカ系アメリカ人や先住民の音楽に影響を受けており、それがこの交響曲に色濃く反映されています。 この作品は、クラシック音楽のレパートリーの中でも特に人気があり、世界中で頻繁に演奏されています。その普遍的な魅力と、異文化間の交流を象徴する作品として、多くの人々に愛され続けています。 ドヴォルザークの交響曲第9番『新世界より』に関する補足説明: ### コンテキストと影響 - **アメリカ滞在の背景**:ドヴォルザークは、1892年から1895年までの間、ニューヨークの国立音楽院(現在のジュリアード音楽院の前身)の院長を務めていました。彼のアメリカ滞在は、彼の作曲スタイルに新しい視点をもたらし、特にこの交響曲においては、アメリカの風景や文化が強く反映されています。 - **民族音楽の影響**:ドヴォルザークは、アメリカの民族音楽に深い関心を抱いていました。彼はアフリカ系アメリカ人のスピリチュアルや先住民の音楽を研究し、それらの要素を彼の音楽に取り入れました。これは、彼のチェコの民俗音楽に対する取り組みと並行しています。 - **普遍性**:『新世界より』は、特定の民族音楽を模倣するのではなく、それらの精神を取り入れ、独自の芸術的言語に融合させたことで、普遍的な響きを持つ作品となりました。 ### 音楽的特徴 - **構造とテーマ**:各楽章は独立していますが、全体としては統一感があります。特に、第1楽章と第4楽章は、主題とリズムにおいて強い関連性を持っています。 - **楽器使用**:ドヴォルザークは、この交響曲で英国式ホルンやクラリネットなど、特定の楽器の色彩を効果的に使用しています。これにより、独特の音色と雰囲気を作り出しています。 - **民謡の影響**:ドヴォルザークは、アメリカの民謡やスピリチュアルを直接引用しているわけではありませんが、それらのスタイルを模倣してオリジナルの旋律を作り出しています。 ### 歴史的・文化的重要性 - **受容と影響**:この交響曲は、初演から大成功を収め、アメリカだけでなくヨーロッパでも高く評価されました。19世紀末から20世紀初頭にかけての音楽界において、異文化間の融合という新しい潮流を象徴する作品となりました。 - **現代への影響**:『新世界より』は、映画やテレビ、広告など、現代の多くのメディアで引用されています。特に第2楽章のメロディは、広く知られている音楽の一つとなっています。 このように、ドヴォルザークの交響曲第9番は、音楽的な傑作であるだけでなく、文化的、歴史的な文脈においても重要な作品です。 ### 背景と作曲の動機 - **アメリカの文化的アイデンティティ**:ドヴォルザークは、アメリカの音楽がヨーロッパの伝統に依存するだけでなく、独自のアイデンティティを持つべきだと考えていました。彼はアメリカ音楽が、アフリカ系アメリカ人のスピリチュアルや先住民の音楽から多くを学ぶことができると信じていました。 - **音楽教育への影響**:ドヴォルザークのアメリカでの滞在と活動は、当時のアメリカの音楽教育と作曲のアプローチに影響を与えました。彼は、アメリカ固有の音楽スタイルを確立するために、アメリカの作曲家たちに民族音楽の探求を奨励しました。 ### 音楽的要素と創造性 - **ハーモニーとリズム**:『新世界より』は、特にハーモニーとリズムの面で革新的です。ドヴォルザークは、伝統的なハーモニック構造を用いつつも、アメリカの民族音楽の特徴を取り入れ、独特のリズミックなパターンを作り出しました。 - **旋律の発展**:ドヴォルザークは、単純な旋律を取り入れながらも、それを複雑で豊かなオーケストレーションで発展させる手法を用いています。これにより、聴き手に深い感動を与える楽曲が生まれました。 ### 影響と評価 - **評価の変遷**:初演当時から高い評価を受けていたものの、20世紀に入ると一時的に「過小評価」される時期もありました。しかし、その後再評価が進み、現代ではクラシック音楽のレパートリーの中で最も重要な作品の一つと見なされています。 - **文化的象徴**:『新世界より』は、音楽を通じた文化的な理解と交流の象徴としても重要です。異なる文化的背景を持つ音楽的要素の融合は、異文化間の対話の可能性を示唆しています。 ### 現代文化における影響 - **映画やテレビでの使用**:この交響曲の特に第2楽章は、その感動的なメロディのために、多くの映画やテレビ番組で使用されています。これにより、一般の聴衆にも広く親しまれています。 - **教育への応用**:音楽教育の分野でも、この交響曲はしばしば教材として用いられます。特に、オーケストレーションの教材としての価値が高く評価されています。 『新世界より』は、その時代を超えた普遍的な魅力と、音楽が異なる文化を繋ぐ架け橋となり得るという強力なメッセージを持つ作品です。 Walk Into Siena チャンネル登録 https://www.youtube.com/channel/UCqAFiZznfr5Y7wgfV_sOiGQ Walk Into Siena コミュニティ https://www.youtube.com/@WalkIntoSiena/community ドヴォルザーク 再生リスト https://youtube.com/playlist?list=PLTtHiFCVwL1x2DxWUVTICb1L-FZxOGuUu クラシック全般 再生リスト https://youtube.com/playlist?list=PLTtHiFCVwL1yxp2hTQ64gcreupYj8u6jd #ドヴォルザーク #交響曲第9番 #ホ短調 #作品95 #B178

ドヴォルザーク:交響曲第9番 ホ短調 作品95, B.178
アントニン・ドヴォルザークの交響曲第9番は、ホ短調であり、作品番号は95、作品表記はB. 178です。この曲は1893年に完成し、ニューヨークで初演されました。 この交響曲は、ドヴォルザークがアメリカを訪れた際に刺激を受けて作曲されました。ドヴォルザークはアメリカの黒人民族音楽や先住民のメロディを取り入れ、その影響を強く受けた作品となっています。そのため、「アメリカ交響曲」とも呼ばれることがあります。 交響曲第9番は、全4楽章から成り立っており、約40分ほどの演奏時間があります。曲の特徴は、アメリカ民謡の要素や、舞曲風のリズム、力強い旋律などです。また、緩やかな第2楽章や活気に満ちた第4楽章など、様々な雰囲気が楽しめる作品です。 この交響曲は、ドヴォルザークの代表作の一つとして知られており、非常に人気のある作品です。その旋律の美しさや情感豊かな表現が、多くの人々に愛されています。 The Symphony No. 9 in E minor, "From the New World", Op. 95, B. 178 (Czech: Symfonie č. 9 e moll "Z nového světa"), popularly known as the New World Symphony, was composed by Antonín Dvořák in 1893 while he was the director of the National Conservatory of Music of America from 1892 to 1895. It premiered in New York City on 16 December 1893. It is one of the most popular of all symphonies. In older literature and recordings, this symphony was – as for its first publication – numbered as Symphony No. 5. Astronaut Neil Armstrong took a tape recording of the New World Symphony along during the Apollo 11 mission, the first Moon landing, in 1969. The symphony was completed in the building that now houses the Bily Clocks Museum in Spillville, Iowa. 00:00 I. Adagio - Allegro molto 11:58 II. Largo 22:08 III. Molto vivace 30:20 IV. Allegro con fuoco 演奏者 DuPage Symphony Orchestra (orchestra) Barbara Schubert (conductor) 公開者情報 DuPage, IL: DuPage Symphony Orchestra 著作権 Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 備考 Performed 12 February 2012. From archive.org 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 交響曲第9番 ホ短調 作品95, B. 178 は、アントニン・ドヴォルザークが1893年に作曲した交響曲であり、ドヴォルザークが作曲した最後の交響曲である。一般に『新世界より』(または『新世界から』、英語: From the New World、ドイツ語: Aus der neuen Welt、チェコ語: Z nového světa)の愛称で親しまれており、かつては出版順により『交響曲第5番』と呼ばれていた。 概要 ドヴォルザークは1892年に、ニューヨークにあるナショナル・コンサーヴァトリー・オブ・ミュージック・オブ・アメリカ(ナショナル音楽院)の院長に招かれ、1895年4月までその職にあった。この3年間の在米中に、彼の後期の重要な作品が少なからず書かれており、「作品95」から「作品106」までがそれである。 この作品は『弦楽四重奏曲第12番 ヘ長調《アメリカ》』(作品96, B. 179)、『チェロ協奏曲 ロ短調』(作品104, B. 191)と並んで、ドヴォルザークのアメリカ時代を代表する作品である。ドヴォルザークのほかの作品と比べても際立って親しみやすさにあふれるこの作品は、旋律が歌に編曲されたり、BGMとしてよく用いられたりと、クラシック音楽有数の人気曲となっている。オーケストラの演奏会で最も頻繁に演奏されるレパートリーのひとつでもあり、日本においてはベートーヴェンの『交響曲第5番 ハ短調《運命》』、シューベルトの『交響曲第7番(旧第8番)ロ短調《未完成》』と並んで「3大交響曲」と呼ばれることもある。 愛称の由来 『新世界より』という副題は、「新世界」のアメリカから故郷ボヘミアへ向けてのメッセージ、といった意味がある。全般的にはボヘミアの音楽の語法により、これをヨハネス・ブラームスの作品の研究や『第7番 ニ短調』(作品70, B. 141)、『第8番 ト長調』(作品88, B. 163)の作曲によって培われた西欧式の古典的交響曲のスタイルに昇華させている。 作曲の経緯と初演 上述のようにこの曲は、ドヴォルザークのアメリカ滞在中(1892年~1895年)に作曲された。アメリカの黒人の音楽が故郷ボヘミアの音楽に似ていることに刺激を受け、「新世界から」故郷ボヘミアへ向けて作られた作品だと言われている。こうしたことから「アメリカの黒人やインディアンの民族音楽の旋律を多く主題に借りている」と解説されることがしばしばあり、後述するように既存のアメリカ民族音楽とこの曲の主題との間に類似性がみられるという指摘もある。しかし、ドヴォルザークは友人の指揮者オスカル・ネドバル宛ての書簡に「私がインディアンやアメリカの主題を使ったというのはナンセンスです。嘘です。私はただ、これらの国民的なアメリカの旋律の精神をもって書こうとしたのです」と記しており、既存の素材からの直接的な引用については明確に否定している。 初演は1893年12月16日、ニューヨークのカーネギー・ホールにて、アントン・ザイドル指揮、ニューヨーク・フィルハーモニック協会管弦楽団による。初演は大成功だったと伝えられている。 曲の構成 全4楽章、演奏時間は第1楽章提示部の繰り返しを含めて約45分(ただし、第2楽章のテンポ設定によっては、この繰り返しせずに45分を超える場合があり、実際にそのような録音も存在する)。アメリカの音楽の精神を取り入れながらも、構成はあくまでも古典的な交響曲の形式に則っており、第1楽章で提示される第1主題が他の全楽章でも使用され、全体の統一を図っていることが特筆される。 第1楽章 アダージョ - アレグロ・モルト ホ短調、8分の4拍子 - 4分の2拍子、序奏付きソナタ形式(提示部の反復指定あり)。 演奏時間は10~13分程度(提示部の繰り返しを省くと8~10分程度)。 第2楽章 ラルゴ 変ニ長調、4分の4拍子、複合三部形式。 演奏時間は10~13分程度であるが、レナード・バーンスタイン指揮イスラエル・フィルハーモニー管弦楽団の演奏のように18分を超えるものもある。 第3楽章 モルト・ヴィヴァーチェ ホ短調、4分の3拍子、複合三部形式(A-B-A-C-A-B-A-コーダの形で、2つのトリオを持つ)。 演奏時間は7~9分程度。 第4楽章 アレグロ・コン・フォーコ ホ短調、4分の4拍子、序奏付きソナタ形式。 演奏時間は10~12分程度。 Walk Into Siena チャンネル登録 https://www.youtube.com/channel/UCqAFiZznfr5Y7wgfV_sOiGQ Walk Into Siena コミュニティ https://www.youtube.com/@WalkIntoSiena/community ドヴォルザーク 再生リスト https://youtube.com/playlist?list=PLTtHiFCVwL1x2DxWUVTICb1L-FZxOGuUu クラシック全般 再生リスト https://youtube.com/playlist?list=PLTtHiFCVwL1yxp2hTQ64gcreupYj8u6jd #ドヴォルザーク #交響曲第9番ホ短調 #作品95 #B178