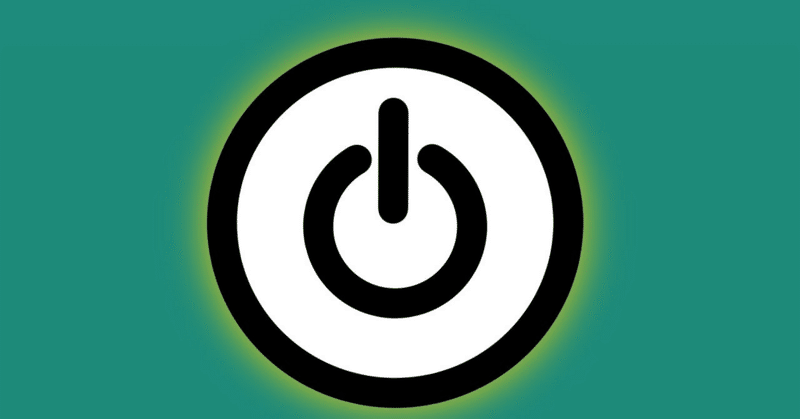
短編小説『スイッチ』
❶
ぼくは死んだ。死因はスイッチを押したこと。そのスイッチは別に爆発するものでも、ミサイルを発射させるものでもない。被害はぼく一人。それも、少しのことだ。ぼくは少ししたらよみがえる。どれくらいにしようかな、数時間じゃつまらない。見つけてもらえなかったら人知れず死んでよみがったことになるし。だからとりあえず、大事にならないように1日と少しかな。
ぼくはなるべく大きな音を立てて死ねるように準備をしていた。きっとスイッチを押した後、机の上に突っ伏すように死ぬだろうと思ったから、僕の頭が机に当たった瞬間に机の上に置いていたお皿が割れるようにしていたのだ。その目論見は成功。ぼくは消えゆく意識の中、皿が割れる音を確かに聞いた。
でも、人は来なかった。しまった今日は平日だから、兄は学校、お父さんは仕事に行っている。お母さんはもしかしたら買い物に行っているのかもしれない。
ぼくは情けなくよだれをたらして醜い顔をさらしている自分から顔をそらして、一度部屋を出た。
ドアノブが掴めない。あ、そうかぼくはもう死んでいるんだった。
階下に降りるとお母さんは料理中だった。お母さんは昔から料理中は集中しているから聞こえていなかったのかもしれない。もう一度仕掛けを作動させようと部屋に戻る。ぼくだってバカじゃない。一度で成功するとは思っていない。もう一度皿をセットして……ってしまった。つかめないんだった。
困った。死んでいるのに気づかれるまではとても暇だ。体はふわふわと浮いてはいるけど、家から歩いて数十秒くらいのところからは出られない。もう十年以上も生きている家の中をいくら見ても面白いものはないし、料理しているお母さんの前にばぁと出てみても表情一つ変えないから面白くない。それどころか、真剣な顔のお母さんはぼくを怒るときに似ていて怖かった。
不幸中の幸いだったのは、僕が死んだのがお昼近くだったことだ。お昼になったら呼びにきてくれるだろう。それで、気づいてくれるはずだ。
時計が進むのと、料理が食卓に並ぶのを交互に見てその時間を待つ。
ついにそのときは来た。
「ゆうたー、ご飯よー!」
お母さんはぼくの名前を呼ぶ。返事どころか物音一つしない。当たり前だ。なんてったってぼくは死んでいるんだから。
「あの子、まだ寝てるのかしら」そう言って、トレイに料理を載せるお母さん。ぼくのところまでもってきてくれるのだろうかと思ったが、お母さんはトレイ全体にラップをかけただけだった。一つ一つにかけるより手早いからとよくお母さんがするやつだった。
お母さんはぼくが死んだことに気がつかないまま、ご飯を食べ終わり、ドラマを観終わり、皿洗いを終え、昼寝までし始めた。なんて人だ! 息子が死んでいるというのに! ぼくはお母さんにぴったり重なる遊びを何回かして暇をつぶした。あんなに大きく見えたお母さんの体はすっかりぼくの方が大きくなっていて驚いた。腰を折り曲げてなんとかぴったり、ではない尻は飛び出してしまったものの、それ以外はおおむねぴったりに重なったときだ。
「うーん」とお母さんはうなった。ぼくが重なっていることに気がついたのだろうか。さすが、お母さんと思ったのも束の間、
「隆生さん、健太……」
夢でも見ているのだろう。お父さんとお兄ちゃんの名前をあげた。なんでぼくの名前だけないのだろう。
考えていると悲しくなってきた。お母さんと体を重ねていても、全くお母さんの気持ちがわからない。泣こうにも、幽体は泣けない。代わりに水道水がドバッと出た。
その音でお母さんは起き、急いで蛇口を閉めた。
どうやらぼくは触れることはできないけれど、自分の感情がたかぶると、周りのものを少し動かすことができるらしい、ということが何度か実験してみてわかった。といってもほんの少しだけ。水道でいうと、皿にあたって跳ねた水がシンクの外には出ていかない程度の、ほんの些細なものだ。
これをしすぎると、心が疲れる。体はまったくといっていいほど疲れないのに、不思議だなと思っていると、
「故障かしら?」と何度も蛇口を強くしめるお母さん。なんだか面白くて、もう一度やってみるけど、面白かったのがよくないのか、ヤカンのフタが転んだ程度だった。
「もーなんなのよ」と床にころがったヤカンのフタを拾い、またつけたお母さんは、そのタイミングでぼくのことに気がついたのか、ようやく料理を部屋に持ってきてくれた。
「まったく、汚いわね。ほら、ゆうた、ご飯よ。……もう! 寝るならちゃんとベッドで寝なさいよ、全く。うわ、皿も割れてるじゃない! また暴れたの!? なんとかいいなさい!」お母さんがぼくの体を揺する。そうしてようやく、ぼくの目が見開かれ、だらしなくよだれを垂らしているのを発見し、死んでいることに気がついた。
「救急車!」と慌てて階下に降りて行くお母さん。ぼくはそろそろ頃合いかと、スイッチに手を伸ばす。これをもう一度押せばぼくはよみがえることができるのだ。そうしてさらにお母さんを驚かせてやる。
……あれ? 押せない。……あっ、そうか!
ぼくは今幽体だから押すことができないんだ!
ぼくが絶望しているなか、遠くからサイレンの音が聞こえた。
❷
「あぁ、やっぱりいいねぇ、人間の絶望する声っていうのは」
ぼくの体が救急車の中に運ばれていく。さすがというべきか、ぼくの情けない顔は救急隊員が来る前に綺麗に拭いてくれ、口も目も閉じてくれたおかげで痴態をさらさずにすんだ。けっこう可愛い女性隊員だったから余計たすかった。
「焦る声もいい。ゾクゾクするねぇ」
「さっきからうるさいな」
「あーこれは、これはすみません。いやぁ、はやくあなたの魂を食べたくてうずうずしているんですよ」
そうごまをするみたいな仕草をする男。目深にフードを被り、全身をコートにつつむ。いつだって切先を光らせている大鎌を背中に持つ彼は死神だ。
「た、魂を! ち、ちょっと待ってくださいよ! ぼくはこの後ちゃんと生き返りますから」
「えぇ、えぇ、ご安心ください。あなたはまだ死んでいません。まだお医者様が死亡宣告をしていませんからね」
そこは人間のルールを遵守するのか、と感心している場合じゃない。ちゃんと生き返ると死神に息巻いたのはいいものの、その方法が全く見つからない。
「ち、ちなみにもし魂をとられるとして、あとどれくらい時間は残っているんですか?」
「体が焼けるまで、ですね。あなたが火葬されるかどうかは知らないですけど、だいたいそんな感じです。ポチッと焼却炉のボタンを押された瞬間にひょいっといただきますよ」
まるで工場見学にきた子どもに説明をするみたいに愉快そうにいう死神と対照的にぼくは焦りを隠せない。
「あぁ、あぁ、いいですねぇ。焦る音」
「うるさい」
ぼくは病院先で死亡が確認され、棺に入った状態で家に返された。お父さんとお兄ちゃんが学校や仕事を早退けしてくれ、家族が全員揃う。
「ほんと、生意気なやつだよ。今日は彼女とデートだったのに」お兄ちゃんはぼくの顔を見るなり、憎たらしそうな顔でそう言った
「そういうことを言わないの」とお母さんは言ったけど、止めようとはしない。お父さんには一言も発さない。それは悲しんでいるからではなさそうだ。ずっとノートパソコンで持ち帰ってきた仕事をしている。それを一瞥するお母さんも泣いていなかった。むしろほっとしたような顔をしているのは気のせいだろうか。
お兄ちゃんが居間の電話の横にある親戚のリスト中に電話をかけてくれた。
「せっかく、久々に家族全員集まったんだから、ぱーっと外食でもいかね?」
「馬鹿を言うな。こんなときに」お父さんがノートパソコンを閉じて一息つくと、
「明日のゆうたの葬儀にいくらかかると思ってるんだ」とメガネの位置を直した。
「あっそれもそっか。まったくゆうたのやつは最後まで迷惑ばっかかけやがって。……ま、母さんの料理は外食より美味しいからいいけどね。これもらってい?」
お兄ちゃんはそう言ってぼくが食べるはずだったお昼ご飯をたいらげる。うまいうまいと言って全部平らげるのをお母さんは愛おしそうな目で眺め、薄くではあったけどお父さんも笑っていた。まるでぼくなんていなくてもいいみたいな、理想の家族像にぼくはいらなかったみたいで、悲しい気持ちになる。
でも、蛇口から出る水がお母さんが気づかないほどちょろちょろだったのは、そうだということをうっすら気づいていたからだ。
昔から迷惑ばかりかけてきた。小さい頃は体が弱くて、病院にばかり通っていた。ぼくにお母さんはかかりきりになって、それが悔しかったお兄ちゃんは必死の努力で、文武両道、品行方正、成績優秀な人間になった。お父さんはそれがうれしいらしく、いろんなところにお兄ちゃんを連れて行ってあげていて、ぼくはそれがうらやましかった。
ぼくの病気が治ってからはお母さんの関心は、そんなお兄ちゃんばかりに向いた。いろいろなことを出遅れたぼくはいじめられ、引きこもるようになった。それからはまるで存在していないみたいに扱われているように感じることが増えた。
だからぼくはあるとき急にやってきた死神の誘いに乗った。
「自分が死んだ後の周囲の様子をみてみたくないですか? なぁに、一度死にますがすぐによみがえられますよ」そう言って死神が出してきたスイッチは、押すだけで、簡単に死と生を切り替えられるという代物だった。
ぼくが死んだ後、ぼくが大切な存在だったとまた気づいてくれるかもしれない。そう思ったぼくは迷うことなくそのスイッチをもらった。
しかし騙されたようだ。よくよく考えれば、死んだ後でそのスイッチを押せるはずがない。
❸
お葬式には、いきなりの連絡だったにも関わらず、多くの人が訪れた。お父さんの会社の人、お母さんのママ友、お兄ちゃんのクラスメイトまでいたけど、ほとんどぼくが知っている人はいない。きっとただ付き合いできた人がほとんどだろう。
でも、その中で一人だけ、知っている子がいた。いとこのひなたちゃんだ。ひなたちゃんはぼくが小さい頃入院していた病院の近くに住んでいた子で、よく遊びにきてくれていた。おかあさんがいないときのほとんどを彼女と過ごした。ぼくの病気が治ってからは、こっちの子と仲良くやっていくために、あまり遊びに行かないようにと言われてあまり会えていなかった。しばらくして、ひなたちゃんはちょっと変わった子だから会わせないようにしているというウワサを聞いたきり、彼女のことを忘れていた。
「あんなに遊んでくれたのに、ごめんね」とぼくはひなたちゃん言う。するとまるでううん、と否定するように首を振った。
距離はわりとあったし、ぼくの声は聞こえていないはずなので、多分虫かなんかが彼女の顔の前にいたのだろう。
「違うよ」ひなたちゃんは大きな声で言った。その目はしっかりぼくを捉えていた。
「びっくりした! またあんたは急に変なことばかり言って!」とひなたちゃんのお母さんに手を引かれる。彼女はそれを振り払ってぼくの元まで駆け寄ってきた。
「ちょっと外に行こう」
「え?」
ぼくが驚いている間に、さらに彼女は驚きを重ねてきた。なんと、ぼくの腕を掴んでいたのだ。
「久しぶり」
ひなたちゃんに葬儀会場の外にあるテラス席みたいなところに連れてこられたぼくは「ど、どういうこと? ぼくのことが見えるの? 聞こえるの? そうだとして、なんで触れるわけ?」
「さあ」
ひなたちゃんはぼくの頬に手を当ててじっと目を見てくる。それが全ての答えだった。彼女はぼくに触れることができるし、ちゃんと見えているし、声も聞こえている。
「今度は私の質問ね、なんで死んだの?」
「えっと、それは」
ぼくがスイッチのことを伝えると、ぼくから目を逸らして、後方の死神を見た。
「おおっと、そんな睨まれても、私は私の仕事をしているだけですからね」
「人を騙して魂を食べるのが仕事?」
「騙すなんて人聞きの悪い、私は聞かれたことはしっかりと答えています。彼が深く聞かなかったのがいけないのです」
「商品には説明義務っていうのがあるんじゃないのかしら」
「それは人間側の都合ですから」
先ほどは魂をいただくのは、人間の医者が死亡を確認し、火葬場で焼かれてからだと人間社会に合わせたようなことを言っていたくせに。
「まぁたしかに死神に人間の道理を通そうと言っても無駄ね。じゃあ、ちゃんと聞かなかったゆうたくんの代わりに聞かせて、彼が生き返る方法は本当にスイッチを押すことなのね」
「えぇ。このスイッチを押すだけです」
「あなたが私を騙していて、私も死ぬって言うことは?」
「私は嘘はつきません」
「他に私や周囲の人に影響は?」
「ありません」
「じゃあ話は早いわ」
そう言ってひなたちゃんはスイッチを押す。ひなたちゃんも怖かったのだろう。押す瞬間に目を閉じた。ゆっくり開いたかと思うと、ぼくの顔に触れた。
「ダメだ。私じゃ、もともと触れられるから、生きているかどうかわからないわ」
そう言って立ち上がると、近くにいた葬儀会場のスタッフに話しかけはじめる。
「あそこに男の子が見える?」
スタッフの女性は困った顔をしたあと、見えますよと言った。ひなたちゃんが表情を輝かせたのも束の間、スタッフの女性が指差した方向は、先ほどまでぼくが座っていた、ひなたちゃんが話しかけていた方向にあった椅子だった。ぼくはひなたちゃんの真横にいるので、スタッフの人は嘘をついていることになる。
はぁ、とため息をついたかと思うと、「どういうこと!」と死神に詰め寄った。急に大声をあげたようにスタッフからは見えただろう。彼女の目からすれば、ひなたちゃんは何もないところに話しかけ、急に怒る女の子だ。はじめは不思議ちゃんくらいに思われていただろうけど、やばいやつだと本能が理解したのか、スタッフは室内に逃げていった。
「私は嘘はついていません。それを証拠にあなたは死んでいませんし、だれも迷惑はかかっていません」
「でも、ゆうたくんが生き返っていないじゃない。スイッチを押せば生き返るんじゃないの?」
「ええ」
「じゃあおかしいじゃない!」と言ったところで、ひなたちゃんははたと立ち止まる。
「もしかして、生き返るにはスイッチを押す以外に条件がある?」
「ええ」
「それはなに? 教えなさい!」
死神は一瞬狼狽えたように見えた。
「もうほぼ答えみたいなものですが、今更これを教えてもどうにもならないでしょうから特別に教えましょう。このスイッチは、本当に彼に生きてほしいと思う人が押さなくては意味がないのです」
「私は、思っているわ。でも押しても生き返らなかった。それはどうして?」
「本当に思っていますか? それを証明はできますか?」
「証明って、気持ちを証明なんてできないに決まっているじゃない。そうやって言葉のあやで逃げて魂を貰おうとするなんて、ほんと悪魔ね!」
私は悪魔ではなく死神ですが、と訂正する死神をよそに、スイッチを持って葬儀会場に戻るひなたちゃん。ぼくも彼女を追いかけると、そこには手当たり次第にスイッチを押してほしいと頼み込むひなたちゃんの姿があった。多くの人は無視するか、困ったように笑うだけだ。多分彼女が変わった子だということはこの会場にいる人のほとんどが知っているのだろう。押してくれる人は数人いたけれど、もちろん変化はない。
「ひなたちゃん、落ち着いて」ぼくが声をかけるとようやくひなたちゃんは人々にスイッチを押してくださいと差し出す手を止めた。
「で、でもこれじゃゆうたくんは生き返らない」
少し周囲がざわつく。でもそう言ったのがひなたちゃんだとわかると、誰しもがみんな納得したように元の喧騒に戻った。
「でも、手当たり次第にやっても意味ないよ。対象を絞ろう」
ぼくは自分に生きていてほしいと思っている人がいるとしたら誰だろうと考える。すぐに浮かんだのは幼き日、ぼくを心配そうに見つめるお母さん。
そう告げるとひなたちゃんは急いでぼくのお母さんの元に走った。それを追いかけながら、ぼくは強い不安に襲われる。もし押してぼくが生き返らなかったら、それはつまりぼくが愛されていないという証明になってしまう。知りたいけど、知りたくない。
でもぼくの不安は、急いでいるひなたちゃんがぶつかった人の持っているものを落とさせるくらいの影響しかなかった。
ついにスイッチはお母さんの前に出される。そこにはお父さんとお兄ちゃんもいた。三人は入り口で喪主として受付をしていた。
「あら、ひなたちゃん、久しぶり。小さい頃、入院してるゆうたとよく遊んでくれたわね」
「本当だ。ひなたちゃん、大きくなったねぇ。美人さんになって」
「ゆうたと久しぶりに会うのが葬式ですまないね」
三人とも張り付いたような笑顔でそう言ってせーのと息を合わせたように悲しそうな表情になる。
「そんなの今はどうでもいいです! このスイッチを押してください!」
ひなたちゃんはスイッチを三人の目の前に差し出す。さすがにそんなことをされると想像はしていなかったんだろう、三人とも顔を示し合わせる。
ここで、ふざけたことをするな! と怒ってスイッチを壊してくれたほうが良かったかもしれない。
三人とも、ひなたちゃんをかわいそうな子みたいに見て、優しく押してくれた。でもぼくは生き返らなかった。
❹
ぼくの葬式はつつがなく進んだ。午後からは、ぼくのクラスメイトも来てくれた。ぼくをいじめていたクラスメイトたちは、ぼくの知らないぼくとの思い出を話していた。
「仲の良かった友達とかいないの」
「一瞬仲が良かった子は二人いたけど、これいじょう仲良くしたらいじめるからって言われていじめっ子側に回った子と、仲良くしているふりだけして、裏ではぼくのことを悪く言っていた子だね」
その子たちは来てすらいないようだった。
「じ、じゃあ、恋人とかは?」
「いるわけないじゃん」
「す、好きな人とかは?」
「いないよ」もしいたとしてもぼくの片思いだったらスイッチを押してもらっても意味はないだろう。なんでそんなことをわざわざ聞くのかわからない。
「諦めないでよ。私が必ず、ゆうたくんを生き返らせるんだから!」
少し大きい声が響く。でもその場にいた誰しもがひなたちゃんが言っているというだけで、まるで聞こえていないみたいに無反応だ。
ぼくは煙をじっと見つめる。ゆらゆらとくねらせながら登っていく煙。でも途中で見えなくなってしまう。魂を食べられたぼくはきっと天国には行けずに、あんなふうに途中できえてしまうんだろうな。死が近いからだろうか、それでもいいかという気がした。
葬式も終わりに近づいてくると、ひなたちゃんのお母さんがやってきて、「もう帰るわよ」と彼女の手をとった。
「いやだ! まだゆうたくんを生き返らせていない!」
「あなた、葬式でまで、そんな変なこと言わないでちょうだい! ほんと、はずかしい」
ひなたちゃんのお母さんはひなたちゃんを引きずるようにして会場を出て行く。引っ張られてない方の手でぼくに手を伸ばしてきた。ぼくも思わず、彼女に手を伸ばす。でも届かなかった。
「終わったな」
死神がぼくの肩に手を置いて言った。笑いを堪えているのがその手の揺れでわかる。早く魂をいただきたくて仕方がないのだろう。
「うん。なんだったらもう魂をとってくれてもいいけど」
「そういうわけにはいかないんですよ。魂は体に強く結びついている。体がなくならないうちは私たちは手を出せないんです」
なるほどやけに人間のルールを遵守すると思ったら、そもそもそういう事情だったのか。
ぼくの遺体が入った棺は顔だけ見えるようにされた状態で火葬場まで運ばれる。誰もがぼくの顔を見ていたので、ぼくは自分の遺体に重なるようにして、その視線をあびてみた。
なるほど、誰も本当にぼくに生きていてほしいと思っている人がいないのがわかる。大切な人が死んだからではなく、早く終わらないかなぁと思っているであろうことがわかる虚無な表情、いじめていたクラスメイトがほっとした表情をしているのは自分の名前が書かれた遺書が見つからなかったからだろう。お母さんもお父さんもお兄ちゃんも同じような表情をしていたのは少し辛かった。でも、ぼくの感情はぼくの顔の前で開く棺の扉をカタカタ揺らしただけだった。
ぼくの遺体が入った棺は火葬用の金属製の担架に置かれる。
誰しもが口々に別れの言葉をかけてくれる。声のイントネーションとそれぞれの表情が合っていなくてゾッとしたけど、棺の戸が閉められ暗くなると眠たいくらいしか思わなくなってきた。
ゴトゴトという棺を窯に入れる音より、死神の笑う声の方がうるさい。いや、それよりも大きなお音がする。いや、これは、声? ぼくは棺の中から見えるわけでもないのに、目を開けた。
「待って! ゆうたくん! 行かないで!」ひなたちゃんだ。てっきり帰ってしまったのだと思っていた。でも、もう無理だ。参列者全員の顔を見た。全員、ぼくに生き返ってほしいなんてこれっぽっちも思っていないよ。クラスメイトはいじめがバレなくてほっとしてるし、家族はやっかいもののぼくがいなくなってせいせいしてるよ。
棺が少し戻され、また顔の扉が開けられる。眩しいと思ったのも束の間、ひなたちゃんの顔が天井の光を遮ってくれる。
「ありがとう、でもぼくはいいんだ。きっとぼくに生きていてほしいと強く思っている人なんていないから」
「違うわ! 私は生きていてほしいもの!」
そう言った後で、自分が一度スイッチを押して生き返らせることができなかったのを思い出したのだろう。口をつぐんだ。涙を目からいっぱいこぼす。いくつかがぼくの頬にかかる。ぼくは自分の遺体と重なっていたのをやめて、彼女の横に立った。彼女の視線は箱の中から、自分の真横に移動する。
「ゆうたくん!」ひなたちゃんはぼくに抱きついた。
周りからすれば変な茶番を見せられているようなものだろう。遺体を燃やそうとした最中、急に変な子として親戚中で有名なひなたちゃんがやってきて、その彼女がまるでそこにぼくがいるみたいに振る舞うのだから。
「死神! 聞こえてるんでしょ! 私の魂をあげるから、ゆうたくんの命を返してよ」
死神はゆっくりその姿を表す。彼女はぼくを抱きしめていた手を死神の胸ぐらに移動させて、その手元にあるスイッチをふんだくって、何度も押した。
その様子を見ていた数人が涙ぐんでいた。
変なことをしている人、という目が、そこまでしてぼくがいないことを受け入れられずに悲しんでいる人に変わり、感動的に映っているのだろう。いわゆる棺に縋るように泣いて騒ぐのと同じだ。
ふと顔に何か当たって痛い。見ると。花や、手紙やらだった。先ほどまで目の前にいたひなたちゃんはいなくなっている。
ぼくは棺の中にいた。
「離してよ! まだゆうたくんは!」と外から声がする。
「あんたって子は! 本当にはずかしい!」
絶好のタイミングだ! と思った瞬間、体が動いていた。棺のフタを持ち上げ、勢いよく、体を起こす。思ったより、金属製の担架の上はバランスが悪く、転んで棺の外に出される。
「いててて」
頭をさすりながら顔を上げると、その場にいた人は誰しも青ざめた顔をしている。それもそのはずだ。死んだはずの人が生き返ったのだから。
その中で一人だけ瞳を輝かせていたのは、今にも母親にビンタされそうになっているひなたちゃんだった。掴まれた手を振り切り、ぼくのもとに駆け寄ってきた。かと思えば、抱きつかれ、またバランスを崩したぼくは転ぶ。
ぼくはよみがえった。理由はスイッチを押したこと。
ひなたちゃんのお母さんが、ビンタをするためにあげた手は、その対象を失い、自分の頬をこれでもかとつねることに移行していた。
了
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
