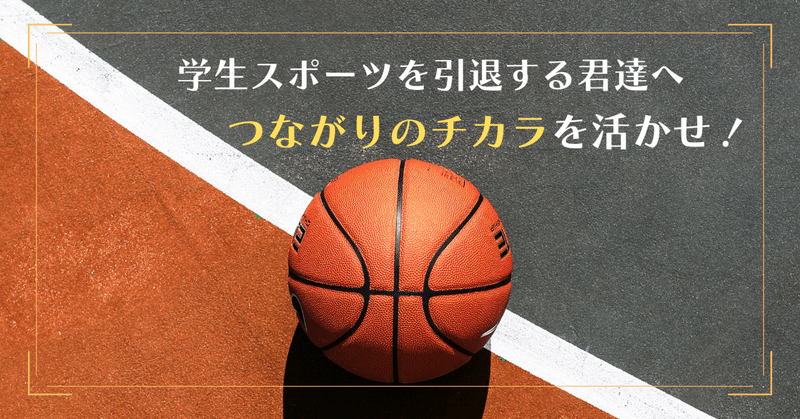
学生競技経験は、その後の歩み方で輝く
バスケットボールを喩えに出して、「学生スポーツを引退していく選手こそ、つながりのチカラを感じてその後も生きてほしい」というメッセージを、2010年頃にTwitterで連投していた。
当時、大変多くの方々からレスポンスをいただいた140字のTweetの数々。
■noteにも再掲する意味
小学生、中学生、高校生、大学生…どのステージでも、学生スポーツは、必ずどこかの段階で競技生活を終える「引退」を迎える。
世間一般では、華やかな舞台で選手としてどれだけの戦績を残してきたかに注目されがち。
しかし、学生スポーツの「醍醐味」は、競技生活で培ってきたことを「次にどう活かすか」という点にある。
仮にプロに進んだとしても、競技生活の時間よりも、引退してから社会生活を過ごす時間のほうが、遥かに長い。
そうだとしたら…学生スポーツで、ココロとカラダに染み込ませた経験を、いかに社会で活かしていくか…そこに「自分を活かして生きていく生活者」になることの醍醐味がある。

そして、再び過去のTweetを掲載するのは、【学生スポーツや部活は、そもそも何のためにあるのかという「目的」を、親御さんも指導者も再認識してもらいたい】という意図もある。
それが2010年当時、大きな反響となって拡散もされていった。
あれから何年経とうと、「学生スポーツでの人育てのあり方と、経済活動での価値づくりのあり方には、間違いなく深い相関性がある」と確信しており、noteに再掲載することにした。
気持ちの切り替えに関するTweet
部活バスケ引退も多いこの時期…指導環境に恵まれた子も、そうでなかった子も…引退した次の日からの過ごし方が大切。バスケで得た感動と苦い思い出は、必ず次へ活かそう。真摯な姿勢で気持ちを切り替えるべき人生ステージは何度もくる。常に次への切り替えと備えがとても大切。
シュートを決めた後に気を抜かずにすぐにDF。シュートを外しても気を落とさずにすぐにDF。挑戦が成功しても失敗しても、すぐに次に備える…これは社会人大人になってからも求められる姿勢。学生バスケで染み込ませたその姿勢は、自分が働く場において役に立つ時が、必ず訪れる。

作業と仕事の違いに関するTweet
味方にシュートを決めてもらいやすい丁寧なパスを出すのが「仕事」。相手を思いやらない雑なパスは「作業」…つまり『誰かの役に立てること・その人の笑顔を思い描いて行動するかどうか』で、その後のチームの成果が大きく変わる。バスケはそれを学ぶ場。コレは大人の職場でも同じ。
「仕事」をしようとする人は、日頃から指示内容の本質を理解し、自分にできることを探そうとするため「不測の事態」の対応能力も養える。「作業」しかしない人は、指示内容と違う状況が生じた時の対応能力は薄い。不測の事態への対応能力が高いチームが強いのは大人の職場でも同じ。
とりあえず目の前の「作業」には取り掛かろうとはするが、手に負えないと他の人に委ねる…または、誰かやってくれるだろうと知らんぷりする人は大人でも多い。自分がやるべき「仕事」を自分で見つけ最後まで全うする習慣は、徹底したマンツーマンDFをするミニバスケからも養える。

目立たぬ働きの価値に関するTweet
「自立」は、親に頼らなくても自分で立てる力、大人に言われなくても自ら行動しようとする力。その先に、自分で選んだ道は自分で責任を持ち、甘えを封じるためにも自分を律する姿勢が生まれる。だから、「自立」は「自律」も産む。稚拙な大人こそ、ミニバスケから学ぶべき点も多い。
たった一つのナイスDF、ナイスリバウンド、ナイスパスやナイスブロック。目立たずともその仕事は大いなる存在価値であり、次へのつながりの一歩。毎日高い意識で取り組んでいる姿勢が判るその一瞬に賛辞を贈ろう。やろうとした姿勢を認めよう。社会に出てもそういう人が求められる。
ミスした事への罵声や怒号よりも『スコアに表れない仕事』をした人への感謝が大切。必死にルーズに飛び込む・体格劣勢でもステイローでポジションを死守する・懸命にリバウンドフォローに走る・素早くタオルや水筒を差し出すなど…着目すべき点はたくさんある。大人の職場でも同じ。
スタメン、ベンチスタートの控え、ベンチ入りできない者…それぞれ仲間と一緒に夢を掴むために、常に「今の自分にできる仕事」を探し続ける者の集団は、日常生活でも一味違う。人に言われる前に、まずは自分で考え行動に移せる人が集まる組織は常に輝いている。大人の職場でも同じ。
社会に出たら、理不尽なことや、想い描いていたとおりに事が運ばれないことが多い。だからといって、人に頼ってばかりや、依存しては残念。学生バスケで身に染み込ませた「自分にできる仕事を率先してやる姿勢」は、社会でも誰かが見てくれている。価値創造は個々の実践力にある。

キレイごと…大いに結構なTweet
敵は相手チームではない。自分と相手との身体能力の比較で勝負は決まらない。君の心のスキが出来たら必ずやられる。どんな対戦相手であろうと、闘う相手は常に自分自身だ。自分に強い子は高い壁こそワクワクする。君が社会に出た時、自分に挑んだ経験が役に立つ。失敗は挑戦者の証。
「理想ばかり求めても試合に勝てない」はたしてそうか?キレイごと大いに結構!人を蹴落としても勝ち抜くという今の経済社会と似たよう少年スポーツ指導ではなく、心豊かな価値を創る人を育てたい。子供達の『心』をさらに「楽しく」「強く」「美しく」するチームこそ、価値がある。
頂点を目指すのは良い事だが「意味」がある事にしてほしい。「目指した先で、自分はどういう人間になっていたいか」という信念があることが学生バスケでは大切。信念なき頂点は、一過性の笑顔に止まる可能性もあるが、頂点未到達であっても、育まれた信念は「人としての芯」となる。

引退後の生きざまに関するTweet
競技生活の経歴は、その後の本人の努力次第で、輝きも曇りもする。人に必要とされるのは、経歴よりも配慮ある人柄と豊かな価値創造力。深い感謝の気持ちを軸に人間形成を磨くための学生競技だ。親がそのあたりまえを忘れがちで、経歴ばかりにこだわる危険な方向となるのは大変残念。
世の大人達のモラル低下や、心豊かさを失った経済スタイルの話と、学生バスケやミニバスケでの人間形成の話を結びつけることは強引なことではない。人に幸せをもたらすための自己研鑽・工夫・仲間づくり・共感・笑顔…その大切なことに気づき、築ける親子を多く輩出したいからね…。
自由には責任が伴う。しかしブレーキが利かなくなった自由経済の成れの果てが「経済効果」という身勝手な理由の正当化。自分さえ良ければイイという風潮の乱開発や経済活動は、そろそろ敬遠されてもイイ。心豊かさを今取り戻さないと、自然の摂理から本当の自由が奪われる時が来る。
社会での関連性についてのTweet
子供達は規律だけでなく、自由と自主性で潜在能力が伸びる。自由には責任が伴うからこそ、自分達で考えさせて、多くの失敗と小さな感動を自ら繰り返せる環境が大切。知識よりも、経験による直観と考え抜こうとする知性が磨かれることで、「意識」を自由にできる人が育まれるからね。
金払う俺を満足させろ!…この姿勢だけでは世の中ギクシャクする。私は債権者だから、ひれ伏して債務を履行しなさいと言わんばかりで、日頃あなたも人様に喜んで頂いた成果でお金を得ていることを忘れた瞬間。カネは天下の回りもの?ボクらはカネではなく人の笑顔と感謝で回したい。

補足1)つながりを認識する重要性
大人になって社会に出て働く…家庭を築いて家族を守る…自分らしい暮らしを営んでいく…その全ての行いにおいて「つながり」が不可欠。
そして、どんな仕事でも、「つながり」という価値を産み出している。
そうしたことは、案外、小中学校だけではなく、高校や専門学校でも習わない。そうした認識が無いまま、大学を卒業して就職していく人も多い。
社会で価値づくりに勤しんでいるボクらは、それをとても憂いている。
概念的な事だが、いくつか箇条書きにしてみよう。
小売店などのお店運営なら、お客さんが望むモノをお客さんの代わりに探してきて、満足するモノを「つなげる」
運送会社なら、遠くのお客さんのもとへ大切に届けるという、モノを「つなげる」
雑誌出版や新聞社なら、多くのお客さんのもとへ正確な情報を「つなげる」
保育士や学校の先生なら、正しく、強く、美しく子供達を育んで、次のステージへ「つなげる」
銀行なら、正しいお仕事で事業を大きくしようとする会社へ少しの間お金を「つなげる」
飲食店なら、美味しくて幸せになるような食事をお客さんに出して、明日への笑顔に「つなげる」
プロダクトデザイナーなら、洋服や家具などで機能性やデザインで、お客さんの生活を豊かにすることへ「つなげる」
家庭の主婦・主夫なら、家族が暮らしやすくするために掃除・洗濯・食事などで、今日の笑顔に「つなげる」
どうだろう?
自分達の働きの先には、どういう幸せにつながっていて、その満足度の対価として、お金が入ってきているという認識を持って働く。
そうではなくて、職場でただ指示された作業をしてお金を貰う。
どちらのほうが、心豊かでクオリティの高い働きと生き方になるだろう?

補足2)つなげるものは何であるべきか?
「カネは天下のまわりもの」という表現がよく使われる。
お金は一箇所にとどまるものではなく、常に人から人へ回っているものだから、今はお金が無い人の所にもいつかは回ってくるという励ましの意味。
しかし、この国の経済風潮は、いつの間にか「お金⇒豊かさの象徴⇒カネさえ払えば受け取った相手はこちらにメリットを与えて当たり前」のような雰囲気になっている。
それは大袈裟だろうというが、紛れもない事実だから虚しさを感じる。
一人ひとり、自分ができる仕事をしっかりして、自分にできないことは他の人がしっかり仕事をしてくれるからこそ、相互に感謝が生まれる。
それが循環するから経済となる。
おカネという代替品を使った「ありがとうの循環」が「経済」なんだ。
そうであるならば、「カネは天下の…」のクダリでは、まわすべきはお金ではなく「感謝と笑顔」なんだよね。
世間では、いつの間にか、その「あたりまえ」の循環が鳴りを潜め…おカネを払う側が偉い人で、払われれる側がそのおカネをもらうために媚びるという雰囲気が主流となっていった。
それって、ボクらにしてみると、とても滑稽かつ軽蔑すべき光景だが…それが普通でしょ?…だから自分は「勝ち組」になると豪語する人すら多い。

確かに、モノが溢れ、利便性が整う社会で、ある意味「豊かさ」の象徴とされる見栄えの良いモノが、もてはやされるようにもなっていった。
しかし、ステイタスや地位や贅沢な家財などだけが豊かさの象徴となりがちで、この国はどこか「心豊かさ」は失われてはいないだろうか…。
とりあえずは「勝ち組」よりも、お客様に喜ばれる価値を創る「価値組」を目指した方が良いんじゃないかな?
でもね…これまでの残念な空気を作ってきたのは、我々大人の責任なんだ。
あきらかに「あたりまえ」が崩れ、政治力や資本力など大きな力によって、人為的に造られた「常識」のレールに載せられて来た結果…
これはナニか違うんだけどな…とは気づきながらも、「仕方ない…これが社会だ」とあきらめてきた我々大人の責任だ。

■変わるべきは我々大人から
弥生時代以降、最終的には「富が吸い上げられていく計画的管理体制」の構造で日本が成り立ってる。
だから、気づけば労働搾取的な構造は、産業革命で資本主義が台頭する前から存在していたから、仕方ないのかもしれない。
それが仕方ないとしてもだ…
やはり「富」を生むにしても、個々が「心豊かさ」を失ってはいけない。
だからこそ、ボクらは…
「ありがとうの循環」というあたりまえが失われている経済循環を、次世代の子供達と共に取り戻したいと思ってるんだよね。
そして、学生スポーツで培ってきた人への感謝・配慮・絆…その「つながり」を社会で存分に活かしてほしいんだ。
もちろん、吹奏楽や文化活動で心を磨いてきた若い人達も同じこと。
そのためには、結局は「まずは我々大人から」ということになる。
それで、ぜひ我々と同世代や大人達にお願いしたいのは、ご自身のお子さんや若い新入社員とは「対話」をしてほしい。
何年も前にTwitterでの反響でとても多かったのが「我が子に読ませます!」というレスポンスだったんだけど…それは、大人としての無責任に近い違和感があるんだよね。

言い聞かせるのではなく対話を!
その当時Tweetしてきた数々のことは、ボク自身、「自戒の念」で示したことも多いから、今でもできていないこともたくさんあるし…学生にはまだまだ難しい表現だってたくさんある。
つまり、「読ませる」前に、ココに書いてあることを題材にして、自分自身はナニを感じるのかを咀嚼した上で、まずは親から(上司から)次のようなことを自分の言葉で語ってみて欲しい。
どういう人のどんな幸せをもたらせてようとする人が職場に集まり、そうした中で自分はどういう働きをしている。
そして自分達が産み出した価値によって、お客様にはどういう未来を築いてもらいたいと思っている。
そういうことを…まずはお子さんに話してみていただきたい。
そう…!
コレが案外「理解共感してもらえる」ように話すのが、なかなか難しい。
なぜなら、自分自身がそのことを整えられていないからだ。
つまり、日頃の仕事ぶりについて、我が子が理解してもらえるように説明できない自分に気づく機会にもなる。
でも…その「気づき」が大切なんじゃないかな。
「自分は社会でどのようなつながりを創っているのか」を語り始めてこそ、やっと親子(上司と部下)との対話にも、リアリティが出てくる。
それがないと、単なる説教にしかならないから、Twitterでも記載した上記項目を「読ませる」ことをしても、何も響かないんだよね。
ONE TEAMを間違えない
ラグビーワルドカップ日本開催で、日本代表選手陣に素晴らしい感動を貰った中で…にわかに「ONE TEAM」という言葉があらゆるところで使われた。

ここで注意すべきことがある。
とにかく「チームのために」「仲間のために」「組織のために」という表現が添えられて、「チームに貢献することがとにかく美徳である」的な取り上げ方をする人もいたのが、すごく気になった。
チームや組織が掲げたビジョンや、「どういう人達にどのような幸せをもたらす」という目的に向かって個々のチカラを発揮して、仲間と一体感となるというのなら解る。
つまりは、チームや組織の「目的が何か」ということだ。
チームや組織は、その目的に近づこうとするための「集合体」に過ぎない。
その「集合体」のために「自分を犠牲にすることが美徳」ということを言っているのではない。
「One for all , All for one」という言葉をよく引き合いに出される。
ところが、学生スポーツの強豪校や企業においても、「One for all」しかなく、個の犠牲を美徳化した空気の中で、個が全く報われない「All for one」など皆無という場面がたくさんある。
それは、日大アメフト事件や、各企業での過労死の問題が裏付けている。
学生スポーツならば、目的は人間形成を磨くということであり、「全国大会出場」や「全国制覇」はあくまでも「目標」に過ぎない。

学生スポーツのあらゆる競技で、未だに「チームのために」が歪んだ空気で、抑圧的かつ軍国主義的な体制となっているところが後を絶たないのは…明らかに目的を間違っている。
明らかに間違っているが、抑圧的空気の恐怖政治体制となっている強豪校が未だにどれだけいるか…。事件になっているところなど、氷山の一角だ。
もし、競技人生を終える・引退する際、もしそのような歪んだ空気感が常識であったり、目的・手段・目標が錯綜していたがために、人への気配り・感謝・絆が足りなかった場合は、引退の時期を機に、今後の自分のあり方を問うてみて欲しい。
親子でそういうことを話し合う機会があれば、むしろその後の歩みにおいて、素晴らしい財産になる気がするんだ。
とにかく…コドモ達の意識を変えたければ、まずは我々オトナからだ!!
躍心JAPAN団長
河合 義徳
#キレイゴト上等
#子供達の意識を変えたければまずは我々大人から
#躍心JAPAN
#やり方よりあり方
#勝ち組より価値組
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
