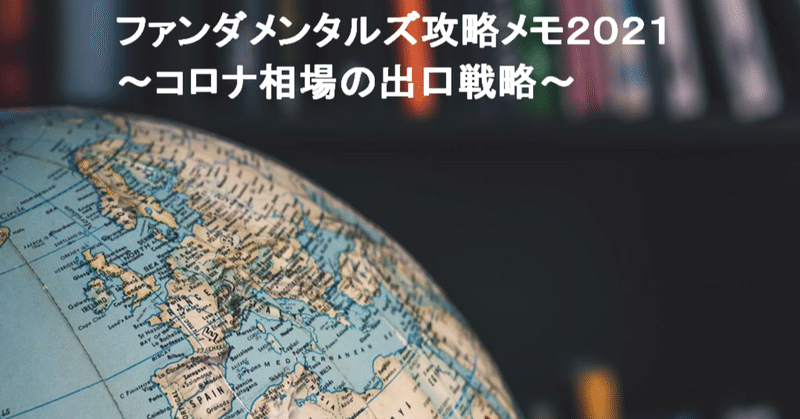
ファンダメンタルズ攻略メモ2021
始めに
好きなアクション女優はクロエ・グレース・モレッツちゃん!
どもども、タラリコです。
昨年、コロナ相場のファンダメンタルズを見る上でのまとめとして
ファンダメンタルズ攻略メモを執筆してから半年ほど経ち
この時の見立てから若干のズレは出たもののコロナ相場は
転換期に入ってきたかと思います。
次の大きな流れを見逃さないためにも
今、チェックすべきファンダメンタルズの
要点を僕なりの視点でまとめることで
2021年版のファンダメンタルズの攻略メモとしたいと思います。
ココまでのあらすじ
ココまでのコロナ相場の流れはファンダメンタルズ攻略メモにてまとめた
内容と重複する部分になりますが、ダイジェストで解説すると
①コロナショック発生
コレによって株価は大幅下落して歴史的な経済危機に成る
②アメリカFRBはコレに対してリーマンショック以来の
ゼロ金利政策を発表
※金利には2種類あり
短期金利(都市銀行等が中央銀行にお金を預けた時の利息)
長期金利(国債を購入した際の利回り)
中央銀行(FRB)が操作できるのは短期金利のみで
長期金利は短期金利を下げる事で間接的に操作されています。
短期金利を下げることで銀行は中央銀行にお金を預けても
利益にならないため、企業へ融資をして利益を上げようとし
結果して市場に資金が流通して経済刺激&株価上昇に繋がります。
③ゼロ金利政策の結果、株価の指数はコロナ前を上回り
コロナ収束を待たずして最高値を更新
④コロナに有効なワクチンが開発され摂取がスタートし
コロナ収束=ゼロ金利政策の終了を予見する市場参加者が増え
長期金利が上昇する
※長期金利の上昇は株価の上昇にとっては向かい風で
FRBの次の一手が注目される(今ココ)
若干駆け足でのダイジェストですがざっくり言うと
コロナ相場はワクチンの普及で転換点にきてる
って認識でOKだとおもいます。
長期金利については後の項でもう少し掘り下げていこうと思います。
FRBの動きが注目されるとなると
やはり、中心人物となる人は....
この物語の主役はパウエルFRB議長

このコロナ相場後半戦を語る上ではやはり、中心人物である
パウエルFRB議長の視点に立って考えることが近道かと思います。
株保有者・FXトレーダーの目線は一旦切り離して彼の立場になって
考えることで、FRBのコロナ相場出口戦略の真意が見えてくると思います。
パウエル議長が避けたい最悪の未来
「テーパータントラム」
不景気時に施工されるゼロ金利を始めとした金融緩和政策は
確実に好景気をもたらしますが、それが続くと市場が加熱しすぎて
バブルとなり、最後には崩壊してしまいます。
その為、ある程度の経済回復が見込まれた段階で
緩和を縮小して市場への過剰な資金の流入を減らし
景気を意図的に冷ます必要があります。
不景気
↓
金融緩和
↓
好景気
↓
金融引締
↓
不景気
経済はこんな感じのサイクルで
終わらないワルツのような四拍子で流れます。
(ワルツは三拍子ですがw)
金融緩和のあとには必ず金融引締がある
問題は、ゼロ金利政策クラスの金融緩和となると
引き締め方を間違えると恐ろしい反動が起きてしまうことです。
過去にあったゼロ金利政策時の悲劇として
リーマンショック脱却からの金融引締時には

当時のバーナンキFRB議長が突然に金融引き締め(テーパリング)
を発表したために市場が癇癪を起こす現象テーパータントラムを
引き起こしてしまいました。
テーパータントラムの別名はバーナンキショック
リーマンショックの出口戦略で失敗し自身の名前を冠する
経済ショックを引き起こす事はFRB議長の立場からすると
最上級に不名誉な大失敗と言えると思います。
そして、おいそれとゼロ金利政策なんて出来ない理由もこの
引き締めの難しさにあります。
(東洋には長年マイナス金利の国もあるらしいですが....)
パウエルさんはこの最悪の事態を避けたいという前提があるため
徐々にさり気なく、市場に金融引締を意識させる必要があるわけです。
株価の上昇を維持しつつ、緩和の出口も緩やかに意識させる
非常に難しいことを要求されている立場なんですね。
まさに苦労人主人公でございます。
パウエル議長の悩みのタネ 長期金利の上昇
2021年の1月中旬以降はコロナワクチンの普及に反応して
米国の長期金利(10年債利回り)が上昇しています。
ここで長期金利について掘り下げてみます。
長期金利は国債保有者が貰える利回りのことですが
国債が売れる(需要が高まる)と利回りが下がり
国債が売れ残る(需要が低下する)と利回りが上がります。

これは仮に100万円で年率4%の10年債だとしても
10年経過する前に売買されることで利回りが増減するからです。
経済ショックの時には国債の「元本保証」が重要視されるので
10年後の利子分を差し引いた高値で売買されるため国債が需要が高まると
利回りが低下するわけです。
この辺りは少し難しいかもしれませんが
・経済危機では国債が買われる
・国債が買われると利回り(長期金利)が下がる
・経済が回復すると国債の需要が低下して売られる
・国債が売られると利回り(長期金利)が上がる
・通貨は金利の低い国から高い国に流れるため
金利上昇はドル高につながる
コレくらいの認識でも差し支えはありません
長期金利が上がるということは
10年後の通貨の価値があがる事を意味するので
会社の価値/通貨の価値=株価の関係から
金利上昇は株価に対しては逆風になります。
(実際はもっと複雑な計算式があります。)
特に今現在の業績ではなく未来の業績拡大を見込んで
株価が高騰しているハイテク株を中心とするグロース株は
この金利上昇の影響を顕著に受けてしまいます。
また、国債が売れ残ると長期金利は上昇するため

バイデン大統領による追加経済政策に伴った
国債の新規発行が続いたことも長期金利の上昇の一因となっています。
少し皮肉なようですが経済回復の兆しや対策が株価に悪影響を及ぼす
って所は経済の難しさでも有り面白さでもありますね。
パウエル議長は長期金利上昇に対して
どんな手段に出るか
株価を回復させることで経済全体を復活させるべく
ゼロ金利政策を進めてきたパウエルさんにとって
長期金利が上昇して株価に悪影響が出ることは決して
望ましいことではありません
大型経済指標の代表格である雇用統計で良い結果が出るほどに
長期金利は上昇して、FOMCでのパウエル議長の対応に
関心が集まってくるかと思います。
雇用統計とFOMCの関係
少し脱線して雇用統計とFOMCが何故重要指標なのかを
ここでさらっと解説しておきます。
アメリカのFRBは日銀などの他の国の中央銀行と違って
株価と経済の安定化以外にもう一つ使命を掲げています。
それがアメリカ国民の雇用の確保です。
なので、雇用統計の結果が悪いとFRBは金利などを調整して
経済を刺激して雇用を確保を「目指さなければならない」のです。
そして、雇用統計の結果を受けてFRBが対策を発表する場が
FOMCというわけですね。
私はよくコレを競馬に例えて
FOMCが競馬のレースだとしたら雇用統計は
その結果を予想するための競馬新聞の様な存在
と説明しています。
さて、話を戻してパウエル議長がFOMCにて
金利上昇に対してどんな対抗策をとるのか
パウエルさんの立場でとることが可能な
手札を紹介していきたいと思います。
①量的緩和の拡大(債権購入ペースアップ)
長期金利は国債の売れ残りによっても上昇するので
FRBが毎月購入する国債を量をアップすると言うものです。
一般的に中央銀行がお金を刷るというのは正確には
国が国債を発行し、それを中央銀行が新規に発行した通貨で
買い取ることで、政府に資金が入りそれを政府が市中に流通させる
というフローで行われます。
今現在、既にコロナ化で平常時以上のペースで通貨発行と国債の買い取りを
実施しているFRBですが、このペースを上げることで長期金利の上昇を
抑制するというものですね。
②SLR規制緩和の延長
SLRとはリーマンショックの時に都市銀・地銀が
株などのリスク資産をレバレッジを掛けて取引しすぎていた為に
ロスカットしてしまい結果して多くの都市銀・地銀が倒産してしまった
事を教訓にアメリカの都市銀・地銀のリスク資産を資本金の何%までと
保有限度を制限したルールの事です。
コロナ禍のゼロ金利政策下では長期金利の上昇を抑えるために
この規制から米国債の保有制限を解除して都市銀・地銀が国債を
大量に買えるようにしていたんです。
そして、その規制緩和の有効期限が2021/3/31だった為に
コレを延長するかに注目が集まっていました。
③イールドカーブ・コントロール(YCC)
イールドカーブ・コントロールは簡単に言うと
①の量的緩和の超極端な発展版です。
イールド(長期金利)カーブ(推移)コントロール
なので、端的に言うと長期金利が決めた値になるまで
中央銀行が国債を買いまくると言う政策です。
通常の量的緩和ですら、後に緩和を締め付ける時の反動が
リスキーな為に緩和の拡大に消極的になるのがセオリーな中で
YCCは非常に過激な強攻策だと言えます。
余談ですが、東洋には長年マイナス金利を維持しつつ
YCCにて長期金利も限りなく0%に近い値に抑えている
恐ろしい国があるそうです。
パウエル議長の導き出した答え
これらの手持ちのカードの中でパウエル議長が取った対応は

何もしないでした
正確には何もしないではなく、長期金利には直接的な対策はせず
要人発言の場で市場をなだめ続けると言うものでした。
緩和の強化で後に緩和終了時の反動が大きくなり
第2のバーナンキショックになるリスクをとらず
2023年までゼロ金利政策は継続すること
今の金利の上昇も一過性のものであること
ゼロ金利を終わりにする時と量的緩和の縮小の時は
かなり前もってアナウンスすること
等を丁寧に説明して市場参加者の株式狼狽売りを
抑え込む事を選びました。

パエルさんは元々、市場との対話に長けた人との評判が高く
リスクをとらず得意な「対話」でこの金利上昇局面を
乗り切ろうとしているんですね。
3月のFOMCでの要人発言の場では①③の量的緩和の
拡大に関してはやんわりと否定しつつ②のSLRに関しては
明言を避けて後日、金曜日の市場閉場間際にSLR緩和延長無しを
さらっと発表して他事で株も狼狽売りされることなく
土日で頭が冷えた市場参加者達によって株式も健全に推移していきました。
見えてきたハウエル議長の戦略
ここまでパウエル議長について掘り下げてくると
彼の狙いの様なものが見えてきたように感じます。
後の金融引締時にリスクになりえる追加緩和は避けて
徹底して得意な市場対話で株価の下落を抑える
一貫してこの姿勢を貫いていますね。
なので、今後の雇用統計・FOMCでの注目点としては
パウエル議長がこのまま金利上昇局面を対話だけで
抑えられる事が出来るのか?
になってくるかと思います。
そしてパウエルさんの対話が成功し続けた場合は
経済回復と共に金利が上昇しても市場はそれに徐々に慣らされて
金利上昇とともに株価も緩やかに上昇していくと思われます。
今までは株高=ドル安で推移していた為替も
今後は株高=ドル高でコロナ前の相関関係になっていくかと思われます。
今後の注目度の高い経済イベント
今の相場の中心人物たるパウエル議長の動きを掘り下げたことで
大まかに株式とドルの動きを見通せてきたかと思いますが
せっかくですので私自身の予想も踏まえてこのあと大きく
株価が動くであろう経済イベントについて解説していこうと思います。
大きな節目になるFOMCは9月!?
量的緩和の項でも説明したとおりFRBは現在、経済回復のために
国債を大量に買い上げる量的緩和を実施中ですが、予定通りコロナの
ワクチンが普及することで9月の雇用統計時にはコロナショック前の
水準に失業率の低下が迫ってくる事が予想されています。
すると、FRBとしては今の過剰なドルの発行は不健全なインフレを生み
パウエル議長はそれが加速する事で第二のバーナンキショックが
起きることを恐れていますから、9月のFOMCでは量的緩和に対して
何かしか動きがあると思われます。
勿論、ココで急遽緩和の縮小に踏み切ればバーナンキさんと
同じ轍を踏むことに成るので、このタイミングでかなり先に緩和縮小する
という、事前アナウンスがあると見込まれているわけです。
市場が癇癪を起こさないように繊細な説明が要求されるため
パウエル議長の腕の見せ所に成るわけですね。
もちろん大なり小なり株価には影響があるでしょうから
9月のFOMCでは金利が大きく上昇して株価は調整下落が
あると思っています。
場合によってはこの9月の下落は7月・8月の雇用統計の結果次第で
信憑性が増していき、8月あたりから株式市場は織り込んだ
値動きをする可能性も頭に入れておきたいですね。
バイデン大統領による
アメリカン・ジョブズ・プラン
仮に9月に大きく株式の調整下落が有ったとしても
悲観的になる必要は無いかもしれません
10月以降にはバイデン大統領による歴史的な大希望経済刺激策
アメリカン・ジョブズ・プランが実施される可能性が高いからです。

コレは経済刺激の一環としてバイデン大統領が打ち出した
2兆3000ドルの超大規模インフラ整備計画です。
電気自動車の充電設備や道路整備
半導体メーカーへの支援
5Gを始めとする次世代通信網への大規模整備
AIやバイオ部門の最先端技術への巨額投資 etc
税金を上げて公共事業でお金をバラ撒く傾向にある
米民主党の政権史上でもズバ抜けた規模の大規模な計画が
予定されているわけです。
今現在の米国株価の上昇もこのアメリカン・ジョブズ・プランの
発表を好感してのものだと思われます。
ただ、コレが何故10月以降の実施に成るかと言うと

アメリカの上院は民主党・共和党で50議席で拮抗していますが
法案を通すためには60議席が必要となるからです。
上院が50議席で拮抗しているとなると60議席の賛成は
得られませんが、裏技として「財政調整法案」と言う抜け道があります。
これは1会計年度に1度だけ51議席の賛成で法案と通すことが
出来るというモノです。
50:50で票が割れた場合はハリス副大統領が51票目
を投じるため確実に法案が通るわけです。
アメリカの1会計年度は
10月1日~翌年9月31日迄なので10月まで待つ必要があるんですね
(今回の会計年度の分の権利は既に3月の追加経済政策で使っている)
このプランが無事に成立した場合、9月で押し目をつけた株価は
再び大きく上昇する事となると予想しています。
緩和縮小のアナウンスとアメリカン・ジョブズ・プランの為の
追加の国債発行で長期金利は大きく上昇するかもしれませんが
それを許容して株価も上昇して株高・金利高・ドル高の流れに
なっていくものと予想しています。
余談ですが、アメリカン・ジョブズ・プランの財源は
法人税を10%引き上げる事で捻出すると発表されていますが
おそらく、コレは経済回復の腰折れリスクに成るため
後回しに成ると予想されてます。
このプランも後に増税での景気冷え込みのリスクを抱える
劇薬的な側面があるわけですね。
なのでアメリカの増税のタイミングに関する報道も
今後は重要なファンダメンタルズになってきますね。
コロナ相場転換期における日本円
アメリカ経済についてパウエル議長を中心に掘り下げてきましたが
もう一つ、為替を見る上で注目すべき我らが日本円について
補足としてファンダメンタルズ的な視点で解説しておきます。
正直言ってアメリカ経済・ドルの動向に比べると非常に
簡潔な説明になります。
ざっくり言うと
円の価値は下落していきドル円は上昇していくでしょう
コレは日本での経済対策を担う

麻生副総理と黒田日銀総裁の方針から読み取れます。
ココまでの記事の中でもちょいちょい匂わせておりましたが
コロナショック以降にゼロ金利政策を進めたアメリカと違い
日本は何年も前から上記の2名のタッグの元で
マイナス金利政策を続けているからです。
金融引締の際のリスクを伴うゼロ金利の上を行くマイナス金利政策
銀行が日銀にお金を預けると利息ゼロどころか元本が減ってしまう
恐ろしい政策です(笑)
それだけではなくコロナショックからの経済回復の兆しが見えても
日本では長期金利は上昇しません
なぜなら、日本は......
イールドカーブ・コントロール(YCC)で長期金利もゼロだからです。
ココまでの記事を読んでいただければパウエルさんが
苦悩の末にこれらの劇薬的な対策に手を出さないことを選んだ
事が伝わったかと思いますが
麻生黒田ペアはこの劇薬をガブ飲みしてるわけですね!

オイオイオイ死ぬわアイツ状態です
私自身は日本のデフレ脱却には麻生黒田ペアの尽力は不可欠であり
この二人の手腕には未だに期待しているのですが
日本の経済的な状況の特殊性は理解いただけたかと思います。
ですが、去年までのドル円の相場を見てきた人ならば
ココまで読んで疑問に思うことがあるかと思います。
じゃあ何故2020年は円高だったのか?
徹底的なマイナス金利政策下の日本なのに2020年は
コロナショック以降、ドル円は下落を続けて、一時期は
ドル円が100円を割る観測までされていました
マイナス金利なのに何故?と思われると思いますが
コレは日本円が安全通貨として非常時に
買われる特性が有るからです。
リーマンショックやコロナショック、3.11の震災など
何故、日本円は非常時に買われるのか?
諸説あるようですが分かりやすいところだと
日本国内の機関投資家・個人投資家の多くが自国ではなく
海外に資産をもっており、彼らが非常時にこれらを
一部ないし大部分を売却して円に両替して手元に送金することで
災害に備えるフローがあり災害=円買いの動きが毎回起こるため
災害時に金融緩和で自国通貨の価値が下がるのを警戒した
他国の投資家達もそれに便乗して円を買うというのが定石に
なっているからです。
アメリカがゼロ金利政策を実施しても
日本はマイナス金利なので本来ならドル高円安になるところが
ドル円が下落したのはそういった背景からです。
ですが、ワクチン開発によってコロナ収束の
観測が高まると他国の投資形も円を売って自国通貨を買い戻すため
今後は金利差に応じた値動きに切り替わっていくと予想されます。
そのためファンダメンタルズ的には円の下落目線は非常に強く
ドル円はまだまだ上昇の余地があると考えられるわけです。
ファンダメンタルズは投資に活用できるのか
ここまで、中々の長文になってしまいましたが
ワタシ的に今のファンダメンタルズを見る上での要点を
網羅できたかと思っています。
(情勢の変化に応じて加筆・修正をするかもしれませんが)
ここまで読み飛ばさずに見てくださった方の中に
ファンダメンタルズや政治・経済の流れを読み取っていくのが
面白いと思ってくれる方が一人でも居たら幸いです。
私自身、トレードをしていく上での優位性を求める以上に
追っていくのが楽しくってファンダウォッチしている部分が
非常に大きいのは事実ですからね(笑)
ではファンダメンタルズを追って投資に役に立つのか?
と言うとコレは人によるとしか言えません
例えばFXのトレードでファンダを気にすることで
チャート分析のノイズとなってしまい邪魔になると
持論を展開する人もいれば、そもそもファンダメンタルズは
チャートに織り込まれているので気にする必要がないと言う
人もたくさん見てきました。
多分それも一つの真実だと思います。

殺人事件現場に毎週現れる見た目は子供頭脳は大人の
某小学生が言うほど世の中は単純じゃありません
真実なんて一つじゃないって世界も有ると思います。
それこそ元銀行ディーラーやヘッジファンド出身の
投資家の方々にファンダメンタルズを軽視する人は
一人もいませんし誰も嘘を言ってはいないんですね。
あくまで皆が言っているのは
「自分が勝てるようになった方法」であって
ファンダメンタルズとの付き合い方の正解は
その人自身が試してみないとわからないかと思います。
さて、ここまで長々と予防線を張った上で
私自身のファンダメンタルズの活用方法を
軽く紹介しておきます。
取引通貨の最終判断材料になる
たとえばポンドでのトレードで例にすると
ポンドドル、ポンド円、どちらも上昇トレンドのなかで
ちょうどサポートラインで押し目をつけました
ココまでの記事を読んでどちらかにエントリーするならば
ポンドドルとポンド円、どちらでロングエントリーしますか?
チャート的にどちらも同じ用に上昇しそうであれば
ファンダ的にも円安の可能性が高いためポンド円をロングしますよね?
エントリーの根拠はテクニカルでも
最終的な判断材料としてファンダの知識が役に立つ場合もあります。
今を学んで未来に備える
コレがファンダを学ぶ上で一番大きい利点だと思うのですが
今のようなコロナショックと言う特殊な相場環境を
観察して、実際に相場に参加し生き残ることは大きな財産になると
言う考え方です。

私の好きな偉人の一人、プロイセンの鉄血宰相「ビスマルク」の言葉に
愚者は経験に学び、賢者は歴史に学ぶ
とありますが、我々の様な愚者でも経験に学ぶことは出来るわけです。
今回のコロナショックで資産を増やした人の中には
リーマンショックを生き延びた愚者も
リーマンショックを体験せずとも歴史に学んだ賢者も
両方居たと思いますが、次の経済ショックの際には
(あってほしくはないですが)我々も経験に学ぶ愚者になって
スマートに立ち回りたいものです。
その為にも、今のコロナ相場の経済ショックからの
金融緩和~金融引締までの経済の流れを体験できる
生きた教材から目を離さずに学んでいきたいと思います。
最後に
今回、私は今の相場の主役としてパウエル議長を中心に
ファンダメンタルズを解説してみましたが、極力難しい言葉を
使わずに解説するつもりが何だかんだ専門用語を使ってしまったり
まだまだ改善の余地のある内容だったかもしれません
ですが、コレを読んでくれた人が今の世界経済の概要を
なんとなく把握する叩き台くらいにはなったのではないでしょうか?
チャートだけでなく、その裏のファンダメンタルズにまで目を向けることで
今まで何気なく聞き流していた経済ニュースが一つの連続した
物語のように楽しめる切掛になってくれたら幸いです。
ご拝読ありがとうございました。
また、私がファンダメンタルズや経済を学ぶ上で
活用させてもらっているオンラインサロンコミュニティ
亀心隊ではこういった議論を日頃からさせていただいているので
ファンダメンタルズや投資について
堅苦しくなく学びたいと思う方が居ましたら
是非とも亀心隊への参加をオススメします
亀心隊参加URL
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
