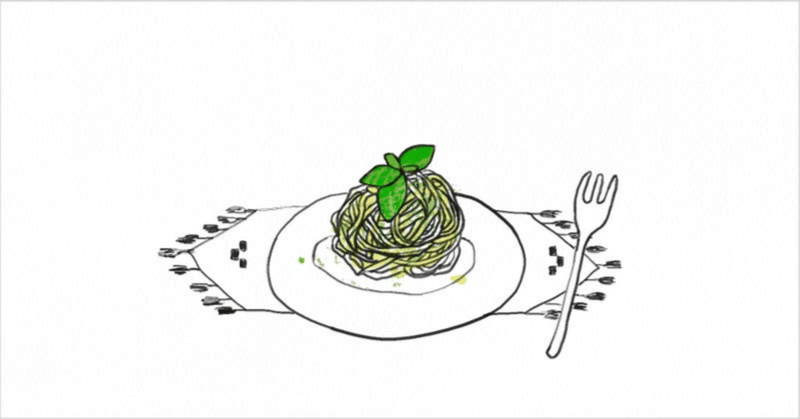
夕食
「私は食事に愛があるのです。」
そう言って手を合わせたのは、いつも通りのAさんだった。
「まるで私には愛がないみたいじゃないですか。」
大盛り無料のパスタセットをプラス200円で超大盛りにしてもらっていた私は、山に盛られたボロネーゼを前に居心地を悪くした。
「そう聞こえましたか。」
「たくさん食べてたくさんお腹いっぱいにするのも愛ですよ。」
二人前は約束されている量のボロネーゼとは対照的に、Aさんの前には子供でも物足りないだろう小盛りのきのこパスタが置かれている。
わざわざ大盛り無料の店に来て、少なめを頼む人なんているんだ、と驚きながら、Aさんの一口目を見守る。Aさんはいつも、一口目を一番長く、一番大切に味わう。時間が経って麺が伸びたり熱が冷めたりしない限りは、何度食べても味付けは同じなのに。Aさんは一口目が一番美味しいのだというように、大切に食べる。
Aさんは見られているのに気が付いて口元を手で覆った。不意に気まずくなって、私はテーブルに目を落とす。木製のテーブルは完全な長方形ではなく、木の幹をそのまま縦に切ったような不規則な形をしていた。これが本当に一枚板なのかそれ風にしているのかは分からないが、こだわりがあって好きだと思った。私はその独特に波打った辺を手のひらでなぞりながら、テーブルに置かれた調味料を確認して味変の予定を立てる。
「食べないんですか。」
Aさんに促されて、食べ始めるのを忘れていたことに気が付いた。また愛がないとか言われそうだと警戒して、すぐにフォークを取った。
「きのこ好きなんですか?」
Aさんのきのこパスタに視線を合わせて私は言った。最初、メニューに目を通してすぐそれに決めていたので、印象に残っていた。
「ええ。」
Aさんは口元に手をあててそう返事して、二口目を口に入れた。
「私はきのこ嫌いです。なんかくさいじゃないですか。食感もなんかぶにぶにするし。」
Aさんはそれには答えず、きのこパスタをぶにぶにと咀嚼しながら私の目を見つめていた。食事中は一段と無口になるAさんに少し呆れて、彼が全て飲み込むのを待つ。
同じ値段なら肉が入ってるボロネーゼやミートスパゲティの方がお得なのになあと思いながら、そもそも小盛りを頼んでいたことを思い出して可笑しくなる。
私も何口目かのボロネーゼを口に入れて、店内を見渡しながら咀嚼する。壁に掛かった時計の針は6時40分を指していた。何気なく手首の腕時計を確認すると、6時25分。スマホを取り出すとそこには18:40と表示されていて、自分の腕時計がずれていたことに気が付いた。
「それにしても君、食べるの早いですね。」
やっと飲み込んだAさんが言った。相変わらずこの人は一口が長いなぁと思う。すぐに飲み込んで次を食べた方が早くお腹いっぱいになるし、口の中で味が薄くならないから絶対いいのに、彼のその妙な癖が不思議だった。
Aさんが次の一口に行ってしまったらまた暫く話せなくなるため、私は口に入っていたものを急いで飲み込む。
「私が早いんじゃなくて、Aさんが遅いんですよ。」
食べるのが早い方であるとは自覚していたが、極端に遅いAさんに言われるとなんだか癪だった。
「私も遅いですが、君もまた大分早い。」
Aさんが二口目を飲み込んだ時点で、私の大盛りボロネーゼは元の三分の二程度の量に減っていた。
「これは有り難いんですが、私と一緒に食事する人はみんな気を遣って食べる進度を合わせてくれる。君にはそれがないからある種楽ですね。」
Aさんが楽と言うなら、本当に楽なんだろう。
「ただ、やっぱり君はすごく早いですね。喉につまらなせないか心配になります。」
今、Aさんが話している間にも、私はまたフォーク一巻き分を飲み込んで、二巻目を咀嚼していた。
「ちゃんと味わってますか?」
「ひどいですね、ちゃんと美味しいなあと思いながら食べてますよ。」
Aさんに答えるために飲み込んで、手元で次の一口の準備をする。
「美味しいと思うのと味わうのとは少し違う気がします。」
Aさんはパスタを食べて美味しいと言うくらい簡単にそう答えた。
私にはそれがどう違うのかは分からないが、その二つが少し違うという感覚は理解できた。
私は味を感じ取るということを意識して、話しながら既にフォークに巻いて待機していたボロネーゼを口に運ぶ。
トマトベースのひき肉のソースが平たいパスタに絡む。よく味わうと、パスタ自体に塩気がついていることに気付き、ソースがパスタに馴染んでいる訳だなと思った。ほんのりと、恐らくトマトとは違った酸味と独特の香りを見つけて、ワインか、と思う。ソースには肉以外に細かく切った人参や玉ねぎやパセリが入っていて、食感は単調じゃない。玉ねぎの他に白い野菜が入っているのが見えて、そこだけ取って食べてみるとそれはセロリだと気付く。なるほどこれがセロリの風味なんだな、などと考えながら咀嚼している内に、少しずつ食感がなくなっていく。ゆっくり食べてゆっくり飲み込んでいると、だんだんと味は薄くなる。私はいつの間にか味わうという目的を忘れて、口の中でなるべく早く細かくして飲み込む効率を上げようという無意識に支配されていたことに気付いた。
「分からないです。味わうというより、味の分析という感じになっちゃう。」
「分析した結果、どんな味でしたか。」
「どうなんだろう、結局……ボロネーゼの味……。胡椒の香りがすごく強くて良かったです。」
「それは君がそこの胡椒を何振りも入れたからでしょう。」
Aさんはテーブルの端に置かれた調味料を目線で指した。
味わう、ということを自分なりにしてみて、その時、私は美味しいと感じていなかったなと思う。
「味に集中すると、寧ろ、美味しいと感じることを忘れてしまいます。Aさんはいつ、美味しいって感じるんですか。」
Aさんは再びパスタを口に運ぼうとしていた手を止めて、
「ずっと、でしょうか。食べて、美味しいと感じるのは、無意識にでもそれを味わっているからなのです。」
そう言ってパスタを口に入れた。
Aさんの声色には不思議とこちらを納得させる響きがあった。しかし、その正しいであろう言葉は、上手く私の心に落ちてきてくれなかった。
分からないです、と言おうとして、Aさんがパスタを食べ始めてしまっていることに気付いて、やめた。さっきまでは客がまばらだった店内は、午後の7時を過ぎてほとんど満席になっていた。がやがやと客の話し声が響く。
私は、目の前のボロネーゼを見て、今度は私が食べたいように食べようと思った。愛とか味わうとかそういう後付けの理由は無視して、私の心が赴くままに食べてみようと思った。
テーブルに置かれたオリーブオイルを回しかけ、塩を少し足して、タバスコを入れる。すぐ、フォークにパスタを大量に巻く。そして一口で、食べる。
美味しい! と思った。自然な感想だった。ひき肉の濃いソースが舌にぶつかり、味を伝えてくる。オリーブオイルやタバスコを足してさっきより単純になったその香りが、私の舌を包んで、鼻に抜けた。口いっぱいに頬張る。唾液に溶かされて味が薄まる前に飲み込む。すぐに、次の一口を食べる。そうすると、まさにエネルギーを補給しているという感じがして、生き返る心地がする。そして、美味しい! と思う。
美味しさを感じた私はAさんを見て、
「お腹が空くっていうのは、身体の危険信号なんですよ。」
Aさんの返答は求めていなかった。私は自分が納得するために、声を出していた。
「エネルギーが足りないって言っている身体に、精一杯、エネルギーをあげたいんです。」
「これが私にとっての、自分に対する愛で、食事に対する愛なんです。」
これが私にとっての食事なんだ。これが、私にとっての美味しさなんだ。
牛ひき肉がたっぷり入ったソースと、モチモチに茹でられたフィットチーネ。これらを次々に飲み込むと、タンパク質と炭水化物がたくさん摂れる。身体が喜ぶ。美味しい。そこへテーブルに備えられていたパルメザンチーズを大量にかけると、脂質が十分に追加され、食事の効率が上がる。
脂質にコーティングされて味がまろやかになったことを感じて満足して、何度か咀嚼して、飲み込む。大きいものが喉を通って胃に落ちていく感覚がして、食べたものが身体に蓄積されている感覚がして、やった、と思う。
パスタの味に飽きてきたのでスープを飲み始める。卵が入っている。塩の味がする。そしてパセリ、人参。
再びパスタに移る。口の中で肉が、野菜が、穀物が、弾ける。
パスタを食べ終えて、私はAさんの方へ視線を移した。彼の皿にはまだ数口分残っている。彼はまた、じっくり咀嚼して、飲み込む。
「見ている私の方が気持ち良いような食べ方ですね。確かに、君のような食事も良いのかもしれません。」
Aさんは結露して濡れたコップを手に取り、ゆっくりと水を飲んだ。
「満足しましたか。」
そう言って、また、冷めたきのこパスタを食べ始める。
今の私に、満足、という言葉を当て嵌めるのは、少し違和感があった。
確かに、お腹は膨れていた。しかし、完全に満腹ではない。苦しいが、まだ入る。まだ入るということは、私にとって、まだ身体が欲しているということだった。
「Aさんのおかげで、食事というものが分かった気がします。すっきりしました。」
咀嚼しながら私を見るAさんの瞳は、私に対して無言だった。
「ありがとう。今日は私が出しますね。」
店員を呼び、Aさんの好きなアイスコーヒーを頼む。そして、ポタージュスープと、ローストポークを注文する。
それが運ばれるまで、暫し空白の時間が生まれた。Aさんは今も咀嚼している。
私は、Aさんが手をつけていなかったサラダの皿をこちらに寄せて、食べ始める。まずは葉酸やカリウムが含まれたサニーレタスとタンパク質が多く含まれたささみ肉を一緒に食べる。次に、わかめのマグネシウムを食べる。緑色のカルシウムとオレンジ色の食物繊維を同時にフォークで刺して食べ、添えられた赤いビタミンCをつまむ。
それらの栄養が実際に入っているかどうかとか、身体にどれだけ吸収されるかどうかとか、そういったことは私にとって重要ではなかった。ただ、栄養を身体に入れているという感覚が重要だった。ただ、食べているという感覚こそが美味しさだった。
店員がやってきて、Aさんの前にコーヒーを置いた。私の前に豚肉とスープを置いた。
早速、私はそれを食べる。大きく切った肉を食べる。横に添えられた野菜を食べる。穀物を食べる。たんぱく質を食べる、カリウムを食べる、ナトリウムとビタミンB1を刺す、リンを掬う、マグネシウムを飲む、カルシウムを食べる、炭水化物を食べる、
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
