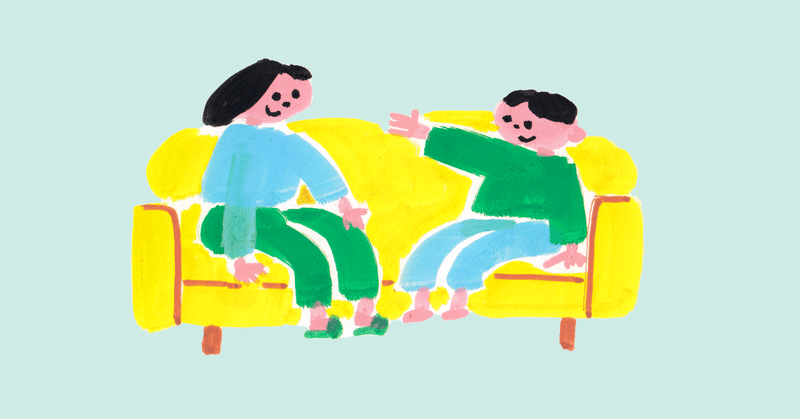
「英語で情報を伝え合う」という導入のやり方
最近気に入っている教材の導入方法があります。それが「英語で情報を伝え合う」というものです。参考にしているのは、
布村奈緒子『テキスト不要の英語勉強法』KADOKAWA
という書籍です。この本のなかで、布村先生は一般の読者向けに勉強方法を提案されているのですが、先生の授業のやり方も書かれており、やってみたいなと思ったものを取り入れています。
今まで、新しいユニットや読み物の導入をする際、準備に時間がかかったり、結局は生徒は聞くだけ、見るだけの受動的な授業にしてしまったりした経験がありました。また、ゲーム的なものをするのもあまり好きではありませんでした。
ですが、生徒に「英語で情報を伝えてもらう」という活動を導入に取り入れると、生徒が教材により興味をもち、新しいことを知り、また生徒同士でも「あの子はそんなことを知っているんだ」と新しい発見をする場面が見られました。そしてこの導入が、テキストの英文を読んでみようという意欲につながったように思います。
今回は、光村図書『Here We Go 2』のLet’s Read 2 “Meet Hanyu Yuzuru” というフィギュアスケートの羽生結弦さんへのインタビューをまとめた英文を扱った時の導入をご紹介いたします。
① 新出単語を確認する
② 扱う人物や出来事の写真または動画を少し見せる
③ ペアや周りのお友達と1分半話をさせる
④ 出た情報を発表してもらう
① 新出単語を確認する
まずは新しい単語の発音や意味を確認します。学校によっては、リストにして配布することもあるので、それを使います。実はこれが、すでに英文の内容のヒントにもなります。苦手な子はこのリストを頼りに、後半の活動に参加します。今まで習った単語のと関連、反意語、類義語も聞いたりしながらテンポよくいきます。
② 扱う人物や出来事の写真または動画を少し見せる
絵やイラスト、動画などの視覚教材は大いに活用します。デジタル教科書には関連した動画がはいっていることも多いので、活用すると良いと思います。時間もなく、動画もなければ教科書のUNITごとの扉絵に触れるだけでも楽しいです。
今回、羽生さんの題材には教科書の動画はなかったので、YouTubeから探しました。
Yuzuru Hanyu interview from CBC Sports
https://youtu.be/sR4P-dRvgk4
見せたのは冒頭から3分ほどのみです。羽生さんが英語でインタビューに答えているところ、そしてコアな思いのところは日本語で話している場面です。日本人が英語を話している場面は刺激になるでしょうし、日本語で話している部分もあるので、苦手な子もなんとか内容に集中できます。内容も本文に合っており、いい動画に出会えました。
③ ペアや周りのお友達と1分半話をさせる
ここまできたら、生徒に問いかけます。
What do you know about him?
そして、まずは、友達やペアと、あるいは1人で、羽生さんについて知っている情報があるか考える時間をとると伝えます。
その後出てきた情報を教えてほしい、できれば英語でチャレンジしてほしい、苦手な子は、単語リストをヒントにするのとを伝えます。そしてタイマーをセットし、よーいドンです。
布村先生の書籍では、この③はなく、高校生たちに、すぐに英語で発表させていました。しかし、公立の中学生にはいろんなレベルの生徒たちがいること、人前で発表することにまだまだ互いを意識してしまう(思春期真っ只中)生徒も多いことから、考える時間をワンステップ置いています。友達と話すことで自分の意見に自信を持てたり、少しあいまいな知識を友達に相談することで、次の発表につながりやすくなる効果を感じています。
④ 出た情報を発表してもらう
時間が来たら、英語あるいは日本語で発表してもらいます。出た意見は、マッピングのような形で黒板に書いたり、英文をどんどん書いていったりして、視覚情報として残しておきます。テンポを大事にしたいので、あまりキレイに書かず、メモのように板書しています。
得意な子は、英語で発表しようとします。うまく表現できたね、とほめます。日本語で言ってくれた情報も、簡単な文に直してクラス全体で英語にしていきます。あ!それ単語リスト使ったら言えそうじゃない?と言うと、勝手に気づいてくれることもあります。
羽生さんについて出た英文は
He is a figure skater.
He is from Sendai.
He likes くまのプーさん.
( Winnie the Pooh という原作のタイトルを知っている生徒もいました)
He got two gold medals.
He went to Canada to practice skating…
などです。ほとんどが中1レベルの英文です。でも、これらは、彼らが自分の知っている情報を英語で伝えるために、自分の中からひねり出した英文です。このようなことを経験させることで、英語を知っているだけでなく、使う力がつきます。
長く英語を勉強していても、簡単な英文が出てこない、という経験をした方は多いと思います。学んだ英語を使って、何かを伝える機会は日本にはあまりありませんし、いざ仕事で必要になった時に一夜漬けで何とかなるほど英語は甘くありません。ですので、その機会を今から作ってリハーサルさせておくのです。
この導入から、生徒たちは、習ったばかりの英語も、「英語で情報を伝え合う」ことに使えると気づきます。友達が言った日本語、英語を通じて情報を得ることで、「ああ、あの子はこんなこと知っているんだ」と思う子もいるでしょう。そうすると、その情報が少し特別なものになり、英語が頭に残るかもしれませんよね。教師からの一方的な情報ではなく、友達から伝わった、友達に伝えたという経験を英語を通して得ることができます。その英文につながるフックをいろんな形で残すことで、その英文にアクセスしやすくなるのです。そのような機会を、この導入で生徒に与えることができます。
今日は、「英語で情報を伝え合う」導入のやり方について紹介しました。
① 新出単語を確認する
② 扱う人物や出来事の写真または動画を少し見せる
③ ペアや周りのお友達と1分半話をさせる
④ 出た情報を発表してもらう
この導入方法を取り入れてよかったことは、生徒が自分の持っている情報を英語で伝えるということを通じて、既存の知識にアクセスする機会を増やせたことです。また、生徒からの発言を多く引き出せるので、授業にも活気がでます。ぜひ、試してみてくださいね。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
