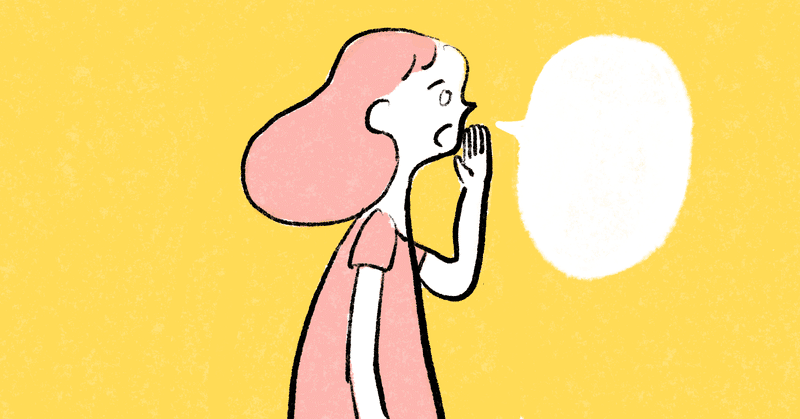
『脳が認める外国語勉強法』から、発音を学ぶことについて
ガブリエル・ワイナーという方が書いた本を読んだので、それについて書きたいと思います。”Fluent Forever”という作品を翻訳したものです。共感できる点もあり、なかなか真似できないなと思う点もありました。日本の学校で英語を教えるということにつながるヒントになればと思います。今日は、発音を学ぶことについて書かれた記述について、簡単ですが書きたいと思います。
①発音から始めれば学習時間は短くて済む
日本の小・中学校で英語を教える時、1番抜けているなと感じるのが英語の音に関する教育です。ただネイティブのような発音を目指す、ということを推奨したいのではありません。英語には、日本語に無い音がたくさんある。リズムも、息の量も全然違うので、教えてあげないと、英語がただの雑音に聞こえてしまうので、学習効率が悪くなる、ということです。
この点については、私も賛成です。10代のころ、中国語を4年半ほど学びましたが、最初の半年は発音の授業でした。先生の部屋で、自分の発音を録音してもらい、ここがこうだからもっとこう、というふうに具体的な指導もありました。結果、英語よりも中国語のほうが先に口から出る、という経験もしました。英語の方が学習歴が長いのに、です。
互いのストレスを無くすために、正確な発音やアクセントを学ぶ
このようなことも、著者は指摘しています。
外国語なまりが強いと、語学力(と知性)を実際より低く見られやすい。実に不当な話だが、その理由は理解できる。何を言っているのかよくわからない人や、自分の言っていることがちゃんと伝わっているのか不安になる人とは会話がしづらい。(中略)その人との会話そのものを避けようとすることもあるだろう。
ダイヤモンド社
これについては、もしかしたらいろんな意見があるかもしれません。でも、特にこれから英語を使っていくかもしれない子どもたちには、伝えてあげなければいかないと思います。子どもたちが出会ったことがある英語を話す人、特にAETのような方々は、ある程度日本に興味があったり(英語教育に熱意があるかは別かもしれませんが)、日本人の特性に理解がある方が多いです。ですから、子どもたちや、日本人教員が話す英語を「聞こう、理解してあげよう」としてくれていると思った方がよいでしょう。
しかし、それは残念ながら特殊な状況なのです。実際英語でのコミュニケーションの現場では、自分からアピールしなければ話も聞いてもらえないような状況もあるでしょう。自分たちのことを好意的に思っていない人とも、英語で話さなければこともあります。私が知る限り、生徒は英語を発音することに関して積極的だと思います。そういう状況を話してあげることもよいですし、話さずともいつの間にか基礎が身についているような、そういうことも理想かもしれません。
短いですが、今日は発音について書きました。中学校ではフォニックスの学習も入ってきています。でも正直生ぬるいな、と思います。もう少しいい何かがあればいいのにと思っています。それを探したり、作ったりしていかなくてはいけないと思っています。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
