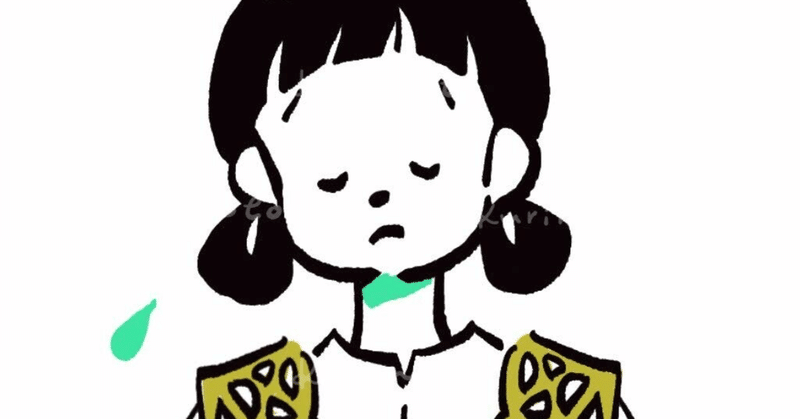
なぜその生徒は単語を覚えられないか
どんな教科でも、その教科が得意な子とそうでない子がいます。授業では、教科書をどんどん進めていかなくてはいけないので、その単元で出てくる単語や文法を十分習得できていない生徒がいたとしても、いつまでも復習に時間をかけるわけにはいきません。目の前で英語につまづいている生徒がいても、そのサポートに十分な時間をかけられないのが現状です。
生徒が英語が得意でないと感じる理由の中に、単語が覚えられないということがあると思います。そこで、生徒が単語を覚えられないのはなぜか、ということについて考えたいと思います。
なお、この記事は、アレン玉井光江先生の『小学校英語の教育法 ー 理論と実践』(大修館書店)を参考にしています。
①アルファベット 認識に時間がかかっている
②英語の音に対する気づきが不十分
①アルファベット認識に時間がかかっている
英語の文を読むには、単語を理解しなくてはなりません。そして単語を理解するには、その一つ一つの文字を認識する必要があります。このことについて著者は、
単語を覚えられない生徒は、単語の中の1つ1つの文字の確認に時間がかかり、単語全体で何を意味しているのか考える余裕もなく、単語を記憶するところまでたどり着けない
大修館書店
述べています。そんなレベルから?と驚くかもしれませんが、実はアルファベット という文字認識の時点から、つまずいている可能性があります。
私は毎授業の単語テストの答え合わせ(自己採点の形式)で、答えの単語を黒板に書きながら、スペリングをアルファベット読みで言わせることがあります。communicateだったら、スペリングは?と聞いて、生徒がc, o, m, m…という具合です。これをすると、意外とすらすら言える子とそうでない子がいることに気づきます。アルファベット の名前(例えばBの名前は/biː/)がその文字の音(例えばBの音は/b/)に関連しているので、
B/bを[biː]と読み、認識できる子はB/bで表される/b/と言う音についても早くから習得することができる
大修館書店
ことになります。ここに、単語を早く覚えることができる生徒と、覚えるのに時間がかかる生徒の差があるように思います。
昨今は小学校で英語が始まっているので、生徒たちは中学校入学時にアルファベットにある程度慣れているように感じていました。英語の音を発することにもあまり抵抗がないように感じていたので、昔のようにアルファベットを一からしっかり教えなくてもいいのではと考えていました。また、教科書のボリュームも増えたので、すぐに単語を練習したり、本文の内容に入っていったほうが生徒のためになるのではないかとも思っていました。
しかし、このアルファベットの文字指導の重要性を考えると、おろそかにはできないと感じます。英語が好きな子、習い事等で親しんでいる子もいれば、授業以外では全く英語には触れてこなかった子もいます。ローマ字は学んでいるにしても、後者にとっては私が思っている以上に、アルファベットの認識が負担になっているかもしれません。
②英語の音に対する気づきが不十分
英語を読むときに必要な要素の1つである「英語の音に対する気づき」(phonetic awareness )について考えたことはありますか。私は最近、この要素が、日本での英語教育に欠けているものであると考えています。日本語にはない英語の音をしっかり教え、それを聞いたり自分で発音したりできるところまで育ててあげる。これを土台として単語を覚え、文章を理解していけるように指導してあげると、テストで良い点が取れるだけでなく、英語をツールとして会話で使っていける生徒が育つのではないかと思っています。逆に言えば、この音の認識がしっかりしていないと、ただアルファベットが並んでいる暗号のようなものを覚えるという苦行を強いることになってしまうでしょう。現に、そのように苦しんでいる中学生はたくさんいるように思います。
音と文字との関係を教えるフォニックスについては、中学校入学の段階で取り入れている学校も多いと思います。ただ、これを学ぶことが生徒が単語を覚えることを助けているように感じたことはないように思います。c,a,tのそれぞれの音素を理解し、それらを合わせてcatと上手く発音することができる生徒は、中学校に入る前にある程度、英語の音を学んでいる生徒だけです。実際、入学して数ヶ月経っている時期に生徒から、「先生、英語ってなんなん?ローマ字と違うん?」と聞かれたことがあります。私はこの時、自分の指導力のなさを痛感しました。でも、彼に一から英語の音素レベルでの理解を指導するには、時間的な余裕はありませんでした。ですから、授業中の活動で困っているときに手助けをしてあげるくらいしかできることはなく、根本的に彼の疑問を解決することはできなかったと思っています。
今回は、なぜその生徒は単語を覚えられないのか、について書きました。
①アルファベット認識に時間がかかっている
②英語の音に対する気づきが不十分
この2つについてどのように解決していけばよいかは、別の記事で書いていこうと思っています。単語を覚えられないことについては、努力不足など、本人のせいにしてしまいがちです。ですが、彼らが日本語が母語である場合は日本語を話し、日本語の音をひらがなや漢字のような文字にしていくことができるように、英語の音と文字への理解も初期の段階から促してあげる必要があると思いました。その具体的な方法として『小学校英語の教育法ー理論と実践』にのっているリタラシー活動実践は参考になります。これから、どのように中学校の授業で実践していけるか、探っていきたいと思いました。
生徒たちへの単語指導について、困っていることはありますか?よければ、コメントで教えてくださいね。
①でアルファベット の文字指導をおろそかにしてはいけないと言いました。それと同時に、英語の音を音素のレベルで認識させてあげる必要があると思います。私自身も学校で誰からも教わったことがありません。ですが、自分が中国語を学んだ経験から、その必要性を強く感じています。
私は中学を卒業して入った高専で、中国語を4年半学んだ経験があります。最初の半年は発音をみっちり教えられました。先生は、私たちが将来仕事で使うことを想定し、話せるようになるための指導をしてくれました。卒業前に自信をもって話せる外国語は、英語よりも中国語だと感じていました。今ではすっかり忘れてしまっていますが、その時の、何かを外国語で言おうとしたとき中国語のほうが先に口に出る感覚を、今でも覚えています。
英語には日本語にはない音があり、それを認識するための訓練を、日本の子どもたちにしてあげる必要があります。その土台があれば、中学校以降で学ぶ文法や読解問題などが、テストのためだけで
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
