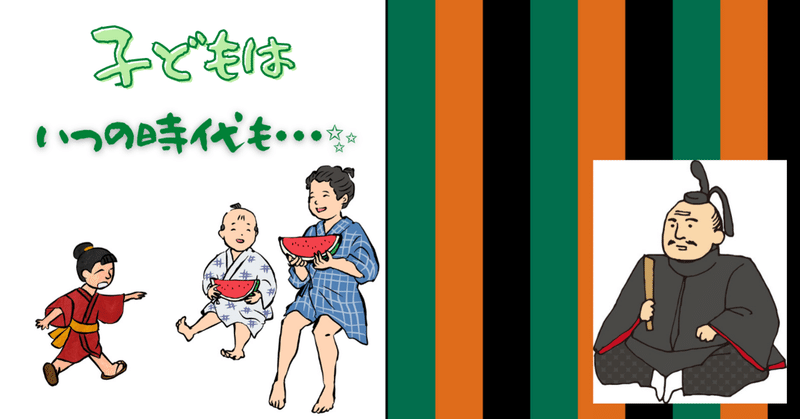
江戸時代の子育ての考え方に学ぶ①/小児はり☆
はじまり
鍼灸臨床の現場で小児はりを行っていると、両親の様々な子育ての方法や考え方、そして環境に対する工夫を会話の中でよく耳にします。子育てに正解や不正解はないと思いますが、とくにお母さんは、子どもの状況を敏感に察知しながら、時に厳しく、時に寛容に、子どもと向き合っています。
ネットやSNSで子育てに関して多くの情報が簡単に手に入る時代となり、便利にはなりましたが、その反面、核家族であることが多い現状において、周囲に気軽に子育てを手伝ってもらえる環境は少なくなっています。お母さん、お父さんへの心や身体への負担が大きくなっているのも事実です。
小児はりは、子どもの心や身体にあらわれた症状を緩和、改善するばかりでなく、子どもと一緒にその症状や状況に悩んでいるお母さんやお父さんの心と身体の負担も緩和、改善していくことができる方法です。
子育てにはマニュアルなどはなく、毎日がぶっつけ本番であり、それ故に悩みや問題も多く発生します。小児はりへ来院する期間が長くなればなるほど、両親との関係も深まり、多くの子育てに関する悩みを共有し、相談される立場となります。
そんな時に大切だなと思うことは施術者の知識であり、心の広さや温かさ、柔軟さ、心の配慮などの人間性であるのだと思います。小児はりを行うだけではなく、その心の営みにも脳みそを総動員して対応しなければなりません。
そんな時、ふと感じたことがありました。「学校などがなかった江戸時代は、どんな子育てをしていたのだろう?」と。そこにも、小児はりの臨床現場で役立つ情報があるのではないかと思い調べてみました。
日本は、江戸時代後期ともなると世界でも有数の識字率や教育力だったと聞きます。それも武家や裕福な身分の子どもばかりでなく、庶民の子どもにもある程度の教育は行われていたと言います。
興味津々です。
ここから先は
¥ 500
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
