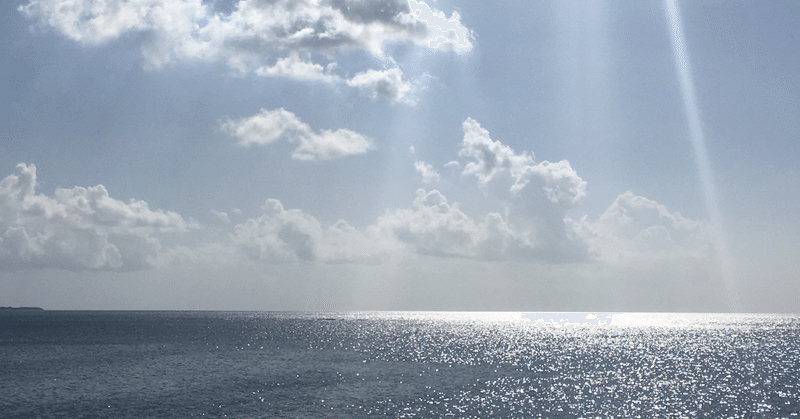
【私見】アフターマイナス金利における企業の資金調達面から見た影響
マイナス金利が解除されたが、その背景にあるのは日本の実態経済が利上げに耐えられる、というものではなく、過度に円安に振れた為替を是正したい、というもの。
ところが解除後も円安は続いており、このため更なる利上げが続くことを想定する必要がある。
このような環境下において、企業の資金調達面からはどのような影響があるだろうか?
2016年のマイナス金利導入、あるいは2013年の量的質的緩和以降、長らく続いた低金利の中で、企業にとっては利払が抑えられ、資金繰りに余裕ができていた。
また、企業が投資プロジェクトの検討に際したハードルレートは、企業自身が低コストで資金調達が可能なので目線感は下がり、低採算の案件でも着手できていた。
一方、金利がこれから上がることで、この二つのロジックが逆に回り始める。
つまり、①企業の資金繰りはタイトになり、またそうなると懸念する銀行が増えることで融資姿勢は厳しくなり、結果、資金繰りに行き詰まり倒産が増える、②資金調達のコストが上がるため、企業は採算の取れる投資プロジェクトを厳選する必要があるが、一方で資金調達コストの上昇見合いで高いリターンが欲しいジレンマに陥る。
②については、既に、上場企業においては東証と経産省の旗振りのもと、投資効率の改善が要請され取組む企業が増えていた。この流れが金利引上げを通じて非上場企業にも求められる、ということ。リスクとリターンのバランスについて、過去の低リスク低リターンでも許容されていた時代に慣れた経営層が多いわけで、リターン水準を引き上げればリスクも増えるところ、この増えるリスクを見極める分析能力が培えている企業は限定的だろう。ようは、リスクを見誤り失敗する事例が増えるだろう、ということ。
結果どうなるか?というと、資金調達が絞られる中で、正しくリスクが見極められず投資の失敗を重ねることで一層資金繰りがタイトになり、行き詰まり倒産する企業が増えるだろう。
加えて、上場企業は株主によるガバナンスが働き非効率な投資については是正を促す余地があるものの、非上場企業のガバナンスは幅広いステークホルダーではなく創業家や経営者といった限定的な株主によるもの。投資ファンドが入っている場合を別として、株主の面からは期待しづらい。
日本では、エクイティ的に資金をべったりローンで張る銀行がガバナンスを効かせるべきところだが、銀行員自身がリスクリターンのバランスの見極める分析能力を過去の低金利下で培えていないと考えるのが妥当だろう。ようは、ガバナンスが聞きづらい非上場企業ほどリスクを正しく見極めれず失敗する場合が増えるだろう。
もちろん、低金利環境下においてもリスクリターンを見極める能力を培い成長を続けてきた、あるいはこれから成長する企業もあるだろうが、そうではない企業が多数おり、そうした企業の淘汰が始まるだろう。
こうした考察をふまえて、企業と個人でどのような取り組みが必要になるだろうか?
企業については、まず経営層がリスクリターンを見極める能力があるかどうか認識し、ないのであれば外部から人を調達するか、調達できないなら投資プロジェクトは無理には進めない、という心づもりが必要。余剰キャッシュがあるなら株主に還元すれば良い。
個人については、こうした淘汰が始まることを認識し、自身の労働時間や資金を淘汰される企業に投資することは避け、生き残る企業に投資するべきで、そもそも、そうした企業を見抜くスキルを培う必要がある。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
