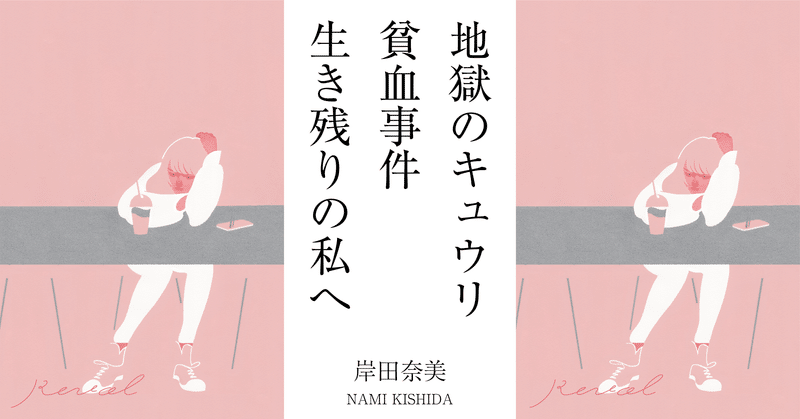
「地獄のキュウリ貧血事件」生き残りの私へ by岸田奈美
私が通う中学校に、話が長い校長先生がやってきたとき。延々と自分が若い頃にキュウリ農園で苦労をしたという話を聞かされ続け、何人もの女子が貧血でバタバタと倒れていく惨事があった。
後に伝わる「地獄のキュウリ貧血事件」である。
あのころの私は、本当に考えが浅かった。
不謹慎極まりないが、当時わたしは、朝礼で倒れることにただならぬ憧れを持っていた。さあ、さあ、私も華麗に倒れて保健室に運ばれるんだ。「わたし……まだ、まだ大丈夫です」って、健気なセリフの一つも吐いてやるんだ。
しかし私は「愛情をたっぷり込めたらキュウリは甘くなり、出荷されていった」というオチまで、しっかりと聞き終えてしまった。
愕然とした。自分から負けにいったつもりのサドンデスゲームですら、生き残ってしまった。
悔しくてその日の終礼で、わざと倒れたふりをしてみたけど、気絶とはほど遠く不自然にゴロリと転がってしまったので、急に柔道の受け身をとったと思われてしまった。
なぜ、そんなにも、朝礼で倒れたかったのか。それは、私が病弱なヒロインに憧れていたからだ。美少女戦士セーラームーンに出てくる土萠ほたるちゃんのような。土萠ほたるちゃんは、ミステリアスな美少女だ。身体のすべての線が細くて、病気がちで、表情も少ない。しかし、傷を癒やす能力を持つ土萠ほたるちゃんは、果敢に敵へ立ち向かい、健気にも仲間を支え続ける。
サウイフモノニ ワタシハ ナリタイ。中学生になった私の頭の中で、宮沢賢治が荒ぶっていたのだ。
しかし、どうだろう。実際の私は強靭で豊満な身体を持ち、喋るよりうるさい表情を浮かべ、傷を癒やすどころか毎日のように遊具でハッスルし傷だらけの鼻たらしであった。土萠ほたるちゃんとは対極に位置する。補色の関係である。
結局わたしは、小学校、中学校、高校と、一度も朝礼で倒れることはなかった。
大人になった私は、インフルエンザや胃腸炎などを経験し、さすがに健康が一番だと言うことに気がついた。病弱なヒロインへの憧れもなくなった。
でも依然として、貧血になったこともなければ、たいした生理痛もない。女の同僚や知人と話しているときに「生理痛きつくてさ、もう最悪」や「貧血気味なんだよね」という嘆きが聞こえると、大変だし、気の毒だなと思う。
一方で「もしかして私、女性として、欠陥があるんじゃ……」と、不安になる自分もいた。こんなこと、身体が丈夫なことの自慢や嫌味みたいで、誰にも言えなかった。
「そうだね、大変だね。わかるよ」と、深刻そうな顔でうなずいた。最後の一言は嘘だ。わからない。私には痛みがわからない。だから、不安だった。
ほとんど縁のなかった貧血が、ある日を境に突然、身近になった。
私の母が、入院してから毎日のように貧血で倒れるようになったのだ。
母は大動脈解離の手術をした後遺症で、下半身の感覚がなくなっていた。なにが起きるかというと、ひとたび身体を起こすと、上半身の血が下半身へ一気に流れ、戻らなくなる。感覚があったなら、血管がどうにかこうにか上手いことやって戻るらしい。人体の不思議である。
運ばれてきた病院食にありつくため、電動ベッドをちょっと起こしたら、気絶。
売店へ行くため、車いすに乗ろうと身体を起こしたら、気絶。
シーツを変えるため、看護師さんに抱っこしてもらったら、気絶。
人間ってそんなに何回も意識をリセットして大丈夫なのか。
はたから目撃していて、めちゃくちゃ不安になった。
これがスーパーファミコンだったら、セーブデータが消し飛んでいる。
しかし母のセーブデータは消し飛ばなかった。
その代わり目覚めると、脂汗をかいて「あかん、めっちゃしんどい」と息も絶え絶えにつぶやき、パタリと眠るのであった。
母の場合は「地獄のキュウリ貧血事件」が生徒にもたらした鉄欠乏性貧血ではなく、脳貧血という種類のようだったが、貧血のしんどさには変わりない。
「貧血ってそんなにしんどいん?気絶したらなんも感じひんのとちゃうの?」
ここぞとばかりに、私は聞いてみた。こういうとき、親子の関係性は便利である。
「しんどい。気絶するまでにけっこう気持ち悪い感覚が続くし、起きたら吐き気もすごいし、倒れる前にどっかぶつけてたりしたら痛いし。めっちゃ怖いねん」
私は、病弱なヒロインにあこがれていた過去の自分を恥じた。目の前で何度も何度も苦しみ、戦っている人を見たら、とてもつらい。
鬼気迫るリハビリをこなした母は、少しずつ、貧血になる回数が減っていった。
治ってよかった。しかし、安心したのも束の間である。平日の昼にダラダラ仕事をしていると、母の同僚から、私に電話がかかってきた。
「奈美さん!お母さんが倒れました」
頭が真っ白になった。
「講演の準備をしていたら、真っ青になって、車いすから崩れ落ちちゃって。今は控室で横になってて、意識もあります。本人は貧血だって言ってるんですが」
貧血。またお前か。
そうだ、もともと貧血になりやすい人が、気合いでそう簡単に治せるわけがない。
母はずっと、一人で不安と戦っていたんだ。
それでも働くしかない毎日に、身を投じていたんだ。
「奈美さん、どうしますか?」
「どうしますかって……どうしたら……」
情けないことに、私は完全にパニックだった。あわあわしていた。
電話を片手にオフィスをうろうろしていたので、デスクに腕や足をぶつけまくって、本の山などをなぎ倒す、なんの役にも立たない悲しき怪獣と化していた。
「あっ、もういいです。救急車呼びます。とりあえず急いで来てください」
ピシャリ、と電話口で言い放たれた。
この同僚、普段からめちゃくちゃ怖いのだ。オフィスの掃除を忘れていたら、妖怪人間ベラが爪で鉄塊を引き裂くときみたいな形相で怒られたし、書類を取り違えたら半日も視界に入れてもらえなかった。
冤罪でもおかまいなしにバチギレしてくるので、小心者の私は同僚を陰でベラ姉と呼ぶなどの反撃をし、距離を取っていた。
しかし、このときばかりは、めちゃくちゃ怖い同僚に感謝した。
同僚は怖いだけではなく、迅速な判断力の持ち主であった。
私が現場に駆けつけると、ちょうど救急隊員に運ばれる母と対面した。
おくるみのように毛布に包まれ、ストレッチャーに縛りつけられながら「奈美ちゃん、こっちこっち」と力なく声を発する母は、なんというかシュールだった。
思ったより元気そうだったので、衝動的に写真を撮ってしまい、同僚から「そんな場合ですか」とバチギレされた。
病院で検査した結果、やっぱり貧血だった。
少し休んだら元気になるという。入院も必要なかった。
点滴につながれ、ベッドに横たわる母と、しばらく話をした。
「私な、ずっと思っててん。みんな頭痛でも生理痛でも頑張って仕事してるのに、私だけが貧血なんかで休んで迷惑かけるわけにはいかへんって」
母はぽつり、ぽつりとつぶやいたあと、悔しそうに目を閉じた。
「でも結局倒れて、救急車まで呼んでもらって、迷惑かけてしもた。ごめんな」
「私はなんもしてへんよ。でも、ママがどんだけしんどいんか、私にはわからへん。ママが大丈夫って言う限り、倒れるまでなんもできへん」
なにもできない私も、悔しかった。
「うん。それは当たり前や。自分のことは自分にしかわからへん。周りの人を守るためには、まず自分を守らなあかん。守るっていうのは、自分の痛みと不安をちゃんと理解するってことなんや。わかってるのに、私はできてへんかったわ」
自分の痛みと不安を、理解する。
どんな病名がついても、どんな診断がくだっても。
世の中の何人が同じ症状を訴えても。
人によって、限界は異なる。
倒れる人もいれば、耐えられる人もいる。
しんどくなるかもしれない不安で動けなくなる人もいる。
だから結局は、自分で自分を守るしかないのだ。
その線引きに、正解も不正解もない。
「あのな。私、貧血とか生理痛とかないから、心配はするねんけど共感ができへんくて、それがずっと不安やってん」
思い切って私は、母に打ち明けてみた。
母はキョトンとして、それはそれは病人っぽい儚げな笑いを浮かべた。
土萠ほたるちゃんみたいだった。
「痛みに共感なんて、できひんくて当たり前や。奈美ちゃんは、マラソンめっちゃ好きな人に、マラソンはしんどくないから走れって言われて、走れるか?」
「いやや。絶対むり」
私はマラソンが嫌いすぎて、学校のマラソン大会を不正に欠席したり、禁止された近道をしたりしていた。真面目に勉強をしているというのに、なぜあんなにしんどい思いをさせられなければならないのか。
「でも世の中には、マラソンを走られへんっていう人の気持ちがわからん人もいっぱいおるねん。それは仕方ない。共感なんかできへん」
「じゃあ貧血や生理痛でしんどいって言ってる人にどうしたらええん?」
「そういう人もいるんやなって、認めるだけでええよ。病名とか痛みの程度とか関係ない。その人が痛いとか苦しいとか言ってる、その気持ちを絶対に認めること」
それだけ言って、母はしばらく眠った。
起きたらピンピンしていて、塩ラーメンとチャーハンを食べて帰った。
貧血や生理痛の苦しさをわからなくて、後ろめたかった私はもういない。
その代わり私は、苦しみを認められる人でありたい。
あなたが戦うなら、背中を押したいし。
あなたが休むなら、そっと守りたい。
だから元気になったら私を、どうか助けてほしい。
あなたがいないといつも失敗ばかりする、私を。
Written by 岸田奈美
Edited by はつこ
illustrated by aka

共感いただける方々と一緒に素敵なコンテンツを作りながら、貧血のない世界を目指します。応援いただけると嬉しいです。
