
苦い味の表現「ビールの苦み」
苦味は本能的に「毒の味」として認識されています。しかし、人生経験を重ねていくと「これは食べても平気なもの」と認識できるようになります。
苦みは微量でもノドの奥の方で感じ、呑み込まないで吐き出せる「味」です。コーヒーの場合、それを美味しいものとして味わい楽しむためには、学習が必要です。そもそも輸入文化であり、コーヒーの味風味の判断規準は日本人の味覚の伝統の中にはありません。改めて、適正なコーヒーの味風味を学び、身につけなければなりません。コーヒーを扱う者は、お客様にそれを伝え、消費者育成しなければなりません。
ビールの苦み
「IBU (International Bitterness Units) 」(国際苦味単位)
日本で一般的に飲まれているラガービール系統のIBUは「20」前後
バドワイザーIBU 10
アサヒスーパードライIBU 16
キリン一番搾り IBU 21
サッポロ黒ラベルIBU 21
サントリーモルツIBU 21
サッポロエビス IBU 25
上記の大手ビールと比較して
苦みが弱いもの
フルーツビールやヴァイツェン系 IBU 20前後以下
苦みが強いもの
ぺールエール、黒ビール系 IBU 30からIBU 50前後
バーレイワイン、IPA(インディア・ペール・エール)IBU 30からIBU 100前後
それで思い出しました。
クラフトビールバー5Tap
新しいテレビドラマのセット。(2018年後半「獣になれない----」)
店名は「ビール業界でタップはビールサーバーの注ぎ口の意味。例えば「12タップあるバー」は「12種の樽生ビールが飲める店」ということ」らしい。

5Tapの5Tapめは「----バーレイワイン(Barley Wine)とは、300年ほど前からイギリスで作られている高アルコールビールです。バーレイとは大麦のことで、バーレイワインの名はワインの如き芳醇な香りと高いアルコール度数を持つビールであることを意味します。一説には、ブドウが育ちにくい気候のイギリスにおいて、ワインに対抗できるお酒をビールで作り出そうとしたことで生まれたともいわれています。この名前が使われ出したのは19世紀末から20世紀初頭に入ってからで、それまではオールドエール、ストックエールと呼ばれるスタイルの中に含まれていました。強いて言うならば、オールドエールよりもバーレイワインの方がアルコール度数が高く、香りや味がより濃くワインに近いといえます。ただ、人によってはこれらの間に明確な区別はなく、バーレイワインはオールドエールの一部に過ぎないとする人もいます----」
この解説の前半を松尾マスターがセリフで。
ともあれグラスが次々変わり、なかなか物語に貢献しています。第4話は「よくある」「起承、転、結」の「転」のひとつでしょうか。野木さん、ずいぶん古臭い「転」じゃないかしら、いやノスタルジックな、なのかな。

野木亜紀子作「獣になれない----」終了。全10話。
古臭い「やおい」みたいな言葉を思い出しつつ。
ビール・バーで近所に住む男女が出会った、です。
主人公は全くの天涯孤独な女性です。何とか文京区の比較的安いアパートで暮らせるだけ稼いでいます。
ワインのようなビールを飲んでいましたが、最終回はIPAでした。徐々に「香りと苦みが非常に強い」ビールにシフトしていくのは、まあ面白く。
「当て書き」っぽく感じましたが、よくわかりません。そうなら、あまり「うまく」ないかしら。
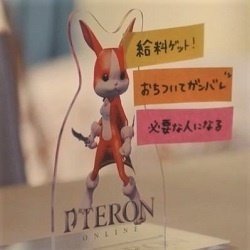
IPA と書いてアイピーエーと読む。インディアペールエールの略称で、18C末、インドがイギリスの植民地だったころに、インドに滞在するイギリス人にペールエールを送るために造られた。海上輸送中に傷まないよう、防腐剤の役割を持つホップを大量に投入したため、香りと苦みが非常に強い。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
