笑うバロック展(97) テノール独演会または「三大テナー」を探せ
バロック時代には独唱曲がどんどん登場し、宮廷歌謡、オペラアリアからモテットまで作曲されています。教育用の練習曲や、声のための協奏曲まで。
改めて調べてみると、思いのほかテナーの独唱CDが少なく驚きました。
もちろんもともとバスのソロなどは少数派のはず。とはいえ台頭してきたカウンターテナーの録音から比べると。そしてカウンターテナーが復興の一翼を担ったカストラートの分野が広がると、メゾソプラノの活躍が増えます。
声楽の中に占めるテナーの位置関係から、バロックの独唱だけでCDをだすテナーは、あまりいません。
特別なのは相変わらずバッハのカンタータの独唱アリアくらい。それでもカンタータ録音から抜粋編集したものが多いと感じました。コジェナーのソロデビューのような盤は男声にはどうもなさそう。
バロックオペラには欠かせないというようなテナーでも、同様。カストラート流行以来カウンターテナーではいきなりアリア集デビューという例もあります。
そこで、ひとりのテナー歌手の独唱中心のバロック音楽のCDを検索したり、聴けるものは聴いたりしてみました。
ナイジェル・ロジャース(1935-)のテノール独唱によるディンディア作品集「オルフェオの嘆き」。
特に初期バロック音楽を中心に活動した偉大なテノールが1992年にリリースしたもの。「うがい唱法」の啓蒙者だけあって「迷いのなさ」が伝わってきます。
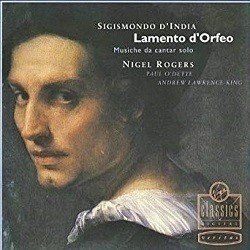
ロジャースはモンテベルディで活躍しました。次のジャン・ポール・フシェクール(1958-)は、フランスものに欠かせない人。ラモーのオペラアリア集などこの人ならでは。2007年に「痒いところに手が届く」ナクソスから。
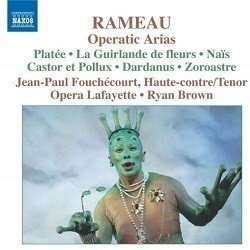
いつもあまりに淡泊にサクサク歌ってしまうので、よい声なのにちょっと残念なハンス・ヨルク・マンメル(1973-)。
フェニーチェとブクステフーデのカンタータ集「おお甘美なる時」。2007年リリース。
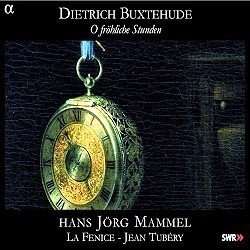
バロック声楽の「三大テナー」は上の3人です、って、うーんそれでいいのかしら。
プレガルディエンとかなさそう、テナーはリート方面に進出していってしまう傾向が強いかも。
しかしブンダーリヒとかローゼンミュラーとか録音していたし、探せばまだ何か見つかるかも。
もう少しつっこんでみよう----続く。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
