笑うバロック展(116) 招聘元よ、よりよく生きよ「トゥッティ」
アレグロ・ミュージックという興行会社の会員を一時。
会員向けに情報誌を提供していました。A4を3折した縦長の冊子で、要は封筒にピッタリ入るものでした。
(いまはダイレクトメールのニュースレター「ノン・ヴィブラート」を作成している模様)
何しろヒリアード・アンサンブルとタリス・スコラーズの招聘元。その後の古楽演奏会の発展に貢献したと思います。
武蔵野文化や王子の独自路線も彼らの活動が影響していると、思います。パーセル・カルテット招聘はオペラプロジェクトに発展しましたし。
アレグロは、ソティエという会社の流れだったような気がしますが。ソティエは、ギター系演奏会や、クイケン兄弟を招聘した会社でした。アレグロは1985年設立と。30年になるのですねえ。立派だと思います。
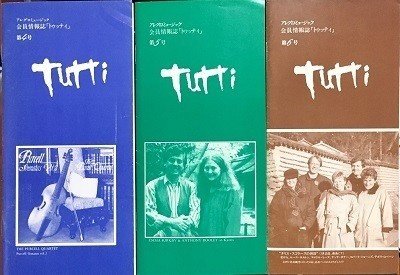
当時、大橋先生が3つのグループの紹介をしたエッセイ。偉い先生なのに、ご自分の分野の啓蒙のためには骨身を惜しまない方でした。
そして、何より短絡的に「わかりやすい」ことをきちっと避けて発言をされる方でした。
このエッセイもそうした先生の良さが出ているように思います。先生らしくきちっと「宣伝」してくださっているなあ。この頃CDの国内発売用に解説執筆も積極的でした。
ロンドン・バロックの日本公演は、ずいぶんと調律に時間をかけるグループなんだなあ、という印象が今も。
「通奏低音が、あたかも人の心の中心にあるべき倫理感・良心・節度のように中心に響き、上声二声部は、あたかも人の情念のように右に左に大きく揺れ動くかのように作られている----トリオ・ソナタこそ、イタリア・バロックが発明した<言葉を使わないオペラ>なのだ」
先生、この年齢になって、最近やっと何となく先生のいわんとすることがぼんやり「聴ける」ようになってきました。若い時は寝ちゃってました、すいません。
「トゥッティ」4号(1989年9月)
パーセル・クヮルテットの来日によせて----(大橋敏成)
パーセルのトリオ・ソナタ集(1683)(4つのパート譜のソナタ集〔1697)も含めて)は英国音楽史の金字塔。そのパーセルの名を戴いたのがこのトリオ・ソナタ演奏団体パーセル・クワルテットだ。これが今までになく本格的なトリオ・ソナタ専門グループだということは、いま英国の古楽演奏の世界で、もっとも重要な役割を果たしている生粋の英国人女流コンサートマスター、ソリストたちM.ハジェット、A.バリイ、C. マッキントッシュ、E.ウォールフィシュのうち2人までもが、このパーセル・クワルテットに加わっていることからも理解できよう。英国はルネサンス音楽のみならず、バロックの分野でも、規模においても質においても大陸のそれを凌駕せんばかりの昨今である。
17、8世紀のトリオ・ソナタの演奏解釈には、通奏低音の楽器編成法、ピッチ、調律、音程、弦の選択など、未だ解決されていない多くの問題がある。これは単に理論上の論議なのではなく、これが理想的に実践されると、驚くほどの美しさで楽曲が再現されるのだから重要なのである。昨年、英国の芸術振興会は、これらの諸問題を研究すべく奨励賞をこのグループに与えている。彼等の演奏の質の高さを考えると、その研究成果は大いに期待されるところだ。
今回の演奏曲目では、バロック室内楽のハート・ピース、ヴィヴァルディのラ・フォリアで終わるプログラムAは、ヘンデル、ロカテッルリ、パーセルと名曲ぞろいで索晴らしかろうに決まっているが、私には17世紀ドイツ弦楽の粋、ビーバーの作品をふんだんに、入神の演奏で聴かせるだろうプログラムBが待ち遠しい。何故なら、ビーバーはヴァイオリニストの心情に最も近い作曲家の一人だからだ。
さて、パーセル・クワルテットの魅力を一言でと問われれば、それは英国の音楽家らしい暖かい音楽ではないだろうか。しみじみとした緩徐楽章の演奏を聴いてみてほしい。演奏家というのは苦労人なのだな、とか思ってしまう。2人の卓越したヴァイオリニストのあらゆる意味での相互理解から醸しだされる暖かい音。しかもそれは聴くたぴに味わい深くなってゆく。
「トゥッティ」5号(1990年7月)
ロンドン・バロック来日によせるエッセイ(大橋敏成)
<J.S.バッハ、トリオ・ソナタ集>を聴いて
I.ザイフェルト(Vn)R.クヴィルト(Vn)C.メドラム(Ve)w.ハント(Vg)
J.トール(Gem)Sプレストン(Fl)Lベズノシーク(Fl)
(ハルモニア・ムンデイHMC901173)ANFより国内盤
この親密な世界、しかし今や、新しい提案をしたくなる。
バッハの「トリオ・ソナタ」をまとめて聴けるレコード・CDとなると、1980年録音のゲーベル、1985年録音のメドラムの二つぐらいしかないのではないだろうか。興味深いことにこの二人は、この曲集に限らず、同じような曲を前後して録音しあう傾向があるので、それに何といっても、ザイフェルトもメドラムも、かつては、ゲーベルの〈ムジカ・アンティカ・ケルン〉の中枢を担っていた音楽家達なので、ついこの二つの録音を聴き較べてしまう、音楽も性格も全く違う二人の演奏家のうえに想いを馳せながら……。このように書きだすと、両者の演奏比較論でこのCDを紹介するのかと思われるだろうが、僕としては、ゲーベルの凝縮された世界の方に心が傾きそうなので、それはさけて、ここでは〈ロンドン・バロック〉に『トリオ・ソナタ集』の録音についての新しい提案をしてみようと思う。
(二人とも、この語ってしかるべき事実を言いたがらない。とにかく1978年、チャールズとイングリットはケルンと決別し、ロンドン・バロックの旗挙げをした。二人が結ばれロンドンに本拠を移したことが、英国の弦楽に新風を吹き込むことになる。英国古楽界がバロック中心になるのはこの頃からなのである。)
かって僕は、くロンドン・バロック> の響きのユニークさについて次のように言ったことがある。「----それは通奏低音の芯となるチェロと、上声を歌うコンサート・マスターのヴァイオリンとの響きの絶妙な関係にある。メドラムのチェ口は、音程、アーティキュレイション、強弱、饗きの長短、音色の変化など、あらゆる点で的確この上なく、それを表現する奏法は、あくまでコンパクトで、無駄のない、実質的で、それでいてみた目に決して派手に写らないものだ。これは、弦楽技法から観察したやや専門的な説明だが、彼は身体の筋肉のある一点から発する、弦楽器の本質的な音をつくる理想的な方法を体得している希有の弦楽奏者だ。それにたいして合奏体の最上声部を受け持つ夫人のイングリットのヴァイオリンは、チェロのそれを、技法的にも音楽的にも、のびのびと拡大してみせるのである、チェロの弓が5センチ動けば、ヴァイオリンの弓は15センチ動くと言うように。これは<回転するレコードの中心の動きと円周の動きのような関係で音楽を作る> と言ったら、理解しやすいだろうか。身体を解放的に一回転するかのように、この楽団の音は響く。身体の中心から発する動きは小さいが、その強いトルクが円周の速さをつくるのである。
この現象を納得させてくれるのは、『パーセルのファンタジイ』(EMI CC 33) 、『シュメルツアー、ムファットのソナタ』(HMC901220) 、シャルパンティエ8声のソナタ、(HMC901244) 、などであり、特に『マレの音階』(HMC901105) であろう。すなわち、イングリットが合奏体の最上声部を受け持ち、チャールズが低音を受け持つ限り、それが何声の音楽であろうとこの音響は生まれる。しかし、トリオ・ソナタのような曲種ではどうだろうか。
トリオ・ソナタは、ご存知のように、対等の高音2声部とそれを支える低音部の三声部からなっている。この三声の関係は、通奏低音が、あたかも人の心の中心にあるべき倫理感・良心・節度のように中心に響き、上声二声部は、あたかも人の情念のように右に左に大きく揺れ動くかのように作られているのである。演奏する人の心の動きをこれほど引きだしてくれる形式はほかにない。トリオ・ソナタこそ、イタリア・バロックが発明した<言葉を使わないオペラ>なのだ。だから上声二声があるときは寄り添い、ある時は強く対立しなければならない。二人の個性豊かなソリストが必要なのだ。
〈ロンドン・バロック〉のようにメドラムとザイフェルトが主軸で動いているグループでは、どうしても情念の針が一方に傾きすぎるのである。親密さは伝わるのだが、対立する力が不足なのである。なかなか二人になれないもどかしさ、三人では一人多すぎる……。このCDでは、『捧げもの』 のハ短調トリオのように、大名曲で上声の二つが音色のちがうヴァイオリンとトラヴェルソによっていれば、対象が歴然として、余り問題にならないのだが、二つのヴァイオリンによる演奏では、同調する志向が強すぎる。そんなわけで、『マレの音階』でのような成功はここにはない(と僕は思う)。
さて、ザイフェルトは、遠大な家庭計画のために、ここのところしばしば黒崎ひろ氏にコンサート・マスターの座を譲っている。ザイフェルト自身が黒崎氏を選んだのである。彼のご父君はN響のヴァイオリニストであったが、ひろ氏を本物の音楽家に育てるぺく、ご自身ウイーン・トーン・キュンストラーに転職され、幼児から最上の教育をめざされた結果が今日のひろ氏である。1979年にクライスラ一国際コンクール第2位を受賞しているヴィルトゥオーソ・ヴァイオリニスト。技術の美事さ、音楽のすがすがしさ、それにこの楽団の音の理想をよく理解した解釈でほかのメンパーから尊敬を集めている。そして今や、ヨーロッパ古楽界でフリーのコンサート・マスターとしてもっとも評価の高い人なのだ。〈ロンドン・バロック〉のコンサート・マスターとしての演奏(ソロも含めて) は、『ヘンデル、アーベル…』(EMICDC7 49 7992)で聴ける。
さて、私の提案は、ザイフェルトと黒崎がメドラムをはさんで、このCDの曲目を再演してもらいたいということである。そうすれば、二人の個性豊かなソリストによって、きっと理想的なトリオ・ソナタ集の演奏が生まれるに違いない。そして、願わくば、日本でその演奏を披露してもらいたいと思うのだが、会員の皆様はどう思われるだろうか。
「トゥッティ」6号(1991年2月)
フレットワークwithキャサリン・ボット
なんて、美しい人!キャサリン・ボットの登場です。ヴィオラ・ダ・ガンバのアンサンブル、無限なる宇宙の響きを想起させるようですね。初来日といっても、ウィリアム・ハントはロンドン・バロックで、リチャード・ブースピーはパーセル・クワルテットのメンバーとしてお馴染みです。CDの売れ行きも驚異的、ヴァイオル・アンサンプルのプーム到来か!?彼らのCDは、アメリカのレコード店ではポップスのコーナーにも置いてあり、若者たちにも人気があるそうです。
フレットワーク来日によせて(大橋敏成)
〈フレットワーク〉とキャサリン・ボットの来日で、偉大な音楽遺産、英国コンソート音楽やコンソート・ソングが堪能できることになった。この分野の音楽は、日本でも一部の専門家やガンバ協会員によって演奏されてきたとはいえ、英国のこの道の大専門家によって紹介されるのはこれが始めてである。
ルネサンス・バロック時代の楽器は、その時代の音の理想が<人間の声> であったので、声楽アンサンブルにならって、同質の音で高音から低音まで得られるように、相似形の大小の楽器で家族のようにセットされることが多かった。その中でも、人の声のように表情が豊かで、表現が大きく自在なのがヴィオラ・ダ・ガンバ(英国にはヴァイオルViolという固有名があるが、今日では国際名称ヴィオラ・ダ・ガンバが使われている。以下、ガンバとする)であった。ガンバ族のための特別の合奏曲が、第一級の作曲家によって集中して作られたという現象は、1600年前後100年の英国をおいて他にない。おそらく、この分野の音楽は愛好家の需要によって書かれたものなのだが、にもかかわらず、その大きな特長は、内容が深く充実していることであろう。
1600年代の70年頃まで、ガンバは英国の市民生活の中で独特な役割を演じていた。裕福な市民や知識人たちは、大小6台からなる1セットのガンバ(Chest of viols) を揃えていて、友人達を招きあっては合奏を楽しんだと言われている。弾いた曲は、ファンタジアや舞曲の形式をかりた合奏曲。これらはルネサンス風に対位法や模倣を主に展開していくもので、演奏技術の要求は高くないが、織綾が精緻にできていて、最上声部が主役というのではなく、各々のパートが大きく主張するというか、シェイクスピア的というとちょっと大袈裟だが、脇役でもしゃべっているときは自分が主人公というような曲ばかりなのである。そしてそれらの曲を楽しんだのは宮廷人、大学人、知的な市民であり、そのなかには時の為政者チャールズ1世やクロムウェルの名すらあるのだから、現代人が忘れてしまった私たちとは違う内実が、彼らの人間関係を規定していたに違いない。17世紀中期のリュート・ガンバの大切な教本、T.メイスの『音楽の記念碑 Musick's Monument 』は、ガンバのファンタジアについて、いみぢくもその内容を「いわば、この中にはたくさんの悲壮的な話や、修辞的かつ崇高な講義、微妙でしかも鋭い議論、心の内面にとって非常に適応する心地よいもの、魂のために大切な内密さ、そして知的な力、などが含まれていて、その真価を言葉で説明することは難しい」と説明している。
『イン・ノミネ』ついて
英国1600年前後のガンバ合奏曲のレパートリィを見渡すと、『イン・ノミネ』と題されたファンタジア風の曲がしつように現れるのに気づく。これらの曲は、一つの声部が長い音符で引き伸ばされた節、すなわち定旋律を弾く間に、他の声部が模倣や対位法でこれにからむという書法によっていて、いわば、ルネサンス期のミサ曲の器楽版なのである。一般にこの手の曲種では、使われる定旋律の題名がニックネームとなって呼ばれるが(13,20のように)、『イン・ノミネ』に使われている定旋律は、グレゴリオ聖歌のアンティフォナ『グローリア・ティビ・トリニタス』 なので、どうしてそれがイン・ノミネと呼ばれるのかが、専門家のなかでも、長いあいだ謎とされてきた。これが1950年代に、二人の学者によって同時に解明されたのだが、それによると、『グローリア・ティビ・トリニタス』を定旋律とするJ.タヴァナーのミサ曲(1540年代、CDはザ・シックスティーンNSC 107で聴ける)の中に答が隠されていたのである。すなわち、このミサ曲のベネディクトゥスの一部分にイン・ノミネと歌う4声の部分があるが、これがあまりにも美しいので、これをそのまま合奏曲に転用したのがその起こりだというのである。やがて、それを範として、その同じ定旋律を使った同種の曲が、合奏・鍵盤・リュートのために作られるようになり、それをタヴァナーのオリジナル曲の歌詞に倣って『イン・ノミネ』と呼ぶようになった(定旋律として『グローリア・ティビ・・・』を使っているのにもかかわらずである)。
作曲は1550年代から活発になり、それはパーセルの時代までも追求され続けた。ガンバ音楽の響きに安らぎを求める人は、『イン・ノミネ』の演奏に耳を傾けることや、自身で『イン・ノミネ』の演奏に参加されることをすすめたい。ガンバを習いはじめた人のためには、演奏容易な定旋律のパートがリザーヴされているのも、この音楽作りの世界の嬉しさである。
1989年12月に来日したパーセル・カルテットは、清水、佐倉、松本、京都、富山、東京で7公演。4号の表紙はシャンドスのパーセルのソナタ集。裏はシックスティーンの「メサイア」。
1990年ロンドンバロックは、福井、各務原、東京、京都、大阪、東京、町田、東京と11日間8講演。
フレットワークは、1991年6月に9日間6講演。黒石、清水、富山、佐倉、大阪、東京。清水、富山、佐倉など、おそらく招聘元と良好な関係があったと思われます。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
