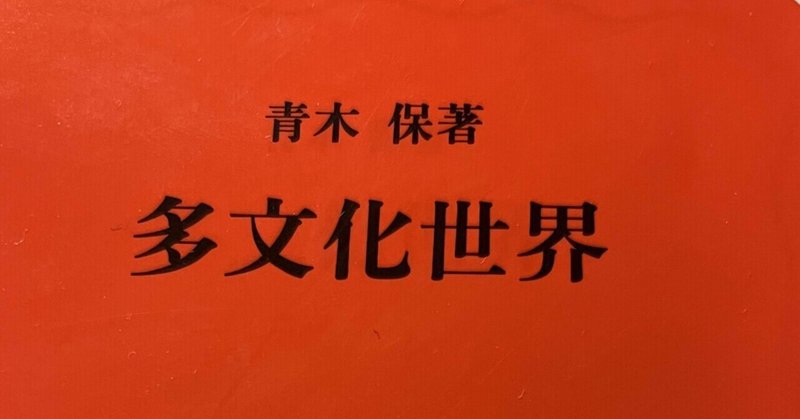
青木保氏の『多文化世界』4
前回までを振り返ります。1では、なんとなく国際社会化することは良いことだという私の考えが甘いということが分かりました。そこで2では、国際社会化よりも具体的な多文化共生について考えみましたが、これについても問題点がありました。3で、1.2を通して、多文化共生社会の具体的な実現方法を考えてみました。今回4では、その実現に際しての注意点について考えます。
かつて、アイザイア・バーリンという思想家がいた。彼は、われわれ人間の問題に対して、一つの解決方法しかない、それが「究極の解決」であると思い込むあるいはそういう見方や思想を信じること自体が反人間的な行為であって、「理想の追求」の際には注意深く冷静にかつ批判的にならなければならないと考えた。
個人一人が幸福になっても他人はそうはならないし、自分はこれが正しいと思っても他の人は必ずしもそうは思わない。人間と社会にはいろいろな選択肢があって、それを調整することに意味はあっても、一つの解決だけをある個人が他人に押し付けることは非常に大きな弊害を招くと筆者は考える。ごくごく当たり前のことだ。
バーリンは考える。いくつかの価値は衝突せざるを得ないと。「最終的解決」それに伴う「最終的価値」を我々は求めるが、そもそも価値は統合することは出来ないので、「最終的価値」自体が矛盾しているという。「最終的解決」の可能性は幻想であり、しかも極めて危険な幻想であるらしい。どういうことか。もし、そのような最終的解決が可能だと本当に信じるなら、それを得るためにいかなる犠牲を払っても惜しくはないと考えるようになるからだとバーリンは考える。ヒトラーのユダヤ人虐殺などがその具体例だ。
「理想の追求」自体は必要なことと筆者も考える。たた、その際には注意深く冷静に批判的になることが求められる。筆者は、グローバル化が進展する今日では、さまざまな価値や原則にどこかでお互いに折り合いをつけながら、共存する方向を何よりも優先させていくことが重要であると考える。一つの解決方法しかない、それに全部従えという方向は、たとえその方法が民主主義的なものであっても、時として非常に危険な結果を招く可能性があると考える。
筆者自身は言及していないが、1でも取り上げた同時多発テロにおいても、結果これと同じ原理が働いたのではないかと私は思う。アメリカは、世界の同一システム化が唯一の解決方法だと思っていたのではないか。結果、イスラム教徒たちはこれに反発してテロが起こった。「理想の追求」に際しての注意点として、一つ前の段落で「一つの解決方法しかない、それに全部従えという方向は危険だ」というバーリンの考えを載せたが、その具体例が同時多発テロな気がする。
私も、何かを実現したいと主張している身として、ぜひバーリンそして筆者の考えを参考にしたいと思った。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
