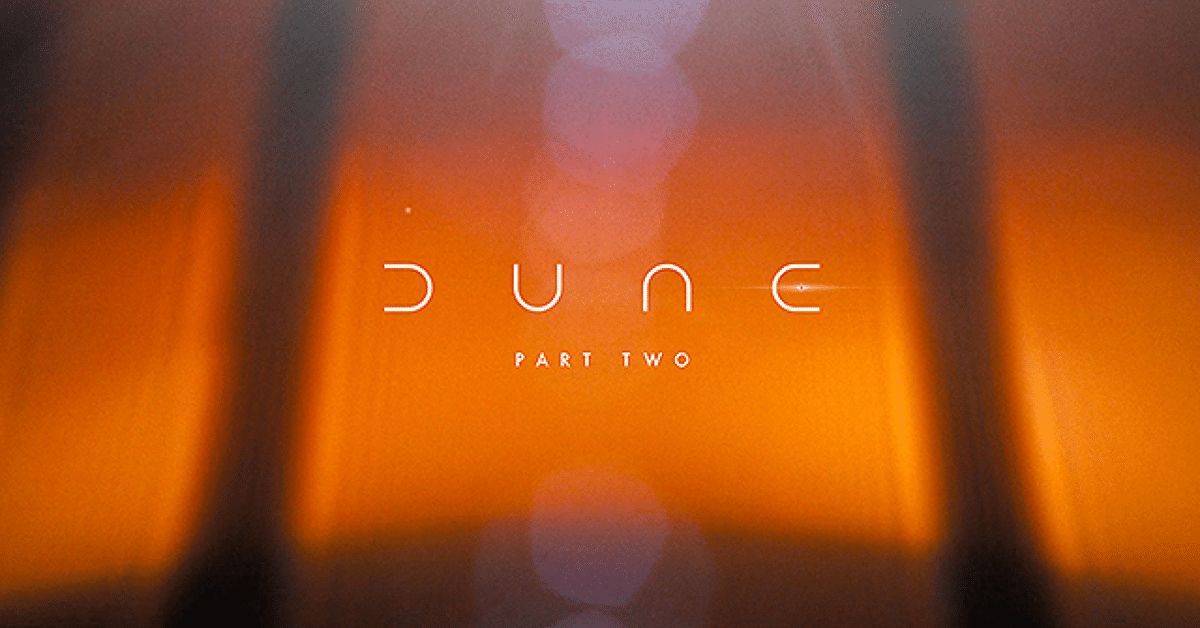
『OPPENHEIMER』と『Dune part two』を鑑賞。
ここ最近話題の洋画大作『OPPENHEIMER』と『DUNE part two』をそれぞれ公開してから数回劇場に足を運んだ。どちらも監督が非常に秀でていた作品であった。いくつかの要素を提示しながらそれぞれの作品の良さについて述べていこう。
まずIMAXで見るべき作品としては『DUNE part two』の一択である。全編IMAX画角で見ることができ、アスペクト比を気にする必要もないため画面に集中できる。砂虫の大群のシーンをはじめ、あらゆるビュジュアルが映画館でしか再現不能の大画面に展開されており、そこに大音響が加わることでまさしく現代の映画体験としてふさわしい一作であるからだ。
一方の『OPPENHEIMER』はIMAXで見ても面白いシーンはあるものの、当作品は会話劇を軸としておりそのシーンにおいては機材の都合上台詞を拾うに大変困難を極め、どうしても通常のシネマスコープで撮るしかない。そのため、トリニティ実験や前半の成り行きを描いていくオッペンハイマー氏の天才を描写するパートは十分に満足な画として楽しめるのが、後半になるにつれて通常のシネマスコープパートが増えるため、アスペクト比が都度変わる。これが非常に気になる。ノーラン監督はご存知の通りIMAXでの撮影の先兵的な立ち位置にいるため、会話劇においてIMAXが通用しないこともおそらくは分かっていただろう。それは撮影監督のホイテ・ヴァン・ホイテマもおそらく同じ。ただ、そこまで凝ってIMAXで見る必要性があるかといえば、正直無理してみなくてもいい。通常のシネスコープでみたほうがアスペクト比の移り変わりもそこまで目につかないため集中できるはずだ。
作品の感想としては、『DUNE』はSF小説の大家というべき存在であり、もはや作品の伝説さを今更書く必要性もない。yahoo映画レビューで先行上映でみた感想を投稿しているので詳しくはそれを探してみていただきたいのだが、ここで改めて整理すると第一部の序章というべき『砂の惑星』の後半の映像化にあたるが、脚色した部分含め圧巻であった。前作の段階で編集と脚色がかなりうまく機能していたため、当然『part2』もその領域か、あるいはそれ以上の作品として発表されることは想定していたものの、予想を遥かに上回る原作忠実度とのちの展開を全て把握している原作勢でもあるヴィルヌーヴ監督だからこそ、妹アリアのパートと、チャニ描写が原作とは異なる展開を迎えたのだろう。それによってある種の現代性を帯びている作品としてみることも可能になっている。この調子であの悲劇的な『砂漠の救世主』をどのように映像化するかが今からとても期待できるポイントだ。最もヴィルヌーヴがこれから撮る作品で最重要になる作品は『宇宙のランデヴー』であることに違いないのだが。『arrival』と同じトーンで描くことができたのであればその時こそ、SF映像主義の金字塔『2001年宇宙の旅』クラスのものが出来上がると確信している。やはり『インターステラー』ではダメだと思うとか、そういうことも考えてしまった。
結論をささっと書くのであれば今の最前線をいく監督の一人であることを真っ向から思い知らされた。そんな作品でした。
『OPPENHEIMER』は原爆の父ロバート・オッペンハイマーの生涯、というよりも紆余曲折の人生を描く物で前評判としてかなり評価が高く、また題材から大きく注目を集めた作品だ。日本ではヒットメイカーのノーラン監督の作品であること、そしてオスカー主要部門を受賞した作品という箔もついた上での公開だったため、身構えた人も少なからずいたはずだが、そう思った人ほど肩透かしを感じたのではないか。つまり原爆についての映画としてみるスタンスでスクリーンを見ていたらその実、描かれる内容はソ連のスパイ疑惑についてのパートが大半を占めていたことについて、「赤狩り映画ですか」と思った人は多いということである。自分も例に漏れず最初に鑑賞した際真っ先に色々な意味で想定していた内容と幾分か違うということだ。本作を映画評論的な形で形容するのであれば宮崎駿監督の『風立ちぬ』と黒澤明監督の『羅生門』そして『十二人の怒れる男たち』で知られるシドニー・ルメットの社会派映画という印象だ。これが第一印象。二回目を鑑賞した際は、登場人物がどのような人物なのか、という点を頭にいれて鑑賞したのが、ラストに名前だけで登場するジョン・F ・ケネディの存在がかなり重要ではないか、ということに比重をおいて本作品を再考したところ『OPPENHEIMER』の精神的な続編として『VON BRAUN』という映画を作ることでアメリカの歴史を映画という媒体を使って巧妙に伝えられる一編を作れるのではないか、という点だ。アメリカとソ連の競争という意味では六十年代にはいり「十年以内に宇宙に行く」とケネディ大統領が宣言したことで宇宙開発競争が始まったと言っても過言ではない。そしてその軸に登場する重要人物はロバート・ゴダード(米)でありコンスタンチン・ツィオルコフスキー(露)であり、ヘルマン・オーベルト(独)そしてセルゲイ・コロリョフ(露)とヴェルナー・フォンブラウン(独)のという二人の関係性が組めるのである。言ってしまえば『OPPENHEIMER』で登場した独のマックス・ボルン、ヴェルナー・ハイゼンベルグといった立ち位置に上記の登場人物がとって変わるくらいの感覚で描けるのである。世界初を成し遂げた「スプートニク一号」をはじめ、数々の記録を残したソ連と人類初の月面着陸、そしてNASAにつながる米国という構図も今振り返ればそこまで想像に苦労することもない。なぜ『OPPENHEIMER』でここまで逸脱した、恣意的ともとれる解釈を延々書いているかというと、V2ロケットの描写がそのまま作中に登場するからである。V2ロケット、すなわちペーネミュンデ陸軍兵器実験場で開発された代物であり、その製作指揮をしたのはフォン・ブラウンなのである。つまり劇中に言及さえないものの、見えない行間として登場しているのだ。それがICBMとなり、、という描写が描かれているのが、オッペンハイマーの幻視であるとはいえ、怖いというのが本作の恐ろしさでもあるのだが。
あと『ベストアンドブライテスト』も映像化したらやっぱりアメリカの歴史ノンフィクションとして面白い気がする。
以上のように、自分として『OPPENHEIMER』が主題となるテーマとは別方向の気分で見てしまっているところが多く、その路線で作品を解釈するとより面白い作品として考えることができるので数多くの人が想定したような感想とは少し違うものになってしまった。が、作品というのはオープンになった以上どのように解釈されても良いものであると思うので自分が感じた感想をこのまま貫いていきたいと思う。『OPPENHEIMER』は自分の中ではそういう作品になりました。
結論としては両作品とも非常に面白い作品であった。『DUNE』に関しては、個人的な二大マイベスト小説の一つということもあり(アイザック・アシモフの『銀河帝国の興亡』)なので、言わずもがな脚色されていながらも軸はかけていたのでやっぱり大傑作だとおもうしヴィルヌーヴはやっぱり信用できる。近年こそ大作が目立つが、こういう監督になれてしまうのも初期〜『arrival』までのフィルモグラフィーの秀逸性を踏まえればやっぱり当たり前だと思う。
『OPPENHEIMER』は色々と解釈を広げると個人的に面白い映画として鑑賞することができたので概ね満足といったところです。
今やこのように映画体験として得られる高揚感のある作品というのは滅多にお目にかかれないため、このような作品がしっかりと公開され、楽しめるという贅沢ができる現代に感謝をしつつ締めとさせていただければと思います。
では。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
