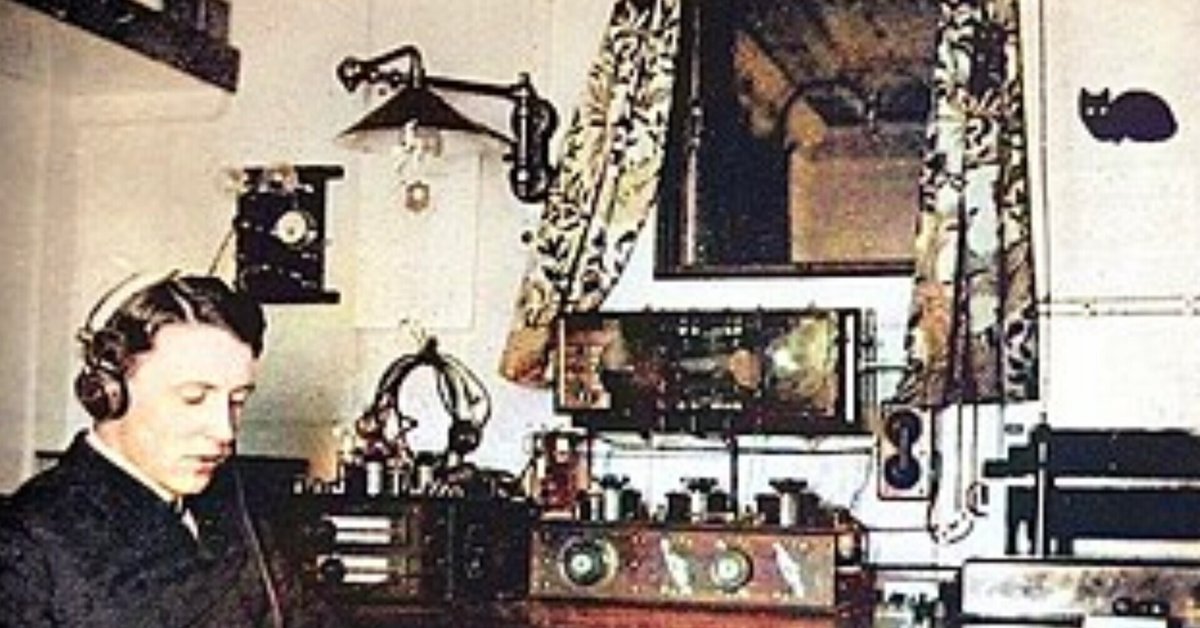
船舶の通信士になる為には一体何をどうしたらいいのか???②
こんにちは徒然です、現役の通信士であるわたしが通信士になる為の方法を説明していきます。前回の『船舶の通信士になる為には一体何をどうしたらいいのか???①』はご覧いただけましたでしょうか?②ではより具体的な説明をしていきたいと思います。(画像は前回と同じく拾い物です)
①の終わりに、通信士関係の海技士資格で必要な要件は
・対象の無線従事者資格
・乗船履歴
・船舶局無線従事者証明
・必要な講習の受講
と書きました。今回は『対象の無線従事者資格』というものを詳しく説明していこうと思います🙂
⛴通信士関係の海技士(通信 or 電子通信)は海技士(航海),(機関)と違い、まずは無線従事者資格の取得をしなければ海技士試験を受けることができません。航海や機関の海技士を取得したい方の多くはまずは4級、3級あたりから取得するというのが一般的です。(多くの海事系の学校はその取得のためのカリキュラムを組んで卒業時に海技士を取得する、という流れになっています)
(いきなり1級からとったらいいじゃないか??)というの向上心強めの方がいるかもしれませんが、航海と機関の2級1級はいきなりは取れないシムテムになっています。本筋から外れるので省いて説明しますが、2級1級は相応の職務歴が必要なのでいきなりは取得できません。3級を取って職務歴をつけた後2級1級を取得していく、という流れです。(先に2級1級の筆記試験を受けることはできる)
航海/機関の海技士資格は、(各級の筆記試験に合格)+(各級に対応した乗船履歴)、これを基に各級の口述試験(試験管からの質問に口頭で返答をする試験)を受けて初めて合格になります。中には3級海技士のための海自系の学校在学中に2級1級の筆記試験を合格する方もいるようで(優秀ですね)、ですがまだ職務歴がないので海技士資格としては扱えません。(2級1級の筆記試験を合格してると就職に有利に働くことがあるそうです)
ですが、通信士の海技士試験は相応の無線従事者資格がないと受験資格すら与えられません(必要なのは無線従事者資格だけじゃないけど・・・)
予め資格を取ってからさらに資格試験??なんか不利だな・・・、と思われるかもしれませんが特に有利不利はありません。(理由はまた今度)ここまでは現役の海技士資格取得者なら知っていることだとは思います。
無線従事者の資格のみでも船舶の無線操作はできますが(級によって操作できる無線機は色々)無線従事者資格は海技士資格ではないので、海技士資格がなければ船舶職員になることは絶対にできません。
通信士になるための海技士は海技士(通信 or 電子通信)ですが、相応の無線従事者資格によって自ずと種類と級が決定します。
その相応の無線従事者士資格というが
・1/2/3級海上無線通信士(4級というものもあるけど、価値的に省略)
・1/2級総合無線通信士(3級もあるけど価値的に省略、2級も怪しいけど☠️)
この5つです。この資格を基に、
・海上無線通信士(以下、海通)を海技士にした場合→海技士(電子通信)
・総合無線通信士(以下、総通)を海技士にした場合→海技士(通信)
になります🙄。例えば1級海技士(電子通信)には1海通が必要です。(わたしは1級海技士電子通信です、海通で海技士(通信)を受験することはできません)。したがって通信士になるにあたっての最初の関門はこの『各級の無線従事者資格の取得』になります、これがないと何も始まらないです。
『それならとにかくまずは無線従事者資格取ればいいんだ🙂???』なんですが、試験問題を見て100人中100人が(あ、無理)となるのが現状です。航海士や機関士はなんとなく大変そう、でも通信士ならいけるかも??と思って覗いてみた方もいるかもしれませんが、わたしの周り(現役の航海士含む)で無線従事者試験にトライした人は1人もいません。わたしも初見は(あ、無理)でした、問題の意味がわからない、問題の専門用語がわからない、、、かなり絶望した記憶があります。振り返ると第1ステージでいきなりラスボスが来たようなところでしょう。
自分の話で恐縮ですが、わたしは1級の海通、総通と1級陸上無線技術士を取得していますが、無線関係で最初に取得したのが3級海上無線通信士(3海通)でした。どの資格もひたすら勉強しなくてないけない科目は無線工学なのですが、当時の勉強法は(意味わからんけど😥、とにかくやろう)(意味わからんけど😥、とにかく覚えよう)というものでした。1月から勉強して、3月の試験合格に標準を合わせとにかく過去問をひたすら覚えた、そんな記憶があります。わたしは船舶関係だけでなく物理や電気などの工学系も全くの知識がなく(文系なので🙄)、最終学歴は高校です。高校卒業当時は大学にも進学せず、何もしていませんでした(バイトくらい)。なんとなく誘われた船に遊びにいきながら仕事をさせてもらい、大学に進学しなかった後ろめたさからくる陰鬱とした気持ちを無線の資格試験に向けることができたことは幸運でした。わたしのTwitterにて『必要なのは参考書と気合と根性』と表現したことがありますが、試験問題を見ればその意味は少なからず理解できると思います。
3海通の試験科目は無線工学、法規、英語、通信術の4つで別の機会でまたそれぞれ詳しく説明しようと思いますが、工学の対策としては海通の各級の過去問を解くことに尽きます。取得は3海通でも1海通でも構いませんが、無線従事者資格の取得が最大の難関ではありますが、これがないと始まりませんので通信士になりたい方は取得あるのみ、取得には勉強の継続あるのみです。
通信士無線従事者資格の試験問題は試験主催者である日本無線協会のHPから確認できます、(なんだ楽勝じゃん)と思われた方は凄いです。
ちなみに、通信士の海技士免状が取得できるカリキュラムを持った養成学校はないのか?と言いますと・・・ありません☠️(わたしの知る限り☠️)。ですが一部の水産高等学校の専攻科課程から無線従事者の資格が取得できるようです。本当はいろいろあるといえばあるのですけど、最終的に1海通/1総通は自力で取る以外はないと思います。
そんな中おすすめをするならば2海通を取得することです。まず3海通を取り、その後2海通にチャレンジするというのが現実的な方法ではないかとわたし個人は考えています。『1級以外価値ないぞ!!』とおっしゃる方もいるかとは思いますが、船舶未経験の人間がたどり着ける現実的なところを鑑みればご納得いただけるのではないでしょうか?2海通は2級海技士(電子通信)の海技士試験に必要ですが、2級海技士になるならこれくらいのレベルの問題を解くのは当然ともいえます(個人的にはその割にお手軽ではあるとは思う)。この記事の中で航海/機関は3級取得後でないと2級/1級は取得できないと言いましたが、通信/電子通信はいきなり1級/2級海技士を取得することも可能です(わたしはいきなり1級海技士(電子通信)を取得しました)(2海通はいいですよ、GMDSS船上保守対応資格ですし)←これの説明もいづれまた😉
というわけで、今回は船舶の通信士になるにあたって絶対に必要となる海技士免状最大の関門、無線従事者資格について説明しました。無線従事者資格がなければ通信士関係の海技士試験を受けることは絶対にできません。取得は大変ですが100人諦めるところ諦めなかったたった1人になりましょう🤗
TKS BIBI OUT
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
