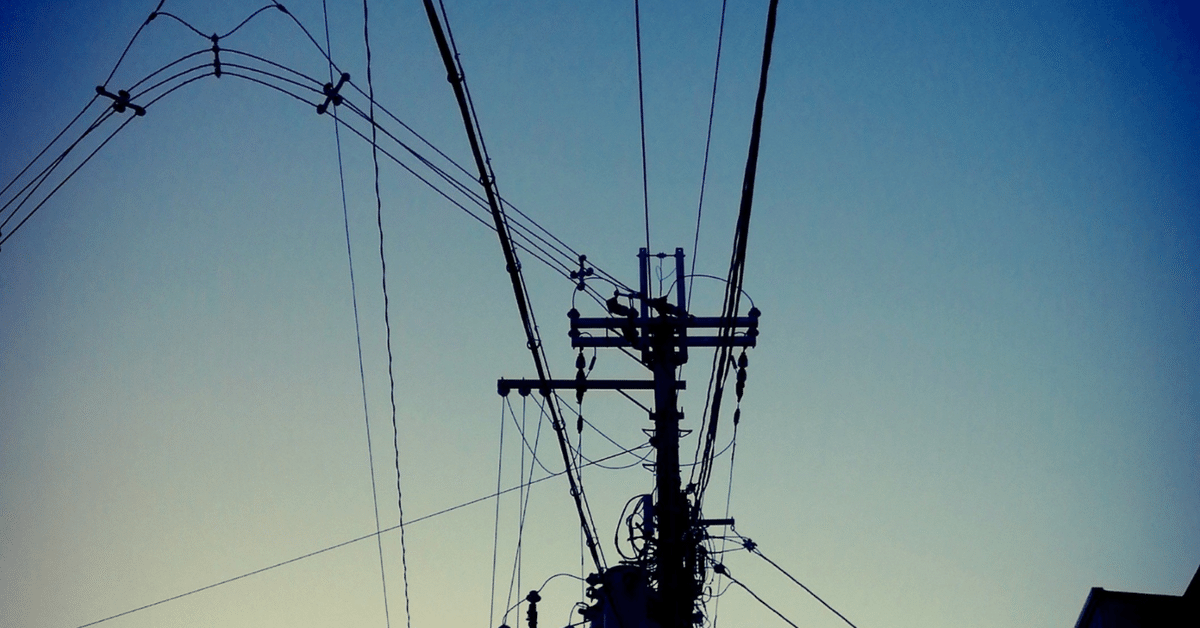
怪談師には憑いている(第二章)
第二章 怪談は生きている
「いやあ、ラッキーだったな。おれ、このライブのチケット争奪戦に負けてさ。柳瀬さまさまだ」
七種先輩は鼻歌なんて歌って、近年まれにみる上機嫌だ。
「そんな大げさな」
「大げさなわけあるか。こういう箱は入れる人数少ないしさ。まして怪談王子を間近で見られると来たらチケットなんて瞬殺ってもんだ」
そういうものなのだろうか。
現在、わたしと先輩は渋谷のとあるライブハウスに来ている。
――よかったらこれどうぞ、ペットボトルのお礼です。
怪談蒐集の帰りぎわ、そう言って蓮見さんがくれたのは、怪談ライブのチケットだった。
ワンドリンク制のため、わたしはアイスコーヒー、先輩は生ビールをそれぞれ買って、よさそうな席につく。
入店時にもらった演者のチラシを見ても、もちろん知っている顔なんていない。
けれどなかには女性の怪談師もいるようで興味をそそられた。彼女たちはどんな話をするのだろう。
いっぽう先輩は、
「東海林(とうかいりん)ショージも出るのか。おれ、この人の話好きなんだよな。おおっ、こんなゲストが来るんだ、ラッキー」
なんてビールで喉を潤しながらひどく楽しそうだ。
これだけ喜んでもらえたなら、ムックの企画を紹介してもらった恩返しくらいにはなるだろう。
私もアイスコーヒーで口を湿らせながら、店内を見回した。
まだ開園までは三十分ほどあるが、ざっと見る限りでは席の六割以上は埋まっているようだ。
怪談王子効果なのか、若い女性が多いような気がする。
「先輩は、怪談ライブにもよく行くの?」
「おれか? 好きな怪談師が出るときは結構行くかなあ。怪談を聞きたいだけなら動画でもじゅうぶんだけど、怪談師によっては、こういうところで生でしか話さないって決めてるネタもあるみたいでさ」
「へえ、例えばどういうネタ?」
先輩はあごをさすりながらちょっと首を傾ける。
「そうだな。おれが聞いた中だと、存命の人に関する話とか、実際に起こった事件事故についての話とかが多い印象かな」
「なるほど、プライバシーに配慮してってことなのね」
「あとは実在の集団――しかもちょっとヤバめの団体に関する怖い話とかもそうだな」
「ヤバめっていうと、宗教とかヤクザとか?」
「しーっ。ばか、声がでけえよ」
「ごめん」
そんな話をしているうちに、ライブは始まった。
照明が落ちた客席とは対照的に、ステージには眩しいスポットライトが落ちる。
演者が一人一人登壇しては、自慢の怪談を披露していく。
いかにも肉体労働系の仕事に就いていそうな屈強で強面な男性。銀座のクラブで働いていそうな品のよい中年女性。金髪にTシャツのチャラいパリピっぽい青年から、会社役員のような落ち着いた風格の高齢男性までと顔ぶれも様々だ。
語る内容も、先輩の言葉通りバラエティに富んでいてなかなか面白い。
しんみりと泣ける話もあれば、眉をひそめたくなるような人間の心の闇に迫る話もあった。密漁組織に偽名で潜入したときの恐怖体験を語るなんて話もあり、つい夢中で聞き入ってしまった。
今度は自分でもチケット買ってきてみようかな。
そう思っていると、蓮見さんがステージに上がった。
やはり怪談王子ファンだったのか、若い女性客たちがそこかしこでざわめく。
数日ぶりに見る彼は、今日も喪服のような黒スーツだ。
肌が白くて顔立ちが整っているから、強烈なライトを浴びると、どこか作りものめいて見える。
明るいガラスケースの中に据えられた、高級な特別製の人形のようだ。
「こんばんは、蓮見才人です。今日はお集まりいただき、ありがとうございます」
低いけれどしっとりした、いい声だ。
炎天下を一緒に歩いたときの気安い感じともまた違う、余所行きの声と顔。
蓮見さんの声には癒し効果があると動画のコメントに書いていたファンがいたけれど、納得できる気もする。
天は二物も三物も与えてしまうらしい。
「さて、みなさんは『黒い日曜日』という曲をご存じでしょうか」
蓮見さんはゆったりと語り始めた。
*
『黒い日曜日』は一九三〇年代にハンガリーで発表された曲です。
この曲が生まれたいきさつをモデルに映画化もされたので、ご存じの方も多いかもしれませんね。
重く雲が垂れこめた暗い日曜日に亡くなった恋人を想って嘆き続けた男が、最後には自殺するという歌詞で、曲調も非常に陰鬱で重いものです。
ハンガリーではこの歌を聴いて自殺する若者が相次ぎ、イギリスBBCでは放送禁止曲に指定されたという逸話もあります。
これと似ているものに、『トミノの地獄』という詩があります。
『黒い日曜日』が作られたのと近い一九一〇年代に日本で書かれたもので、トミノという少年が地獄を旅するという内容のわずか十三行の詩なのですが、これを声に出して読むと死ぬと言われています。
いずれも、ウェブで検索する際は自己責任でお願いしますね。
前置きが長くなりましたね。
そろそろ本題に入りましょうか。
このお話をぼくに聞かせてくれたのは、ぼくの知人の妹さんです。
仮に小松さんとお呼びしましょう。
小松さんが小学生のとき、学校でこっくりさんが大流行しました。
みなさんの中にも、子どもの頃にこっくりさんをやった経験のある方は多いんじゃないでしょうか。
これくらいの年齢って、怖いもの見たさが恐怖心を上回っちゃうんですよね。
いけないことをしているというスリルや、わくわく感もそうさせるのかもしれません。
ただ、小松さんが教わったこっくりさんは、かなり独特なものでした。
こっくりさんをやったことがある方ならおわかりだと思いますが、初めにこっくりさんを召喚するときに呼びかけますよね。
「こっくりさん、こっくりさん、おいでください」というアレです。
ですがこの学校のこっくりさんは、あれに歌うような節がついていたのだというのです。
しかも通常の呼びかけの他に、もう少し長めの歌詞があったそうなんです。さらには、コインに指を置いている二人だけじゃなく、その場に参加している全員で歌うのが決まりだったそうなんです。
その様子を想像してみると、ちょっと異様ですよね。
でも小松さんはもちろん、同級生たちはそれが当たり前だと思っていたので、特に違和感はなかったそうです。
類似のものに「エンジェルさま」や「キューピッドさん」などが、やり方自体はほぼ同じです。なので、小松さんの話は非常に興味深いものでした。
実際にぼくの前で小松さんはそのフレーズを口ずさんでくださったのですが、ここではやめておきますね。
さて、あまりに何度もこっくりさんをやっていたため、小松さんたちの脳裏には、そのメロディがすっかりしみついていました。
みなさんも経験がありませんか?
繰り返し何度も聞いた曲がふとしたときに頭の中によみがえって、無意識のうちに脳内で何度も再生してしまったりすること。
あれって、イヤーワームとかディラン効果とか呼ばれる現象だそうなんです。小松さんたちもそんな感じになっていたらしいんですよね。
そうしているうちに、ぽつりぽつりとおかしなことが出始めました。
授業中に突然叫び出す子があらわれたり、暴力的になってクラスメイトにけがをさせる子が出たり、学校に来なくなってしまう子までいたそうです。
これはさすがにおかしいぞということになり、学校側は生徒に聞き取りを行ったそうです。
そこでこっくりさんをやっていたことがばれた小松さんたちは、もうしないと約束させられました。
ここまででしたら、思春期の少女によくある集団パニック事件で終わっていたかもしれません。
ですが、この話には続きがあるのです。
小松さんたちはやがて中学生になりました。
自分用のパソコンを買ってもらった子もいて、そうした子の中にVチューバ―にはまり、自分で作詞作曲した歌をキャラに歌わせてみる子が出ました。
その子が歌わせたのが、そう、あのときに流行ったこっくりさんの歌だったのです。
その子は動画をユーチューブに投稿しました。
ですが素人の投稿動画なんて、そうそう再生回数が伸びるものじゃありません。
他にもいくつか投稿してみたものの、思うように観てもらえないことでつまらなくなって、間もなく更新しなくなったそうです。
それから数年が経ち、小松さんは大学生になっていました。
ある夜、ベッドに寝転んでSNSを眺めていた小松さんのタイムラインに、見覚えのある動画が流れてきました。
どこかで見たような気がします。
それもそのはずで、それはあのときに小松さんの友だちが投稿した動画でした。
アップされた当初は再生回数が二十回にも満たなかったのに、今は数十万回を超えていいます。
何事かと思ってポストを読んだ小松さんは驚きました。
あの動画は『再生すると霊に憑かれる動画』として拡散されていたのです。動画のコメント欄には、再生して実際に奇妙なことが起こったという書き込みがたくさんありました。
しかもその中には、霊に憑かれて操られた末に、自ら命を絶つという事態に発展したものまでありました。
小松さんは怖くなり、動画を投稿した友人にすぐに連絡を取りました。
もちろん友人も驚き、動画を削除しようとしました。
しかし、アカウントを登録する際に使ったスマホのメールアドレスは、もう解約してしまっていたのでログインできません。
そうしている間にも、どんどん拡散されていく動画を、二人はただ眺めているだけしかできませんでした。
問題の動画は、まだウェブ上のどこかにあります。
何が起こっても構わないという方だけ、検索してみてください。
これで、ぼくの話を終わります。
ご清聴、ありがとうございました。
*
「蓮見さん」
ライブが終わった後も、蓮見さんはしばらくファンの女性たちに取り囲まれていた。
最後まで親しげに会話を交わしていた黒髪ロングの美人女性が立ち去った頃合いを見計らって、声をかけた。
「柳瀬さん、来てくださったんですね」
「はい。ありがとうございます。すごく楽しかったです」
「それはよかった」
「それから、こちらはライター仲間の七種です。蓮見さんの大ファンだそうですよ」
「えっ」
いきなり紹介されて、先輩は面食らっている。ドッキリが成功したような気分だ。
「本当ですか、それは嬉しいな。ぼく、『憑かれる』話ばっかりしているから、飽きません?」
「そんなことないです! どのネタもすげえ面白いです!」
早口になる先輩の焦りっぷりがおかしかった。
「あのさ、ちょっといい?」
蓮見さんと別れ、さて帰ろうか、それともこのまま飲みにでも行くかと話していたときだった。
後ろから声をかけてきたのは、ぱさついた金髪にラフなTシャツ姿の青年だった。
誰だっけ? 何となく見覚えがあるけど――と思っているわたしの隣で、先輩が言った。
「あれ、もしかして、クッチー朽木さん?」
先輩の言葉で思い出した。
そうか、さっきのライブに出ていた怪談師の一人だ。
彼の怪談の内容は、陰惨な殺人事件が遭った事故物件に住んでみて、そこでの体験を語るものだった。
被害に遭った人への気遣いがなく、怖さ優先といった印象で、正直あまり好きになれない内容だったことまで数珠つなぎで思い出し、嫌な気分になる。
そもそもわたしは映画でもそうなのだが、大きな音や前触れなく飛び出してくる怪異などで脅かされるのが苦手なのだ。必要以上に身振り手振りが大げさだったり、演技がかって声を張り上げるような語りもあまり好きではない。
その点、蓮見さんの怪談は淡々とした語り口で好印象だった。
低くて落ち着いた声を聞いていると、怖い話のはずなのにどこか癒されるような感覚になってしまう。女性ファンが多いのもうなずける。
「さっき、王子と話してんのがちょーっぴり聞こえちゃったんだけどさ、あんたたちライターなの? 本とか書いてる感じ?」
「まあ、そういう仕事もありますが――」
「ねえねえ。あんな顔だけのやつより、おれを取材してよー。おれ、こう見えて本格派の怪談師だからさ」
さすがに先輩もすぐには返せず苦笑いだ。
なるほど、こういうふてぶてしさがあれば、事故物件や心霊スポットに突撃できるのかと妙な感心をしてしまう。
「それにさ、大きな声じゃ言えねえけど、あいつ、やべえ噂あるんだぜ」
朽木は声をひそめて顔を近づけてきた。
つい反射的にのけぞってしまう。
先輩はさすがにわたしほど態度には出していないが、眉間に刻まれたしわは隠しようもない。
わたしたちのそんな反応など歯牙にもかけず、朽木はノリノリで言った。
「なあ、あんたらも気になるだろ。ここじゃなんだから場所変えて話そうぜ。おれ、飲めるところがいいな」
わたしたちが腰を落ち着けたのは、ライブハウスから徒歩十分ほどの居酒屋チェーン店だった。
「かんぱーい!」
ビールジョッキを構えて、朽木は上機嫌だ。
おそらくここのビールもつまみも、わたしたち持ちになるのだろう。
「プハーッ! いやあ、ライブ後の一杯はうまいね! あらためて、おれ怪談師のクッチー朽木、よろしく」
「七種牧生です」
「柳瀬恵です」
「そんなかしこまらずにタメ口でいいよ。気楽にいこうぜ」
よく言えば人懐こく、悪く言えば図々しい。
人の懐に飛びこむのがうまいと言い換えることもできそうだ。
朽木はわたしたちの戸惑いなどおかまいなしに、切りこんできた。
「なあなあ、あんたらってライターなんだろ。普段どういうもん書いてんの? ウェブ? 雑誌? 単行本?」
「おれは雑誌中心かな。隔月刊のアトランティスってオカルト雑誌がメイン。ウェブ記事も少しなら書いてる」
「わたしはウェブと雑誌が半々くらいですね」
「めったにないけど、あとはゴーストライターとかかな」
「えっ、先輩そんなこともやってるの?」
先輩の言葉に、わたしのほうが驚いた。
「どうしておまえがびっくりしてんだよ」
「だって初耳だもん。それ何? 芸能人本の代筆とか?」
思わず食いついてしまったわたしに、先輩は苦笑いだ。
「ちげえよ。そういうのが回ってくるようなコネはねえ。自費出版やってる会社との契約さ。自分の本を出してみたいけど、交通事故の後遺症とか障がいとかで、本人が書くのが難しい人の代わりに書くんだよ」
「へえ、ライターってぼろい商売なんだな。おれにもできそう」
その言いざまにカチンときた。
思わずにらみつけてしまうけど、本人は気づいていないようだ。
「おれさあ。本出してみたいんだよね。ほら、最近さ、怪談師が本出すことも多いじゃん?」
「そうだな。最近は怪談師が文庫や四六判を書くことも増えてきた感があるな」
「なあなあ、そういう企画を通せそうなとこのコネってない? 出版社の知り合いとかでさ。あっ、自費出版以外で頼むよ」
なるほど、だんだんわかってきた。
朽木がわたしたちと話をしたがったのは、これが狙いか。
蓮見さんの話題を出せば食いつくと思われたのだろう。実際にそうだけど。
「うーん、どうだろうなあ。おれが付き合いあるところは、単行本はあんまり出してないから」
「えー」
朽木は子どもみたいに唇をとがらせた。
「そういうのは、文芸系の出版社にコネがあったほうが話は通りやすいと思うぞ」
「マジかあ。怪談王子のやつはどうやってコネ作ったんだよ、ちくしょう。やっぱり顔か。イケメンは得だよなあ」
いや、それもないとは言わないが、イケメンというだけで仕事が取れるほど、この業界は甘くないはずだ。
依頼の決め手になったのは、人間性や持ちネタの内容ではなかろうか。
――と思ったが、それを口にするとこの場が炎上しそうなのでやめておいた。
蓮見さんはこれまでにもいくつかの版元から何冊かの怪談本を上梓しているので、それがよほどうらやましいのだろう。
わたしもライター仕事を始めたときは、「どうやって出版社とコネ作ったの?」と知り合い程度の人間から悪気なく聞かれたものだ。
コネに夢を見すぎな人は多い。
わたしとて先輩からの紹介だったからコネと言えなくもないけど、文章を書いて口に糊していきたいのなら、普通に売りこみに行けばいいのに。たこわさを摘まみながら思う。
待ちの姿勢で「何かおいしい話がないかな」と思っているだけなら、いい話は降ってこない。
わたしがこれまで担当した仕事のいくつかは、知り合った編集者にやってみたい企画を持ちかけて結びついたものでもあるのだ。数の上ではすごく少ないけど。
「まあ、知り合いの編集者に聞くだけ聞いてみるよ」
「マジか! やったあ!」
先輩の社交辞令に、朽木は子どものように喜んだ。
この業界あるあるだが、「一応聞いてみる」は本当にただ聞いてみることだけを指し、仕事の確約というわけではない。世知辛いことだ。
「それで、さっきの話なんだけど」
先輩が催促すると、「わかってるって」と朽木は手をひらひらさせた。
「怪談王子の噂だろ?」
「そのために酒おごってるんだからな。ちゃんと話せよ」
「まあそう焦んなって」
朽木はビールをあおって口を湿らせる。
さっと周囲に目を配ると、耳打ちするように言った。
「王子のファンや王子に接触した人間が、何人も行方不明になったり死んだりしてるって噂、知ってるか?」
「はあ?」
思わず高い声が出る。
何かあったのかと周囲の客の目がこちらに向いた。
わたしは口元を押さえて、朽木をにらんだ。
「ちょっと、突拍子もないこと言わないでよ。蓮見さんに失礼でしょ」
「あんた、やけに王子の肩持つじゃん。もしかしてあんたもファン?」
「ファン……ってほどじゃないけど……蓮見さんと今、仕事してるのよ」
「ふうん? だったら余計にちゃんと調べたほうがいいんじゃないの? あいつが裏でやってることがバレたら、仕事吹っ飛ぶかもね」
「そこまで言うからには、何か証拠をつかんでるんだろうな」
「当たり前じゃん」
朽木はポケットからスマホを取り出す。
ついついと画面に指を滑らせた後、わたしに向けてきた。
「これ、おれのファンの子から来たタレコミ。読んでみてよ」
*
クッチーはじめまして!
いつもチャンネル更新楽しみにしてるよ!
今日は、クッチーに相談があってメールしたんだ。
警察に行ったけどちゃんと話を聞いてもらえなかったし、あたし、ほかに相談できる人もいないから。
あたし、クッチーの怪談を聞いて怪談ライブが好きになったの。
だから友だちをライブに誘ったんだ。
友だち、そのときに出てた怪談王子にすっかり沼っちゃったの。
怪談はクッチーのほうが面白いと思うけど、王子もかっこいいもんね。
その子、優しい感じのイケメンに弱いんだ。
フーゾクで働いてるんだけど、前にもイケメンホストにハマって借金してたから。
でも今はホスト通いもやめたって聞いたから、安心してたんだよ。
それから何度か、その子と一緒にライブに行ったんだけど、いつの間にかその子、怪談王子の追っかけみたいなこともはじめてたみたいなんだ。
SNSでも、王子ファンたちとつながって、色々情報交換していたみたい。
たぶんそこからの情報なんだけど、「王子と二人で会える方法があるんだって」って言ってて。
あたし最初、ガセネタだと思ったんだよね。
だって王子なんて雲の上の人じゃん?
モデルもやってるし、テレビにも出てるし。
だからきっと、だれかにうまいことだまされてるんだって思ったんだ。
そんなの絶対に怪しいよ、やめときなよって言ったんだけど、聞かなくて。
その子のSNS仲間とのやり取りも見せてもらったんだけど、
「王子は高位の存在に憑かれてるから、その存在に気に入られると、王子にもふりむいてもらえる」って書いてあった。
ヤバくない? 何の宗教よ、って感じでしょ。
たしかに王子の怪談って、「霊に憑かれた」とか「狐が憑いた」とか、何かに憑かれる話が多いけど、飛躍しすぎじゃね?
そう思ったから、そのまま言ったら、その子、不機嫌になっちゃって。
メッセージ送っても既読スルーされるようになったんだ。
だけどそれから一か月くらいしたとき、その子からメッセージが来たの。
「王子に会いに行ってくるね」
すぐに返信したけど、既読にはならなかった。
アパートにも行ってみたけど、たぶんずっと帰ってきてないみたい。
郵便受けにチラシがいっぱいつっこまれてたから。
その子、フーゾク勤めがバレて親に絶縁されてるから、他に頼れる人がいないの。
お願いクッチー、友だちを探してください。
友だちの名前は■子っていいます!
怪談王子って、絶対ヤバいって!
*
「どう?」
「どうって言われても……」
ニヤニヤした笑みを貼りつけて顔を覗きこんでくるので、反射的に体を引いてしまう。
「ヤバそうなにおい、ぷんぷんするだろ?」
それには答えずに、先輩にスマホをスルーパスした。
しばらく小さな画面を目で追っていた先輩も、あごに手を当てて唸った。
「うーん、これにどれだけの信ぴょう性があるかだなあ」
「何だよ、おれのファンを疑うのかよ」
「そういうわけじゃないけど、これが本当のことを言ってるって保証もない」
「これだけで、蓮見さんに関わった人が行方不明になったり死んだりする根拠とまでは言えないんじゃない? これくらいの文章だったらわたしだってすぐ書けるし」
さっきライターを軽んじるような発言をされたものだから、つい言葉が尖る。
けれど朽木は平然とした様子で、またスマホ画面についついと指を滑らせた。
「もちろん、これだけじゃないぜ。他にも決定的な証拠があるんだ。ほら」
画面に表示されていたのは、鉄道事故のニュースだった。
夕方の帰宅時間帯、ホームに電車が侵入してきたところへ、飛びこんだ中年男性が即死したというものだった。
「……これが、どうしたっていうのよ」
「まあまあ、そう急かすなって。で、この事故の目撃者の一人がSNSにアップしてた写真がこれなんだけどさ」
朽木は別の画像を表示させた。
それは線路に倒れた被害者らしき男性のものだった。
線路状に散乱した、男性のものとおぼしき靴や鞄と、その中身。
灰色のスーツが血を吸って黒く濡れている。
横たわる男性の体はおかしな方向に捻じ曲がり、とっさに目を伏せたからちゃんとは見ていないが、体の一部がちぎれているようでもあった。
吐き気がこみあげてくるのを、奥歯を噛んで飲み下す。
誰でもスマホを持つようになった昨今、事故や事件現場に遭遇すると凄惨な場面をこぞって撮影し、SNSに投稿する者は後を絶たない。
おそらくはこれもそうした経緯で投稿されたものだろう。
歪んだ承認欲求だ。吐き気がする。
わたしが顔を背けようとしたのがわかったのか、朽木は慌てた声を出した。
「おっと、待てよ。もっとちゃんと見ろって」
「趣味悪いわよ。何を見ろって言うのよ」
「今拡大するから。ほら、ここだよ、ここ」
朽木は画面上で親指と人差し指をつまんで開くように動かした。
すると画像が拡大され、男性の体のすぐそば、線路上に小さな円形のバッジのようなものが落ちているのがわかる。
「見えた? これ、何のバッジが知ってるか?」
この画像では小さくてわかりにくいが、蓮の花とイタチか狐のような動物が刻印されているようだ。
そのことに気づいた瞬間、周囲の音がざっと遠ざかる。
全身の血の気が引いて、指先がつめたくなっていくのがわかった。
さっきまで赤くなっていた頬が、今は青ざめているだろう。
そんなわたしを、朽木は死体画像を見せられて怖がっているとみたのか、ぐっとギアを上げてきた。
「これはな、『いずなの使徒』っていう、新興宗教団体の信者に配られるバッジなんだよ」
隣の先輩が「いずな?」とつぶいている。
「ああ。しかもこいつがつけてるのは、その中でもたくさん献金した高ランク信者か団体の役員だけがもらえるものらしい。ランクで金・銀・銅って色分けされてるらしくてさ」
画像のバッジは、輝く金色だ。
朽木はすっかりぬるくなったであろうビールをあおると、ダンと音をさせてジョッキを置いた。
「なんでおれがそれを知ってるかって? ちょっと前だけどさ、取材を通して知り合った人が、たまたまここの団体の役員クラスの信者だったんだよね。もう脱退しちゃったらしいんだけどさ、抜けるときに色々持ち出してきたらしいんだ。で、その資料をこっそりもらったり、色々と教えてもらったりしてたわけ」
抜け目がないことだ。
おそらく、怪談のネタに使おうということなのだろう。
資料の内容によっては、出所がバレてしまいそうで危険な気もするが、彼にそういった配慮ができるかどうかは怪しい。
「このおっさん、ニュースでは自分で飛びこんだってことになってるけど、SNSの書き込み見ると、何かに引っぱられるみたいにして線路に落ちたつってる人が複数いるんだよな。信用できないんなら後で調べてみ」
先輩はさっきから隣でスマホをいじっている。
最初は飽きてニュースでも見ているのかと思ったが、どうやらそうではないらしい。
ちらっと見えた画面から察するに、SNSで検索して朽木の話の裏づけを取っているようだ。
「この〇〇って被害者のおっさんだけど、この『いずなの使徒』って団体に奥さんと娘がハマっちゃってさ。奥さんが有り金全部抱えて出家しちまったらしいんだよ。で、団体から家族を取り戻すまでをRTAするって名目でSNSにアカウント作ってるんだ。本名でアカウント取ってるから、検索したらすぐヒットするぜ」
「あった。これだろ」
先輩が見せたスマホ画面には、たしかにあの男性の顔写真がプロフィールに設定されたアカウントだった。
自己紹介欄には『いずなの使徒の悪行を許さない! みなさんぼくを応援してください!』と書かれている。
呟きの内容は、民事裁判の経緯や、教団に送ったメールとそれに対する教団側のリアクションの内容。教団施設に出入りする信者をつかまえて自分の家族の所在について尋ねる様子の動画だったりと、わたしから見ても危なっかしさを感じるものだった。
「これ見て、なんかピーンと来てさあ。例のもらった内部資料を読み返したわけ。で、驚くべき事実にたどりついたってわけよ」
朽木はもったいぶった動きで、自分のバックからクリアファイルに入れられた資料を取り出した。
「この宗教団体――『いずなの使徒』の代表者は、瑜伽(よぎ)っていう六十代のおばさんなんだけどさ。そいつの本名、何だと思う?」
朽木が資料の付箋がついた箇所をめくる。
「そいつの名前は、蓮見真智(まち)っていうんだぜ」
そのページに貼られた画像は、六十代とは思えないほどに若々しい女性の姿だった。
髪質や目元の雰囲気が、怪談王子を彷彿とさせる。
「なあ、これってただの偶然だと思うか?」
朽木はニタニタ笑うと、手を挙げて店員を呼びつけ、ビールのおかわりと鶏の唐揚げを追加した。
*
調べてくれた七種先輩によると、『いずなの使徒』の代表の瑜伽は、茶吉尼(ダキニ)天の生まれ変わりを自称しているらしい。
予言の力があると謳い、多くの支持と寄付金を集めているようだ。
実際、瑜伽の予言はよく当たるという話で、信者には政財界や芸能界の大御所も少なくないようだ。
教団のパンフレットには、わたしでも知っているような有名タレントや大物政治家が、胸に教団のバッジをつけて瑜伽とにこやかに握手をしている写真が、でかでかと掲載されていた。
茶吉尼天はヒンドゥー教ではダーキニーと呼ばれ、人肉を食らう羅刹の仲間だという。それが日本に伝来し、密教に取りこまれて性愛をつかさどる神とされた。
また白い狐にまたがった姿で描かれることから狐を使役するとされたようだ。
古くから狐は、人の精気を吸ったり人の死を予言したりするともいわれていた。そうした要素を瑜伽は教団の要素として取り入れたのかもしれない。
無論、朽木の言うことをわたしも先輩も頭から信じているわけではなかった。
そうではないが、万が一ということもある。
場合によっては、せっかくのムック本企画がお蔵入りになってしまいかねない。
そうなると先輩が半年をかけて密着インタビューしてきた女優としても活躍する美魔女怪談師、栗生(くりゅう)静(しずか)の記事もお蔵入りになってしまう。
わたしたちはあの教団を中心に、独自調査を進めることにした。
わたし自身も、真実を知りたかった。
蓮見さんの背後に何があるのか。あのやさしい笑顔は本物なのか。
朽木と会ってから約一週間後、わたしは先輩のマンションへ向かった。
「で、先輩のほうは収穫ありましたか。あ、これお土産です」
先輩お気に入りのコーヒーショップで買ってきた、アイスコーヒー(LLサイズ)を渡す。
流れるように受け取ってぐびりとやりながら、先輩はうーんと唸った。
「あいつの言うことだから、最初は都市伝説レベルの信用度しかなかったんだ」
「わたしもそうよ」
「あの教団に不利になるようなことを言ったりやったりした人が、事故や事件にまきこまれたと思われるケースはウェブ上の書きこみからいくつも見つかった。表に出てないだけで、朽木のファンの子の証言みたいに、失踪している人間はさらに多いのかもしれない」
「……わたしも、ほぼ同じ意見なのよね」
アイスハニーラテをちびちび舐めながら、わたしもうなずいた。
「事故に巻き込まれたっていっても、朽木が持ってきたケースと一緒で、周りからみて自殺や故意には見えなかったという証言があるだけだ。何ら物的証拠はない。目撃者がたくさんいる中で階段から落ちたり、車道に飛び出したりしてるからな」
「ただ、多くに共通しているのが、自分の意思じゃなく、見えない何かに取り憑かれて操られているみたいだった――」
「そういうこと」
あっという間に空になったプラスチックカップを、先輩がクズ箱にほうりこむ。
「やっぱり……都市伝説なんじゃないかな。もしくは陰謀論」
「教団か怪談王子にうらみを持つ人物の犯行だって?」
数年前に世界を襲った感染症により人々が閉塞感を感じていたあの時期、かつてない規模で世界中を様々な陰謀論が駆け巡った。
家に閉じこもる日々が続き、外の社会との接触を断たれた人々は、ネット上の情報に浸って過ごす時間が多くなった。
そうした情報の中には、発信者によって都合のいい結果をもたらすことを目的にしたフェイクニュースやフェイク動画がたくさん混じっている。
ありもしない事件、ありもしない事故、ありもしない犯罪。
わたしの知人の中にも、日がな一日家に閉じこもってネット漬けになるうちに、すっかり陰謀論者になってしまった子がいる。
だから少なくとも、そうした思考に陥る人がいることはわかる。
「陰謀論だったら、フェイクニュースを流すだけでいいでしょ。実際に人を殺したり誘拐したりする必要はない」
「まあ、そうだよな」
「今、あそこでいったい何が起こってるのかな」
「あそこ?」
怪訝そうな顔をされて、うかつにも一瞬咳きこみそうになった。
「えっ? ああ、『いずなの使徒』のこと」
「まあ、おれたちにできるのはここまでかな」
「そうね」
それが妥当な線だろう。
わたしたちは警察でもなければ、ましてや探偵でもない。
これ以上、捜査ごっこに手を出すのはリスキーだ。
こちらはしがないライター、対してあちらは多くの信者を従え、政財界にも顔がきく組織だ。
フリーランスが生きのびていくために必要なのは、餌と罠のありかを察知する嗅覚なのだ。
「幸か不幸か、王子と教団の明確なつながりへの糸口は見つからなかったな。蓮見なんてよくある苗字さ。単なる偶然の一致だったんだろう」
「そう言えば、朽木さんのほうはどうするの?」
「んあ?」
あくびをしていた先輩は間抜けな声を出した。
よく見ると、あごに無精ひげが伸びている。
この件の調べものか、それとも原稿を書いていたのか。伸び具合からしておそらく昨夜は徹夜だったのだろう。
「だって、編集者を紹介するんでしょ? 本気かどうかわかんないけど」
「それならもう紹介したぜ」
「えっ、担当になってくれそうな人がいたの? まさかこの話してないよね?」
「するわけねえだろ。本を書いてみたい怪談師がいるんだって、話してみたんだよ」
「ちなみにどこ?」
先輩は口の端を曲げて意地悪く笑う。
「自由文学舎」
飲みかけていたラテが気管に入りそうになってむせる。
「ちょっと、そこ自費出版のところじゃない」
「おいおい。自費出版もやってるってだけで、普通の商業出版が主力だぜ」
「……先輩、あいつの言ったこと、実は相当根に持ってるでしょ」
「気のせいじゃね?」
朽木がタレこんできた件はおそらく、時間とともに風化していくだろう。
これ以上、わたしたちが――わたしが気にする必要はない。
そう思っていたのだ。
あの報せが、飛びこんでくるまでは。
