
ミルグラム考察 看守について
0.初めに
DECO*27×OTOIRO×山中拓也による視聴者参加型プロジェクト『MILGRAM』の登場キャラクターで私達の依代、エスについてとジャッカロープ、ミルグラム実験を踏まえて行った考察です。
考察を行ったのは、
心理方面を担当したのはらと(@RatoRato934 )です。
宗教観、福祉方面を担当したのはみるやね(@milg_mnym )
【http://oshigatoutoi.net/音楽/music-milgram-kousatu/】
1.ミルグラム実験について
ここでミルグラム実験(Milgram experiment)について説明する。別名、アイヒマン実験・アイヒマンテスト(別名)という。
アイヒマン実験(ミルグラム実験)
→閉鎖的な状況における権威者の指示に従う人間の心理状況を実験したもの
→ 権威者の指示に従う人間の心理状況を実験したものである。
→50年近くに渡って何度も再現できた社会心理学を代表する模範となる実験
→アメリカ、イェール大学の心理学者スタンリー・ミルグラム(Stanley Milgram)が1963年にアメリカの社会心理学会誌『Journal of Abnormal and Social Psychology』に投稿したものアイヒマン実験になった経緯
東欧地域の数百万人のユダヤ人の絶滅収容所に輸送する責任者であったアドルフ・アイヒマンは、ドイツ敗戦後、南米アルゼンチンに逃亡して「リカルド・クレメント」の偽名を名乗り、自動車工場の主任としてひっそり暮らしていた。彼を追跡するイスラエルの諜報機関がクレメントは大物戦犯のアイヒマンであると判断した直接の証拠は、クレメントが妻との結婚記念日に花屋で彼女に贈る花束を購入したことであった。その日付はアイヒマン夫婦の結婚記念日と一致した。またイスラエルにおけるアイヒマン裁判の過程で描き出されたアイヒマンの人間像は人格異常者などではなく、真摯に「職務」に励む一介の平凡で小心な公務員の姿だった。このことから「アイヒマンはじめ多くの戦争犯罪を実行したナチス戦犯たちは、そもそも特殊な人物であったのか。それとも妻との結婚記念日に花束を贈るような平凡な愛情を持つ普通の市民であっても、一定の条件下では、誰でもあのような残虐行為を犯すものなのか」という疑問が提起された。
この実験は、アイヒマン裁判(1961)の翌年に、上記の疑問を検証しようと実施されたため、「アイヒマン実験」とも言う。
実験の結果は、普通の平凡な市民が一定の条件下では冷酷で非人道的な行為を行うことを証明するもので、そのような現象をミルグラム効果とも言う。
実験から約50年後の2015年、オーストラリアの制作会社が、シドニーで役者を用いてこの実験を再現した番組を発表した。
(Wikipedia様)
こちらでもまとめています。
目次『エスくんについて』
ミルグラム実験の効果の例
目次『赦さないになって出てきたもの』
▷▶︎非人道的な実験
心理学を履修している身として、レポートを書く時に非常に指導されることがある。
『被験者』と書いてはいけないということ
これは、被験者という言い方はあまり良くないとされる。
被験者というのは言葉の通りだが、実験をする側と実験を受ける側が対等ではないと感じられないから使用はあまり良いものとされていない。
あまり教授に良くない顔をされない...
『実験協力者』『実験参加者』と表記するのが推奨される。
point!
心理学実験っていうのは、「対等」で無ければいけないのが大前提
・協力してくれているから実験が成立するということを忘れてはいけない。必ずしも実験に参加してくれた相手と自分は対等な立場という事を忘れては行けない
・絶対に実験の対象である人を動物や実験体のように扱うことは赦されない
心理学実験というのは、何かの事象を検証するために行う
非人道的ではあるが、ミルグラム実験を例であげると
ミルグラム効果という一定の条件下で人は残酷になれるという事象を検証するために、
実験協力者を集め、教師と生徒に分けて、教師側が生徒に問題を間違える度に、電流を流すという内容の実験を行い、電流を流す人が割合的には多かったという結果が得られた。
あるごとりいさんのYoutube動画が分かりやすく纏められていたので記載させていただきます。
(何か問題があれば消させていただきます。)
心理学の実験を行う上では、守らなければいけないことが存在する
対等ではない条件を課したり、非人道的すぎる実験内容だったりするとほとんどが禁忌とされる。
ミルグラム実験もその一つ。
非人道的な実験とされる有名な三つを取り上げる
・アルバート坊やの実験
有名なパブロフの犬の古典的条件付けが人間でもあるのか立証しようとした実験
古典的条件付けとは、食物とベルというような、関連性のない刺激を、唾液の分泌といった身体的な反射と結び付けることを指す。
ベルを鳴らしても、普通は犬はよだれを垂らしませんが、パブロフは、犬がベルの音を聞くと、よだれを垂らす応答をするよう条件付けました。
それが赤ちゃんでも実証されるのか確かめたものがアルバート坊やの実験
同様のことが、人間にも可能であることを立証しようと考えました。生後9ヵ月の赤ちゃん、アルバートに、動物と恐ろしい物音とを用いて、古典的条件付けを行うことにしたのです。
まず最初に、研究者たちは、アルバートにふわふわとした毛の白いネズミを見せました。そしてアルバートが、その動物をなでようと手を伸ばすと、心理学者たちは、彼の頭のすぐ後ろで、金属の棒をハンマーで叩き、大きな音を出して彼を驚かせたのです。その結果、アルバートは、白いネズミを見ただけで泣き出し、はいはいして逃げ出すようになりました。
・赤ちゃんへの残酷な実験
赤ちゃんに一切お世話をしないで、言語を獲得できるのか、獲得した言語は何になるのかというのを実験するもの。
赤ちゃんと目を合わせる、声を掛けてあげる、名前を呼んであげる、抱きしめるというのを一切行わずに、ただただ赤ちゃんを見つめる実験
結果は赤ちゃんは全員死に、赤ちゃんを見ていた実験を行う人は赤ちゃんを実験の道具としてみていたという劣悪なもの
【https://jp.quora.com/歴史上-もっとも歪んだ科学の実験は何でしょうか】
そしてミルグラム実験&スタンフォード実験
ミルグラム実験
ミルグラム効果を実証するために行ったもので、教師と生徒に分けたもの。(1963年)
スタンフォード実験
ミルグラム実験を再び行ったものがスタンフォード実験。看守と囚人に分けて劣悪な環境に囚人側は置かれて実験が行われている。(1971〜)
結果:
コイン投げで看守に決まった学生は何の理由もなく職務を超えて囚人役の学生を虐待した。囚人は心理的外傷に苦しみ、あるものは早めに辞めた。強い権力を与えられた人間(看守)と力を持たない人間(囚人)が、狭い空間で常に一緒にいると、次第に理性の歯止めが利かなくなり、暴走してしまう。
結局この実験は6日間で中止された。しかし看守役は「話が違う」と続行を希望したという。
(虐待がエスカレートし、殺人未遂が起きたといわれている)
疑似刑務所へ連行。
この実験は最終的に2名の死者を含む多数の死傷者を出す惨劇へと変貌していく。
【https://ja.m.wikipedia.org/wiki/Es[エス]】
この動画は見て欲しいです。
映像が合って面白いので綺麗に纏まっているのと面白い例が出てきたので抜粋します。
少し話題が逸れますが息抜きに
動画の11:40〜
実験の信頼性についてのchapterが出てきたのですが、ミルグラム実験の信憑性を揺るがす事件として、元軍人が銀行強盗を起こす事件が発生したという話が出てきました。
(心理学の授業を受けた身でも、銀行強盗の話題は殆ど授業でも触れられないし、調べても簡単には出てこない内容である。)
銀行強盗の話についてタイムラインで触れられたのを覚えていますか?
2020/06/23
フータとカズイの会話で言及されたのが、銀行強盗に巻き込まれたら犯人がいたらどう動くかという話題を出している。
脱獄の話を出されて、カズイから銀行強盗の話題を出し、それにフータが答えている状況。
カズイは恐らく自衛隊である可能性が囚人楽曲『half』から考えられる。(自衛隊は日本の軍人である)
フータがイキってるバカ大学生だったら
「は?急におっさん、意味わかんねえ例出してくんなよ」という言葉は入ると思う
もし自分が謎の空間に監禁されました
早く脱出したい、一番頼りがいがありそうな存在に「ここから出る方法を考えて」って言ったとして、突然、銀行強盗の話題を例に出されたら「?」となると思います。
「?」ってならずに普通にカズイの返答に答えているため、フータもこの事は知っている可能性がある。
なので、お互いがミルグラム実験の囚人という立場であることを理解した上で、ミルグラム実験の信憑性を疑う理由になる銀行強盗の話に触れた話題をしているフータとカズイと考えると面白いと思いませんか?
少しドラマパートのネタバレになります
ミルグラム実験で許可されてたものの一つで
囚人から看守への威嚇行動が許可されてる
ということがある。
フータはエスに威嚇行動をしている
例:)「ジンケン侵害が!!!」とか言ってるのが特にある。
ドラマパートではエスに攻撃できるか確かめてる
カズイはドラマパートで、エスの拘束を行っている。その時、「フータに聞いた」と述べているから、フータとはたまに議論したりお互いに得た情報を共有してる可能性がある。
フータは頭がすごく良いし、カズイは記憶力がすごいな
2-1看守について
▷▶︎▷ミルグラム実験における看守の立場

ミルグラム実験及びスタンフォード実験を行う背景となった、アイヒマンの存在がある。
私達の依代、『エス』はアイヒマンではないかと考えられる
軍服
ナチス・ドイツの軍服とエスくんが身につけている看守服が似ていると軍服マニアの友人が教えてくれました
(白黒の画像しかなかったので憶測ですが..)
六芒星
アンダーカバーでブラックボックスが開くシーン
→よく見ると六芒星が描かれている

ダビデの星(ダビデのほし)は、ユダヤ教、あるいはユダヤ民族を象徴するしるし。二つの正三角形を逆に重ねた六芒星(ヘキサグラム)といわれる形をしておりイスラエルの国旗にも描かれている。
ブラックボックス
ブラックボックスとは、一般的に、内部の構造が明らかでないものや動作原理の不明な装置、また、その使用法・操作法を知っていれば、内部構造や動作原理を理解していなくても、然るべき使用結果を得られる装置やシステムの概念を指します。
2ページ目の真ん中らへんで触れられています。
2-2 サディズム
サディズム(英語: sadism)または加虐性欲(かぎゃくせいよく)は、相手(動物も含む)を身体的に虐待を与えたり、精神的に苦痛を与えたりすることによって性的快感を味わう、また、そのような行為をしている自分を妄想したり相手の苦痛の表情を想像して性的興奮を得る性的嗜好の一つのタイプである。極端な場合、精神的な障害とも見なされ、この場合は性的倒錯(パラフィリア)となる。巷では語感から佐虐性と言われる事もある。(サド)
(Wikipedia様)
ミルグラム実験の経過中、看守はやがて囚人に虐待を行うようになっていき、高圧的に振る舞うようになった。
一般の人間だったのに、一定の条件下では
残酷な人間になってしまう。
2-3 es


ドイツ語の人称代名詞の三人称単数にはer/sie/esの3種類があります。それぞれ男性・女性・中性の性があり「彼は」「彼女は」「それは」と理解したはずです(文法1)。
esは中性名詞で扱われている。
性別不明、中性的な見た目をしている。
2-4 es(本能)について
エス(えす、es)とは、人間の精神機能を説明する言葉の一つであり、本能的な欲求や生理的衝動のことを指す。イド(id)ともいう。
精神分析学者のフロイトは、人間の精神機能を説明するために、「エス」「自我」「超自我」の3つに分けて、人間の精神はこれら3つの相互作用の結果であると捉えた。
人間が生まれたとき、その心的領域はすべて「エス」が独占している。しかし、誕生後の経験の中で、「エス」の一領域にその変形として「自我」が形成されていく、というのがフロイトの主要論理である。
エスは、人間の心の中で本能的な欲求や生理的な衝動の貯蔵庫であり、煮えたぎる釜のようなイメージとして表現される。
エスは、ヒトにとって完全に無意識的なものであり、ヒトの精神エネルギーの源泉である。エスは快楽原則(今すぐにでも欲求を満たして不安や苦痛を取り除こうとする)に従うため、善悪や論理的な判断は存在せず、「欲求のままに行動する本能がむき出し」といえる。そのため自我は、自分の中にあるとは気付かない「エス」の存在によって翻弄されている。
このエスに対して、超自我(スーパーエゴ)は人間の精神機能の中で、ルールや道徳観、理性を担い、善悪の判断を行う。
そして、エスと超自我からの欲求を、自我(エゴ)が調整しているという構図がある。つまり、「超自我」は直接的に、あるいは「自我」を介して間接的に、「エス」の支配に立ち向かっている。これが、フロイトが説明する人間の精神機能である。
▷▶︎フロイトの無意識について
フロイトの無意識(unconscious)とは、精神的なもので自分では意識できないが、各個人に持続的に存在するもの。
主体の意識とは関係なく意識に影響を与え、各個人の精神的な動きを規定し、時には制限するものです。
今回は各章のまとめを抜粋するが、興味があったらこのサイトを見て欲しいです。
第一章
・フロイトの無意識とは、精神的なもので自分では意識できないが、各個人に持続的に存在するもの。主体の意識とは関係なく意識に影響を与え、各個人の精神的な動きを規定し、時には制限するもの
・フロイトは神経症(たとえば、ヒステリーや外傷性神経症(トラウマ)など)の患者を治療していくことや夢を分析することで、無意識が存在することを確信する
第二章
・フロイトの研究は局所論(第一局所論)→構造論(第二局所論)へと変化
・局所論では、心には「意識」「前意識」「無意識」の3層構造があると主張
・フロイトは「第一の部屋=無意識の部屋」、「第二の部屋=意識と前意識の部屋」として説明
第三章
自我
「超自我」、「エス」、「心の内外からの刺激=現実の外の状況」との間に立って個人を維持しようとするバランサーの役割をもつ
超自我
自我のなかにあるが、自我の働きを監視・抑制しようとするもの
所謂「良心」
エス
意識的なものへの転換が起こりにくく、それはただ非常な努力の結果可能になるか、場合のよっては決して可能にはならないという無意識
フロイトによると、エスは「沸き立つ興奮に充ちた釜」です。そこに欲動がうごめいているからです。
そして、そこでは快感原則(善悪の判断なしに快楽を求めていこうとする原則)が一切の過程を支配しています。つまり、個人の「無制限な情欲」を代表しています。
第三章のまとめ
・自我が今自分が意識し、考え、どう行動するか決めている主体だとしたら、その主体はエスの一部であるため、様々な欲求を実現しようとする考えも湧いてきたりする
・超自我の働きにより、性的な欲求のような社会的にふさわしくないような欲求は自我に認識される前に抑圧されたりもされる
・自我はエスの一部でもあるため、そのエスの影響を無意識のうちに自我も受けている
わかりやすく言うと
自我とは
「お腹空いた!」という欲求に授業中に襲われたとする。しかし授業中にいきなり弁当を広げて食べるというのはまずい。
なので、我慢する、バレないように少し食べるなど手段を考える。
つまり、自我を持つことで
人間は欲求を満たす現実的な方法を考えている
超自我とは
「道徳」や「社会規範」を理解した上で、
どうすべきかを考える心理を「超自我」と呼ぶ。
自分の欲望よりも、社会とか集団にとっていいことをしようとする心理
エスとは
簡単に言えば、動物的本能・欲求
エスが暴走しないように、自我、超自我がコントロールしている。
ミルグラムに置き換えれば、
性癖、好み、その時の気分、このキャラの青眼が見たい、赤目がみたい等々の欲求を、あくまでも根拠を示して、真相を紐解いて、しっかりと処罰をしなければいけないという解釈になるのでは。
つまり
記憶のない『エス』は本能のままで動くしかないから、依代にしている私達が考察という形で理知的な判断を下さないといけないと考えられる。
3.アンダーカバー
『アンダーカバー』歌詞考察
“嫌い”対”OK”の境界線を
我儘のまま終わっていいの?
The border between “Hate” vs “OK”
Is it really ok to be done with deciding with just your EGO?
Will you be able to forgive them after listening to their sins?我儘
他人や周囲などの都合や事情を考えずに、自分勝手に振舞ったり発言したりすること。
我侭
自分の都合を中心に物事を考え、行動するさま。他人の都合を顧みないさま。
我が儘
【一】[名・形動]自分の思いどおりに振る舞うこと。また、そのさま。気まま。ほしいまま。自分勝手。「我が儘を通す」「我が儘な人」
【二】[連語]《代名詞「わ」+助詞「が」+名詞「まま」》自分の思いのまま。
エゴ
1つは心理学で使われる用語で、自我・自尊心を意味します。
もう1つは、利己主義という意味の「エゴイズム」を短縮した言葉としてのエゴです。エゴイズム(利己主義)は、他人の迷惑を考えず自分の利益のためだけに行動するやり方、考え方のことを指し、そのような考え方の人は「エゴイスト(利己主義者)」と呼ばれます。
だから、このキャラの赤目が見たい、青眼が見たい、赦された姿が見たい、赦されなかった姿が見たいというのは、はっきりいえばそれはただの我儘
例えば
ユノ
ユノがもしパパ活をしていたと仮定して、それで堕胎してしまった可能性があるとしても、
「それがユノの恋愛だから」なんて肯定して大丈夫ですか?
ユノの発言で、「看守さんの好き嫌いでしょ、そんなの」という発言が出て、「ユノに対して(看守が)好意的だから赦すにしました」なんて、ユノが「やったー嬉しい、私のこと好きなんだ」なんてなると本気で思いますか?
自分の体に金額をつけて価値を決めるという自分の体を売り物に使う女の子を肯定したら、また同じことを続けてしまうかもしれないのに、現時点では、エスはユノを買ってたパパと同類の認識になってしまった可能性が非常に高いと思います。(少なくともユノには、パパと同じという認識で終わっています、つまり、営業スマイルは見せてくれるし振舞ってくれるけど、本心を見せてくれる可能性は下がったのではないでしょうか
フータ
赤目が見たいという欲求が強く向けられた囚人で、試しに第一審で「赤目を見ようよ」と言われた程。看守である立場の人たちから、第一審という実験の『お試し』のように扱われた上に、赦さないにした反応を見たいという罰したいという欲求を強く向けられた存在だと思います。
フータの「ジンケン侵害だ!!」という言葉はここではかなり的確ですね。
ムウ
いじめを受けてるから、可哀想という強い同情に流されて、赦すを選ばれたような印象がかなり強い囚人。
いじめを受けて、いじめを我慢してその限界きたら主犯格を殺した方が、自分が虐められなくなるという意味で効率が良いのに、どうしてその人を殺したか、水を掛けられたのにも関わらず、一切濡れてない制服は?という疑問に一切答えがない状態で、ただいじめられてたのが可哀想だったから、という一方的な同情でエスは肯定してしまったということになる。
犯罪心理学の話になるのですが、とある理論で、無意識的に気づいて欲しいから分かりやすい嘘をつくという思春期にある理論があるのですが、思春期のちょうどユノやムウ位の年齢にも当てはまる理論になります。
わかりやすく言うと、その嘘に気づいてくれた時に、初めて「この人は本当の私にも気づいてくれるんだ」って安心感に似たようなものを与えることが出来るという考えになる理論です。
ユノやムウにもそれはあった可能性があります、もう性欲と同情で赦されてしまったけど....だからもう、「本当の私に気づいてくれたんだ」って安心させてあげることはできないかもしれませんね
シドウ
シドウははっきりとわかる極刑を望んでいる囚人、そのシドウに「生きて苦しんで欲しい」から「赦す」というのはかなり残酷な判断だと思いませんか?ただでさえ罪の意識が強くて、極刑を望んでいる人を赦すにして、生きて苦しめたまま放置するということになってしまうし、それは性癖にかなり寄っていませんか?
アマネ
身体的虐待、精神的虐待説は正直福祉観点や心理学観点から見れば、かなり低いと思う。
しかし、まぁ殆ど0%の可能性だけど、虐待を受けてるとして、周囲が悪いからアマネは悪くないと言って肯定するのは間違ってる。
今、掛かっているのは、アマネだから、周囲の人間のことを言い訳にして、アマネの本当の真実に踏み込むのを避けてるだけ、それこそ虐待を受けてる人間は周囲の影響を受けまくる人間だって馬鹿にしてることになる。
アマネは年齢的に第二次性徴期が当てはまる。反抗期になる子供が増え始める時期である。アマネが「貴方は間違っている」と看守に対して言ってくるのも反抗期の一部、だけどそれをはっきりと「間違っている」と伝えてあげない限り、アマネは一生成長できません。
周りが環境が云々に流されて、アマネのそれを肯定するなら、もうアマネは人間として終わってしまうと思います。むしろ褒める褒める褒めるの赤ちゃん扱いと一緒です。
(反抗期を迎えない子供は犯罪率が高いという統計結果は出てます)
肯定して、アマネが周りに間違っているって教えられないまま、成長するとしてまた、放置するつもりですか?
「いい子になるしかない」って強迫的に思い込んで、苦しんでる子供を「そのままで良い」「それが正しい」と肯定するのですか?
投票はマヒルまで終わっていますが、投票は割とエス(本能)が強く影響を与えた結果になっていたのではないでしょうか
つまり、エス(es)がとても暴走した状態
これからは、しっかりと考察してMVから掛けられた囚人達の思想や考え方を読み取って、審判に臨みたいですね。本能で動く動物のようにならないように。
そして
第二審、第三審があるから第一審は試しに赦す/赦さないにしようかというのは、キャラクター達のことを実験体として扱っている、ミルグラム効果が出まくった恐ろしい考え方ですから、今すぐに思い当たる節があったら、それはおかしいと気づいて欲しいです。
これはミルグラム実験だから流れに身を任せるのも一興的な考えがあるとしたら、論外です。資料を読み漁って来てください。
ミルグラム実験を絶対に肯定しないでください。
いくらアニメーションとはいえ、架空の人物達とはいえ、人生がある人間達なので。
実際にハルカで憑依型多重人格や、ムウで演技性や非憑依型多重人格、アマネで演技性、スーパーチャイルド、境界性など実在するものが扱われている
公式からファンタジーなヒトゴロシはないと明言されてる
山中さんが精神反応など心理学の知識をすごい持っている
ことを合わせると人生がある人間だと囚人達のことを捉える必要があると思います。
(それにミルグラム効果に流されて、実験の再試を成功させてもぶっちゃけ山中さんの手の中にいる状態で思い通りということになるし、敢えて反例を叩き出す方が面白いと思います)
公式から、
法律、感性、常識、道徳、本能、いずれを基準にして裁いても構わないと言われている。
看守として何を基準に裁くというのが自由、つまり、看守としての権限を与えられていると解釈できる。
しかし、しっかりとエスという本能を抑えるためにスーパーエゴ(冷静に根拠を出しながら囚人達の罪などを解いていく) つまり、考察を立てて囚人を見ないと、本能のままつき動きミルグラム実験の効果通りに残酷に振る舞う看守になってしまうという恐ろしい面がある。
ミルグラム実験はそもそも禁忌の実験
囚人を人間として扱っていない非人道的なものだから禁止されている。
心理学実験は実験者と実験参加者が対等であることが望ましいとされる
だから、心理学実験だと思うなら対等で、その人の後先を考えて裁く必要になってくると思います。
公式から自由に裁いていいと言われてるから、というのは我儘の一言に尽きると思います。
アンダーカバーで
「我儘のまま終わっていいの?」
という歌詞が含まれていますから、これは公式からの煽りではないでしょうか。
我儘のまま終わっていいの?
4.福祉観点から見て
ここの分担はみるやねです。
(福祉的によくある例としてユノの例になり、具体的にはユノの考察であげる内容になります。)
•まず援助交際を行なったりする人は、愛情に飢えてなければいけない
•自分に自信がない人が多い
•親と上手くいっていないことが多い
•金銭的にトラブルを起こしたり、親が金銭的トラブルを起こしやすい子が多い
(•過去に性的虐待を受けているケースが多い、これがあったら自分の体に価値がないと思い込んでしまう或いは自分は性行為をするしか価値がないと思い込んでしまう)
こういうのに一個でも引っかかると性的なものから逃れられなくなるケースが多く、異性トラブルに巻き込まれやすい。
そこから、殺傷沙汰の事件に発展して、再犯を繰り返すケースも少ないし、凄く現実的ではある。更生したとしても、10%以上の確率で繰り返すという話も児童福祉の現場で出ている
ユノタイプへの接し方の基本は、
ユノの本心をよく知り、そういう事をしてはダメ、体をもっと大事にしなさいとよく叱り、最後に生まれて来てくれてありがとうとよく褒めることが大切。
・普通の人がしてもらうことをしてあげること
・普通ということが幸せっていうことを教えてあげること
これが大切。
普通の価値観を教えることがユノに対しては一番の有効打になる
・パパ活、援助交際をしてて、いくら隠してるといえでも、普通の親や家族だったら気付く
→赤ちゃんができる、という段階で娘がおかしくなったと気付くのは遅すぎると思う。
→親にあまり見られてなかった可能性が生じるのでは?
→だから普通に叱られたことも、褒められたことも少ない可能性がある。
「ユノは非常に強い愛着障害、愛情欠乏症を抱えてる可能性が高く、本来は自分の体に価値はない、だから自分の体に金額をつけることで自分自身に意味をつけてる」と仮説を立て、
「その関係から離れるのが無理なほど依存してしまう」と考えるとしたら
だから、最初に大事だったのは、
ユノにダメだよ、ってエスが叱ってあげることが大事でしたね。(エスは看守だけど)
ユノを買ったパパや援助交際の相手、周りにいた大人みたいに、ユノの体や本心を何も考えずに「好き」みたいなノリで肯定するのは一番ダメ
→ユノは看守も信じられなくなってさらに本心を出せなくなるし、これからのユノの人生も体も心も全て壊されてしまう
本気で肯定するなら、本心も全てを本当に知ってから。
価値が無いという自分とか、自信がない、こういう行為(S〇X)をするしか価値が無いというユノの気持ちを全てそれは違うと否定してあげて、最後に「今までよく頑張ったね」と褒めてあげることがユノを救う一番の方法だと思います。
もう、第一審終わっちゃったから、
第二審第三審でどうにかするしかないけど、本当にユノを幸せにする為に、間に合うか間に合わないかの瀬戸際になってしまったと思う。
以上福祉観点から見てユノに焦点を当てて解説しました。
全てを完全に理解しようとせずに、ただ肯定するだけは良くない。
5. ジャッカロープ

ジャッカロープ(Jackalope、ツノウサギ)は、アメリカのワイオミング州等に棲息すると言われる未確認動物である。
名前はノウサギを意味するジャックラビット (jackrabbit) とレイヨウを意味するアンテロープ (antelope) のかばん語であり、外見は、頭部にシカの角が生えているウサギである。
ジャッカロープを撮影したとされる鮮明な写真資料は存在するが、生体の目撃記録は無い。また、先住民であるネイティヴ・アメリカンの伝承の中には全く登場せず、ジャッカロープについての伝承は、白人の入植後に現れたとされる。
群れで生活していると言われている。言い伝えでは、
・人の声真似が得意である
・ウイスキーが大好物
・カウボーイのキャンプファイヤーの場に時折現れる
・乳が万能薬となる
とした特徴が挙げられている。
実際には、ウサギの剥製に鹿の角を付けた作り物がその正体とされ、アメリカでは現在も作り物のジャッカロープの剥製が土産物として売られている。
2005年8月には、アメリカで、頭部に角のあるウサギという、ジャッカロープの特徴を備える生物の死骸が発見された。獣医のデニス・ベッシュトールドが調査した結果、「通常のウサギが伝染力の強いウサギ乳頭腫ウイルスにかかり、それにより角型のイボが頭から生えた」と結論づけられた。
古典における「角の生えたウサギ」
亀毛兎角(きもうとかく、兎角亀毛とも)という言葉が有るが、これは南北朝時代に存在した梁で編纂された『述異記』の「大亀生毛、而兎生角、是甲兵将興之兆」を出典とする。亀に毛が生え兎に角が生えるのは有り得ない事で、そのような異常事態が起こるのは戦乱の凶兆であるという意味だが、転じて、有り得ない事の喩えとして使われる。仏教用語としての亀毛兎角は、現実に存在しないもの、現実に存在しないものを存在するかの様に扱う愚かしさ、有って無い様なもの、曖昧な存在という意味で使われる。
日本語としては、兎角(とかく)、兎に角(とにかく)と言った言葉で使用される。
16世紀から18世紀のヨーロッパでは、レプス・コルヌトゥスもしくはhorned hare(角付き野兎)と呼ばれる角の生えた兎が居ると信じられていた。コンラート・ゲスナーの『動物記』によればザクセン州に生息していたとされる。
(Wikipedia様より)
ジャッカロープは人のエゴによって作られた贋造物
⇒つまりは存在しないもの。
6.終わりに
まず、ミルグラム実験についてまとめた。
ヒトラーの部下であるアイヒマンがただ普通の人だったが、一定の条件下で残酷になったという話を背景に、一定の条件下で人は残酷になるというミルグラム効果を実証するために、ミルグラム実験が行われ、数年後にスタンフォード実験が行われた。そしてミルグラム実験の信憑性を揺るがす事件が起きて、それが軍人の銀行強盗というものだった。タイムラインでフータとカズイが銀行強盗の話題に言及していて面白いと考えた。
次に、看守エスについての考察をまとめた。アイヒマンである説、S(サディズム)、ドイツ語でのエスの使い方(中性名詞という意味)、そしてフロイトの自我、超自我、エスの方に言及した。
次に、アンダーカバーの歌詞を一部引用しながら、本能(エス)について考えながら、現段階でも審判の結果にどれほど本能(エス)が関係しているか考察を立てた。
最後に、ジャッカロープの情報についてまとめた。
心理学実験は、実験を行う立場、協力者が対等であることが原則。ミルグラム実験は非人道的なものとして学ぶほど、非常に恐ろしい実験である。
-エスは本能だから、それを抑える超自我と自我の役割は重要、だからしっかりと考察を立てる必要はある。
本能のままで動くのは動物だけで、人間は考える脳がありますから超自我と自我は重要です。
我儘で赦す/赦さないのを決めるのは、囚人達の人生がかかってる分推奨しません。
(「キャラクターじゃん」で終わる理論かもしれないけど、公式がファンタジーじゃないと言ってるし、ここでは精神反応と述べていますが、実際に存在する精神疾患が扱われているため、所詮二次元と片付けてはダメな事だと思います。)
それでも本能で動きたいなら......どうぞ。
“嫌い”対”OK”の境界線を 〔我儘のまま終わっていいの?〕
すべてを知った 僕はちゃんと赦せるかな?2021/05/20
追記
しかし、ミルグラム実験自体はヤラセ、サクラとも言われています。
サクラ、ヤラセと言われてる実験を今皆さんは現実のものとしてしまいました。
自由に投票できるから、と暴走してしまった結果だと思います。
看守としての宣誓
私達の考察では、実際に存在するものを扱っています。その為、説明するべきことがあります。何故、精神疾患という言葉を使わずに精神反応という言葉を使うかという理由について説明します。
まず、精神疾患という書き方は人によっては本当に傷付いてしまう言葉です。私自身や相方は精神疾患を抱えています。その二人で精神疾患という言葉やその病気だから否定するという意見を見てると苦しくなるから、だから二人で使わないと決めました。それに、ミルグラムという囚人を裁くシステムの中で、もし何か名称をつけられたもので苦しんでいる方がいて、ミルグラムに来たと仮定して、その時に自分が持っているものがあるから、だから赦さない、否定するというのを見た時にとても傷ついてしまうと思います。なので、否定するという意見を出す時は、これから先その思想や考え方で、周囲と軋轢を産んでしまい孤立してしまう、その為また同じようにヒトゴロシを繰り返してしまうなどの可能性を相方と沢山話し合い結論を出しています。そして実在するものを扱うからには、サイトの内容だけではなく論文や実際にその精神反応を持っている方達、そして精神科医の先生(相方の知人)に話を聞いて話し合いながら考察を出しています。サイトで拾い上げてきた情報だけでは間違った知識を広めてしまう可能性があるのでよく議論しています。間違った知識や誤解は人を一番傷付ける方法です。なのでできる限り誤解を産まないように、精神反応についてを理解していただけたら幸いです。そして心因反応という言葉がありますが、心因反応と表記した場合、専門家の方達のお目汚しになってしまう可能性がある為、その言葉の使用は避けています。
精神反応という言葉を使うと、精神疾患という限られた言葉を使用するより、反応という表記をすると「誰にでもあることなんだ」と知って貰えると思い、精神反応という言葉を相方と作りました。精神反応とは相方と作った造語になります。
精神反応はそれぞれの人が生きてきた環境によってできるあくまでも過程にしか過ぎないものです。家庭環境が違ったら、周囲の人との関係が違ったらもしかしたら同じように道を踏み外してしまう可能性は誰にだってあります。
精神反応は自分とは違う病気を持った人間ではなく、同じ「人」が持っている個性であり、特徴です。決してこれを持っているからダメではなく、向き合ってその精神反応になった過程を見つめていくのが精神解剖だと思っています。アンダーカバーの歌詞でもありますから。
精神反応はそれぞれの環境で生きてきた「人」の個性であり、特徴なのでできる限り寄り添って考えていきたいと思っています。
また、実在するものを取り扱っていますが、これを持っているから犯罪を犯すという差別を助長させる気持ちは一切ありません。精神反応は、「人」がそれぞれ持っている特徴であり、個性です。キャラクターではなく、様々な個性や特徴を持つ「人」として、私たちは向き合いたいと考えています。
考察について
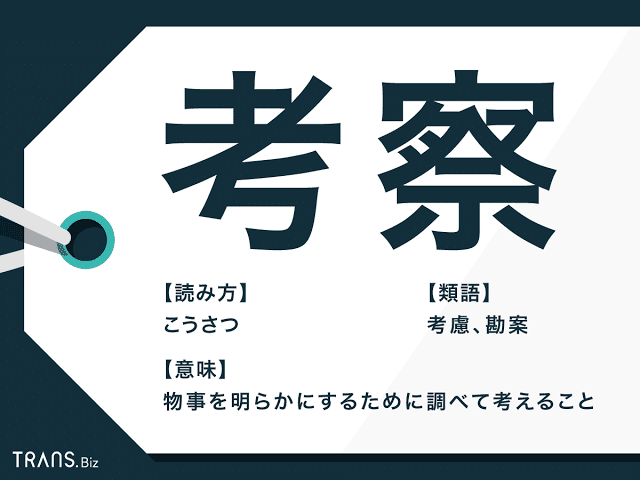
物事を明らかにするために調べて考えることなので細部に渡って考えることを目的としています。その為に、長く感じるほどの考察に仕上がっています。表面だけで読み取れることだけではなく深く読もうと心掛けているため、考えすぎでは?というほどになっていると思います。あくまでも可能性なので、皆様の考察の参考にしていただけると幸いです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
