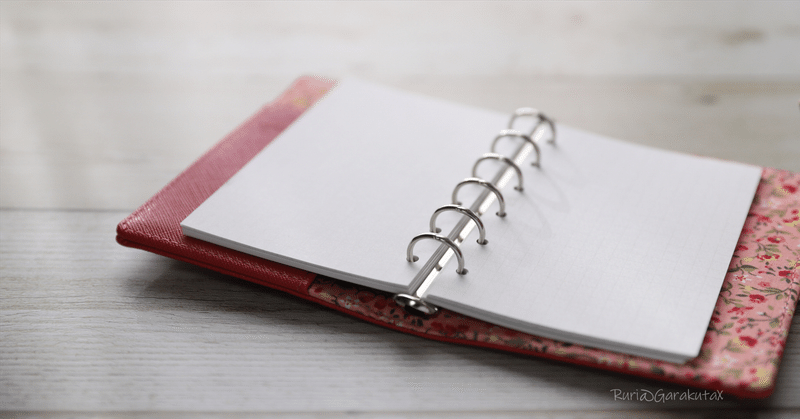
『人を賢くする道具 』「第1章 人間中心のテクノロジー」のまとめ
概要
私たち人間の脳は、現代的な文明に見あうレベルの能力は持ち合わせていない。人の能力を支援するテクノロジーを自らで作ることで発展してきた。言い換えれば、人の能力は「自分の能力を向上させる道具だて」を自分たちで作れる、というメタさにある。
そのテクノロジーはよかれあしかれ人間に影響を与える。頭をうまく使えるようにもすれば、うまく使えなくするようにもする。もし、頭をうまく使っていきたければテクノロジーをどう作り、どう使うのかに注目するのが重要である。
しかし、そうした観点において「人間」が忘却されつつあることを著者は懸念する(機械中心の見方の浸透)。人間の認知は単純ではなく複雑であるが、機械中心の見方では単純なものが好まれる。この不一致が人間にとってよくない結果をもたらす。
関連して、テクノロジーの適用が問題になる。人間の認知は体験的なものと内省的なものがあるが、エンタテイメントを中心として使われているテクノロジーは体験的な認知を助ける反面、内政的なものは助けない形になっている。そもそも、二つの認知は対称ではない(たとえば重力環境下において上方向と下方向は対称ではない。放置していれば自然に下に落ちる)。体験は比較的簡単だが、内省は苦労が必要。よって、より注意を向けるべきは内省的な認知を助けるようにテクノロジーをデザインすることであろう。
整理
上記のように、第一章では現代的(執筆当時の1993年頃)な状況が確認された上で、人間の認知の特性を踏まえながら、こうなれば良いだろうと期待される状態が整理される。
一つ目のポイントは、人間存在にとって「テクノロジー」は欠かせない存在だという点。単に便利というだけでなく、人間の有り様そのものに関わってくる。この「テクノロジー」は、マクルーハンなら「メディア」と呼ぶだろうし、卑近に言えば「道具」となる。著者は「アーティファクト」という表現も使っている。人工物、くらいの意味。物理的な人工物もあれば、情報的な人工物(言語や論理)もある。それらも人間が使う「道具」と言えるだろう。
人間は人間として独立した存在ではあるものの、その中身は閉じておらず、むしろそうした外部との相互作用によって成立している「生態系」のようなものだと考えられる。テクノロジーもそうした外部に位置づけられる上に、それは人間が自ら作り出せるものである。だからこそ、テクノロジーについてはわれわれ人間自身が責任を持つ必要がある(彗星が地球にぶつかることに人間は責任を負う必要ないだろう)。
言い換えれば、人間について考える差異に「人間」だけを考えればよいわけではなく、その周辺も視野に治める必要がある。本書はその中でも「認知に影響を与えるテクノロジー」を視野に入れていると言える。
二つ目のポイントは、そうしたテクノロジーを考える上では、逆に人間について考える必要がある、という点。これは先ほどの構図を逆向きに捉えたと考えていい。つまり、人間が自身で閉じていないのと同じように、テクノロジーも閉じてはいない。人間との相互作用においてその役割が発揮される。よって、優れた技術のテクノロジーがあったとしても人間をおいてけぼりにするものでは、その評価は厳しいものにならざるを得ない。
合わせると「人間が使うテクノロジー」というものについて考察するのが本書だと言える。
三つ目のポイントは、本書の根幹を為す概念「体験的認知」と「内省的認知」の区別である。著者自身何度も強調しているが、人間の認知はこの二つだけではないし、また排他的に(二律背反的に)働くものでもない。あくまで本書の議論をクリアにするための便宜的な区別だと捉える。上で、この二つの区別はきわめて有用だと言える。
「体験的認知」は二重過程理論のシステム1に、「内省的認知」はシステム2に相当するだろうが、著者が採用したこの概念(用語)の方が文脈が豊かであり、状況を把握するのを助けてくれる──言うまでもないが、まさにこれが認知のテクノロジーなのだ──。
私たちは体験的・没頭的に状況に埋め込まれることがある。そうしたときは意識の働くは貧弱でむしろ無意識的に動ければ動けるほどスムーズになる。その極地がいわゆるフロー状態であろう。熟練の極みだ。
一方で私たちは内省的・俯瞰的に「考える」こともできる。これは倉下が「思う」と「考える」を区分したのと同じ意味合いにおいてそう言える。そこでははっきりと意識が駆動しており、状況や状態について考察し比較し分析し反省することができる。込み入った計画立案などもこのモードによって行われる。変化を生む、未知の状況に対応する、という場合にはこうしたモードが活躍する。
人間はこの二つのモードを用いながら、日々を生きている。そして、それぞれのモードにおいて役立つテクノロジーのデザインは異なる。
これが本章の、引いては本書全体の大きなメッセージだと言えるだろう。
コメント
著者は「人間中心のテクノロジー」という表現を用いているが(原著を当たっていないので原文がどう表現されているのかはわからないが)、この言い方だとあまりに人間至上主義に捉えられるかもしれない。
本書を読めばわかるが、これは「機械中心になりすぎている状況に、もっと人間の視点を取り戻そう」くらいのスローガンだと捉えていい。本書も「反テクノロジーではなく、人間擁護」という表現を用いている。
人間が快適であればその他はどうなってもいいし、そのためにテクノロジーは従事せよ、という視点ではなく「あまりに人間存在が軽んじられていませんか」という警句であることは念頭においておきたい。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
