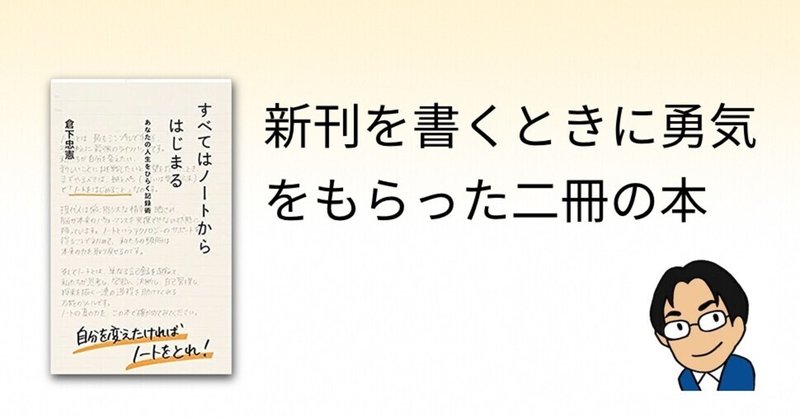
新刊を書くときに勇気をもらった二冊の本
2021年7月23日に新刊が発売になった。
この本には、結構な思い入れがある。もちろん、これまで書いてきたすべての本に思い入れがあるわけだが、輪をかけていっそうそれが強い、ということだ。
一つには、不調からの復帰一冊目という点がある。一時期まったく文章が書けないほどの不調に陥り、仕事どころか人生の道行きすら見失いかけていた状況があったのだが、なんとかそこから回復して文章を書けるようになり、こうして本一冊を書き上げることができた。
体調が回復してきて、ひさびさにパソコンを開けて文章を書けるようになったとき、喜びに打ち震えたのを今でも思い出す。ああ、自分は文章を書くことが好きなのだと。いや、心の底からそれを必要としているのだなと、実感できた。そういう経緯があったので、何はともあれ本が書き上がったこと自体を言祝げる。
また、逆説的に聞こえるかもしれないが、そうした経験を経たおかげで本の執筆について開き直ることができた。妙な規範意識というか「こういうタイプの本ならば、このように書かれるべきだ」という先入観に固執しなくなった。せっかくこうして文章を書けるようになったのだから、その体験を最大限良いものにしたい。危機はいつ訪れるかわからない。もしかしたらこの本が最後の本になるかもしれない。なのに、不完全燃焼していてよいだろうか。否、断じて否。
というわけで、これからは一番大きな振り幅で本を書こうと思った。格闘ゲームの大パンチのような執筆。空振りしたときに隙は大きくなるが、それでも最大威力の攻撃。そんな本を書こうと努めようと思った。だいたいにして、もう40歳をこえている。細々した仕事もやってはいくが、一つのまなざしとして「大きな仕事」は常に視野に入れておきたい。
そういう思いを抱いたのは、何も不調の経験からだけではない。二つの本の影響も強い。
頭を揺さぶられた『勉強の哲学』
一冊目の本は、千葉雅也さんの『勉強の哲学』である。拙著の「おわりに」でも示しているが、私は『勉強の哲学』を読んだときに、ほんとうに頭をガツンとやられたような感覚があった。「ああ、本ってこういう書き方をしていいんだ」という直覚があった。それまでの私が一つの理想像としていた「正確に整えられた章立て」とは異なるビートのある章立て、緩急のある文章、そして読者を予想外の場所に連れていく筆さばき。
そうした文章は、「実用書・ビジネス書」以外の場所ではよく経験していた。たとえば哲学書がそれだ。いや、そもそも『勉強の哲学』はタイトルからしてきちんと「哲学書」を名乗っているではないか。それが実直に実行されているだけとも言えるが、しかしたしかにそこには「実用書・ビジネス書」としての存在感もあるのだ。
その感覚は「とわられない」在り方なのではあるが、しかし単にフリーダムやアナーキーというのではない。あたかも一つのノリから別のノリへ知らない間に移っていくような──それが『勉強の哲学』の主題の一つでもある──、そんな読書体験がそこにはあった。私はそれを単純にかっこいいと思ったのだ。教育的効果だとか、売れ行きだとか、文体の巧拙とか、そういう話の前に美的感覚としてかっこいいと思った。私の中にあった、一つの規範意識(「hogehoge本」とはこのようなものだ)が、そのとき書き変わってしまった。もう、後戻りできないほどに。ポイントオブノーリターン。
単に知識を伝達するのではなく、読み手の考え方を揺さぶってしまう本。それがつまり、私にとっての「大きな仕事」である。無論、知識を伝達することは大切な仕事だ。欠かせないとすら言える。ただ、自分にとってもはやそれだけでは物足りない感じがある。一つの目標として(つまり達成可能かどうかはさておき)「大きな仕事」を目指したい気持ちになった。それが『勉強の哲学』からの影響である。
(ちなみに、気がついた人は気がついているかもしれないが、拙著の「はじめに」の冒頭の一文は『勉強の哲学』インスパイアである)
光を照らしてくれた『独学大全』
もう一冊は読書猿さんの『独学大全』だ。この本も「異例」であり、よくある本の形式から逸脱(それも著しく)している。拙著では一家に一冊あればよい本とこの本を紹介しているがこれは嘘偽りない感覚である。私たちは学び続けることが必要であり、2時間で読めて3日後に役立たずになる本ではなく、この本のように相方となってずっと「引いていける」本があれば心強い。
でも、それだけではない。私が『独学大全』から受けた影響は、この本がものすごく支持されている、という一つの事実である。どう考えても「やさしい」本ではない。言い換えれば、読者に万能感を与え「いい気分」にしてくれる本ではない。人間ってダメなやつだ、という悲しい現実認識からスタートしている。一方で悲観したり、「ただやればいいんです」のようにほとんど虚無主義に近い放任スタイルでもない。人間はダメなヤツではあるけども、そこからできることはあるんだよ、というメッセージが発信されている。そのメッセージが支持されているのだ。
読者を弱者に固定して「この方法さえあれば、あなたはうまくいきますよ」と説くようなものではない。万能感だけを与えて、リアルな状況をまったく考慮しないノウハウでもない。そういう、「これまでのビジネス書の書き方」とは一線を画した本の内容が支持されているのだ。つまり、読者はそこにいるのだ。
私たち物書きは、いつも見えない読者に向けて本を書いている。見えないことは恐怖であり、必要だと思う決断でも十全に下せないことは多い。しかもそれが、ビジネス的な影響も加味されるならばなおさらだ。
しかし『独学大全』は光を与えてくれた。これまで見えていなかった読者の存在を感じさせてくれた。そのことは、私の本の売れ行きに何の確約も与えてくれはしないが、少なくとも「賭ける」ための勇気は与えてくれる。それで十分だ。もともと執筆はバクチであるのだから。
さいごに
ご存知の方も多いだろうが、そのような二冊の本に影響を受けて執筆された『すべてはノートからはじまる』は、なんとお二方が共著者である『ライティングの哲学』と同じレーベルから同じ日に発売となった。その事実を知った私のアンビバレントな感情は推して知るべしである。
ともあれ、現状いただけている感想は好意的なものが多い(私が事前に予想していたよりもはるかに多い)。本は読者のために書かれるのだから、もうそれだけで十分である。願わくば、私が受け取ったものを、それとは違った形で読者の皆様が受け取ってくれていることを。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
