
J・コールの〈無謀〉な夢を読む ("The Audacity" By J. Cole)
Writer: @vegashokuda
ニュー・アルバム『The Fall Off』への序章でしょうか? J・コール(J. Cole)がシングル2曲のパッケージ『Lewis Street』をリリース!
コールの現在の立ち位置が窺える内容となっており必聴なのですが、それとほぼ時を同じくして、スポーツを扱うメディア=The Players' Tribuneにエッセイを寄稿しています。
ここでは私の所感を述べることはしませんので、ぜひ下掲の翻訳をお読みください。
第1章 – 2つの山
木製で黒いスクリーンのうるさいデジタル時計が、赤く光る数字で「6:00」を示していた。目を開けると、小さな寮の部屋をシェアする2人のルームメイトを起こさぬよう、すぐさま身体を転がしてアラームを止める。外はまだ暗い。「もし行くなら、6時15分までに出ないといけないぞ」と自分に言い聞かせる。今朝6時半からトライアウトの第2ラウンドと最終ラウンドが開かれようとしている、セント・ジョンズ大学男子バスケットボール部の新しい練習施設=Taffner Field Houseまでは、徒歩でキャンパスを横切って10分ほどだ。俺は初日から召集がかかってきた、10人の有望な候補者の一人だ。最後の決断に考えを巡らせながら、ベッドに横たわったまま天井を見つめていた。
字面だけ見ると、大学バスケットボール・チームのロスター入りを果たすかもしれないと考えるのは、ワクワクすることのはずだった。でも、その前の24時間、俺はずっと悩んでいた。その1年前、書類の手続に不備があったせいで、1年生でトライアウトに参加する機会を逃した。もう同じ過ちは犯さないと自分に誓った。その1年間は、全国からやってくる優秀なライバルたちを相手に週5日、キャンパスでプレイした。セント・ジョンズにもバスケ選手はいた。高校バスケでプレイしていた奴はごまんといたし、中にはディビジョンⅠ[1]の弱小チームなら簡単にやっていけそうなプレイヤーもいた。これは私見にすぎないけれど、この小さなバスケットボールのコミュニティで、俺はトップ選手の一人だった。
ただ、俺は遅咲きだった。高校でもプレイしていたけれど、高4[2]の年が終わって初めて本当の自信を持ち始めた。俺は6フィート3インチで、高い身体能力と競争心を持っていた。基礎的なスキルで大きく欠落している部分を、クリエイティビティとテクニック、そして意志の力で補っていた。俺が19歳の時のゲームを一言で形容するならば、それは〈ポテンシャル〉だった。
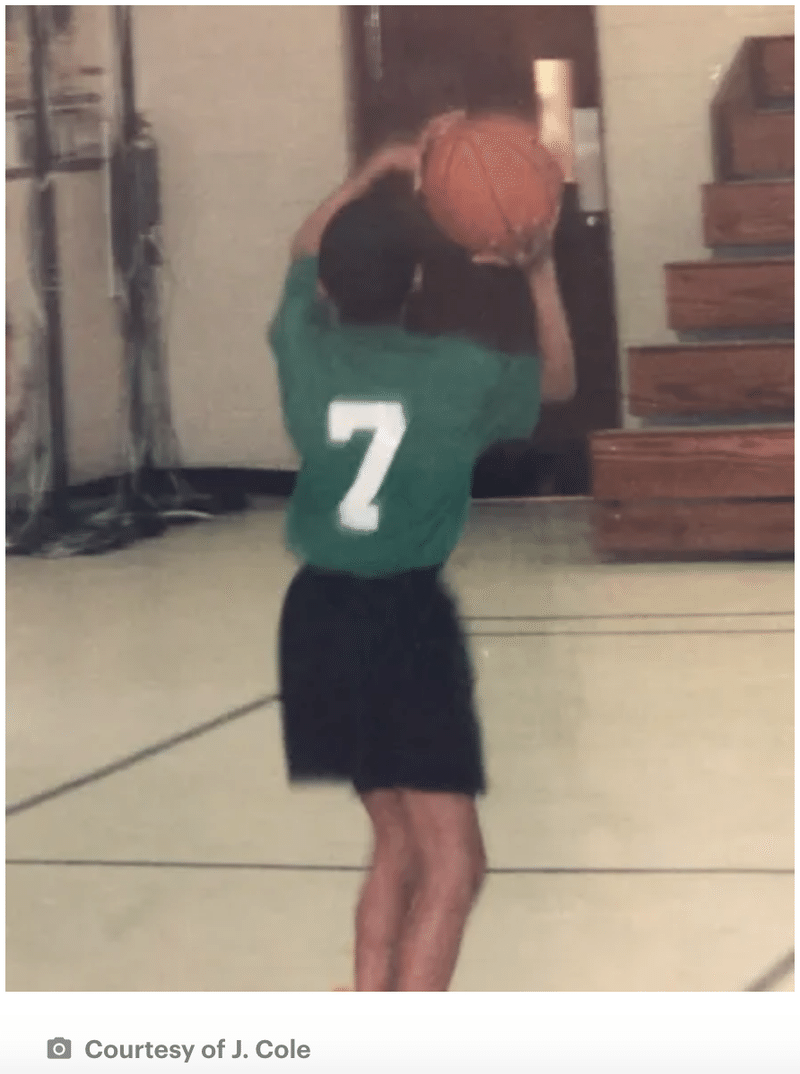
そのポテンシャルはトライアウト初日に開花した。他の50人くらいの奴らと、Big Eastプログラムのベンチに永久に腰掛けるチャンスを本格的に争った。端的に言って、その日のコートで、俺はカマした。次々にゲームをプレイしドリルをこなすうちに、その日の初めに感じていた不安は、このフロアで自分がベストなプレイヤーかもしれないという自信に満ちた気づきに取って代わられていた。「マジか。俺が大暴れしてこのチームを作り上げられるぞ」と思った。次の日に再び召集される10人のプレイヤーの一人として自分の名前が呼ばれた時、実感が伴った。
チームに入れる可能性に、間違いなく子供のような喜びを覚えた。その日中、あの赤いジャージを着てマディソン・スクエア・ガーデンでプレイする(レイアップの列に参加し、ベンチの端から大きな拍手を送る)のを想像した。それに、またチームの一員になれることは、自分にとってすごく特別な意味のあることだった。高校時代以来感じていなかったファミリー感・帰属意識。数えきれないほどのジョークと素晴らしい思い出に加えて、チームでプレイすることは強い絆とアイデンティティをもたらしてくれる。たとえもしそのポジションが底辺だったとしても、だ。でも、大事なことがある。俺は自分のことをよく理解していた。実際にロスター入りを果たしたとして、底辺に留まるつもりなんてさらさらなかったのだ。
自分自身の分析結果はこうだった:俺には終わることのない〈進む力〉がある。本当に何かを成し遂げたいとき、俺は深く掘り下げて、それを達成するために必要な労働倫理と洞察力、忍耐がどんなものかを見出す。それを明白に示す最初の例として、母は次の話をしてくれる。いつしかNBAでプレイする夢をヴィヴィッドに描いていたティーンエイジャーの時分、俺は1年生でも2年生でも、JVチームから漏れた。そのどちらにも打ちのめされた。1回目は、14歳のエゴが「俺はチームに入った白人の奴の何人かよりは絶対上手い。こんなのどうかしてる」と吐き捨てた。そのちょうど翌年の落選は、自分が思っているほど上手くないのだとはっきり告げてくれる、必要としていた類の、目が覚めるような現実だった。その警鐘を受け取り、人生で初めて本当に努力し始めた。コートに立つ機会はわずかだったものの、3年生のうちに学校代表チーム入りを果たした。もう一夏を練習に費やし、4年生のシーズンまでにはスターターになっていた。これらは、ほとんどの人には大して重要でない出来事のように思えるかもしれないけれども、俺にとってはそれ以降の人生への鍵を開けてくれたものだった。「俺も山を登れるんだ」と、自分に証明することができたのだから。
基礎的なスキルで大きく欠落している部分を、クリエイティビティとテクニック、そして意志の力で補っていた。
その日、眼前に立ち現れた山は、D1でプレイすることよりもずっと高く立ちはだかっていた。心の中では、自分がチーム入りを果たせば、いつかリーグでプレイするという長年の夢に火が点くと分かっていた。自らを高めることに数えきれない時間を費やし、願わくば4年生までに少しでも出場の機会を得られる自分自身を思い描いた。その次には、卒業してかませ犬チームの職人的役割を果たし、海外リーグのロスターのスポットを狙う自分を思い浮かべた。全てはいつの日か究極の山頂である、ナショナル・バスケットボール・アソシエーション(NBA)にたどり着くために。
こうした未来を自分の中で描きつつも、俺には逃れられない現実があった。俺はニューヨークの学校に、違うミッションを持ってやってきたのだった。登頂すると自分自身に約束した、別の山があった。同じくらい急で、同じくらいたやすく滑落してしまう山。そもそも思い込みでもしないかぎり、登れるとは到底信じられない山。俺はラップ界のレジェンドになるためにニューヨークに来た。13歳でその芸術と恋に落ちた時、部屋の壁からバスケットボールのポスターを剥がし、代わりにヒップホップの偉人たちの写真やリリックを貼り付けた。バスケットボールと違って、ラップでは仲間の誰と比べても俺の実力は抜きん出ていた。ノースカロライナ州ファイエットビルからニューヨークに出てきたのは、その目標への、静かでありながら目標の定まった旅の第一歩だった。
その朝、ベッドに横たわりながら、俺は岐路に立っていた。左に進んでバスケットボールに人生を捧げ、遠くにあるNBAでのキャリアへの長く困難な道を歩むのか。それとも、右に進んでここに来た目的を果たすのか。時計が6:15を示すと、寝返りを打ち、顔を羽毛布団で覆って眠りに戻った。
第2章 – 再会
ここから先は
¥ 300
「洋楽ラップを10倍楽しむマガジン」を読んでいただき、ありがとうございます! フォローやSNSでのシェアなどしていただけると、励みになります!
