▼『生のみ生のままで』▼『うしろめたさの人類学』
▼『生のみ生のままで』(綿矢りさ、2019)。「私は」と一人称で語る主人公の25歳の逢衣は携帯ショップで働いているのだが、意地悪な客がいて「私」は悩んでいる。その意地悪な老夫婦のことを地の文で自然と「長津様」と呼ぶのが興味深い。ぶっちゃけ話を友人にする時に「様」はつけないだろう。読者はぶっちゃけられてないのだろうか。一方、この小説は女性間の恋愛を描いたもので、「私」は性行為の詳細も熱心に語るのである。語りと読者の関係が独特なのか、「長津様」に象徴される仕事の位置づけが独特なのか。
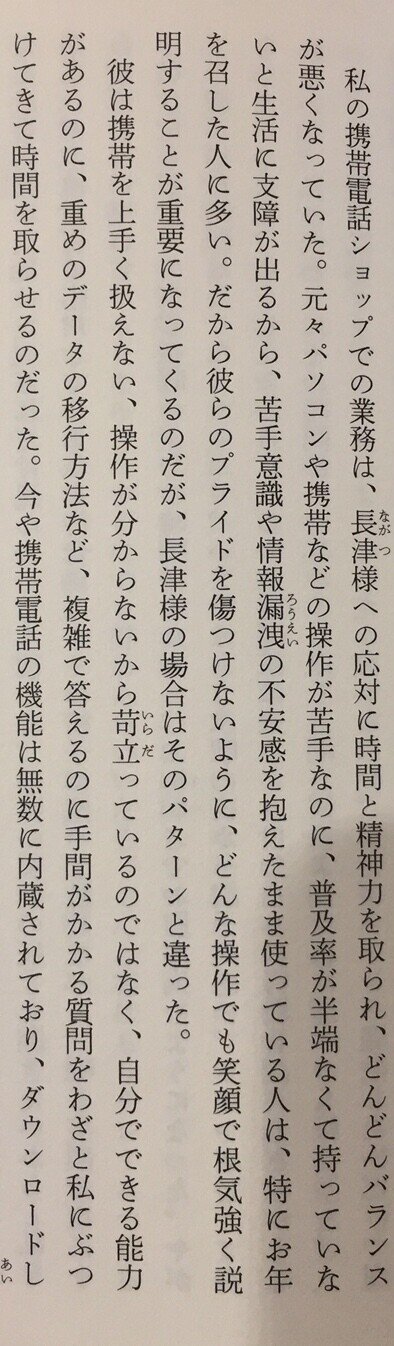
▼「私」に一目惚れする彩夏は女優だ。その容姿は「私」の目を通して説明されるが、彼女についてはテレビに出てくるような女優ということで、まあ適当にイメージできるのである。むしろ、語りを読む限り内面は平凡なのに彩夏が電撃的に一目惚れした「私」がどんな姿形をしてるのかこそが気になる。こうした描写を通じて、少しずつ像を結び始める「私」。
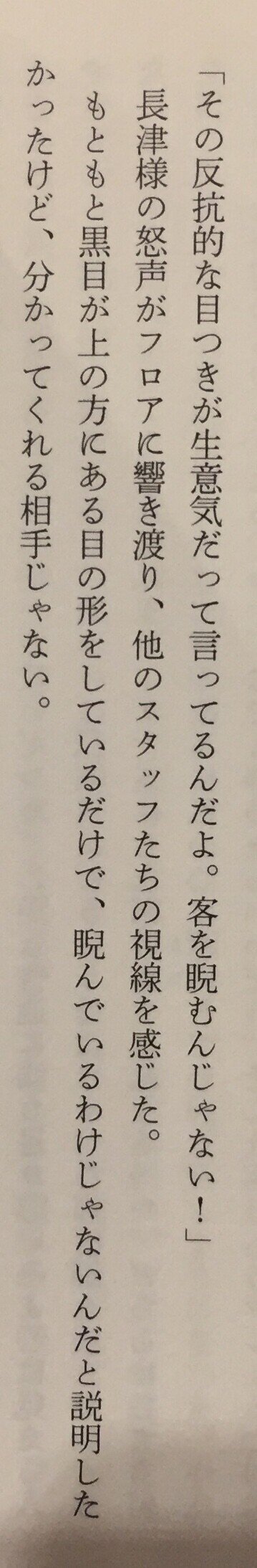
▼たまたま平行して読んでいた『うしろめたさの人類学』(松村圭一郎、2017)にこんな一文があった。白目の効用。そして、上の方にある「私」の黒目の効用。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
