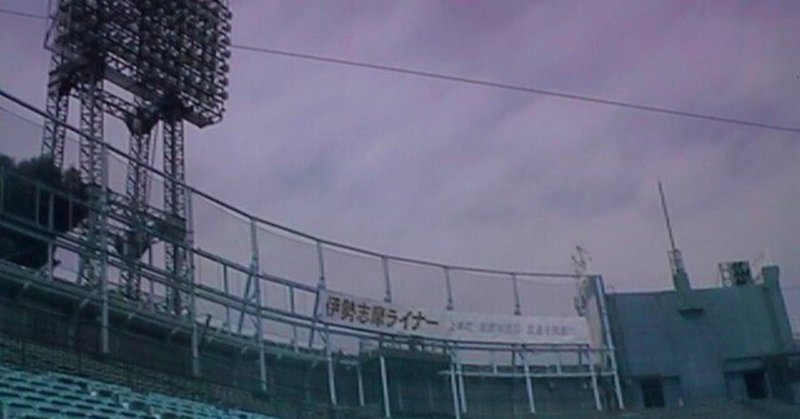
野球紀行/衰退と復活 ~藤井寺球場~
Sさんは、大阪ドームになってからファンが大人しくなったと言っていた。しかし、器が変わったからと言ってファンの気質までそう変わるものではない。ただ、「大人しくない」ファンがそれらしく見えるには、それにふさわしい空間があると思う。
鎌ヶ谷のファイターズスタジアムで、いつも球場全体に響き渡る高い声で応援する、地元では名物的な人物がいる。最近、東京ドームで観戦した時、どこからか聞きなれた彼の声が聞こえた。しかし彼がどこにいるのかわからない。鎌ヶ谷の時のようにはっきりと聞こえず、いつもの圧倒的な存在感が伝わらないのだ。
器の大きさが違うと言えばそれまでだが、人が、騒いだり吠えたりするのは、無限の空間に向けて精神を開放したいという本能があるからだ。だから屋根の存在がそのパワーをさらにスポイルしているとも考える。

それを思い、更に昨日の大阪ドームと今日の藤井寺球場を比べると、藤井寺球場に長年親しんできたファンには余計に大阪ドームが「よその家」みたいに思えるのかもしれない。ファンが大人しくなったというのもわかる気がする。極端に言うと、築地本願寺と国際フォーラムほどの違いがある。
それほど年代ものの上、人が「騒ぐ」様が似合う空間だから、一軍が使わなくなった現在は余計にさびれた感じに見えてしまう。しかし、怪我や病気からの再起という、野球の歴史の中でいくつも生まれてきたドラマが、必ずしも大観衆という舞台を与えられるわけではないように、世間からは忘れられかけたこの舞台で、また一つの復活劇が始まろうとしている。再起不能とまで言われた一人の投手の再起が、この廃れゆく舞台から始まった。8月26日、ドラマは舞台から人へ継承されたのだ。
平日の、ウエスタンリーグの試合らしく人はまばら。しかし少ない観客の多くが最前列に集まっているところに、熱の高さを感じる。これがいつもの光景なのだろう。でも今日は少し違う。ひときわ目立つテレビカメラを担いだ一団や、一目でマスコミ関係者とわかる人達も来ている。昨日Sさんが「明日、盛田が出ますよ」と言っていた通り、今日はバファローズ盛田幸妃投手の実戦復活登板の日なのである。

撲個人にとって盛田は、それほど印象の強い選手ではなかった。ずっとセ・リーグにいた投手だし、パ・リーグに来てあまり見る機会もなく、僕の場合、盛田と聞いて思い出すのは、京浜急行の按針塚駅からベイスターズ練習場へ行く道にある歩道橋に書かれた無数の落書きである。盛田を応援するメッセージが多いのに驚く。「愛してる」なんてのもあった。そんなわけで、「一部に熱狂的なファンを持つ投手」というのが僕の盛田に対する印象だった。その盛田が僕の中で「全国区」になったのは、昨年9月、脳腫瘍の摘出手術を受けてからである。
術後の盛田は、右半身がまったく動かず、野球生命を絶たれる危機にさらされていた。肘や肩の故障ではない。脳腫瘍である。あの津田恒美(故人)と同じ病気だ。選手生命どころか生命の危機でもある。後の報道によると、この試合ではストレートが最高139km/hをマークしていたらしいが、そんな数字以上に、また「球が走っていた」という見た目の印象以上に、「球そのものに"投げられる喜び"を感じた」とでも表現するべきでないかという感じの、今日の盛田のピッチングだった。
一回をノーヒットに抑え、引き上げる盛田を「8」と大きく書かれたカメラが写す。その辺の選手に遠慮なく「子供のために頑張れよ」と声をかける観客達は、ことさら盛田の復活登板で気合を入れるでもなく、おそらくいつもと同じであろう拍手と声援を送る。今、この空間を支配しているのは、復活に沸く熱狂よりも、もっと穏やかな幸福感のようなものに思える。それがかえって盛田が見てきた闇の深さを物語っているような気もする。

二回を1安打無失点に抑えた盛田は、そのままマウンドを高塚に譲る。同時にマスコミと思われる一団も姿を消した。せわしないものだ。しかしそれが彼らの仕事。この時の模様は『週刊ベースボール』9/27号でもカラーで紹介されている。
さて一般の観客の方は、盛田が下がってもテンションが変わる事もなくそこに居続ける。それにしてもみんなよくしゃべる。だが意外なことに、ひときわ大きな野次を飛ばす人物というのがいない。そういう「名物」的人物が多いと聞いていた藤井寺だが、今日は特別なんだろうか。だが、「みんなよくしゃべるけど静か」という環境が僕は一番好きだ。好きなのはいいが、とにかく点の入らない試合で、眠くなってくる。出てくる投手がみな良いピッチングをする。ドラゴンズの方は門倉。主力の調整登板は、普通2イニングくらいで終わるものだが、門倉はなぜかなかなかマウンドを降りない。ようやく六回に内匠のツーベースで活気づく。活気が出ると、バファローズファンの観客がみな顔なじみという事がわかってくる。高そうな望遠レンズで選手の写真を撮る女性がいる。選手の写真を撮るのでもなければ高いレンズなど買わないだろう。
また、選手を撮った写真のアルバムなんかを見せて回っている女性もいる。彼女に限らず、皆、仕事はどうしているのだろう。しかしここのファンの熱心さは、おそらく鎌ヶ谷より上だろう。

1-0でドラゴンズがリードのまま、ついに九回に。門倉が良すぎて、まったく打てそうな気がしない。僕が観ている時は強いはずのバファローズだが、2日続けて一、二軍揃っての敗戦を見るのだろうか。
だが、バファローズファンの常連(おそらく)達は、勝ち負けに無頓着に思えるほどのんびりムードだ。九回表に品田が登板。グローブを持った子供が品田を「おるおる、一軍から落ちた奴」。関西ではやはり子供も関西弁でしゃべるのだが、僕の感覚ではどうも彼らがおやじ臭く見えてしまう。
その品田に、攻撃の前、誰かが「品田、勝ち投手だぞ!」と声をかけた。その声には、応援でもハッタリでもなんでもない余裕のようなものさえ感じられた。まるで、これから当たり前のように逆転するかのように。
そうしたら、先頭打者の村上がいきなりホームラン。いつも同じ場所で野球を観ていると、何が起きるか予知できてしまうものかもしれない。六回よりも大きく沸いた。それまで「茶話会」みたいな雰囲気だったのが一変。盛り上がる時を心得ている。しかし衣川ヒットの後、バントで送るも安部ショートゴロ、平下三振でサヨナラならず1-1で延長無しの引き分け。ウエスタンの既定なのかわからないが、死力を尽くして引き分けという感じではないので、ちょっとモノ足りない。
藤井寺球場にやって来たのは、これが二度目である。最初に来たのは3年前の7月だが、あの当時と変わっていない。変わってはいないが、表舞台としての役目を終え、人気のない平日にやって来ると、年季の入った球場である事が改めてわかる。足元のコンクリや何度もペンキを塗り直したであろう手すり。とうとう電光化しなかったスコアボード。使い込んだ土鍋のように、いろんなものが染み込んでいる。これから衰退期に入っていく、そんな舞台で、この球場とはあまり縁のない一人の投手の、「表の」物語としては語られないであろう復活劇があった。
どうも僕は、ファームやアマチュアの試合に居合わせた時の方が、良いものを観れる傾向があるようだ。(1999.8)

[追記]
盛田幸妃はその後一軍に復帰し、2001年にカムバック賞を受賞。翌2002年に現役引退し解説者の仕事をしていたが2005年に脳腫瘍が再発し、闘病生活の末2015年10月没。享年45歳。
大阪球場にも日生球場にも西宮球場にもついぞ一度も行かず後悔していたので、藤井寺だけは行っておきたいと思っていたが、2度目の来場でとても大事なものを観れたのは幸運だった。
藤井寺球場はバファローズが大阪ドーム移転後は二軍の本拠地として使われていたが、2004年の球界再編騒動で消滅するバファローズの、最後の二軍戦とお別れイベントの後、2006年に解体された。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
