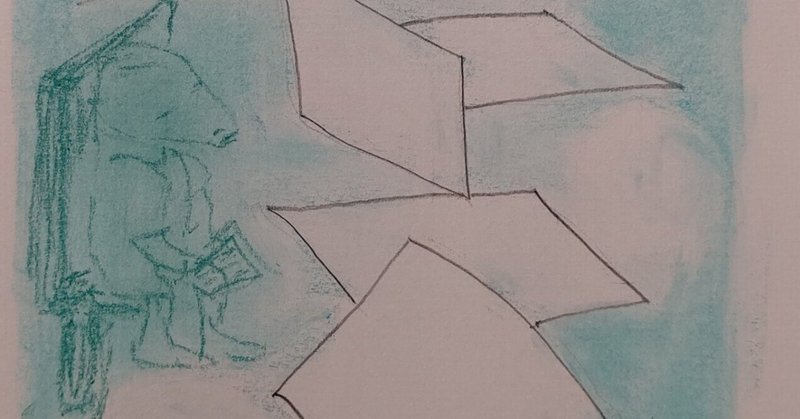
解読 ボウヤ書店の使命 ㉚-7
長編小説『ポワゾン☆アフロディテ№X』の読み直し続き。
《第二章
3 合鍵
手に入れた合鍵は艶々したピンクゴールド色だった。
――あっという間にできるなんて。
翔太は帰りの地下鉄の中で鍵を眺めながら、鍵屋の皺だらけの笑顔を思い浮かべる。痩せて皮膚は土色にかさつき、毛髪は少なくぱさついていた。水分の抜けきったバゲットのようにどこもかしこもすっかり老いていたが、眼球は生まれたばかりの子供のように輝いていた。いわば、この鍵と同じピンクゴールドを思わせる真新しい目。新古の共存はまるで鍵屋の存在そのものだ。建物の外観は古く、商店街のどん詰まりという最果ての立地だというのに、扉を開けて中に入れば見たこともない最新技術だ。スマートフォンに似た器具で写真を撮るやいなや、あっという間に合鍵が出来上がった。
――だけど、本当にこれで扉が開くのか。
翔太は掌の上に乗せた鍵をまじまじと見つめる。
あの八田一之介事務所の外階段を上った先にある二階の扉だ。気休め程度のスチール製で、もはや蹴破るだけでも簡単に開きそうだが、だからこそ、こんな艶やかな鍵が鍵穴に入るなんて、むしろ想像し難い。この輝きだけでもうすでに不似合い。
――本当に合鍵なのか?
マチ子ママから預かっている古びた銀色の鍵と、出来立ての鍵を重ね合わせて型を確認する。ぴったりと合う。間違いなく、これで開くのだろう。翔太は出来立ての鍵を一旦ぎゅっと握り締め、ポケットに仕舞った。
地下鉄を降りると、その足でタウンチャイルドに立ち寄り、日頃からマチ子ママに言われている通り、裏口のドアポケットから預かった鍵を店内に投げ入れた。コトンと床に落ちる軽薄な音がした。しんとしている。店仕舞いした後で、誰もいないだろう。
――マチ子ママって、不用心だよな。
善意で朝食を届けているつもりか知らないけれど、こんなことをしていたら従業員の誰でもが合鍵を作って、八田一之介事務所に侵入することができる。八田は迷惑じゃないのだろうか。実際、朝食配達に行った従業員の感想を総括すると、八田はマチ子ママの届ける朝食をそれほど歓迎していないようだし、ほとんどママの押しの強さに負けて受け入れているだけに違いない。探偵事務所という機密重視の場所なのに、マチ子ママのおかげで隙だらけにされている。
――いずれにしても、タウンチャイルドとはもうおさらばだ。
見収めと思って店の玄関側に回ってみると、きっちりとシャッターが閉まっているにも関わらず、無防備にもペガサスは中に仕舞われることもなく晒されたままで、どう見ても休日の遊園地でじっとしている寂しげな回転木馬だった。灯りの消えた電球をぐるぐると身体に巻き付けられている姿を見ると、幻想ですら飛ぶところを想像できない。
このペガサスにしても、ロダンがアーティストから預かったものの、気に入り過ぎて売るつもりがなく、わざと大袈裟に百万円の価格を付けていたアートだったが、《アフロディテ》にふいに訪れたマチ子ママは瞬間的に気に入って、値踏みもせずに言い値で買い取ったのだ。そのくせ、後は盗られようが知ったこっちゃないと言わんばかりに玄関先に放置している。誰かが出来心で盗んで持ち歩くには大きくて目立ち過ぎるが、それでも本気で計画的に盗もうと思えば盗めなくはない。ママは警戒心がなさすぎる。
――誰かがこれを持ち帰ったからと言って、絶対に百万円で売れたりもしないだろうけど。
翔太はペガサスの鼻の穴に小指を指し込む。じゃりじゃりしている。羽根の先には小さな埃のような虫が一匹止まっていて、硝子玉の眼には朝露が落ちたのか、涙のような雫が薄く溜まっていた。
――さようなら、ペガサス。
頭をトントンと柔らかく叩き、翔太はその場を去った。もうタウンチャイルドに戻るつもりはない。美咲が両手を広げて、「ゴーン、ゴーン」と言いながら《アフロディテ》の部屋を一周した姿を思い出す。
――僕はゴーンじゃないけど。
路地から大通りに出ると、薄曇りだった空も白く光を強くしていた。細い雲の切れ間から青空がすっと一筋覗いている。
――まるで空の鍵穴か。
翔太は歩きながらポケットからピンクゴールドの合鍵を取り出し、裂け目のような細い青空にかざす。キラッと光る。この鍵をゲットするためだけにタウンチャイルドでバイトをしていたのかもしれないとさえ思えてくる。空に差し込んでぐるりと回せば、モーセの海みたいに空が割れて、約束の地に通じる道が現れるだろうか。
――だけど僕は、本当はどこへ行きたいのか。
ポケットに鍵を仕舞う。
この鍵を手に入れるためにタウンチャイルドでバイトしていたのだとすると、ずいぶん長い間、あの八田一之介事務所のチャチ臭いドアを蹴破るための道のりを歩いていたことになる。ずっと幼い頃に物置の前で家出したはずの姉の声を聞いたのも、ロダンと出会ったのも、美咲に頼んでさやかになりすましてもらい姉を脅かしたのも、全てはこの鍵の為だ。こじつけのようだが、翔太はひとまず、そう思ってみる。だとしたら、何を求めているのだろう。この鍵で開けたいのは、なんなのだ。自分でもわからない。
確かなのは、この合鍵をドアの鍵穴に入れてぐるりと回すところを想像すると、意味もなくぞくっとすることだった。
あんなチャチ臭いドアだけで外界を遮断しているつもりになっている八田一之介。その余裕の表情が己の間抜けさを呪う感情で崩れるのを見てやりたいような気もする。もちろん「まぬけにみえて切れ味抜群」というロダンの評価と、それに対して美咲の言った「それ一番ヤバイやつじゃん」という言葉から考えると、簡単に成し遂げられるとは思えないけれど。
どうせ自称辣腕探偵の八田のことだから、当然あんなへなちょこな扉でセキュリティが万全だなんて思っていないのだろう。というよりも盗られるものなどないと考えているのかもしれない。ならば、やっぱり怖い。そいつの持ち物に価値あるものがあろうがなかろうが、「盗られるものがない」と考えている奴ほど最強のものはいない。美咲が言うように、確かに、一番ヤバイ奴だ。
裏口破りを気楽に考えていたけれど、なんだか恐ろしく思えてくる。そんな奴のところに侵入するなんて危険すぎる。なのに、やめようとは思わない。成し遂げる為に歩いてきたのだから。これまでずっと。
成し遂げる。侵入。成し遂げる。成し遂げる。
だけど、
――何を成し遂げる? なんのために侵入するんだっけ?
もう一度ポケットから鍵を取り出して、空の光にかざす。やはりぎらりと輝いて、反射する光線が鋭く目を射した。
一応、侵入するにあたり、目指す物はある。滝田ロダンが八田一之介に「解読してみよ」と挑戦状を叩き付けた書き下ろしの小説だ。それを盗んでくる。滝田ロダンが小説を書けば、どういうわけかそれが実現してしまうと編集者加藤陽一郎が恐れているらしいが、思えば、翔太自身もロダンからは何か見透かされているような気がしてずっと怖かった。解読なんてできそうもないけれど、どうしてもその小説を読んでみたい。もしも手に入れて読めば、姉のまるみが二週間もいなくなった事件についても何かわかるかもしれないと思った。翔太としてはのんびり屋の姉に少し刺激を与える程度のつもりでさやか伝説の「さやか」と遭遇させてみただけなのに、大袈裟な事件になってしまってさすがに戸惑っていたし、調査に八田一之介が参加し始めたのなら、ロダンが差し向けたその小説の中に事件の手がかりがあるのかもしれない。
――でも、読みたいだけなら、ロダンさんに頼めばよかったか。
侵入の為の合鍵まで作ってしまった。
馬鹿なことをしてしまったかと、一瞬立ち止まったが、いや、ロダンに頼むのでは意味がないと思い、再び歩き出した。そもそも、あのロダンのことだ。何食わぬ顔をしつつ、八田一之介に渡したものとは全く違う小説を「これだよ」と言って出してくるかもしれない。だからと言って、八田の事務所に忍び込んでまで小説を盗むことにどんな意味があるだろう。危険なわりには確実な成果が得られるとも思えないのに。
――僕は、どうしてこんなことをしているのだろう。
わからなかった。
――わからない、わからない、わからない。
子供の頃に姉のまるみが物置に隠れていた時に観た薄紫色のオーブについても、その同じ日に交番に現れた「さやか」という少女がトイレに残したオーブについても、何年も調べたり考えたりしたけれど、結局は何もわからない。全ての調査は無駄だった。わからないことだらけだ。
――だけど、わかる必要なんかない。知りたいと思えば、知るために動くだけだ。
帰宅すると、翔太は自室のベッドに倒れ込んで、そのまま眠り込んだ。まるみが「夕飯ができたよ」と言いに来たような気もするが、返事もしないで昏々と眠り続け、ようやく目が覚め時計を見ると深夜三時だった。トイレに行こうとして一階に降りていくと家中の灯りは消えて、誰もが深い眠りに着いているのか、しんと静まり返っていた。全てを置いて夜逃げしてしまった人の家を思わせるほどに静かで、時間さえ止まってしまったかのようだった。
翔太は目を擦り、大きく深呼吸をした。体中が凝り固まって痛く、ひどく長く寝続けてしまった気がする。
シャワーを浴びてからキッチンでミネラルウォーターを飲み、小窓を開けて外を見ると、まだ明けない夜道をヘッドライトのない自転車が一台猛スピードで走り過ぎた。タイヤが道路を擦る音だけが響く。どこからともなくお香の匂いがした。いつでも美咲から発するバニラの香りでもなく、居間の仏壇から漂う線香の匂いでもない。平安時代の宮廷からでも漂ってきそうな高貴な香り。これは、どこかで嗅いだことがある。
――本の匂い?
アフロディテで古書を買い取って整理する時、
「それは激古だけど、激高級な古書だから、こっちでお香を焚く」
とロダンが言って、書斎に持ち運ぶことがある。「温めた炭団を小型の火鉢の灰に入れて、薄くした雲母の上に香木を乗せて焚く」
そうやって、古書に香りを移してから、別格書籍だけを入れたガラスケースに本を移し、非売品として展示した後、懇意にしている研究者たちに連絡を入れるのだ。
「この場合は最高級の伽羅を使う。こんな書籍に興味があるのは目の肥えた学者ばっかりだからね」
ロダンはいつも自慢していた。翔太がその「懇意にしている研究者たち」とアフロディテの店内で出くわすことはなく、密かに顔見知りの研究者たちの輪の中で重要書籍を貸し合うように売買しているらしく、不公平にならないようにロダンが仲介し、一斉メールでお知らせして、早い者勝ちのルールで授受しているらしかった。価格も意図的に吊り上げたり、逆にタダ同然で流通させたりしない。適正価格をロダンが決定し、売れたらロダン自らが梱包して送る。
――あの本の匂いだ。
翔太は大きく息を吸った。重要書籍にお香を焚き占めている時の、ロダンの部屋の匂いがした。
――だとしたら、最高級の伽羅の香りか?
翔太はなんども丁寧に息を吸い込み香りの種類を確かめようとしたが、徐々に霧散していった。そもそも気のせいだったのかもしれないけれど、ロダンの説では、「香りは物質的なものだが、時空を越境し、気のせいではなく、過去や未来からも届く」ものらしかった。
「たとえば、翔太君と僕の間に脳波の回路があったとすれば、僕が嗅いだ香りに対する脳の反応が、脳波として翔太君にも届く。その時、翔太君は時空を超越して、僕と同じ香りを嗅ぐのだ」
ロダンはいいお香を焚くことの重要性を説いた。「香りも、最終結果として脳で感じるものだから、実際に香料の成分が鼻の粘膜にひっついたりしなかったとしても、記憶や予兆によって香るのだ」
――こんな時間にロダンさん、お香を焚いているのかな
そう考えると、再び伽羅の香りを感じ、いい香りなのにも関わらず、何かロダンに脳の中を操作されているような気がしてむかつき、頭の中から消し去りたくなる。
――そうだ、たった今から、八田事務所に侵入しよう。ロダンの小説を盗む。
むしろ伽羅の香りに急かされるかのように、翔太は突如として決意した。
外はまだ暗い。バスも地下鉄も始発にはまだ時間がある。
翔太は物置から自転車を運び出した。家族に気付かれて、こんな朝早くにどこに行くのだと聞かれると面倒だから、なるべく音を立てないように注意深く動いた。
リュックを背負い、ニット帽をかぶる。ズボンのポケットにピンクゴールドの鍵が入っていることを何度も確認する。Tシャツの上に長袖のウインドブレーカーを着て、サドルにまたがった。ペダルを踏み込む。
八田の事務所までは地下鉄の駅で数えると五つ分の距離。それでも、大通りまで出ればまっすぐ進むだけなので、多少距離があっても迷わないから、感覚的には遠くもない。とは言え、信号が邪魔なので、大通りと並行して走っている細い路地を選択して自転車を走らせることにした。
ペダルを踏むと徐々にスピードが増し、頬に当たる風が気持ちいい。人もいないので滑らかに進み、それほど力も必要ではなくなっていく。アスファルトのアップダウンに合わせて、自転車がガチャンと音を立てた。タイヤが道を擦る音も響く。翔太はキッチンの窓から見た一台の自転車のことを思い出した。
――さっきの自転車も、こんな音を立てた。
ささやかな記憶でもないはずのにくっきりと蘇る。同時に、涼しい風に伽羅の香りが混じっている気がした。
――また、あの香り。
猫が目を金色に輝かせて道の端を歩いてくる。翔太の自転車に気付いて、急に角度を変えて横道に入り消えた。コンビニだけは相変わらず明るい蛍光灯を灯している。
ペダルを強く踏み込んでスピードを上げても伽羅の香りは消えなかった。
――伽羅、どこまでも。ついてくるのか。
最初は風に混じってどこかから届いていると思っていた香りは、翔太自身が放っているようだった。呼吸でもなく、汗でもなく、身体にまとわりついている。
スピードを上げて走っているうちに、伽羅の香りが消えてしまうというよりは、いつしか翔太が香りに慣れてしまうことによって、段々と感じなくなり、結果的に伽羅の存在は翔太の中で消滅した。
三十分ほど走り、八田一之介事務所の近くまでたどり着くと、川沿いの歩道を利用した小さな児童公園を見つけて自転車を停めた。時計を見ると午前四時半過ぎ。空は微かに紺の色を淡くしている。公園の横をバイクが通り過ぎた。
事務所は灯りが消えていた。八田一之介は眠っているのだろう。
翔太は事務所の前に辿り着き、工事現場で簡易設置された足場のようなみすぼらしい外階段を見上げた。これを上って、二階の扉から入るのだ。もしも運悪く、八田が起きていたり、いつもの寝室ではなく、二階扉のすぐそばのリビングで眠っていたら、すぐに翔太の侵入に気付くかもしれない。見つかって問い詰められた場合は、
「朝食を届けに来た時に、ピアスを落としたので探しに来た」
と言うつもりだった。そんなことは絶対に怪しいけれど、訴えられたりはしないだろう。持っている鍵は翔太自身がこっそり作った合鍵などではなく、マチ子ママから預かっているものだと思うだろうから。
自転車を走らせてきたことによる呼吸の乱れは整ったものの、今度は緊張のために心臓が高鳴り始める。意識は醒めているのに、身体は怖がっているのか、胸が痛いほどに心臓は暴れていた。
――ほんとに、こんなこと、心臓に悪い。
音を立てないようにその階段を上り、ポケットからピンクゴールドの鍵を取り出して、鍵穴に差し込んだ。なんの問題もなく、すっと入った。左に回す。カチッと音がして、鍵が開く。
扉を開け、入り口で靴を脱いで手に持った。靴を脱ぐなんて、なんとも品のいい泥棒みたいだが、万が一、八田が目を覚ました時に、靴のままリビングを横切って、建物の中の階段を降りていたら、落とし物を取りに来たと言っても信憑性に欠けるだろう。
フットライトがひとつ灯っている。当たりを見渡すと、八田はいない。ということは、いつも通り、奥の部屋で眠っているのだろう。ほっとしつつも、翔太は慎重に音を立てないようにそっと床を踏んで、室内階段を降りて行った。
一階の事務所は真っ暗だった。スイッチを入れて明かりを灯したりすると二階にまで光が漏れて、トイレにでも起きた八田に気付かれるかもしれないから、それはできない。
――懐中電灯でも持ってくるべきだったか。
翔太は一瞬困惑したが、リュックからスマートフォンを取り出し、その灯りで部屋を照らした。探すまでもなく、ロダンの小説が置いてある場所はわかっている。八田が置き換えていなければ、本棚で、その中でも、客用ソファから丸見えの場所だ。
――あった。
やはり無防備に、昨日見た場所に、置いてある。緑色のファイル。
翔太は急いでそれをリュックに入れ、一階の扉から外に出た。もちろん、鍵を外から閉めることはできない。そのまま持ち去る。
その後の動きは、翔太自身が考えても、まるで慣れた空き巣犯のように手際よく滑らかだった。そのまま《アフロディテ》に行き、メディアアーティスツが誰もいないのを確かめてから、実験室でコピーを取る。もしも書斎にいるロダンが入ってきたら、平然と「学校の資料をコピーさせてもらっています」とでも言えばいいだろう。実際には、ロダンが実験室には絶対に入ってこないことは分かっていた。
「全てを管理するうるさいオヤジみたいになるのが嫌だから」
と言うのを聞いたことがあるし、深夜だろうが早朝だろうが、中で作業中にロダンが入ってきたことは一度もない。
ロダンが書いた小説のタイトルは『無人島の二人称』だった。枚数は大量にあるが、きちんと章立てされ、ページナンバーが打たれているので、作業はやりやすく、速やかに終了した。コピーを大きめのクリップで挟み、原本と共にリュックに入れようとしたところで、ふと手を止めた。
――バニラの香り。
美咲がスカートをふわりとさせつつ、回転する時に香った、あの匂い。
――どこから? ん? 小説から?
原本の紙に鼻を押し当て、大きく深呼吸する。やはり、原本の紙から香る。コピーの方も嗅いでみる。こちらは香らない。原本の方だけだ。
――本当はこの小説、美咲さんが書いたのだろうか。
翔太はもう一度原本を開き、上から鉛筆等で書き込みのないページを数枚選んで取り出し、コピーと入れ替えた。この小説に美咲が関わっているのかどうか、このページからわかるかもしれない。少なくとも、本当に同じ香りかどうか、後で確かめることはできる。
時計を見ると、午前五時半。
急いで八田事務所に戻り、今度は一階から入って、小説の入った緑のファイルをそっと元の本棚に置いた。一階の玄関扉の鍵を内側から閉め、そっと室内階段を上がって、二階の扉から外に出た。ここでは外側からピンクゴールドの合鍵を使って鍵を掛ける。
――完璧だ。
手の届きそうな場所に電線があり、数羽の雀が止まって囀っている。空を見ると徐々に白んでいて、いよいよ朝になりそうだった。なるべく音を立てないように外階段を降り、児童公園にまで戻って自転車にまたがった。犬の散歩をしている人が一人歩いていた。
気付いたら、背中にびっしょり汗をかいていた。スムーズにやり遂げたつもりでも、今まで大量の汗に気付かなかったなんて、よほど緊張していたのだ。ウインドブレーカーを脱ぎ、前の籠に入れる。ひんやりとした風が心地よかった。
帰ろうとして自転車を漕ぎ始めたが、この辺りを自転車で走ることは初めてだと気付いて、ふいに遠回りしたくなった。軽くとも成し遂げた犯罪の記憶を和らげたくもある。タウンチャイルドのある繁華街の方向を避け、高級マンションが立ち並ぶ方に向かった。
――もうタウンチャイルドには行かない。
太ももに力を入れて自転車を漕ぐと、どんどんスピードが上がり、実際、ペガサスに乗っているように思えた。美咲に紹介された『次元間超越交流法』という本の扉を思い出す。文言は「ペガサスに乗る者へ」だった。
――この自転車がペガサス? そしてそれに乗るのは、僕だ。
漕ぎながら、『次元間超越交流法』の表紙を思い浮かべる。あの時、青いドラゴンが表紙から飛び出してきそうになった。火の鳥の眼も光ったように思えた。
――なんだったんだろう、あれは。
これから新しい世界に飛び込んでいくのかもしれないと考える。まだ読んでもいないあの『次元間超越交流法』の法則が、翔太の周囲で動き始めている。なんといっても、ページを開いてしまったのだから。それは本の頁であり、八田一之介事務所の扉だ。
高揚感に身を任せて、特に行く道を決めずに闇雲に走っていると、一駅分過ぎたのか、見たことのある風景が現れた。美容専門学校とクリーニング店の建物、その前にある小さな祠。そうか、ここは姉のまるみが働いているセブンイレブンの近くだ。一度だけ、車で母と様子を見に来たことがある。
翔太はふと思い立ってそのコンビニに向かい、駐車場に自転車を停め、ニット帽を深めにかぶり直して、広告が貼ってある硝子窓の隙間から中をそっと見た。コンビニの中までは入らないつもりだった。店で働いている姉と接触したいとは思わなかったのだ。わざわざ会いに来たと思われるのも嫌だった。
ガラス越しに見ると、まるみはレジで接客をしていた。コーヒーの注文を受けたらしく、コーヒーメーカーの操作をしている。当然のことだが、家では見たことのないテキパキとした動きに感動すら覚えた。やるべき時にはやっていたのだ。いつもダラダラしていると思い込んでいたことを謝りたくなる。
――あ、あれは?
スタッフルームから見覚えのある男が出てきた。コーヒーをカップに注いでいるまるみに代わって、客が購入した商品をレジ袋に入れている。手際よい。働き者の筋肉質の日焼けした腕。
――あれはフミヤ? なんで、フミヤが。
翔太は頭を殴られたような気がした。目の前がちかちかする。目をこすって、もう一度見る。やはりフミヤだった。まるみに何か確認しようと話しかけている。まるみはコーヒーカップに蓋をしながら、親しそうに返答していた。それを受けてフミヤは客に何かを伝えた。
――フミヤが姉さんと知り合いだったなんて。
フミヤはタウンチャイルドの大黒柱とも言える存在だった。なんといっても、老舗の洋食店で修業をして腕を上げ、それなのに、理由はわからないがタウンチャイルドに来たと聞いていた。翔太自身も彼のビーフシチューを食べたことがある。簡単な居酒屋メニューとは一線を画す、立派なディナーとして成立する味だった。コンビニでもバイトをしていると聞いたことはあったけれど、まさか、姉のまるみと同じ店で働いているとは思わなかった。
――フミヤの方では僕の姉だと知っているのだろうか。
しばらく、駐車場でスマートフォンを見るふりをしつつ中を伺っていると、今度は「アフロディテ」のメディアアーティスツの一人が買い物をしていることに気付いた。
――ひょっとして、彼も知り合いなのか?
フミヤと親しそうに笑顔を交わしているように見える。
――なんだ これは。
翔太は淡く血の気が引く思いがした。八田一之介事務所に入り込んだ高揚感が一気に消え、肩にどんと重いものが乗った気がする。スマートフォンをリュックに仕舞い、店の中には入らず、再び自転車に乗った。
――ひょっとして、みんな、グルだったのだろうか。僕の方をこそ騙そうとして。
ふと、そんな思いが湧いてくる。
――イミフ。
不安を振り切ろうとして、ペダルを強く踏み込んで走り出す。だけど、どうしてフミヤが? タウンチャイルドから足を洗ったつもりでいたのに、まだ追いかけてくるのか。
――逃げよう。
ペガサスと化した自転車を猛烈に漕ぎながら、翔太はもはや何から逃げようとしているのかわからなかった。
翔太は家に戻り、自室にこもって、ロダンが書いた小説『無人島の二人称』を読み始めた。
小説の中に描かれている村では、時々、姉のまるみのように失踪する事件が起きる。しかしそれはまるみのケースとは違って、一日で戻ってくるか、二度と戻ってこないかのどちらかだった。小説の中でこの事件を解明しようとしている人物たちは、ある特別なブレンド珈琲を飲んだ場合には、失踪した人も戻って来られるのではないかと推測している。
――推測か。
推理小説のわりには、「あらゆる人間たちの、あらゆる推測」だけで終わっている。あのきっぱりとした性格の滝田ロダンがこんな小説を書くだろうか。やっぱり、誰か手下が書いたのではないか。だけど、どうしてそれを八田一之介に解読させようとしたのだろう。
居ても立っても居られなくなって、翔太は美咲にスマートフォンからメッセージを入れた。
<相談したいことあり。空いている日教えて>
数分後、返信があった。
<OK 今日もアフロディテで番台にいるよ>
<バイトは何時まで?>
<四時。ツンツンが来たら交替する>
<その後は暇なの?>
<暇じゃないよ。用がなければやることあるもん>
プライド高めの美咲の眼が睨みつける様子が想像できる。
<そうだね、ごめん。僕のために時間を空けてくれる?>
――うまくひれ伏しておこう。
<OK じゃあ、アフロディテに来てくれる?>
<アフロディテじゃない方がいい。前に一緒に行ったミニシアターの一階はどう?>
<いいよ。ちょっと待たせるかもだけど>
<全然、ずっと、永遠に待つ>
――もう一度ひれ伏しておく。
<わかった。じゃあ、ミニシアターのカフェでね>
<よろしく>
翔太がミニシアターのカフェに着いた時には、ほとんどのテーブルが客たちで埋められていた。午後四時半。すでに麦酒やカクテルを飲んでいる人もいる。こんなに混む日もあるんだなと驚きつつカウンター席に座り、アイスティを注文した。美咲には「永遠に待つ」と言ったものの、こんなに満席状態のカフェでどれだけねばれるだろうかと不安になる。
しかし、十五分も過ぎると、客たちは徐々に壁際の階段を上がってミニシアターに向かい、ついには翔太以外には一人もいなくなった。どうやら五時から上映する映画があり、客たちは上演時間になるのを待っていたらしい。
カウンターに置いてあるパンフレットによると、映画は洞窟に描かれた絵画から地下世界に通じる道を探すドキュメンタリーで、出演者は聞いたことのない俳優ばかりだったが、音響を担当しているのは翔太も知っている有名音楽家だった。音楽だけでなく、ノンフィクション風に撮影されたフィルムの中の雨が降る音や、洞窟の中の風の音も制作しているらしい。恐らく、あの客たちはどちらかと言えばストーリよりも、その音楽や音響の方に興味があるのだろう。
「遅くなってごめん」
美咲が現れたのは五時過ぎで、ちょうど二階で映画も始まった頃だ。アイスティはすっかり飲み干していた。美咲からは相変わらず、バニラの香りがする。部屋の角にあるテーブル席に移動し、翔太は改めてホットティ、美咲はアイスコーヒーを注文した。
「ピザでも注文していいよ」
翔太は美咲に勧める。
「さっき、ツンツンがお土産にくれたサンドイッチを食べたから」
美咲は断った。
「ところで、ツンツンって誰だっけ?」
翔太は知らなかった。
「知らないの?」
美咲は高い声を出して、極端に目を大きく開く。
「ごめん、メディアアーティスツたちの個々の名前、あまり知らない」
ロダンの経営するアート&古書《アフロディテ》には長く出入りしているものの、制作はリーダーから直接頼まれる個人的なものばかりだから、メンバーの中には知らない人も多い。名前を覚えられないのは、番台のバイトをほとんどやらないためでもある。
「髪の毛がツンツンってなってて、話し方もツンツンしてるから、ツンツンって呼ばれているらしいよ」
美咲は黒目をきょろりと上げつつ、自分の髪を真上に引っ張って見せた。
――歌川国芳の妖怪みたい
「そんな人、いたかな」
「いるいる。ツンツン。今日も何か、気取ってツンツンしていた。サンドイッチくれたから、文句は言わないけど」
親指と人差し指で唇をチャックする仕草をした。薄暗いカフェの中で、美咲の周りだけ不変の蛍光色が灯ったように思える。
「ところで、相談って、何?」
美咲はテーブルに届いたアイスコーヒーにストローを差した。
「実は、これ、なんだけどね」
翔太はリュックからロダンの小説『無人島の二人称』のコピーを取り出した。ロダンが緑のファイルに入れていたのと同じように、青いファイルに綴じ込んでおいた。
「これ、見覚えない?」
美咲の前に、とんっと置く。
「何これ」
美咲はアイスコーヒーをストローで何度か吸い込んだ後、グラスをテーブルの隅に置き直し、ファイルを開き始めた。
「ロダンさんの小説、ってことだけど」
「どうして翔くんが持っているの?」
「それは、今は聞かないで。これ、知らないかどうか、それだけ、正直に答えて」
翔太はつい尋問するような口調になってしまう。
「ああっ」
ページを繰っていた美咲は声を上げた。
「知っているの?」
「知っているっていうか、これ、たぶん、コピー頼まれていたやつ」
「コピー?」
「そう。ロダンさんから頼まれた。コピーして、レターパックに入れて、編集者に送る」
「なるほど。それでか」
翔太はほっとする。と同時に、ちょっとがっかりする。
「なるほどって?」
「この小説を手にしたとき――」
美咲のバニラの香りがしたと言おうとして躊躇した。
――そういうこと、言っていいんだっけ? セクハラ?
「これを手にしたとき?」
美咲が翔太の言葉をなぞりつつ、ろくろ首のように首を長くしてこちらに顔を突き出す。きっちりと描いた眉が中央にきゅっと寄っている。
「本当は美咲さんが書いたんじゃないかと思って」
バニラの香りがしたので、という部分は省いた。
「私が、書いた?」
「そう、ゴーストライターみたいに」
「どうして、そう思ったの?」
「なんとなく、直観」
「呼び出して、確かめるほどの直観?」
美咲はひとつも逃がさないと言わんばかりの注意深さで追い詰めてくる。
「いや、まあ、その直観は外れたわけだけど。だって、コピーしただけなんでしょ?」
翔太は背中を後ろに引いてしまう。顎を引いて、手のひらで空気を押し、まあ落ち着いてという仕草をして見せた。
「それはそうだけど、直観で私の顔が浮かんだのだったら、翔くんって、ひょっとしたら、サイコメトリーなんじゃない?」
「なにそれ、サイコメトリーって」
「物質に残されたエーテルから想念を読み取る超能力よ」
美咲は首の位置を元に戻して背筋を伸ばし、人差し指をピンと立てる。「その能力を持っている人の中には、犯罪捜査に協力する人もいる。犯人が残した何かから、犯人の想念を読み取って-―」
「ない。そういうの、ない」
慌てて否定する。「そういう大袈裟なことじゃなくて、バニラの-―」
――しまった、言ってしまった。
「何? バニラって」
「バニラの香りがしたので。美咲さんがいつも着けている香水の-―」
「それで、私が書いたんじゃないかって?」
「まあ、そうです」
今度は詰問されている人のようになった。「香水、着けているでしょう? ちょっと印象的な、甘いやつ、いつも」少し、しどろもどろ。
「いいえ」
「いいえって、それは――」
「着けていないわ。これが私の香りなの」
顎を突き出して、挑発的な表情をする。
翔太はそれを見て、ぷっと吹き出した。「それは無理があるよ」と言おうとして止めた。香水の匂いが強すぎると言っているようなものだし、ひょっとしたら、こういうことでもセクハラの範疇かもしれない。
「そっか、ごめん。じゃあ、ほんとにバカな僕の気のせい」
さっさと謝った。ホットティのカップを手に取り、一口飲む。
「ところで、この小説のファイル、どうして翔くんが持っているの?」
「これは、盗んだんだ」
正直に言った。
「盗んだ?」
美咲が声をひそめた。
「そう。実はね――」
翔太は座り直し、ここまでのいきさつを、ざっと美咲に説明した。
「なるほどね。一昨日の朝に言ってた探偵にロダンさんが小説を仕向けていたことについて翔くんは、どうも今回の事件に関係ある気がしているわけだ。さらに、翔太くんのお姉さんの事件、ひょっとしたら、翔くんの周りにいる人たちが仕組んだことかもしれないって、そう疑い始めたってことか。特に、そのタウンチャイルドのフミヤという人が怪しいって、思っているのね」
美咲は顎に人差し指を当てた。
「怪しいというか、フミヤと姉が知り合いだったなんて、驚いてしまって」
「お姉さんは、翔くんがタウンチャイルドでバイトしていること知っているの?」
「言ってないから、知らないと思う」
「私が翔太くんに頼まれて、さやかになりすましてお姉さんの前に登場した日のこと、誰かにバレていたのかな。誰かに話した?」
「話していないけど、メディアアーティスツの誰かが、僕と美咲さんの企みをこっそりどこかで聞いていたとか、そういうことはないかな」
「あり得るわね。でも言っておくけど、私は漏らしてないわよ」
美咲はグラスの中の氷をストローの先でつつきながら言う。
「信じているよ。あ、でも一瞬、ごめん、疑った」
再び、正直に言った。その方が、話がややこしくならない気がした。
「いつ?」
「この元原稿から、バニラの香りがした時」
「鼻が利くのね」
氷をがらがらと掻きまわす。目を合わせない。
――ひょっとして、本当は美咲が誰かに話してしまったのでは? あるいは、やっぱり、美咲もグルなのか?
「まあね、そうかも。僕はわりと鼻は利く」
「サイコメトリーというよりも、鼻が利くなんて、チョー犬っぽい」
「犬っぽいってなんだよ」
「ワンワンッ、ワン」
美咲は犬の真似を始めた。鼻をくんくん鳴らす。
翔太は驚いてカフェを見渡す。知らない人に見られたら笑われるだろう。しかし、客は誰もいない。カウンターの向こうにいる店員だけがちらっとこちらを見た。
美咲は手を握り締めて、犬の前足の形を作り、
「ワンワンッ、ワン」
首も振りながら真似を強化した。
「ちょっと、失礼でしょ」
「ワンワンッ」
こうなると止めようもない。
翔太はわざとゆったりと紅茶を飲み、収まるまで放っておこうと決めた。
それほど人もいない。だから恥ずかしくもない。
首を横に向けて知らん顔をした。
やっと気が済んだのか、犬の真似を止めた美咲は小説のファイルの表紙を開け、
「あらら?」
と首を傾げた。「これ、ちょっとおかしい。私がコピーした時にはなかったものが入ってる」
「どれ?」
翔太はファイルを覗き込んだ。「なかったものって、どれ?」
「プロローグ。あ、それから、エピローグも。後でロダンさんが付け足したのかしら。それに、これ変だ。見て、このページ!」
「あっ!」
翔太は蒼ざめた。
(第二章 3了)》
※ここまでの解説
あらすじ。
金指翔太は合鍵を使って八田一之介の事務所に入り、ロダンの書いた小説『無人島の二人称』を盗み、コピーを取ってから元に戻した。小説の紙に遠野美咲の着けている香水の匂いが付着していたので、ひょっとしてこの小説は美咲が書いたのだろうかと疑い、一枚だけコピーと入れ替えて返した。
その帰り道、姉のまるみの働いているコンビニをそっと覗くと、フミヤとメディアアーティスツのうちの一人が同じコンビニでバイトしているのを発見して驚く。逆に翔太の方がみんなから騙されているのだろうかと疑った。
遠野美咲と会い、上記のことを伝えたら、小説は美咲が書いたのではなく、コピーを取ったのだと言う。二人で小説を見ていると、美咲が、コピーを取った時とは異なる頁やナンバリングがあることに気付いたのだった。
さて。
いよいよ長編小説『無人島の二人称』の解読が始まりそうだ。そして、タウンチャイルドのフミヤが何か事件に関わっていそうでもある。
都市伝説の謎を解くための鍵がひとつ見つかったとも言える。
小説はまだまだ続く。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
