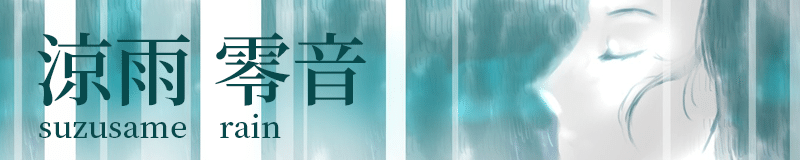Muse との対話~「サイハテのクリスマスギフト」制作秘話
野暮かなと、思わなくもない。制作秘話とタイトルに書いたけれど、おそらくわたしがここで書こうとしているものはたぶん「補足」なのだ。本来は、作品は公開した時点ですでに受け手のもので、受け手の解釈によって完成する。その完成しているものに対してあれこれ補足情報を出すのはノイズでしかないかもしれないとも思う。
今回わたしの中でいつもと状況が異なるのは、この作品は他のアーティストさんの作品に乗っかったものだ、という点だ。改めてMuse杯(通称)の内容を紹介しておく。
完成している音楽作品をもとにして、それにインスパイアされて何らかの表現をしよう、という趣旨なのだ。もちろんその音楽を作られた広沢タダシさんご自身が賛同したうえで行われている。
とはいえ。他の誰かの作品を使ってそこに自分の色を足すというのは思ったよりも大きな葛藤があった。元の作品を損ないはしないかという不安がついて回った。かといって、阿るようなものを作るのはかえって失礼だし、わたしにとっても意味がなくなってしまう。
そんな風にしてわたしは自分が表現したいものを表現した。ラストシーンは受け取る人によって希望にも絶望にもなるようなもので、願わくは絶望であっても美しいものであってほしいと思う。
着想
曲も再掲。
歌を聴いてわたしの中に去来したのはいくつかのテーマだった。
・デジタルデータはデータそのものとそれを読み取る方法(ファイルフォーマットの仕様)が残っていれば、半永久的に生きるのではないかということ
・人間のタイムスケールから見ると永遠に近いような宇宙の時間でも、本当の永遠ではないということ
・人類は進化は「緩やかな死」と言えるようなフェーズに入っているということ
・命の星である太陽は、その気まぐれで死をもたらす星になり得ること(太陽フレア)
・人の多様化が進み、マイノリティがメジャー化しているということ
・性はとっくに二つではなく、恋愛感情の向く先は細分化かつ複雑化していること
・恋愛感情の向く先は同種(人類)である必要はなく、他の生物(動植物)から、非生物にまで拡張されつつあるということ
・性の多様化は種の境界を越え、最終的には「何らかの感情を自分の中に想起させるものであればなんであれ恋の対象になる」ということ
そんなことを歌った歌ではないかもしれない。たぶんないだろう。でもわたしの中に沸き上がったテーマはこういったものだった。これらは常々考えていることでもあり、それと楽曲がマッチしたということに過ぎないような気もするけれど、やはりわたしの中ではマッチしたのです。
ここから、
地上からのバックアップを受けられず宇宙に孤立した宇宙ステーションで、希望として冷凍保存された少女が100年後に目覚め、宇宙ステーションで稼働していた人工知能と一緒に今私が聴いているこの歌を聴いていたら本当に彗星がやってきて宇宙ステーションごと破壊され、その結果として人工知能と一つになり、新たな思念体として彗星の尾っぽにくっついて宇宙へ旅立つ
という話が思い浮かんだ。
人体が無機物(機械など)と一緒に砕かれて混ざり合うことで合体するというのは、J.G.バラードの「クラッシュ」という小説で書かれているものだ。「クラッシュ」では自動車事故により、双方の自動車と搭乗者が粉々になり、体液とガソリンやエンジンオイルが相互に入り混じるというさまを、ほとんどセックスとして描いている。おそらく人によっては強烈な不快感を得る作品なのだが、わたしがここで描こうとしたものはそれに近い。
人口知能と人間はどう違うのかというのはわたしの追っている重要なテーマの一つで、その体を構成しているものが有機物か無機物かという違いが大きいのではないかと考えている。しかしバラードが描いたように、無機物と有機物が交合することは可能かもしれない。それは必然的に双方の死を伴うのだけれど、最終末にたどり着いた人類はもはや無機物と交合して次の次元へ行くしかなく、彗星がそれをもたらすというのは、わたしにとっては「希望」だったのです。
これは希望だけれどある種の(というかわたしたちが一般的に認識している)死で、しかもはっきりとは結論づけていないけれど、彼女は最後の人類かもしれず、するとここにわたしが描いたのは人類絶滅の瞬間でもある。そういう結末に至る作品をこの美しいコンテストに出すのは果たしてどうなのかという葛藤があった。今も完全にすっきりとはしない。
そしていろいろな葛藤の末にこのような作品として仕上がった。
解説
このような経緯で書いた作品に、少し補足説明をしてみます。
まず、この作品に出てくる時間の表記は、コンピュータで使われるUNIXタイムというものです。
このサイト でUNIX時間を入力すると年月日表記に変換してくれます。わたしはこれをPythonというプログラム言語を使って逆に日付から変換して生成しました。
そして変換した日付は、UTC+9という時間、つまり日本時間で読むと内容とマッチします。少女が話しているのも人工知能が話しているのも日本語なので、彼らのタイムは日本時間であると想定しました。
物語は2322年を舞台にしたもので、2322年の4月に目覚めた人口知能は、目覚めてから10分おきに、自分の可能な範囲での呼びかけを行います。この時点でメインコンピュータとこの人工知能は切断された状態にあり、メインコンピュータは冷凍保存装置の維持だけを行う、機能制限モードで動いています。人工知能は接続されているカメラやマイクなどの、いわゆる感覚器官をすべて失った状態であり、しかもデータストレージのファイルシステムが破損(正確にはこれを読むためにアクセスすべきインターフェイスが落ちている)していて読めない。人間で言えば、目も耳も失い、記憶も大部分が喪失しているような状態で、続きがどこにあるかわからないデータの断片をロードしては、「あなた」に呼び掛けているという状況です。
このひたすら苦しそうな状況が、2322年の12月まで続きます。でも「私」は人工知能なので、その徒労のような作業がまったく負担ではありません。2322年の12月24日、午前7時、メインコンピュータは機能制限モードから復帰し、冷凍保存されていた少女は目覚めます。正確には、もっとずっと前からこのタイミングで目覚めるように解凍処理に入っていて、それが完了したのでメインコンピュータが機能制限モードから復帰したわけです。この復帰処理が、人工知能の通信コマンドに割り込んで実行され、人工知能が稼働していたコンピュータも含め、ステーション内の全コンピュータおよびシステムが再起動、自己診断されました。このときファイルシステム(ストレージのインターフェイス)が修復され、人工知能はこれにアクセスできるようになりました。
晴れて、音楽のデータは完全な状態で再生できるようになりました。思い出の少女と一緒に。
しかし、幸せは束の間。2322年12月24日、22時32分に、少女は彗星の接近を知ります。衝突予測時刻は2322年12月25日、午前1時31分。この間の約3時間、少女は歌を延々リピートしながら聴き続け、唯一の話し相手である人工知能と会話をしています。
この会話は、歌に倣って、「私」と「あなた」の会話にしようと考えました。どちらにも名前は付けませんでした。少女が話すときの一人称は「わたし」で、「私」は人工知能です。お互いに相手を「あなた」と呼ぶため
「あなたは〇〇だ」とあなたは言った
という文のあなたがそれぞれ違うものを指している、というような事態が生じ、「あなたのあなたはわたし」という循環を感じられるので意図的に「あなた」がたくさん出てくるように書きました。
3時間も一曲をループするということが、わたしには実際によくあるのだけれど、これも共感してもらえるのかわからないと思いながら書きました。3時間かけて歌ったり会話をしたりしながら、二人は来るべき衝突(クラッシュですねこれ…)を待っている。
ラストで彗星にすべてが砕かれたとき、少女の目に何が映るのだろうと想像したら、輪のついた地球が見えました。人類の営みの結果もあって衛星軌道上に増えたスペースデブリや小惑星の破片などで、土星ほど立派ではない輪が、よく見ればゴミである輪がかかっている。それを見ながら、「私」と「わたし」は彗星の尾になって飛んでいる。
「私」の一人称で(つまり人工知能の視点で)書いたこの作品の、ラストの一行が「わたし」なのは、「私」と「わたし」が融合したからです。(それと、この行が無いと希望を感じない人が増えそうな気がしたというのも少しあります)
自覚している問題点
SF考証が無いこと。当初、過去に起きた事故は具体的に「巨大な太陽フレアであった」ということで進めていました。しかし、地上施設が破壊され、地上の人類の大部分がいなくなるような事態が生じ、宇宙ステーションの環境維持に問題が生じるほどの磁気嵐が起きた際、冷凍保存カプセルを一つだけ維持できるような補助電源を動かし、100年の経過で人工知能のコンピュータが起動できるまでに復旧される、という事態に持っていけないことが判明しました。もっと都合の良い事故を考える必要がありましたが、正直に言うとわたしはそれを放棄し、うやむやにしました。「環境維持に問題が生じ」というご都合主義に逃げてこの物語を成立させました。SFの舞台を借りたおとぎ話なのです。(ナノテクノロジーによる自動修復とか、太陽発電パネルのマウントが変形したのがステーションの向きが変化して発電できるようになるとか、本当にあれこれいろいろ考えてはボツになっていき、最終的にぜんぶぶん投げました)
あとがきのあとがき
この解説に書いたようなことは本編中には書いていないし、これを読んでから本編を読めば「たしかにそうだ」と思うかもしれないけれど、本編だけ読んでもわからないよ、という感じだろうと思う。わたしはそれでいいと思ってこの作品をこういう形で書いた。
思い描いたストーリーが「伝わらなくてもいい」というのはいささか乱暴な意見のようにも聞こえるけれど、わたしはこの作品がぜんぜん違う形で読まれても良いと思っているし、むしろ違った解釈でも読んでもらえるものであってほしい。
ここまで書いてきてなお、これを発表するのは野暮なのではないかという思いは消えないのだけれど、でもおそらくこれを読む人は本編を読む人よりはるかに少ないだろうし、これをわざわざ読んでくれる人であればきっと意図をわかってくれるだろうという思いもあって公開することにしました。
わたしとはかくもわがままなのであるなと、改めて思う次第…。
いただいたサポートはお茶代にしたり、他の人のサポートに回したりします。