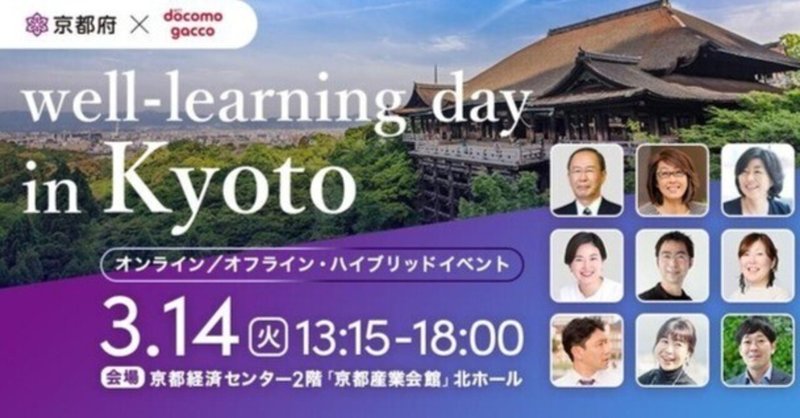
【リアルかばん持ち】Well lerning day in Kyoto
2023/03/14
@京都経済センター「京都産業会館」北ホール
【イベント動画】
信州大学2年の石井恵里です。私は現在、信州大学の特任教授、株式会社docomo gaccoの山田崇さんのオンラインインターン「オンラインかばん持ち」の6期生として活動しています。
今回は、京都経済センターで開催された「Well lerning day in Kyoto」に参加させていただきました。このイベントを受けて最初に出来るアクションは「体験」を「経験」に変えて定着させるために書くこと。そこで、トークセッションやショートピッチで気になったキーワードを軸に学びをまとめました。
山田崇さんProfile
OPセッション「Well learning とwell being」
Well beingとは
Well(良い)being(状態)。幸せ、継続的幸福。なんかいい感じ、いい調子と思えること。頭で理解することではなく感じることであり、日々意識する。幸せだった瞬間についてそれぞれに言語化することで脳内再生して幸せを感じなおす。Being(状態)だから継続的。一瞬一瞬のことに目を向けてみることで継続的になる。自分にとって快適、役に立つ、自分の良さ。強みを発揮できる。
【事例紹介①】生涯現役クリエイティブセンター
特徴
「産」と「労」が一緒に取り組んでいる
ミッション
障害を通じて学び続ける機会を通して、働きたい間、働ける間仕事をし続け社会参画し続けることができる社会を目指す。
【事例紹介②】学びがwell beingになった経験
体験の普遍化
苦しいことがある瞬間を通り抜けることで幸せになる。
一仕事、一学び
自分の経験を血肉にするために、体験したことを汎用的に使える形にして書き留めておく。キャリアを卒業しながら普遍的なスキルを身に付けることができる。普遍化するためには理論の学習が必要であり、理論の中に自分の経験を落とし込む。
自分なりのやり方を見つけるー文章にする
文章にすることでロジックが抜けているところを発見し、体系的にまとめることができる
【参考文献:楠木建『ストーリーとしての競争戦略』】
セッション①
鳥屋尾優子さん(ワコールアイネクスト株式会社)×花村えみさん(Next Wisdom Foundation研究員)
「あれ?学んじゃったな」
学ぼうとして学ぶときと、結果として学びを得る体験は違うもの。学ぶことに積極的になり過ぎて学びが得られていないこともある。
【自然に学ぶ】自分の心をフラットに
人それぞれ認知が違う。同じことを考えていることを前提としない考え方によって、自分のミカタ、他の人のミカタの違いを知るようにする。自分の心をフラットにした状態で他の人の考え方を取り入れる姿勢が大事になる。
自分は相手と違う人間だからすべてが分かるわけではない。考え方の違いは認知の違いでいい悪いではない。
学びに焦りが蔓延している!?
「DX人材にならなければ!」「スキルを身に付けなければ!」と新しい事との出会いが嬉しいはずの学びに焦りが見られるようになってきている。だからこそ、情報を外に取りに行くのではなく、自分の中を見つめなおし、棚卸をしていくことから始めることが重要なのではないか。今目の前にあることに一生懸命にならずに将来のことばかり考えていると焦りに繋がってしまう。
心の栞
一つの経験を複数の角度から見つめなおすことが学び。昔していた仕事を見つめなおすことで考え方が変わることもある。親から言われてきたこと、よく言われていることを歴史的に、グローバルに見直すことでメタ認知ができる。歴史的、グローバルに見るためには教養が必要。学びと学びの点を繋ぐことで時代感が見える。人それぞれ繋ぎ方が違うからこそ、点のつなぎ方によって自分のミカタが形成される。一度立ち止まって自分の中にあるものを内省する。心の栞を挟むように見つめなおす意識を持ちたい。
育児休暇はスキルアップ
育児休暇をとることになると申し訳なさそうにする人が多いように感じる。職場に戻ってきても間が空いてしまったような感じになる。でも、視点を変えてみれば、育児は子供のことをみながら、家事や自分の時間やをやりくりする高度なマネジメントスキルが求められるもの。だからこそ、育児休暇をとったひとこそマネジメントスキルを持つ人材として、もっと仕事にも生かせると考えられるのでは。
【e-lerningで作る】自分と向き合う時間
e-leaningでは人の目を気にせずに自分の学びを深めることができる。対象物に自分が向き合う機会になる。一方で学びは自分の中だけで完結するものではない。学びを共有する機会も同じぐらい求められる。
体験は蒸発、経験は定着
体験は蒸発するけれど、経験は定着する。「体験」を「経験」に、「蒸発」を「定着」にするためには書くこと・話すことが大事。
体験に対して「なぜ?」と考える解釈が別の世界を作る。苦しいことも「楽しい」と解釈できるような社会を創る。頭で考えるのではなく、物事に対して「好き」か「嫌い」かから考え始めてみる。感情を開いて考えてみると定着に繋がっていく。
自分を解き放つところに注目
学びを「積み上げる」、「固める」ものの逆の視点を持つことで、学び続けることが楽しくなるのではないか。つまり自分の中にあるものから自分を解き放ってみるということ。
関係性においての自分
自分は一人ではない。だから関係性の中に学びが溢れていることを意識する。自分と他の人が関係しあうことで+(プラス)になるものが生まれるのではないか。
ショートピッチ①
新田廉さん(京都信用金庫京信人材バンク)
「まちのワークインフラ」の共創を目指す
自分の価値は越境することで分かる。地域内であっても、異なる年代や職業など越境することで「近くにいるのに知らなかった」価値が分かるようになる。
セッション②
西村裕也さん(NPO法人ミラツク/株式会社エッセンス)×笹原優子さん(株式会社NTTドコモベンチャーズ)
まだ言語化できていないこと
相手だけが知っている「言語になっていない”面白い”」をどう世の中に出していくか、ミックスしていくかに着目したい。
学びはコミュニティから
学びはコミュニティがないと出来ない。学んだことの活かしどころを増やすために、所属する組織を増やしてみる。組織が増えることでそれぞれで異なる視点が得られ、視点が増える。学びの積み上げによって、軸が強まり固まるようになる。学びが増えるほど“面白みを受け取れる角度”が増える。
教養 ➡ メタ認知のトリガーを蓄える ➡ 面白みを受け取れる角度の増加
アウトプットのための余白
インプットが多くても余白がないとアウトプットが出来ない。インプット、学びの中に余白を残しながら、つまり全てを詰め込もうとせずに向き合う姿勢を持ちたい。
知らないものに出会う
人との繋がり、関係性によって人から人に出会う。人に出会うと、分からないことに出会える機会が増える。分からないことを楽しむためには新しいことに出会う。人は多面性(出身地、仕事、役割)があるから一つを目的に出会ったとしても他の面にも自然に出会える。分からないことに出会うために”興味がなかったら”参加する。
ショートピッチ②
北林功さん(DESIGN WEEK KYOTO)
コミュニティはぬか床
コミュニティは、ぬか床のように混ざり合わせなければ腐ってしまう。京都はいろいろな地方の文化を融合させて文化を築いてきた経緯がある。だからある意味、京都でしかできないものはない。他のところから取り入れてきたものを洗練させるのが京都の文化。文化の系譜を辿り、これからのコミュニティも混ざり合って新しいものができるシクミを作りたい。
セッション③
塩瀬隆之さん(京都大学)×行元沙弥さん(認定NPO法人グローカル人材センター)
ドキドキする学び
終了してしまう学び(学び続けられない学び)はwell lerningじゃない。
ドキドキする学びは知らないものに出会えること。今は共有が強要されているけれど、個人の中で学びが深まる速度は違う。だからそれぞれがいいことを学んでいたとしても、タイミングやスピードに適応できなかったら学びを受け取れない。誰かに話したくなることがwell lerning。息を吸うように自然なのが”学ぶ”ということ。
知らないからできることがある
知ることは同時に何かを失っている。分かる(=分かつ)。分かれば分かるほど分からないことが増える。世界は知れば知るほど世界が広がる学びと閉じる学びがある。学んだことを全てため込もうと自分の中にとどめるのではなく、その時に受け取れるものを自然体で受け止めていくことで世界を広げる余力を作る。
ショートピッチ③
名高新悟さん((株)名高精工所)
京都を試作の一大集積地にする
クロージングセッション
「好き」と「嫌い」を大人はいつから言わなくなったんだろう。自分の心を開いて、素直に向き合うことから始めると、学びはワクワクに変わり、楽しくなる。全てを吸収しようと抱え込まずに、「好きなこと」から試して、また手放すことを選択肢にしてもいいと思えるように。

認定NPO法人グローカル人材センターや京都信用金庫の拠点となっている施設「Question」もご紹介いただきました。


Yogiboを抱えながら自由なスタイルでセミナ―に参加できる施設。壁には自由に書き込みができてその場で”創造的な対話”をスタートさせられる。登壇者との距離が近い設計も臨場感のある魅力。

学生が自由に使えるコミュニティスペース。小学生から大学生までここで一緒に学ぶことができる。それぞれの興味に合わせたワークショップも定期的に開催されている。
きづき
4時間45分、12名の登壇者の方のトークセッションに参加しましたが、この中で見つけた共通点は「自然体な学び」、「学びのためのコミュニティづくり」、そして新しいものに出会うための「余白」。ひたすらに知識にインプットをするだけではなく、自分にも矢印を向けて「好き」に向き合ってみる。「好き」なこと、ワクワクすることほど人に話したくなり、そこでコミュニティが生まれる。違った視点を持つ人同士が混ざり合うことで新しい価値が生まれる。Questionは世代、職業を越境するその拠点の一つ。そして学びが継続できるように心の中に「余白」を残しておく。人生100年時代の中で新しいものへの出会いを楽しみ続けることができるように、この学びに心の栞を挟み、また振り返りたいと思います。
かばん持ち受付
noteをご覧いただきありがとうございます。
企画の紹介、イベントの取材依頼を受け付けております。希望される方は以下の応募フォームにご記入ください。
応募はこちら
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
