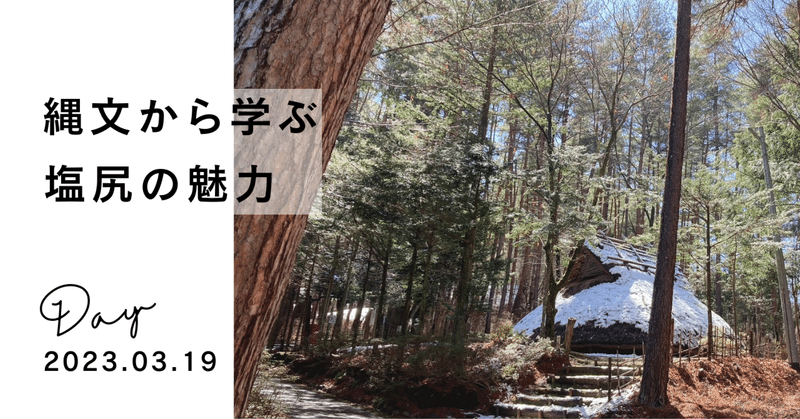
【リアルかばん持ち】縄文から学ぶ塩尻の魅力
2023/03/19
@長野県塩尻市
信州大学1年の石井恵里です。私は現在、信州大学の特任教授、株式会社docomo gaccoの山田崇さんのオンラインインターン「オンラインかばん持ち」の6期生として活動しています。
今回は、長野県塩尻市でフィールドワークに参加させていただきました。谷中修吾さん(BBT大学 経営学部 グローバル経営学科 専任教授/BBT大学大学院 経営学研究科 (MBA) 専任教授)をお招きして、塩尻×縄文の視点で塩尻の面白さを発掘しました。
山田崇さんProfile
Check in @アイマニSHIOJIRI


横山暁一さん(NPO法人MEGURU代表理事)にもご参加いただきました。塩尻青年会議所にも所属されている横山さんは、現在塩尻を拠点に、縄文をテーマにして企画を考えられているのだそう。谷中さんとのお話しを通して、縄文時代の文化を振り返りながら、発酵食品やジビエなど今も信州のブランドとして残っているものについて考えました。
食べ物や物資が貴重な時代だったからこそ大切に利用するための知恵が自然と根付いてきました。今に繋がるエシカルでサステナブルな営みから学ぶところが多くあることに気づきました。
塩尻市立平出博物館

牧野令さん(塩尻市立平出博物館)にご案内いただきながら見学をしました。

縄文時代の研究は、出土品や科学的知見から事実として分かっていることと、そこから考察される推論があります。ただ、教科書や学校で学ぶときには、推論の部分も事実として受け取ってしまいやすいです。
ただ、実際には断定できないものであるからこそ、推論の部分は一つの説にとどまらず自由に考えていいとお聞きしてとても新鮮に感じました。

こちらの出土品も今の似顔絵のようなものとして考えられていますが、現代の人が写真で盛るように理想とされた顔を表していたり、亡くなったこともを弔うために寝ている子供の顔を模していたりと様々な状況を推論することができるとディスカッションしました。

メディアで一つの説が紹介されると、その説の認識が固定化されてしまうため、正しく紹介されにくい、という課題があることも知りました。

塩尻は50cm程度の堆積なので、平出周辺で土を耕すと、このような土器がたくさん出土します。
ここに展示されている土器には様々な紋様が施されています。縄文時代は1万年とトレンドが長く、文化の分布した地域も広いため、横軸に俯瞰すると更なる広がりが見えてきます。

アクセサリーを身に付ける感覚には今と通ずる部分があり、興味深かったです。綺麗な石を見つけて、コレクションしたい、保存したい、身に付けたいという思考から身に付けられる形に加工されていったと考えられています。
一方で、遺跡からは出土品を使っていた人の推測までしかできないので、一人の人物像でイメージが固定されて、生活の多様性が見えにくいです。今と同じように多様な暮らしがあったのではないか、思い巡らしてみるのも面白そうです。

牧野さん、谷中さんからそれぞれの出土品について複数の説をご紹介頂きながら、根本を疑う視点を学びました。事実と推論を棲み分けて話す謙虚さが大切であると感じました。
平出遺跡公園

縄文・古墳・平安時代と3つの時代のムラが復元されていて、復元住居にも実際に入ることができます。建物に入り竪穴住居を体験することで、火の焚き方や明かりの取り方など、今の生活に照らして定説に疑問が生じる点も出てきます。当時の生活様式を推論するからこそ、経験に基づく仮説は重要です。


えんぱーく|塩尻市市民交流センター

えんぱーくの上条史生館長と石井健郎さんにご案内いただきました。屋上からは塩尻市街地や北アルプスが一望できます。


市民とともにほんの魅力を考え、発信する「本の寺子屋」事業などの独自の取り組みや、子供からお年寄りまで自由に時間を過ごし「知の交流」が実践できる多機能な施設をご紹介頂きました。
Check out @アイマニSHIOJIRI

田中暁さん(アイマニSHIOJIRI)から塩尻のワインや地元の農業や産業を残していくための株式会社HYAKUSHOの活動について伺いました。
きづき
塩尻を身近でなじみのある街だと思っていましたが、縄文にフォーカスして突き詰めてみると、初めて出会う発見が多かったです。同じ塩尻を見る視点でも、切り口を変えるだけで異なる楽しみ方ができることに気づけました。
また、今回のフィールドワークでは多くの方に出会い、案内していただきました。”縄文”という文脈で塩尻の中で行われている取り組みを繋ぎ合わさることで新たな価値が生み出せる可能性を感じることができました。
最後に谷中修吾さんから教えて頂いた「縄文型ビジネス」についてご紹介します。
【縄文型ビジネスの4原則】
直観的
縄文人は、その日の啓示で狩りに出掛け、獲物が捕れても捕れなくても、それがその日のベストと考える。“ビジネスモデルはもつが、事業計画はつくらない”からアドリブが利く
協調的
縄文人には、所有という概念がない。そのため争いごとがなく、皆で協力する。“競合他社という概念をもたず、すべてのステークホールダーでコラボする”のが縄文流
フリーダム
火焔型土器などの縄文土器に見られる通り、縄文人は自由な発想で、文様の美を創造した。“常識にとらわれず自由な発想でビジネスを展開する”クリエイティブな人種なのだ
感謝オリエンテッド
縄文人は、自然や宇宙と一体化した世界の中に生きており、何事にも感謝して人生を送っていた。“一期一会に感謝しながらビジネスを紡いでいく”のが縄文的視点
ビジネス成功の秘訣は、縄文時代にあった。
関連リンク
【谷中修吾『最強の縄文型ビジネス イノベーションを生み出す4つの原則』】
かばん持ち受付
noteをご覧いただきありがとうございます。
企画の紹介、イベントの取材依頼を受け付けております。希望される方は以下の応募フォームにご記入ください。
応募はこちら
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
