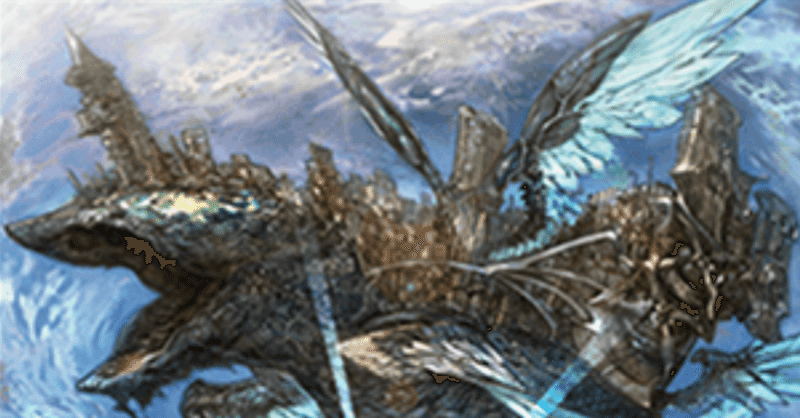
【メビウスCUPND73位】青単サイバー解説【柔軟性◎】
note4本目の投稿です、よろしくお願いします。
さて、これを読んでいる皆様の中でかなりの割合の方が、先月(4月)は様々なデッキの可能性を試したことと思います。3月下旬に行われた大規模なカード能力調整、およびそれまでの常識を覆す新規ギミック「超次元」の追加の影響ですね。私もその一人でした。12弾環境でずっと使用していた【リースNEX】が《ブレイブ・ルピア》のナーフ調整によって大きくデッキパワーを落としたため、握り替える先のデッキを探していました。
その中で本記事の主題である【青単サイバー】に邂逅&ガチ恋をし、一か月のあいだずっとどこへ行くにも使っていました。そして最終的にはランクマッチ(ボルシャックメビウスCUP)にてND最終レート1674、74位で最終レジェンドを達成することができました。NDでの最終レジェンドは自身初です!やっほーい。
遂に!ND最終レジェンド達成しました!!!!青単サイバーをずっと使ってました。小さな一歩ですが、大怪獣環境に風穴を開けられたので満足です。レジェンダリー・デスペラード最強‼‼ pic.twitter.com/gRmn0GeFrC
— クアルト (@Qualt_dmp) April 30, 2022
その記念も兼ねて、今回は【青単サイバー】の解説を記事という形に纏めたいと思います。
それでは……Into the CYBER!!!!(サイバー界の掛け声)
0.序論 ~普及までの道のり~
【青単サイバー】とは、《アストラル・リーフ》《エンペラー・マルコ》の2体の進化クリーチャーを軸とし、それぞれの進化元であるサイバー・ウイルスとサイバーロードを混合した、青単色(S・トリガー等で白をタッチする場合もあり)のビートダウンデッキです。
このデッキは生粋のユーザーズデッキ(↔デザイナーズデッキ)であること、確認する限り本記事が初めての解説記事であること、を鑑みて、本論に先立って成立背景について触れようと思います。
その起源は、いっとまさんというプレイヤーによる、3月度ランクマッチの最終レジェンド達成報告ツイートでした(*当該ツイートでのご自身によるデッキ呼称は“青単テンポビートダウン”でしたが、本記事では普及度を鑑みて【青単サイバー】で統一します)。
キリコカップはND21位でした
— いっとま (@ittoma_mtg) March 31, 2022
使用デッキは青単のテンポビートダウン
最大17連勝、プレイ次第でどの対面も見れるのがナイスでした
半年ぶりのラダー復帰だったので、新鮮な気持ちで楽しめたシーズンでした👍 pic.twitter.com/UArlpVd2lS
「LEGEND OF PLAY'S 2022」での再録以降、【リーフコントロール】のキーパーツとして環境で活躍し続けている《アストラル・リーフ》はさておくとしても、【ラッカマルコビート】以降、環境から姿を消して久しい《エンペラー・マルコ》の久々の躍進に、多くの方が驚いたと思います。さらにその後、動画投稿者のたんぼのたなかさんによる動画でこのデッキが紹介され、一気に知名度を上げることになります。
こうしてメタゲームの土俵に上がった【青単サイバー】ですが、Tier1デッキ群の壁は厚く、最終的なランクマッチでの使用率は全体の4~6%程度に収まりました(by統計調査グループBEANSによる集計)。
上記の使用率およびTier1デッキ群との相性から【青単サイバー】はTier2寄りのTier3デッキ、と私は評価していました。したがって5月度のメビウスCUPで最終レジェンド(シーズン最終日の100位以内)を達成できるのはどんなに多くても3人、0人だったとしても驚かない、と予測していました。しかし結果的にはTwitter上で確認できる限り(by akiraさんによる集計)でも4件の報告があり、大健闘といえる結果になりました。
「思ったより【青単サイバー】がやれた理由」について考察するのは本記事の主題ではないため深堀はしませんが、最も大きいのは「早期にTier1デッキ間のメタゲームから陥落したため、直接的なメタを貼られることがほぼなかった」からだと思っています。カードゲームの面白いところが出ていますね。
また、時系列が前後してしまいましたが、4月中旬に行われた公式大会のバトルアリーナ7thでは、ポニー/JOKER選手が【青単サイバー】を使用して決勝トーナメントを戦いました。惜しくも準決勝で敗れてしまいましたが、試合内容で【青単サイバー】最大のウリである「採れるプランの柔軟性」を全国に見せつけてくれました。【青単サイバー】をしばらく使い込んだ後に試合内容を見返してみると、色々な発見があると思いますので是非に。
1.各カード解説
まずはデッキリストをどん。

さて、漫然と各カードの説明をしていってもデッキ全体の動きが把握しづらいと思われるため、先にこのデッキの勝ちパターンについて、ざっくりと解説します。主なものは以下の4種類です。
1. アグロ(速攻)プラン
リソース管理よりも打点生成速度を優先し、早めにダイレクトアタックを通すプラン。【キリコ】【バイオレンス・フュージョン】などの、「こちらのS・トリガーが効かないタイムリミットデッキ」に対して主に採用します。
2. カウンタープラン
相手にこちらの盾を割らせ、S・トリガークリーチャーによってその攻撃をいなす。その後返しのターンで、増えた打点を使ってカウンターリーサルを決める、というプラン。特に【Bロマノフ】対面で多用します。他の対面でも、最初はアグロプランを採り、相手のデッキの回り具合を見た後にこちらのプランに移行することは多々あります。
3. 波状攻撃プラン
各種コントロールデッキに対して採用します。最近のコントロールデッキは【黒緑速攻】対策でS・トリガーが増量されているので、崩すのは容易ではありません。そのため、《リーフ》・《マルコ》が自身の攻撃でS・トリガーを踏んで除去されることを織り込んだうえで、補充したリソースから次ターンで再度の進化速攻を狙い、スタミナと瞬発力の二本柱で勝ちを狙います。
4. 《ブリザードムーン》4t着地プラン
① 2t《エボリューター》→3t《ウィスパー》《リーフ》→4t《リーフ》の上に《ブリザードムーン》
② 1t《トリア》→2t《エボリューター》→3t《トリア》の上に《羅月ブリザード》→4t《ブリザードムーン》ルナティック進化
のいずれかのパターンで、《ブリザードムーン》を4t目に着地させるプラン。
これが決まると、溢れんばかりに増えた手札からバウンスや進化速攻を連打し、容易に圧殺することが可能です。このデッキでは数少ない、イージーウィンが狙えるプランですが、無理にこだわりすぎるとプレイングが歪みます。決まったらラッキー程度に考えるのが精神衛生上よろしいですね。
さて、それではお待ちかねの各カード解説に入ります。
《アクア・エボリューター》4枚

イバー・ウィルスでもサイバーロードでもないですが、紛うことなきこのデッキの核。なので1枚目に持ってきました。マナ加速手段のないこのデッキにとっては、このクリーチャーを2t目に出せるか否かで、後の展開力に天と地ほどの開きが出ます。
さらに打点として運用できるのも非常に大きいです。2t目に出した後に3t目にこやつで盾を割るかどうか悩む場面は頻出しますが、経験上割った方が将来は薔薇色になります。「S・トリガーを踏んで除去されてしまうと次ターン《マルコ》を出せず、エンジン始動が1ターン遅れる」などの明確なデメリットが予見される状況以外では、積極的に割るべきです。
《トリア》4枚
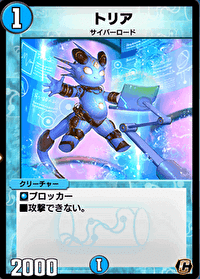
宇宙最強ムーヴ「6マナで《マルコ》進化速攻」に必要なパーツです。他にも、余ったマナで出せる局面自体は多いですが、特に目的なしで出すと殴れない置物と化してしまうため、雑に扱いすぎるのは禁物です。
「次ターン飛んでくるかもしれない《サファイア》の攻撃をチャンプブロックするため」「《マルコ》着地を1t早めるため」「《ヘヴィ》の選ばせ除去に対するデコイとして」など、有効性を見極めて出しましょう。
《キュート・ウィスパー》4枚

序盤は《リーフ》の進化元としてなんとしても引きたい&出したいクリーチャーですが、5マナ溜まって以降は基本的にマナに置きます(《リーフ》は《ツクモ》のデメリットキャンセルに使いたいため)。
うーむ、流石に性能が淡泊すぎて語ることがありません。かわいいよ…。
《アストラル・リーフ》4枚

メインエンジン右大臣。言わずと知れた紙での元殿堂カードです。しかしデュエプレ世界戦では、カードプール増加につれて、紙よりもパワーが1000落ちていることのデメリットが顕在化してきました、現環境ではなによりも《アカギガルムス》の火力範囲に入っているのが渋い。「文句なしに強いが、これ一枚で完結するほどの突出したカードパワーではない」という、丁度いい塩梅に落ち着いているのではないでしょうか。
また、このデッキは【リーフコントロール】とは違い、《リーフ》を維持することでメリットが発生する場面は少ないです。比較的遭遇するものとしても、次ターン《ブリザード・ムーン》への究極進化が見えている状況くらい。ということで、基本的には出した後はガンガン盾に突っ込みましょう。
《ツクモ・スパーク》4枚

進化してデメリットキャンセルすることによって絶大なテンポアドバンテージを稼ぐ、このデッキの神経網。序盤から終盤までずっと強いため、よほどだぶついた時以外はマナに置きません。
また、相手盤面に干渉する手段が少ないデッキ、例えば【黒緑速攻】や【ジャイアント】など、に対しては魂をこめて素出しする勇気も必要です。こいつのピーキーさを制御できるようになれば、【青単サイバー】学科試験は突破できるらしい。
《クゥリャン》4枚

クセがないって素晴らしい。《リーフ》、《マルコ》、《ブリザード・ムーン》とド派手なドロー効果を持つクリーチャーの陰に隠れがち。しかしこのデッキ、序盤は手札消費のほうがリソース補充よりも多くなりがちで、意外と手札がカッツカツになります。そこに3t目のcip1ドローが五臓六腑に染み渡るという寸法であります。
《エンペラー・マルコ》3枚

メインエンジン左大臣。メインなのに、なぜ4枚ではないのか?という問いに一言で答えると、「1試合で2枚目を出しても有効性が低いから」。
《マルコ》は自身の効果で邪魔なブロッカーを盤面からどかすことができるため、基本的に出したターンのW・ブレイクは通ります。ということはその時点の相手のシールドは残り2~3枚となっているので、次のターン以降に追加でW・ブレイカーを召喚する旨みはそれほどない、ということになります。上記理由と、《デスペラード》とコストが被っている点から3枚に落ち着きました。
《レジェンダリー・デスペラード》3枚

新弾カードリストのなかでコイツを最初に見たとき、「見るからに弱そう」と決闘者の勘が迸った方は多いと思います。忘れましょう、一旦。大幅に。
やはりなんといっても前触れなしのスピードアタッカー2打点は奇襲性が尋常ではなく、相手の打点計算を大きく狂わせることができます。アグロプランやカウンタープランを採るときによく発生する、「妖怪リーサルに1点届かない」をこのカードで強引に解決できる場面も非常に多いです。総合的に見て、【青単サイバー】というデッキの持つ性質を裏側からびたりと補完してくれるカードです。初手に引いてしまうとリソース管理の観点からマナに埋めざるを得ないので、2枚投入だと後半に足りなくなる事態が頻発します。ということで鬼の3枚投入。
《神羅ブリザード・ムーン》/《羅月ブリザード》2枚


低カードパワーのカード同士のシナジーで戦う【青単サイバー】における異端児。4t目に《神羅》が着地したときの試合は、もはや別のカードゲームになります。ライブラリアウトを気にしすぎて悪いことはないので、一度ドロー効果を発動した後は目玉かっぽじって山札残り枚数を意識し続けましょう。
また、もう一つの「アタックされない・ブロックされない」効果も一見地味ですが、確定除去が減り気味の現環境に対してほどよく突き刺さっています。「次の相手ターンに《Bロマノフ》or《ライゾウ》が飛んでくるので、攻撃の的を作りたくない」という状況でも安心してタップ状態にできるため、攻撃の手を止めずにすみます。
一方の《羅月》面に関しては、目を瞠る活躍はしづらいものの、小回りの効きやすさが嬉しいです。最終盤で山札を大きく削らずに《ツクモ》のデメリットをキャンセルする手段として使いたくなる場面があるので、リソースが十分だからといって安易にマナに埋めるのは後悔の元になりえます。
~S・トリガー枠~
このデッキの強みの一つであるカウンター性能をある程度保証するため、8枚以上はS・トリガークリーチャーを積みたいです。なぜ8枚かというと、このとき5枚の初期シールドの中に埋まるトリガー枚数の期待値が1枚となるためです。

《キューティー・ハート》4枚

対ビートダウンにおいては《サーファー》を大幅に超えるパフォーマンスを発揮するエグいやつ。現環境では1点ずつ刻むビートダウンデッキは非常に少ない(それこそ、ほぼこの【青単サイバー】だけと言っても過言ではない{確信度60%})ため、S・トリガーで出るときにはほぼ確実にバウンス効果が起動します。
また、アンブロッカブル持ちなのも地味ながら非常に優秀です。これを活かし、詰めの局面で、相手のS・トリガー持ちブロッカーをケアするために《キューティー》で最後に殴るのが最適解となる場面は頻出します。ダイレクトアタックを通す瞬間まではゆめゆめ油断するまじ。
《アクア・サーファー》3枚、《霊騎コルテオ》1枚


元々《サーファー》4枚だったところを1枚だけ《コルテオ》に差し替えた経緯があるためまとめて紹介します。
《サーファー》0枚、《コルテオ》4枚にしている構築もかなりメジャーとなっていますが、私は《サーファー》のほうを高く評価しています。確かに、トリガーで出たときの防御力、という観点では《コルテオ》>《サーファー》です。一方で、コントロール対面ではどかさないといけない相手クリーチャーの数が、各種ゴッドを筆頭にかなり多いため、バウンス札の枚数が重要です。こちらの盾を割ってこないコントロール対面では《キューティー》が無効になってしまうので、手打ち《サーファー》の回数が明暗を分けます。ということで上記の《サーファー》厚めの比率に落ち着きました。1枚だけ《コルテオ》にしているのは、マナに埋めたときに相手にこちらのトリガー枚数を実際より多く錯覚させられる効果を期待してのもの。
とはいえ、この枚数比やそもそもS・トリガーを何枚積むのかについては、環境をよく理解してチューニングする必要はあります。「ビートとコントロールどちらが多いか」「トリガー無効(byシールド焼却など)デッキがどの程度いるか」を考えながら、調節することを推奨します。
2.プレイング(基礎編)
対面ごとのプレイング解説に入る前に、全対面共通の事項について説明します。ちょっと抽象的な物言いが多くなっていますが、【青単サイバー】はその柔軟性の高さゆえに「脳みそを振り絞ってその時の最善解を捻り出す」側面がかなり大きく、ケースバイケースでしっかり考えないといけないためです。頑張ってついてきてください…‼
・エンジン点火はすべてに優先する
【青単サイバー】の核となるギミックは、《リーフ》・《マルコ》召喚時の3ドローで次の《リーフ》・《マルコ》を引き込み、連鎖的に展開し続けることです。
したがって、序盤は1体目の《リーフ》・《マルコ》着地=エンジン点火が最優先です。初手で《リーフ》・《マルコ》を運良く引けた場合は問題ありませんが、引けなかった時こそ腕の見せ所です。トップで《リーフ》・《マルコ》どちらを引いてもスムーズにエンジン点火できるよう、マナ置きの吟味・進化元の盤面準備をすることが肝要です。
・どのクリーチャーをバウンスするかじっくり考える
《ツクモ》や《マルコ》のバウンス効果で相手のブロッカーをどかし、その後の攻撃を通すのは【バウンスビート】王道の動きです。ただし全ての局面で最適解かというと、決してそうではありません。
時にはブロッカーの横にいるシステムクリーチャー(強力な常在効果持ちのクリーチャー)をバウンスして、次の相手ターンの展開を邪魔することのほうが、ゲーム全体で見たときに優れた手になりえます(カードゲームではこのような手を指して「テンポをとる」と表現します)。相手のマナ置きなどから「次のターンになにをしたいのか」を予測し、バウンスの優先順をじっくり考えましょう。
・公開領域のトリガー枚数を把握する
【青単サイバー】は大量ドローを連続させるため、終盤になると非公開領域である山札の枚数がかなり減ります。これはすなわち「シールドに埋まっているトリガーの枚数を、高い精度で推算できる」ことを意味します。
トリガークリーチャーからのカウンターをよく狙う【青単サイバー】にとっては、この推算精度は勝利に直結する重要な情報です。ビート対面では常に公開領域に見えていないトリガーの枚数を意識し続け、トリガーが盾に埋まっていなさそうなら捲るためのゴン攻め、埋まっていそうならカウンター姿勢、と戦法を変える必要があります。
3.プレイング(対面ごと)
ではいよいよ、対面ごとの戦法・注意点解説に入ります。セオリー的には対面ごとのデッキ相性も付言するものですが、このデッキは【キリコ】に不利、【黒緑速攻】に微有利なこと以外は基本的に全対面五分に近いので割愛します。
【キリコ】
ぶっちぎりで一番当たりたくない対面です。
しかし裏を返すと、この対面でどれだけ勝ちを拾えるかが、全体勝率に大きく影響を及ぼすともいえます。勝ち筋は、「相手が事故っている間に速攻を決める」ことのみ。
こちらの盤面にクリーチャーを溜めてからシールドを殴ろうとすると、《ノーブル・エンフォーサー》で小型クリーチャーをビタ止めされて身動きが取れなくなるので得策ではありません。また、トリガー《オリジナル・サイン》をケアしている余裕は微塵もありませんので割り切りましょう。
最後に、戦法と全く関係ないですが、【青単サイバー】をランクマッチで使う上では、【キリコ】相手に全然良いところなしにタコ負けしたときに、どれだけへこたれずに気持ちを切り替えられるかが最重要です。やさしいものを見たり想像して脳を守りましょう。
【Bロマノフ】
4月上旬は【黒緑速攻】対策でトリガー厚めの構築が多く、【青単サイバー】目線でも苦戦を強いられていました。しかしその後、《進化設計図》によるリソース確保を重視した型へ構築が遷移していく中でトリガーが抜けていき、今ではかなり戦いやすい相手となっています。勝ち筋はほぼカウンタープラン一本で、これを成立させるためには、
・序盤に1~2点盾を割っておくこと
・相手の《Bロマノフ》の攻撃をこちらの盾で受けること
が必要です。
一方であまりにもカウンターに寄りすぎ、クリーチャーを横並べしすぎると、《DEATHドラゲリオン》で盤面を一層された時に立て直せなくなります。このため、《DEATHドラ》がくる直前のターンは盤面のクリーチャーで全軍突撃しておくことが最適解である状況は多いです。
【バルガライゾウ】
基本的に対【Bロマノフ】と同じで、序盤に1~2点盾を割っておいてから《ライゾウ》のTブレイクでトリガーを踏ませてカウンターを狙います。《ライゾウ》のメテオバーンで《バベルギヌス》が捲れたとき、《ライゾウ》を破壊してアタックキャンセルされるとマズい、という場面がよくありますが、実戦ではそのようなプレイングはほとんどされたことがありません。なぜだ……?

【黒緑速攻】
軽量ブロッカーである《トリア》がいるおかげで有利気味に戦えます。しかし、墓地進化を連打されて畳みかけられると普通に負けるので、まったくもって油断は禁物です。この対面では、どのクリーチャーをバウンスするかが他の対面以上に重要になります。「墓地進化クリーチャーをバウンスして墓地リソースを減らす」「召喚酔いの非進化クリーチャーをバウンスして確実に1ターン稼ぐ」などの選択肢を吟味しましょう。
また、不用意にシールドを割ると、増えたリソースから一気に盤面を展開されます。ダメージレースで追いつけなさそうなので仕方なくシールドに行く場面も往々にしてありますが、殴らずに溜める選択肢も常に考えましょう。
【バイオレンスフュージョン】
【黒緑速攻】メタの《地獄スクラッパー》、《ジャック・アルカディアス》をかいくぐった上で、《キング・アルカディアス》のロックをいなしてダイレクトアタックを通す必要があります。文章にするとえげつねぇな…。《デリンダー》のOD能力でであまりに大量にドローされすぎると物量戦で勝てなくなるので、ほどほどにリソース補充しながら攻め続けましょう。
殴ってこないデッキなので、《トリア》は腐り気味……と思いきや、《キング》ロックの生贄や《ヘヴィ》の選ばせ除去の囮など、随所で活躍するので脳死でマナ置きするまじ。
【デイガナイト】
打点が伸びにくいこのデッキにとって、《魔弾プラス・ワン》によるシールド追加は非常に厳しいです。「相手の初期シールドが7枚ある」くらいの気持ちでゴン攻めし続けないと、余裕を持って耐えられてしまいます。

バウンスは《ネロ・グリフィス》に当てるのが最高効率ですが、《シーザー》着地を遅らせるために中盤で《ドラム・トレボール》、《アヴァラルド公》を戻すのも有力な選択肢です。
また、12弾環境で【リースNEX】を使っていた人にとっては納得しやすいところかと思いますが、序盤から《羅月ブリザード》で1点ずつ刻み続けると、相手にとって非常に嫌らしいプレイングになります。パワー5000のため《デュアル・ザンジバル》の処理範囲外かつ、タップ状態を保っていると《アルカディア・エッグ》も効かないからです。
【ドロマー超次元】
サイキックにバウンスが覿面に効き、大量ドローでハンデスのダメージを緩和できるので一見ガン有利……に見えます。しかし、こちらの大量ドローは《リーフ》or《マルコ》+進化元クリーチャーの2枚コンボなので、手札を完全に枯らされると、詰みの状況になることが多いです。したがって、呪文コスト軽減の《フランツI世》をバウンスしてハンデス呪文を連打されないようにすることが肝要です。
また、メインデッキに高コストクリーチャーが入っていないため《ツクモ》のデメリットを緩和することができ、戦略を練るうえで重要なファクターとなります。
以降のデッキはランクマッチでの遭遇率が低くサンプル数が少ないため、それぞれ手短に。
【各種コントロール】
Sトリガー持ち確定除去に関して、最近は《策略と魅了の花籠》の採用率が高いです。したがって、シールドを割りに行くときは非進化クリーチャーから殴ったほうが良いケースが割とよくあります。《花籠》で進化クリーチャーをマナ送りしてもらったほうが、マナが伸びて嬉しいからですね。
他にも、相手のマナ置きから「どのカードが採用されていそうか」を読んで戦略を練る必要があるので、環境への理解度が試されるところです。
【ジャイアント】
《西南の超人》にバウンスを当て、相手が展開しきる前にこちらのダイレクトアタックを通します。S・トリガーで《ホーリー・スパーク》を踏むと、返しのターンに一斉トンカチで盤面が壊滅しますが、一生ケアできません。割り切りましょう。
【NEX】
兎にも角にも《コッコ・ルピア》を最優先でバウンス。勝敗はかなりお互いのトリガー運に左右されますが人事を尽くしましょう。
【赤青剣誠】
なぜかクリーチャーが全員スピードアタッカーを持っているのでバウンスが効きづらく、テンポがとれないので苦戦しがちです。S・トリガーでサムライ・クリーチャーが出てきてしまうと《剣誠》の着地が早まるため、シールドブレイクするか否かの判断はいつも以上に慎重に行きましょう。

【白騎士】
S・トリガー《白騎士ゲート》・《白騎士スパーク》のどちらを踏んでもゲームオーバーなので怖いですが、勝つにはゴン攻めするしかありません。《ピラー・オブ・フェザー》+クリーチャー3体以上の盤面を一度作られてしまうと崩せなくなるため、絶え間ないバウンスで阻害します。魂の《ツクモ》素出しせざるを得ないこともしばしば。
4.終わりに
いかがでしたでしょうか。本文中でも何度か触れましたが、【青単サイバー】は対面・状況に合わせて戦法を変えていく柔軟性が非常に面白く、先月1か月間使い続けた私にとっても、今なお新しいプレイングを試す余地が存分にあります。そんな奥深さに届かせる記事となるように書いたつもりなので、同好の士が一人でも増えることを祈っております。
さて話は変わって、平常通りの運営スケジュールならば、5月末に新弾の14弾が発売される見込みです。13弾では顔見せの側面が強かった「超次元」ギミックが本格化することは必至です。しかしこれは言い換えると、強いサイキック・クリーチャーが出るほど、超次元ギミックに強い【青単サイバー】は相対的に強化されるということでもあります。ということでここは余裕を吹かして、新弾に収録されそうなサイキック・クリーチャーたちを見物させてもらいましょうか、わっはっは。

( ゚д゚)
(つд⊂)ゴシゴシ
“相手のターン中、相手の呪文またはバトルゾーンにある相手のクリーチャーの能力によって、自分のサイキック・クリーチャーが手札に戻される時、そのクリーチャーは手札に戻されるかわりにバトルゾーンにとどまる。”
(;゚д゚)
【青単サイバー】の明日はどっちだ!!!!???
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
