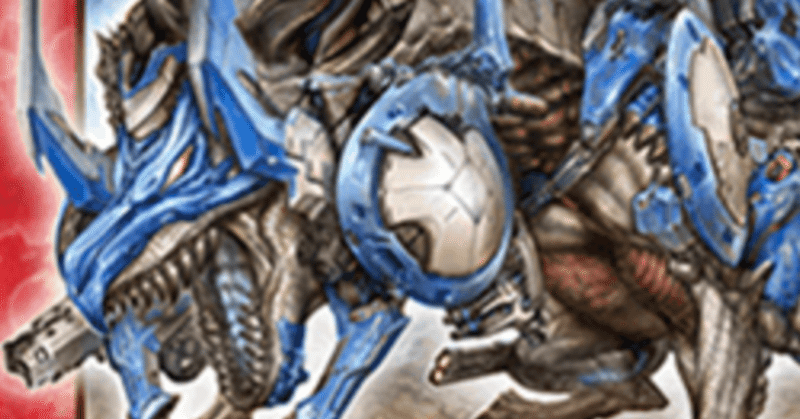
【デュエプレ】勝舞編の個人的思い入れカード3選
デュエプレの勝舞編が、あと数日で幕を閉じる。
紙では2002年~2011年に亘る約9年間を費やしたシリーズを、デュエプレでは2年と9か月で駆け抜けた。色々とどんぶり勘定だが、その密度の比はなんと3倍弱である。圧縮しすぎてブラックホールできてんぞ。
「勝太編に移行するタイミングでUI刷新とかあると楽しいだろうなあ」などと1ユーザーとしては無邪気に夢想していたが、とりあえず現在公開されている情報で判断する限りでは、あまりその方面のアップデートはないようだ。
また新シリーズ1発目のエキスパンションも、概ね平常通りのスケジュール・収録カード数で実装されるようである。一定の売り上げを保ち続けないとサ終というラグナロクが速やかに到来する、北欧神話並みの限界さを誇るソシャゲというシステムの性質的には、無辺なるかなという感じである。
ここ数日、新カード情報に阿鼻叫喚する日々を過ごしながら、ふと「このままだとヌルっと勝太編が始まってまうやんけ」ということに、遅ればせながら気づいたのがつい昨日のこと。
なにか、「区切り」を自分の中に打たねば、と思った。
残された時間とも相談して、簡易的ではあるが「個人的に思い入れが深いカード」を3枚厳選してピックアップし、思い出をつらつら語ることで勝負編にさよならを言う心の準備を整えることにしたい。
<<レベリオン・クワキリ>>

第2弾にて収録。
条件付きではあるが4コストでWBという破格のスペックを誇り、主に自然文明の入った中速ビートデッキで活躍した。
<<ビートダウン>>というデッキタイプの面白さを私に教えてくれたカードである。
私が紙のデュエマをプレイしていたのは、小学校高学年~中学生の頃のこと(第3弾~聖拳編くらい)。当時莫大なおこづかいをもらっていたわけもなく、パックから出たカードの中から「比較的マシ」なカードをかき集めた紙束を「デッキ」と宣う、ごく平均的な子供であった。
当然、レアリティの高いカードの比率が高いコントロールデッキなど組めようはずもなかった。そのため、当時組んでいたデッキは、まあ辛うじて言えばビートダウン戦術をとるデッキばかりであった。
要するに、当時の私は「ビートデッキ」を作ろうとして作っていたのではなく、それしか選択肢がなかったのである。
そして不幸なことに(実は同時に幸運でもあったのだが)、友達にボンボンがいた。彼の操るコントロールデッキ(<<ヘル・スラッシュ>>を使いこなす小学生について、どう思います?)になすすべもなく敗北する毎日。悔しかったねえ。
そんな時代から呆れるほどの時間が過ぎ去った2021年初頭、デュエプレにて第2弾が実装される。
当時の私はポイント枯渇地獄に喘いでいた。サービス初期の配布コインの渋さ等々についてはデュエプレ老人たちによって散々語られてきたところなので、ここではあえて触れまい。
そんな私を含む貧困層にも、救いの手が一応残されていた。
<<アストラル・リーフ>>を4枚生成すれば残りはほぼR以下のカードで組める、【クワキリリーフ】の発見である。
「安くて強い」という売り文句にまんまと引っかかった私は、なんとかして(臓器でも売ったんか?)<<アストラル・リーフ>>を4枚生成してこのデッキを組み、ランクマッチへ意気揚々と殴りこんだ。
……と、いかにも当時のことを鮮明に覚えているテイで書いてきたが、正直、このデッキの勝率がどれくらいだったのかはまったく覚えていない。使った記憶が残っているということはそれなりに勝てたはずではあるが……。
さて、【クワキリリーフ】というデッキの主な勝ち筋は、
<<クワキリ>>で盾を殴る
→相手の手札が増える
→<<クワキリ>>のパワーがさらに上がる
という、<<クワキリ>>の自己完結した強さにかなり依存している(もちろん<<リーフ>>もアホみたいに強いが)。これは流石にデッキを組む前の時点、<<クワキリ>>単体の性能を見ただけで私も気づいていた。
しかし何戦かしているうちに、察しの悪い私でも、さすがにその奥の「「「真実」」」に気づいた。
「これもしかして、相手を『溢れた手札を使い切れない』状態に追い込んでいるから勝てているんじゃないか?」
と。
それに気づいた瞬間、『シールドを割り切ってダイレクトアタックを通せば勝ちのゲーム』としてしか認識していなかったデュエマに対して、ぐんと解像度が上がった気がした。
「相手にしたいことをさせない」というのはコントロールデッキのみが浸れる愉悦だと決めつけていたが、性質は違えどビートデッキも勝ちパターンとしては同じであることを、このとき実体験として納得することができた。
すべては、相手の手札が溢れているほど(≒相手がフルパフォーマンスを発揮できていない時ほど)クソデカになっていくという、これ以上ないほど分かりやすい指標でヒントを与えてくれた<<クワキリ>>のおかげである。
<<大作家ゴリランボー>>

第7弾にて収録。
環境での活躍は特になし。
<<ゴリランボー>>は、私に初めての成功体験を教えてくれたカードである。それまでの私の「デッキ調整」といえば、「なんか思ったより活躍しなかったカードを抜いて、代わりになんとなく強そうなカードを適当に入れる」だけである。そこには方針も理念もない。
先に答えを言ってしまうと、「活躍しなかった理由」をしっかり考えて、逆説的に導かれる「活躍しそうなカード」を入れるのが正しい調整方法なのだが、当時の私は知る由もない。しかしある時、転機が訪れる。その気になる内容とは……??
↓↓続きは以下をクリック↓↓
この記事の冒頭に書いたとおり、当時(11弾環境)使っていた【赤緑速攻】で<<ブレードグレンオー>>がいまいち活躍しなかった理由を「パワーの低さ故」と仮定し、それを克服するために替わりに<<ゴリランボー>>を入れてみたらたまたまうまくいったというだけのことなのだが、私にとってはダイヤモンドの煌めきも霞むような成功体験であった。
このときの成功体験に味を占めまくり、それからより一層このゲームの深淵にどっぷりと浸かることになってしまうのだが……まあそれについては今後別のところで語ることもあろう。
また別件になるが、時は流れて12弾実装直前、<<ゴリランボー>>がNDで使用不可になるタイミングで突然使命感が全身を駆け巡り、当時のリスト(型落ちにもほどがある)で無謀にもランクマッチに潜る様子を、配信サイトのMirattiveで数日間に渡り配信した。特に最終日は非常に多くの皆様に珍獣を見に来場いただいた。遅ればせながら感謝申し上げます。
<<ゴリランボー>>よ、永遠に。
(「ADで使え」は禁句)
<<連珠の精霊 アガピトス>>

第8弾にて収録。
環境での活躍を全部書くために必要な原稿用紙を積み重ねると、月に届く計算らしい。
最初に宣言しておこう。
<<アガピトス>>(ナーフ前)、めっっっっっちゃ楽しかった。
「人類史上でジンバブエドルの次くらいにインフレしてた」と言われる7弾~9弾環境の中でもまず間違いなくトップの汎用性・カードパワーを誇るこのカードに、苦々しい思い出をお持ちの諸兄もおられるかもしれない。
実は私も、8弾の【ゲオルグ天門】全盛期のときは、どちらかというと「やりすぎてるから規制したほうが良い」という言説に素直に共感していた。しかし8弾EXにてこれまでの常識を打ち破るデッキが開発され、その気持ちは一旦粉砕される。
【青抜き4Cアガピ】である。
このデッキを初めて回したときの凄まじい衝撃を、未だに私はほとんど言語化できない。
なんならその前の【ゲオルグ天門】の、「入ってるカード全部パワカ」というこれまた常識破りな構成にも、それなりの衝撃を受けていたはずであるが、綺麗さっぱり上書きされてしまった。
一応それっぽく【青抜きアガピ】の唯一性を語ってみると、「6コストとやや重いクリーチャーがデッキのエンジンになっている」ことであろうか。「デッキのエンジン」といえば「ドロー・ブーストスペル」もしくは「軽量システムクリーチャー」を指すという、それまで漠然と私が抱いていたイメージとはかけ離れたコンセプトだ。『フェアリー・ギフト』が、下方修正されたとはいえ4枚使用できるデュエプレだからこそ成立する無理筋である。
また名脇役の<<G・A・E>>の能力が持つ選択肢の多さも相まって、兎にも角にも「使って楽しいデッキ」であり、狂ったように回していた。そんな気持ちになったのは、前にも後にもこのデッキだけである。
しかし蜜月が長くは続かないのは人の世の常、ご存じのとおり<<アガピトス>>はナーフ調整を施され、いい塩梅の強さに落ち着いた。
一応、ナーフ後も《アガピトス》からの《アマリン》射出ギミックを活かした【ラッカマルコ】を使用して、バトルアリーナ予選のスイスドローで個人最高成績を出せたとかの思い出もあるにはあるが、【青抜きアガピ】の衝撃はまったく色褪せずに今も脳を揺らし続けている。
ということで運営さん、頼む。もう一度だけでいいから【青抜きアガピ】使わせてくれ。
終わりに
この記事を書いて分かったことが2つある。
・自分で思っていた以上に、私は<<クワキリ>>に思い入れがあったらしい(3行くらいで終わると思ってた)。
・冒頭で「あっちゅうまに勝負編終わっちまったべな」的なノリのことを書いたが、こうして振り返ってみると、「カードゲームセンスゼロのおっさんが、辛うじて人前に出せるくらいのプレイヤーになる」ための成長期間としては、そこそこ丁度良い長さだったようである。
ということで、数日後に開幕する勝太編も、ドンドン楽しむナウしていこうぜ!!!(勝太世代全員抱腹絶倒の渾身ギャグ)
それではっ
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
