
電子帳簿保存法への対応について
絶賛対応中(遅い!)ですが、たまにはちょっと真面目に書いてみる。
取引情報の授受を電磁的方式により行う取引のことです
こういったことをやるときには、お役所の文章も一応見るようにしています。以前に比べるとお役所の文章も具体的でわかりやすくなりましたが、例がいっぱいありすぎてわからなくなる(笑)。
で、「こりゃあ何が該当するんだ」というのは、上記にあるこの説明が一番具体で分かりやすいと思います。
(1) 電子メールにより請求書や領収書等のデータ(PDFファイル等)を受領
(2) インターネットのホームページからダウンロードした請求書や領収書等のデータ(PDFファイル等)又はホームページ上に表示される請求書や領収書等の画面印刷(いわゆるハードコピー)を利用
(3) 電子請求書や電子領収書の授受に係るクラウドサービスを利用
(4) クレジットカードの利用明細データ、交通系ICカードによる支払データ、スマートフォンアプリによる決済データ等を活用したクラウドサービスを利用
(5) 特定の取引に係るEDIシステムを利用
(6) ペーパレス化されたFAX機能を持つ複合機を利用
(7) 請求書や領収書等のデータをDVD等の記録媒体を介して受領
(電子帳簿保存法一問一答より)
要は、業者さんや個人の委託先への注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類を電磁的なやり取り(メール・オンラインでのダウンロード・インターネット上のシステム・インターネットFAXなど)でやり取りするケースは全部該当します。
関連各社が解説やセミナーをやっていますが、これが一番わかりやすかった。
電子取引は保管の必要がある
今までこういった取引は、以下のいずれかの方法で保管する必要がありました。しかし、令和3年度税制改正により、2022年1月1日以降は②③が認められなくなります。
①電磁的記録
②COM(電子計算機出力マイクロフィルム)
③書面
問題は、電子保管のルール
ふむふむ、うちは①で取引の内容は全部保管してるから大丈夫、なんて思っていると、この要件につまずきます。
(1) タイムスタンプの付与
(2)関係書類の備付け
(3)見読性の確保
(4)検索機能の確保
細かいことは上記の解説サイトで見ていただきたいのですが、これ、指定がめっちゃ細かいんですよ。
たとえば、(3)一つとっても、まるで「PCに操作説明書を貼っておけ」と言わんばかり。
電子取引に係る電磁的記録の保存をする場所に、その電磁的記録の電子計算機処理の用に供することができる電子計算機、プログラム、ディスプレイ及びプリンタ並びにこれらの操作説明書を備え付け、その電磁的記録をディスプレイの画面及び書面に、整然とした形式及び明瞭な状態で、速やかに出力できるようにしておくこと。
まあこれは、要は「すぐ出せるようにしておけ」ととらえればよいようです。
どちらかというと問題は(4)の方で、たとえば大量の業務委託先があり、その取引記録をシステムで管理しているケースがあったとして、データでは保管していても、下記のような条件に合う形でいつでも出せるかというのは別だと思うんですよね。
なので、割とシステム側での対応が必要になるケースは多いと思います。
電子取引に係る電磁的記録について、次の要件を満たす検索機能を確保しておくこと。
①取引年月日、その他の日付、取引金額その他の主要な項目を検索条件として設定できること。
②日付又は金額に係る記録項目については、その範囲を指定して条件を設定することができること。
③二以上の任意の記録項目を組み合わせて条件を設定できること。
オールインワンのサービス利用が楽
先日からこの条文を前にうんうん考えていたのですが、
・タイムスタンプをつけた保管
・リスト化および検索機能
あたりをどうするのか?というのが結構大事なポイントで、大規模なシステムはプログラムで回収しつつ、小規模なものはデータ書き出ししてスプレッドシート保管でもいいんじゃない?という話に倒れつつあります。
①取引年月日、その他の日付、取引金額その他の主要な項目を検索条件として設定できること。
②日付又は金額に係る記録項目については、その範囲を指定して条件を設定することができること。
③二以上の任意の記録項目を組み合わせて条件を設定できること。
あたりは、リスト書き出ししてフィルタをつけとけばできちゃいますしね。
ただ、何がどこまでオーケーなのかどうかというのは、国税次第というのもありますので、オールインワンのサービスを導入してしまうのが最終手段になりそうです。
取引を電子化するチャンス
いろいろ書いていると「また対応か…」とうんざりしそうですが、実は今回の法改正、取引の電子化を踏まえているので、契約を電子化するチャンスでもあるんです。
そんなこんなでいろいろなサービスが出ています。
みたいにオール電子化できると良きですよね。

電子契約は取引先が対応している必要がある
本来は上記のようなサービスを使いたいのですが、企業間取引でよくあるのは「相手が対応していない」ケース。相手が「印影がある社判でないと受け入れられない」だと、電子契約はアウトなんです。
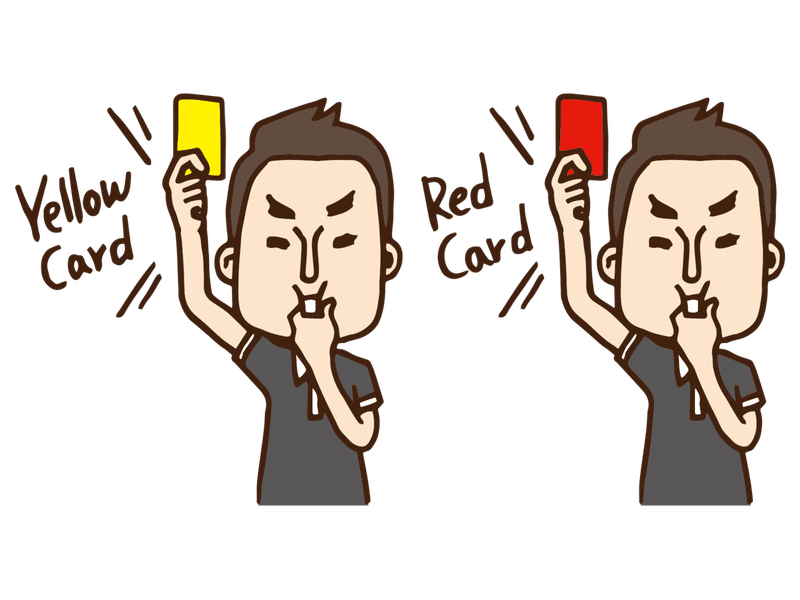
弊社のような中小だと取引先も中小なわけで。根本的なDXはまだ、先の話になりそうです。。。
保存要件がめんどう
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
